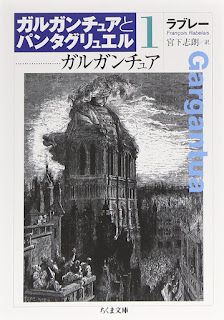天皇はなぜ現人神になったのか。
簡単なようでいて難問である。多くの日本人は漠然と、戦時中の軍部がその無茶な戦いを遂行するために天皇を神にしつらえ、絶対主義体制を作り上げたのだ、と思っている。
しかし生身の人間を神にしつらえるなんて荒唐無稽なことが、軍部の強制だけによってできるはずもない。そこには思想的な地固めとでもいうべきものが、江戸時代以来、長い時間かけて準備されていたのである。
江戸時代の思想的変転の全体像がクリアに概観できるのが渡辺 浩の『日本政治思想史』である。【読書メモ】
『日本政治思想史[十七〜十九世紀]』渡辺 浩 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2017/05/blog-post_11.html
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2017/05/blog-post_14.html
中世になって政権が武家に移ると、天皇の権威は形式的なものになり、江戸時代には名目上のものだけになっていた。江戸時代には天皇は実質的な権力を持っていなかったのである。
これが、幕末にかけてどんどん天皇の権威が高まっていく。しかも不思議なことに、朝廷が何かやって権威が高まったのではない。むしろ朝廷は一貫して何もしていなかったのに、勝手に天皇の権威が高まっていったのだった。そしてそれを演出したのは、皮肉なことに幕府の御用学問たる儒学(朱子学)だったのである。
朱子学は、現実の社会よりも理念的・観念的な——というより、建前的・官僚的な——理屈を推し進め、実際には徳川は武力で政権を握ったのに、「天皇から大政を委任されたから」政権を担っているのだ、と理論化した。そうであるならば、天皇からの信任を失ったら幕府は政権を返上しなくてはならないことになる。ここに「倒幕の思想」が静かに胚胎していた。
朱子学は、元来は統治の学であったのだが、その形式論を推し進めた先に思わぬ変容を遂げたのだ。朱子学は忠君を叫びながら、実際には革命を準備することとなった。
その変容を、儒者たちの文章を丹念に読み込むことで明らかにしたのが山本七平の『現人神の創作者たち』である。【読書メモ】
『現人神の創作者たち』山本 七平 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
儒者たちは、何も最初から革命を考えていたわけではない。それどころか、彼らは民はあくまでも「お上」に忠実でなくてはならないと考え、仮に「お上」が滅ぼうとも忠を貫かなければならないと見なしていた。
その極端な「殉忠の思想」を喧伝したのが、山崎闇斎の弟子浅見絅斎である。浅見絅斎はその著『靖献遺言(せいけんいげん)』で、 政権の存在とは無関係に忠を貫いた人々を描いた。特に、「忠」や「孝」といった個人倫理を貫き通すことに絶対の価値を置いて死を選んだ謝枋得(しゃ・ほうとく)について長大に語り、後に幕末の志士たちが大いに鼓舞されることとなった。浅見絅斎は、統治の学、組織論だったはずの朱子学を個人倫理として再編集したのである。
これこそが、幕末の志士たちが何の役職にも就いていないうちに天下国家を論じる土台でもあった。今であれば、「日本を変えたかったら政治家にでもなれば?」と言われるところを、あくまでも個人倫理としての「忠」や「義」から国政を論じ、行動することを可能にしたのである。
そしてその「忠」の向かうところが、天皇であった。彼らは天皇を絶対化することで徳川幕府を相対化した。自らを天皇の「臣」であると規定することで、幕藩体制から飛び出したのだ。いや、相対化されたのは徳川幕府のみではない。あらゆる階層の人が相対化されていったのだ。
橋川文三は、『ナショナリズム——その神話と論理』で、その相対化によって「国民」が創出される様子を描いた。【読書メモ】
『ナショナリズム──その神話と論理』橋川 文三 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
吉田松陰が水戸学と出会い、歴史を「発見」して、その中心に「忠誠心」を据えたことは、後の日本の行く末を暗示しているようで興味深い。そして「忠誠心」の向かうただ一つの先である天皇に対する「億兆」として、天皇以外の人々が相対化されることになったのである。
そして天皇を超越的な支配者とし、それによって全ての階級を相対化する一種の平等思想が生まれていく。日本における「平等」の概念は、まずは「天皇の前における平等」として構築されたのである。極端に言えば、日本では国民があって、それを統べる者として天皇があったのではない。逆に、天皇がまずあって、それに従うものとして国民が生まれたのである。
とはいっても、明治維新の政策担当者たちが最初から天皇を神として描いていたかというと、そんなことはなかった。
坂本是丸は、『明治維新と国学者』で微に入り細に入り、明治政府における宗教政策を検証している。『明治維新と国学者』阪本 是丸 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/02/blog-post_11.html
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/02/blog-post_13.html
明治政府の宗教政策を担ったのは国学者たちであったが、彼らが目指したのは古代の「天皇親祭にして天皇親政」の体制であった。つまり、天皇自身が神を祀り、同時に政務を執る、という体制だ。彼らにとって天皇は祭祀王であり同時に宰相でもあったということになる。
彼らは、天皇自身が政権を担っていた古代律令制の再現を目指していた。そして彼らの構想は、一時的には実現した。明治2年、太政官の上に「神祇官」が置かれ、「大教宣布の詔」によって神道が国教の地位に据えられた時、彼らが目指した祭政教一致の国家が実現したのである。
しかし国学者たちはそれ以上の構想を持っておらず、時代の変化に合わせて自らの思想を展開させていくことが出来なかった。結局彼らは政権の中枢から体よく遠ざけられ、彼らの理想であった古代律令制は雲散霧消してしまった。
こうして国学者たちの理想は潰えた。表面的には、日本を神の国と見なす狂信的なナショナリズムは修正を余儀なくされ、日本は暫く「万国公法」に従って西洋化に邁進することになる。
ところが国学者たちが政権から遠ざけられてなお、「国学的な態度」はそこに居座り続けていた。本居宣長以来、国学者たちが涵養していた態度だった。
小林秀雄は大著『本居宣長』で、宣長の学問の核心を執拗に追求している。【読書メモ】
『本居宣長(上・下)』小林 秀雄 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
その核心とは、「古代人になりきって古典を読む」ことだ。それは古典に対する正確な読解を行うことを可能にし、『古事記伝』という不朽の業績を成し遂げたが、副作用として、古典に対する一切の批判精神を放棄することをも意味していた。
そしてそれこそが、私には「国学的な態度」の始まりだったと感じられる。『古事記』や 『日本書紀』にどんな荒唐無稽なことが書かれていても、それはそのまま真実であると受け止めなければならないのだ。
このことは、江戸時代の国学者たちにとってすら難しかった。なぜなら、記紀の全てが事実であるはずなどないのだから。実際、本居宣長と上田秋成の間で、神話が事実であるかどうかを巡って「日の神論争」と呼ばれることとなる論争が起こっている。
当時の議論を鑑みると、宣長は非合理なことを主張しており、どう見ても分が悪かった。ところがこの態度が平田篤胤に引き継がれると、神話の世界はこの世とは別のレイヤーに存在しているのだ、という風に変わってくる。篤胤はその世界を「幽冥界」と呼んで実在するものとして扱い、熱意を込めて大量に論述した。
神話を事実として扱う態度は、篤胤によって確立されたと考えて間違いない。
しかしその篤胤ですらも、天皇を神であるとは見なしていない。それどころか篤胤は、天皇も死ねば幽冥界に赴き、幽冥界の主宰神であるオオクニヌシの審判を受けるものと考えた。篤胤の天皇観と現人神とはかなりの距離があった。
実際、明治の政策担当者たちも、誰一人として天皇を神にしつらえるプランは持っていなかった。それなのに、天皇はどんどん神に近づいていった。天皇が神になったのは、誰かの意図した結果ではなかったというのは確実である。
ただ、今の私には天皇が現人神になっていくその過程を説明する力がない。
一つ言えることは、明治後期から大正・昭和初期にかけて現人神という観念が確立してゆくが、それが「国体」の観念と並行して構築されていった、ということである。
そしてそれは、思想的あるいは宗教的に構築されたものではなく、行政的に、もっとあけすけに言えば「内務省的」に出来ていった。
そういう過程は、向坂逸郎編『嵐のなかの百年』に窺うことが出来る。
【読書メモ】
『嵐のなかの百年—学問弾圧小史』向坂 逸郎 編著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/06/blog-post_23.html
本書は明治から昭和初期にかけての学問・言論への弾圧がどのように行われたかを述べたもので、その中には、重野安繹、久米邦武、喜田貞吉、津田左右吉のケースが取り上げられている。こうした学者たちの、学問的に穏当で至極妥当な書物がひとたび右翼主義者の注目するところとなるや盛んに攻撃が加えられ、「国体を毀損する」「国体の明徴に疑義を生ぜしめる」などといって学説が危険なものであると喧伝された。
そして神聖不可侵な「国体」と、その中心にいる神としての天皇=現人神が出現したのである。それは内務官僚と右翼主義者、国粋主義者たちの、なりゆきまかせの共同作業であった。
であるから、戦後、GHQは国家神道を解体し、また天皇の人間宣言はなされたが、誰一人として東京裁判では「天皇を神にしつらえた罪」には問われていない。もちろん、誰か一人をその罪で裁くことは不可能だったし、おそらく連合国にはその意図も無かったのだろう。
しかし、明治以降の日本が、世界征服までも考えて狂信的な軍事国家となっていったその背景には、確実に「神の国」観念があったし、その国を統べる現人神の存在があったのである。
21世紀に、再び天皇が現人神になることは、おそらくないだろう。それでも、なぜ天皇を現人神にしてしまったのか、その反省をちゃんとしないことには、同じような間違いが起こらないとも限らない、と思うのである。
【最後に宣伝】
明治政府が神話を現実化していく過程を、薩摩藩の動向を中心として描いた拙著が2022年6月に刊行されます。上述のような議論も(ただし幕末のみですが)詳しく論述しています。ぜひよろしくお願いします。↓Amazonのページ
https://amzn.to/3LLLnfw
明治政府は、いかにして神話を現実化したのか? その背景には薩摩藩の動向が大きく関わっていた。宮内庁が公認する「神」の墓=神代三陵を巡る幕末明治の宗教行政史を読み解き、神話が歴史へと変換されていった様相を描く。