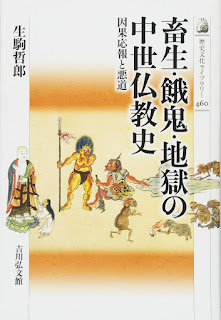墓石によって江戸時代の社会を考察する本。
古代や中世の墓石は芸術性も高く文化財として保護されているものも多いが、江戸時代の墓石は特に貴重なものともみなされず、むしろ無縁仏として整理される対象であり、打ち捨てられてきた。
しかし著者は江戸時代の墓石によって当時の社会を考察することが出来ると主張する。大量の墓石を悉皆調査することでだ。
確かに江戸時代の墓石は(大名墓などを除いて)立派な文化財ではない。しかしそれは逆に言えば、名もない庶民も墓石を造立したということである。古代や中世の墓石がごく限られた社会の上流だけのものであったのに、江戸時代の墓石は全階層的なものであった。江戸時代後期には全国的に半数近くの人々が墓石を建てていたと見られる。だからそれを悉皆調査すれば、社会の有りさまがかなりわかってくるのである。
著者は弘前大学に赴任した際に松前を中心に墓石調査を行った。江戸時代の最北端の城下町である。この辺境の地でも、墓石はかなり造立された。この他著者は交易地を中心に墓石の調査を行っている。それによりわかるのは、歴史人口学(人口の推計)、飢饉の際に死亡した人の推計、社会階層の分析、家族のあり方の変遷、街の盛衰といったものだ。
しかしながら、そうした墓石の悉皆調査による考察は、墓石をデータとしてみるものであるから、参考にはなるがやや味気ないものだ。それよりも面白いのは、やはり墓石一つひとつを見ていくことである。例えば面白い戒名「米汁呑了信士」(ふざけているのか?)、個性的な墓石(挽き臼の形)など見ていて飽きない。
江戸時代から現代まではほとんどの人が墓石を造立した時代であり、古墳が造立された時代を「古墳時代」と呼ぶのなら、「墓石時代」と呼んでもいいのではないかと著者は提案する。墓石時代が到来した理由を著者は6つに整理している。(1)直系家族からなる世帯の形成、(2)儒教思想に基づく祖先祭祀の浸透、(3)寺檀制度の確立、(4)読み書きの普及に伴う文字文化の成熟、(5)海上交通網の整備による石材の遠距離輸送の実現、(6)石工の全国的拡散、である。
しかし現代は樹木葬や散骨など、墓石を敢えて造立しない葬送が一般化しつつある。人口減少時代にあって、墓を見る子孫がいない、墓参りが負担になる、家族像が変化しているといった理由からだ。墓石時代は今終わろうとしているのかもしれない。
墓石を通じて社会を見る視点が独特な本。
2019年12月31日火曜日
2019年12月29日日曜日
『石仏・石の神を旅する』吉田さらさ 著・宮本 和義 写真
全国の石仏のガイドブック。
本書は学術書でもエッセイでもなく、全国の見応えのある石仏(と神像もちょっと)をキレイな写真付きで紹介する本である。
そこに紹介されているのは、学術的に貴重であるとかいうよりも、まずは見て楽しい、感動する、驚くといったものである。いわば本書は石仏の入門書であって、それぞれについても詳細な考察があるでもなく、ごくあっさりと紹介されている。
しかし石仏だけを選んで紹介している本というのは少ないので本書の存在は貴重だ。見応えのある仏像を選んで紹介している本は多いが、本書の特色はまさに「石」という材質に注目してセレクションしたところだ。
石仏は寺の中にあるものもあるが、路傍にあったり磨崖仏であったり、誰でも自由に見ることができるものが多いのが特色だ。当然、写真撮影も自由である。それが旅との相性の良さだと思う。本書は単なる石仏紹介本ではなく、旅のガイドブック的に書いてあって、石仏を見に旅に出たくなる。
ただ、本書は全国を網羅しているわけではなく、あくまでも著者なりの視点で選んだものであるし、それに全く訪問していない地域も多そうである(例えば鹿児島には来ていないようだ)。体系的に石仏の紹介をする本ではないのでそれで全く問題はないが、2倍くらいの分量があったらもっと面白い本になったと思う。
石仏の世界を気軽に旅する本。
本書は学術書でもエッセイでもなく、全国の見応えのある石仏(と神像もちょっと)をキレイな写真付きで紹介する本である。
そこに紹介されているのは、学術的に貴重であるとかいうよりも、まずは見て楽しい、感動する、驚くといったものである。いわば本書は石仏の入門書であって、それぞれについても詳細な考察があるでもなく、ごくあっさりと紹介されている。
しかし石仏だけを選んで紹介している本というのは少ないので本書の存在は貴重だ。見応えのある仏像を選んで紹介している本は多いが、本書の特色はまさに「石」という材質に注目してセレクションしたところだ。
石仏は寺の中にあるものもあるが、路傍にあったり磨崖仏であったり、誰でも自由に見ることができるものが多いのが特色だ。当然、写真撮影も自由である。それが旅との相性の良さだと思う。本書は単なる石仏紹介本ではなく、旅のガイドブック的に書いてあって、石仏を見に旅に出たくなる。
ただ、本書は全国を網羅しているわけではなく、あくまでも著者なりの視点で選んだものであるし、それに全く訪問していない地域も多そうである(例えば鹿児島には来ていないようだ)。体系的に石仏の紹介をする本ではないのでそれで全く問題はないが、2倍くらいの分量があったらもっと面白い本になったと思う。
石仏の世界を気軽に旅する本。
『板碑と石塔の祈り』千々和 到 著
板碑を中心として石塔の世界を紹介する本。
日本では大規模な石造構造物はほとんど存在していないが、石塔については数多く残っており、特にそれが庶民的なものであるだけに当時の信仰を窺わせる格好の遺物となっている。
ではそうした石塔はどのように造立されたか。石塔と言えば五輪塔、宝篋印塔、 層塔、宝塔、多宝塔、無縫塔、板碑があるが、これらは層塔を除いて平安時代後期から鎌倉時代初期、1200年前後の70年間ほどに現れる。そしてそれまでの仏塔とは、仏舎利を安置する礼拝の対象であったが、仏塔は墓塔の性格を持つようになるのである。
さらにこれらの石塔は最初は社会の上流の人々が極楽往生を願って造立するものであったが、15世紀半ばにはそれが農民や町人など多様な人々によって、しかも現世利益など多様な願いを託して作られるようになった。例えば「一石五輪塔」がそういうもので、これは一つの石を五輪塔の形に刻んだもので、製造コストを抑えた既製品が利用されていたそうだ。
著者はそうした石塔の中でも特に板碑に関心を持ち、板碑についてやや詳しく紹介している。板碑は関東で多く作られたもので、本書ではいくつかの板碑についてケーススタディ的に取り上げられている。「誰が何のために造立したのか」「当初の姿はどうだったのか」といったことを一つひとつ探っていくことで、当時の信仰や社会のあり方を知ることができるのである。
板碑の世界の手軽な入門書。
【関連書籍の読書メモ】
『中世の板碑文化』播磨 定男 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2020/09/blog-post_24.html
板碑の世界を概観する本。板碑の世界を手軽に俯瞰できる良書。
2019年12月27日金曜日
『石造物が語る中世職能集団』山川 均 著
宝篋印塔の起源を考察する本。
従来、宝篋印塔は「銭弘淑八万四千塔」をモデルとして日本で創作されたものと考えられてきた。しかし近年、大陸にも宝篋印塔が見つかったことから、大陸の宝篋印塔を模して作られたものだとする説が濃厚になった。ではこれを輸入し、制作したのは誰なのか。
著者は様々な理由から、日本における最初期の宝篋印塔「高山寺宝篋印塔」(1239年)の発願者を證月房慶政であり、その制作者を宋人石工、伊 行末(いの・ゆきすえ)であると推測する。慶政は京都の西山法華山寺を創建した天台宗の僧侶であり、伊 行末は、重源が大仏再興にあたって宋から招聘した石工である。
慶政は、自身が宋に留学しており、泉州近辺で宝篋印塔を見た可能性がある。その記憶に基づいて伊氏に日本版宝篋印塔を制作させたというのである。そして伊氏は代々石工となり、「伊派石工」を形成。またその分派の大蔵氏も「大蔵派石工」として活躍した。
このように1230年代に登場した宝篋印塔は、その後空白をおいて1260年前後に再度あらわれ、また空白期があった後1290年代以降に数多く作られるようになる。この1260年前後に作られた初期宝篋印塔については、律僧の忍性との関連が深く、伊派・大蔵派の石工によるものと考えられると言うことだ。
なお忍性の師にあたる叡尊は、非人や遊女、漁民などのために層塔をいくつか造立しているが、これも伊派石工によるものと見られる。また彼らは非常に完成度の高い五輪塔も造立した。
このように大陸に出自を持つ伊派・大蔵派という2つの職能集団は、100年あまりの間に中世における石塔造営に大きな影響を及ぼし、特に宝篋印塔の像容を確立させた。しかし彼らは忍性没後もしばらく活動を続けていたものの、大蔵派は鎌倉幕府の滅亡とともに途絶え、伊派も徐々に衰退して1350年代には存在が確認できなくなる。なぜ優秀な石工集団だったにもかかわらず両派が衰微してしまったのかは謎である。
宝篋印塔の成立事情を伊派・大蔵派の動向によって推測した意欲作。
従来、宝篋印塔は「銭弘淑八万四千塔」をモデルとして日本で創作されたものと考えられてきた。しかし近年、大陸にも宝篋印塔が見つかったことから、大陸の宝篋印塔を模して作られたものだとする説が濃厚になった。ではこれを輸入し、制作したのは誰なのか。
著者は様々な理由から、日本における最初期の宝篋印塔「高山寺宝篋印塔」(1239年)の発願者を證月房慶政であり、その制作者を宋人石工、伊 行末(いの・ゆきすえ)であると推測する。慶政は京都の西山法華山寺を創建した天台宗の僧侶であり、伊 行末は、重源が大仏再興にあたって宋から招聘した石工である。
慶政は、自身が宋に留学しており、泉州近辺で宝篋印塔を見た可能性がある。その記憶に基づいて伊氏に日本版宝篋印塔を制作させたというのである。そして伊氏は代々石工となり、「伊派石工」を形成。またその分派の大蔵氏も「大蔵派石工」として活躍した。
このように1230年代に登場した宝篋印塔は、その後空白をおいて1260年前後に再度あらわれ、また空白期があった後1290年代以降に数多く作られるようになる。この1260年前後に作られた初期宝篋印塔については、律僧の忍性との関連が深く、伊派・大蔵派の石工によるものと考えられると言うことだ。
なお忍性の師にあたる叡尊は、非人や遊女、漁民などのために層塔をいくつか造立しているが、これも伊派石工によるものと見られる。また彼らは非常に完成度の高い五輪塔も造立した。
このように大陸に出自を持つ伊派・大蔵派という2つの職能集団は、100年あまりの間に中世における石塔造営に大きな影響を及ぼし、特に宝篋印塔の像容を確立させた。しかし彼らは忍性没後もしばらく活動を続けていたものの、大蔵派は鎌倉幕府の滅亡とともに途絶え、伊派も徐々に衰退して1350年代には存在が確認できなくなる。なぜ優秀な石工集団だったにもかかわらず両派が衰微してしまったのかは謎である。
宝篋印塔の成立事情を伊派・大蔵派の動向によって推測した意欲作。
2019年12月25日水曜日
『古寺巡礼』和辻 哲郎 著
奈良の古刹見聞記。
和辻哲郎はこの見聞記をどのような気持ちで書いたのだろう。内容は恬淡としたもので、訪問した寺の先々で寺院建築や仏像の素晴らしさに感激し、またその故事来歴に思いをいたすというものである。特に西域からの文化交渉、ギリシア的なるものの東洋的変容、日本的変容については頻繁に洞察されている。
しかし本書は、どうやらそうした考察を展開するためにかかれたものではなさそうだ。いわば「手慰み」といった雰囲気が漂っているのである。実際本書は刊行するために書いたものではないらしい。そしてそれが却って清新な魅力を生み、本書は寺院観賞の一つの基本的態度さえも形作った。
その態度は、仏像や寺院建築を美術品として観賞しながら、しかも宗教的意味合いを閑却せず、文化史的な知識を用いて読み解くというものである。日本の仏教美術を「発見」したフェノロサや岡倉天心があくまでそれを美術品として見ていたのと違い、そこに信仰の持つ意味合いを加味したのが和辻の新味であった。
しかし和辻は、仏教美術を信仰の対象として見ながらも、「これは有り難い仏さまだ」といった宗教的な感興を極力廃しているように見える。書名に「巡礼」とあるにも関わらず巡礼的態度は微塵もない。和辻は信仰の対象としては少し距離を置きつつ、「日本とは何か」というテーマの下に仏教美術を解きほぐそうとした。フェノロサや岡倉天心が「美術」としてそれらを見たとすれば、和辻は「研究対象」としてそれを見ていた。
そうでありながら、研究書としてではなく、エッセイとして書かれたということが本書の価値であったと思う。ここには大上段の文化論はないが、鋭い考察に基づいた「感性の日本論」がある。
古寺巡礼で描き出した日本論。
【関連書籍】
『西域文明史概論・西域文化史』羽田 亨 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2020/02/blog-post.html
西域の文明および文化の概論。和辻がたびたび言及する西域の仏教美術の概説も知れる。
和辻哲郎はこの見聞記をどのような気持ちで書いたのだろう。内容は恬淡としたもので、訪問した寺の先々で寺院建築や仏像の素晴らしさに感激し、またその故事来歴に思いをいたすというものである。特に西域からの文化交渉、ギリシア的なるものの東洋的変容、日本的変容については頻繁に洞察されている。
しかし本書は、どうやらそうした考察を展開するためにかかれたものではなさそうだ。いわば「手慰み」といった雰囲気が漂っているのである。実際本書は刊行するために書いたものではないらしい。そしてそれが却って清新な魅力を生み、本書は寺院観賞の一つの基本的態度さえも形作った。
その態度は、仏像や寺院建築を美術品として観賞しながら、しかも宗教的意味合いを閑却せず、文化史的な知識を用いて読み解くというものである。日本の仏教美術を「発見」したフェノロサや岡倉天心があくまでそれを美術品として見ていたのと違い、そこに信仰の持つ意味合いを加味したのが和辻の新味であった。
しかし和辻は、仏教美術を信仰の対象として見ながらも、「これは有り難い仏さまだ」といった宗教的な感興を極力廃しているように見える。書名に「巡礼」とあるにも関わらず巡礼的態度は微塵もない。和辻は信仰の対象としては少し距離を置きつつ、「日本とは何か」というテーマの下に仏教美術を解きほぐそうとした。フェノロサや岡倉天心が「美術」としてそれらを見たとすれば、和辻は「研究対象」としてそれを見ていた。
そうでありながら、研究書としてではなく、エッセイとして書かれたということが本書の価値であったと思う。ここには大上段の文化論はないが、鋭い考察に基づいた「感性の日本論」がある。
古寺巡礼で描き出した日本論。
【関連書籍】
『西域文明史概論・西域文化史』羽田 亨 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2020/02/blog-post.html
西域の文明および文化の概論。和辻がたびたび言及する西域の仏教美術の概説も知れる。
2019年12月21日土曜日
『仏と女(シリーズ 中世を考える)』西口 順子 編
仏教における女性のあり方を考える論文集。
例えば高野山や比叡山は女人禁制であった。僧は、女性を近づけてはいけない。また女性は五障三従の身と考えられた(「五障三従」とは、女性は生まれながらに罪深く、男性に従属して生きる存在だ、という仏教の考え方)。さらに女性は往生(浄土へ行く)ができないため、一度男性に生まれ変わってから往生するという「変成男子(へんじょうなんし)」という考え方も生まれた。
歴史的存在としてのブッダが説いた仏教では女性を対等に扱っていたのだが、いつしか仏教の教えは女性を斥けるものとなっていた。ところが中世において、女性は仏教的活動にたくさん参画していたのである。もちろん尼僧の数は僧侶に比べて少なく、また大寺院の住持のような社会的頂点には女性はいなかった。しかし様々な面で中世仏教は女性の存在に負うものも多かったのである。本書は、そうした女性と仏教の関係について7つの論文を収める。
1 貴族女性の信仰生活(小原 仁):中御門家の一条尼は、日夜熱心に勤行を行い浄土へ往生したと見なされた。九条家では家の枢要な財産(最勝金剛院)が女性によっても相続され、家の仏事は女性によって取り計らわれていた。仏教の建前としては女性は「五障三従」の身であったが、実態としては貴族の信仰生活を主導したのは女性であった。
2 女の死後とその救済(勝浦 令子): 男性に比べ女性は地獄に落ちやすいものと考えられ、特に母の堕地獄を救済する信仰が生まれた。また女性自身も堕地獄を避けるために積極的にさまざまな信仰活動を行った。しかし女性は女性であるだけで罪とされたり、子を養育する罪(養育には絶対に殺生が伴うため)が女性だけに課せられていたことなど、当時の仏教は男女差別的と言うほかない。
3 法然の念仏と女性(今堀 太逸):法然の浄土宗では、念仏によって往生できると教えたが、であれば女性も念仏によって往生できるのか。著者は当時の資料を詳細に分析して「女人往生」思想を辿っている。その結果、法然は女人往生を語っていたとされるがそれは伝説であり、法然の女人教化譚が成立したのは、法然没後百年以上経ってから作成された『法然上人行状絵図』においてであることが明らかになった。
4 絵系図の成立と仏光寺・了明尼教団(遠藤 一):初期真宗教団は親鸞・恵信尼夫妻とその子を中心とした家族経営組織によって形成されたが、そうしたやり方を継承したのが武蔵国の仏光寺教団だった。その絵系図を見ると、夫と妻が一対として扱われており、この教団では夫婦が基本単位とされていたことが窺える。さらに了明尼は夫の死後、実施的に住持の立場となった。女性に高い地位を与えた仏光寺は興隆し、当時の山門(延暦寺)から本願寺よりもむしろ真宗の代表と見なされた。坊主・坊守という住職夫妻が寺院を管理していく今の真宗のあり方は、本願寺よりも仏光寺の方が体現していた。
5 女人と禅宗(原田 正俊):中世においては特に禅宗と律宗の尼の活動が盛んであった。曹洞宗では少数ながら男性と対等に扱われた尼が輩出。臨済宗では「尼五山」が設けられ、五山と似たようなシステムがあった。従来、尼五山は行き場のない上流階級の女性が自らの意志とは関係なく収容される場所であったと考えられていた。確かにそういう面はあり、女性は僧衆たちの下にあったことも事実だが、自主的に参禅し得法(悟り)を目指した女性もいた。彼女たちは無学祖元に参じた無外如大(尼僧)を理想像として仰いだ。また臨済宗では五山派以外にも大徳寺派で尼・尼寺が多かった。中国の語録では尼達が男性僧侶と対等に扱われていたから、禅宗では女性を宗教的に無視できなかったのである。禅思想は女性にとって、顕密仏教(当時の支配体制側仏教)のイデオロギーを覆す拠り所となりえた。
6 尼の法華寺と僧の法華寺(大石 雅章):古代の国分尼寺だった法華寺は衰退していたが、叡尊によって律宗の寺院として生まれ変わる。法華寺では尼、尼に準じる存在、近住女など200名を超える様々な女性が積極的に活動した。しかし15世紀初頭には法華寺は「比丘尼御所」となっていた。「比丘尼御所」とは、天皇家・将軍家・摂関家など貴種の子女が入寺する尼寺で、幕府の丸抱え経営であって御所的形態をとり、門跡寺院と同等の存在である。宮廷文化の衰退に伴って、将来結婚が期待できない未婚の子女にとっての宮廷に代わる居場所として形成されたものである。
7 女性と亡者忌日供養(西口 順子):親族の忌日供養は中世仏教の中心であった。従来、忌日供養は女性の手によるものとの認識があったが、実際には男性も忌日供養を行っており女性だけが営んだものではない。しかし貴族において近親の女性が尼となり一族の供養を行うことはよくあることだった。女性は往生できないとの説や「五障三従説」などは理念的に存在していたとはいえ、当の女性自身はそうした言説をあまり真に受けていなかったと思われるフシがある。
全体を通じて、中世の仏教において女性がどのように扱われていたのかというのが、意外とよく分かっていないことが痛感させられた。確かに中世仏教は女性差別的であった。しかし仏事の中心には女性がいたし、貴種の女性は寺院の荘園の相続人として莫大な財産を管理していたりもした。社会の中の女性のあり方自体が、今とはだいぶ異なっていたのに、「尼は僧に従属させられていたからこうだったに違いない」というような思い込みで尼・尼寺の有り様が誤解されていたことも多いらしい。
私自身は、中世仏教への関心というより、中世における女性のあり方を知りたいという思いで本書を手に取った。しかし読み進めるうちに、「中世仏教はどうして女性差別的になってしまったのだろう」ということの関心が移った。
中世において女性は男性と対等な財産権を持っていたし、しばしば家督を相続した。また家の仏事の中心的役割を果たしていた。そして古代の仏教では僧・尼は対等とはいえないまでも差別的な扱いはなかったし、中国の禅宗でも尼が活躍していた。それなのに中世仏教はなぜ「五障三従」や「変成男子」といった女性差別的な言説を展開させていったのか? それが不思議なのだ。
中世仏教の女性のあり方を様々な事例から紐解く真面目な本。
例えば高野山や比叡山は女人禁制であった。僧は、女性を近づけてはいけない。また女性は五障三従の身と考えられた(「五障三従」とは、女性は生まれながらに罪深く、男性に従属して生きる存在だ、という仏教の考え方)。さらに女性は往生(浄土へ行く)ができないため、一度男性に生まれ変わってから往生するという「変成男子(へんじょうなんし)」という考え方も生まれた。
歴史的存在としてのブッダが説いた仏教では女性を対等に扱っていたのだが、いつしか仏教の教えは女性を斥けるものとなっていた。ところが中世において、女性は仏教的活動にたくさん参画していたのである。もちろん尼僧の数は僧侶に比べて少なく、また大寺院の住持のような社会的頂点には女性はいなかった。しかし様々な面で中世仏教は女性の存在に負うものも多かったのである。本書は、そうした女性と仏教の関係について7つの論文を収める。
1 貴族女性の信仰生活(小原 仁):中御門家の一条尼は、日夜熱心に勤行を行い浄土へ往生したと見なされた。九条家では家の枢要な財産(最勝金剛院)が女性によっても相続され、家の仏事は女性によって取り計らわれていた。仏教の建前としては女性は「五障三従」の身であったが、実態としては貴族の信仰生活を主導したのは女性であった。
2 女の死後とその救済(勝浦 令子): 男性に比べ女性は地獄に落ちやすいものと考えられ、特に母の堕地獄を救済する信仰が生まれた。また女性自身も堕地獄を避けるために積極的にさまざまな信仰活動を行った。しかし女性は女性であるだけで罪とされたり、子を養育する罪(養育には絶対に殺生が伴うため)が女性だけに課せられていたことなど、当時の仏教は男女差別的と言うほかない。
3 法然の念仏と女性(今堀 太逸):法然の浄土宗では、念仏によって往生できると教えたが、であれば女性も念仏によって往生できるのか。著者は当時の資料を詳細に分析して「女人往生」思想を辿っている。その結果、法然は女人往生を語っていたとされるがそれは伝説であり、法然の女人教化譚が成立したのは、法然没後百年以上経ってから作成された『法然上人行状絵図』においてであることが明らかになった。
4 絵系図の成立と仏光寺・了明尼教団(遠藤 一):初期真宗教団は親鸞・恵信尼夫妻とその子を中心とした家族経営組織によって形成されたが、そうしたやり方を継承したのが武蔵国の仏光寺教団だった。その絵系図を見ると、夫と妻が一対として扱われており、この教団では夫婦が基本単位とされていたことが窺える。さらに了明尼は夫の死後、実施的に住持の立場となった。女性に高い地位を与えた仏光寺は興隆し、当時の山門(延暦寺)から本願寺よりもむしろ真宗の代表と見なされた。坊主・坊守という住職夫妻が寺院を管理していく今の真宗のあり方は、本願寺よりも仏光寺の方が体現していた。
5 女人と禅宗(原田 正俊):中世においては特に禅宗と律宗の尼の活動が盛んであった。曹洞宗では少数ながら男性と対等に扱われた尼が輩出。臨済宗では「尼五山」が設けられ、五山と似たようなシステムがあった。従来、尼五山は行き場のない上流階級の女性が自らの意志とは関係なく収容される場所であったと考えられていた。確かにそういう面はあり、女性は僧衆たちの下にあったことも事実だが、自主的に参禅し得法(悟り)を目指した女性もいた。彼女たちは無学祖元に参じた無外如大(尼僧)を理想像として仰いだ。また臨済宗では五山派以外にも大徳寺派で尼・尼寺が多かった。中国の語録では尼達が男性僧侶と対等に扱われていたから、禅宗では女性を宗教的に無視できなかったのである。禅思想は女性にとって、顕密仏教(当時の支配体制側仏教)のイデオロギーを覆す拠り所となりえた。
6 尼の法華寺と僧の法華寺(大石 雅章):古代の国分尼寺だった法華寺は衰退していたが、叡尊によって律宗の寺院として生まれ変わる。法華寺では尼、尼に準じる存在、近住女など200名を超える様々な女性が積極的に活動した。しかし15世紀初頭には法華寺は「比丘尼御所」となっていた。「比丘尼御所」とは、天皇家・将軍家・摂関家など貴種の子女が入寺する尼寺で、幕府の丸抱え経営であって御所的形態をとり、門跡寺院と同等の存在である。宮廷文化の衰退に伴って、将来結婚が期待できない未婚の子女にとっての宮廷に代わる居場所として形成されたものである。
7 女性と亡者忌日供養(西口 順子):親族の忌日供養は中世仏教の中心であった。従来、忌日供養は女性の手によるものとの認識があったが、実際には男性も忌日供養を行っており女性だけが営んだものではない。しかし貴族において近親の女性が尼となり一族の供養を行うことはよくあることだった。女性は往生できないとの説や「五障三従説」などは理念的に存在していたとはいえ、当の女性自身はそうした言説をあまり真に受けていなかったと思われるフシがある。
全体を通じて、中世の仏教において女性がどのように扱われていたのかというのが、意外とよく分かっていないことが痛感させられた。確かに中世仏教は女性差別的であった。しかし仏事の中心には女性がいたし、貴種の女性は寺院の荘園の相続人として莫大な財産を管理していたりもした。社会の中の女性のあり方自体が、今とはだいぶ異なっていたのに、「尼は僧に従属させられていたからこうだったに違いない」というような思い込みで尼・尼寺の有り様が誤解されていたことも多いらしい。
私自身は、中世仏教への関心というより、中世における女性のあり方を知りたいという思いで本書を手に取った。しかし読み進めるうちに、「中世仏教はどうして女性差別的になってしまったのだろう」ということの関心が移った。
中世において女性は男性と対等な財産権を持っていたし、しばしば家督を相続した。また家の仏事の中心的役割を果たしていた。そして古代の仏教では僧・尼は対等とはいえないまでも差別的な扱いはなかったし、中国の禅宗でも尼が活躍していた。それなのに中世仏教はなぜ「五障三従」や「変成男子」といった女性差別的な言説を展開させていったのか? それが不思議なのだ。
中世仏教の女性のあり方を様々な事例から紐解く真面目な本。
2019年12月17日火曜日
『オーパ!』開高 健 著・ 高橋 昇 写真
アマゾン川の釣りルポ。
本書は、『PLAYBOY』誌の企画で開高 健 氏がアマゾン川で釣りをして書いたルポ・紀行文・エッセイである。
「オーパ!」とは、現地の言葉で驚いた時に口に出る「わお!」や「おやまあ!」みたいな言葉で、アマゾン川は兎にも角にも驚異に満ちている。世界最大の淡水魚ピラルクー、ほとんど神のごとく偏在している猛魚ピラーニャ、驚異的な引きが楽しめる黄金の魚トラド、アマゾン川は全てが桁外れであり、そしてそこに生きる文化も極端で豪放磊落であり、時に神話的ですらある。
本書は、基本的には釣りの体験記である。どこそこに行って何をどうして釣った、ということが書かれる。ただし、餌がなんだとか、仕掛けがどうしたというような細かい話は出ない。むしろ釣りをする中で著者が体験した「驚異」を中心に話は進む。といってもアマゾンの自然誌を語ろうとするものでもないし、ブラジルの文化誌を述べようというのでもない。そうした大上段の見方を敢えて排して、身の丈に合った体験記に留めようとしているように見える。
しかしさすが文学者の著者だけあって、文章は非常に妙味がある。元来釣りの紀行文というものは文学の一角をなすものではあるが、これは恬淡とした日本の釣り文学とは全く違う、絢爛な新しい釣り文学であると感じた。
それにしても、かつては『PLAYBOY』誌がこうした企画を実行し得たということに、今となっては驚きを禁じ得ない。
桁外れの釣り紀行。
本書は、『PLAYBOY』誌の企画で開高 健 氏がアマゾン川で釣りをして書いたルポ・紀行文・エッセイである。
「オーパ!」とは、現地の言葉で驚いた時に口に出る「わお!」や「おやまあ!」みたいな言葉で、アマゾン川は兎にも角にも驚異に満ちている。世界最大の淡水魚ピラルクー、ほとんど神のごとく偏在している猛魚ピラーニャ、驚異的な引きが楽しめる黄金の魚トラド、アマゾン川は全てが桁外れであり、そしてそこに生きる文化も極端で豪放磊落であり、時に神話的ですらある。
本書は、基本的には釣りの体験記である。どこそこに行って何をどうして釣った、ということが書かれる。ただし、餌がなんだとか、仕掛けがどうしたというような細かい話は出ない。むしろ釣りをする中で著者が体験した「驚異」を中心に話は進む。といってもアマゾンの自然誌を語ろうとするものでもないし、ブラジルの文化誌を述べようというのでもない。そうした大上段の見方を敢えて排して、身の丈に合った体験記に留めようとしているように見える。
しかしさすが文学者の著者だけあって、文章は非常に妙味がある。元来釣りの紀行文というものは文学の一角をなすものではあるが、これは恬淡とした日本の釣り文学とは全く違う、絢爛な新しい釣り文学であると感じた。
それにしても、かつては『PLAYBOY』誌がこうした企画を実行し得たということに、今となっては驚きを禁じ得ない。
桁外れの釣り紀行。
2019年12月16日月曜日
『中世奇人列伝』今谷 明 著
中世における、知られざる6人の小伝。
本書に収められているのは、一般的な歴史書ではほとんど看過される人物であるが、型破りの人生を生きた人ばかりである。「奇人」とはいっても「変わった人」のことではなく、数奇な運命を辿った人のことだ。
歴史書というのは面白いもので、同時代に大きな存在感があった人でも、何らかのことでその重要人物が省略され、後続の歴史書でもそれが踏襲されてほとんど顧みられぬままになっていることがある。本書が収録する6人は、そういう過小評価が続いてきた人たちだ。その6人は次の通り。
法印尊長:尊長は頼朝との血縁から出世し、寺院社会の中でも最高位に上り詰めた。厖大な天皇家荘園が寄進されていた法勝寺の執行を始め、蓮華王院、歓喜光院等の歴代上皇の御願寺の執行、備前の任国司までにもなって、彼の元には全国から財宝が集まった。後鳥羽上皇の信が篤かった尊長は、承久の乱の黒幕となったが乱は幕府から鎮圧され逃亡。最後は捕らえられて壮絶な死を遂げた。
京極為兼:伏見天皇の腹心であり、一流の歌人でもあった為兼は興福寺の騒動(永仁の南都闘乱)に巻き込まれて失脚したが復活。勅撰和歌集『玉葉和歌集』は為兼の独撰となった。晩年には再び失脚して配流され、その業績は以後顧みられることはなかった。
雪村友梅:一山一寧の侍童で聡明だった友梅は中国へ留学するが、日元関係の悪化から捕らえられ長年にわたり中国で幽囚生活を送る。しかし斬首されかけた際に詠んだ「臨剣頌(りんけんじゅ)」が友梅の作とされるほど(本当は無学祖元作)中国でもその学識は認められ、帰国後は各地の名刹の住持を歴任した。
広義門院(西園寺寧子):南北朝の動乱の渦中にいた広義門院は、後伏見天皇の妻であり、花園天皇の准母(名義上の母)であり、また後に光厳天皇と光明天皇も生んだ。南朝が北朝の三上皇・皇太子を拉致し、三種の神器を奪ったことで幕府により北朝の中心として担ぎ出される。幕府は北朝に天皇がいないという異常事態に直面し、上皇后によって天皇の権能が代行できると解釈、さらに「天下同一法」という人事・官位等の全てを過去に遡らせるという大奇策によって切り抜けた。広義門院はこれらの策を実行するための名目上の登場かに思われたが、その権力は実質化し、あらゆる政治の決定に関与、文和2年(1353)には政務を後光厳天皇に譲ったものの、長講堂領、法金剛院領、今出川領という天皇家領荘園の全てを所有し続け、北朝の家督者として死ぬまで重きをなした。
願阿弥:時衆の僧で、著名な勧進聖であった願阿弥は、寛正の大飢饉で京が難民と死体で溢れるや、勧進(募金)を募って難民収容所を開設し人々を救った(しかし多くは収容の甲斐なく死亡したという)。18年後、応仁の乱後には、消失していた清水寺の再建に取り組んで諸国を勧進に巡り成功させた。この背景には、清水寺の参拝者を宛てに生活していた清水坂の乞食非人たちの救済があったと考えられるという。
足利義稙(よしたね):足利義視の子である義稙は、義視・義政という父世代の対立がありながらも、義政の子義尚が若くして陣没したことで棚ぼた的に将軍に就任する。ところが政権を牛耳っていた日野富子と不仲になり、細川政元らがクーデターを起こし幽閉された。脱出後、大内義興の力を借りて将軍に返り咲いたものの、お人好しの義稙には政権運営能力はなく、かつての腹心細川高国との確執から逐電し逃げ延びた撫養(むや:鳴門市)で病没した。武家で将軍を再任したのは彼だけである。
著者自身が後書きで書いているように、本書に取り上げられた6人のうち義稙を除く5人が法体(ほったい:出家後の姿)で生涯を終えている。しかし専門的宗教家と呼べるのは雪村友梅だけである。中世においては、人は晩年には出家するのが普通だったし、また法体であることに各種の便宜があった時代だったからだという。本書の中心テーマではないが中世における出家の意味を改めて考えさせられた。
また、6人の中で私が最も興味を抱いたのは広義門院。幕府によって担ぎ出されたのにもかかわらず、その権力が実質化した過程を知りたくなった(本書ではごく簡単に書いている)。
歴史書ではあまり語られない人物を題材に、いろいろな角度から中世を知れる良書。
本書に収められているのは、一般的な歴史書ではほとんど看過される人物であるが、型破りの人生を生きた人ばかりである。「奇人」とはいっても「変わった人」のことではなく、数奇な運命を辿った人のことだ。
歴史書というのは面白いもので、同時代に大きな存在感があった人でも、何らかのことでその重要人物が省略され、後続の歴史書でもそれが踏襲されてほとんど顧みられぬままになっていることがある。本書が収録する6人は、そういう過小評価が続いてきた人たちだ。その6人は次の通り。
法印尊長:尊長は頼朝との血縁から出世し、寺院社会の中でも最高位に上り詰めた。厖大な天皇家荘園が寄進されていた法勝寺の執行を始め、蓮華王院、歓喜光院等の歴代上皇の御願寺の執行、備前の任国司までにもなって、彼の元には全国から財宝が集まった。後鳥羽上皇の信が篤かった尊長は、承久の乱の黒幕となったが乱は幕府から鎮圧され逃亡。最後は捕らえられて壮絶な死を遂げた。
京極為兼:伏見天皇の腹心であり、一流の歌人でもあった為兼は興福寺の騒動(永仁の南都闘乱)に巻き込まれて失脚したが復活。勅撰和歌集『玉葉和歌集』は為兼の独撰となった。晩年には再び失脚して配流され、その業績は以後顧みられることはなかった。
雪村友梅:一山一寧の侍童で聡明だった友梅は中国へ留学するが、日元関係の悪化から捕らえられ長年にわたり中国で幽囚生活を送る。しかし斬首されかけた際に詠んだ「臨剣頌(りんけんじゅ)」が友梅の作とされるほど(本当は無学祖元作)中国でもその学識は認められ、帰国後は各地の名刹の住持を歴任した。
広義門院(西園寺寧子):南北朝の動乱の渦中にいた広義門院は、後伏見天皇の妻であり、花園天皇の准母(名義上の母)であり、また後に光厳天皇と光明天皇も生んだ。南朝が北朝の三上皇・皇太子を拉致し、三種の神器を奪ったことで幕府により北朝の中心として担ぎ出される。幕府は北朝に天皇がいないという異常事態に直面し、上皇后によって天皇の権能が代行できると解釈、さらに「天下同一法」という人事・官位等の全てを過去に遡らせるという大奇策によって切り抜けた。広義門院はこれらの策を実行するための名目上の登場かに思われたが、その権力は実質化し、あらゆる政治の決定に関与、文和2年(1353)には政務を後光厳天皇に譲ったものの、長講堂領、法金剛院領、今出川領という天皇家領荘園の全てを所有し続け、北朝の家督者として死ぬまで重きをなした。
願阿弥:時衆の僧で、著名な勧進聖であった願阿弥は、寛正の大飢饉で京が難民と死体で溢れるや、勧進(募金)を募って難民収容所を開設し人々を救った(しかし多くは収容の甲斐なく死亡したという)。18年後、応仁の乱後には、消失していた清水寺の再建に取り組んで諸国を勧進に巡り成功させた。この背景には、清水寺の参拝者を宛てに生活していた清水坂の乞食非人たちの救済があったと考えられるという。
足利義稙(よしたね):足利義視の子である義稙は、義視・義政という父世代の対立がありながらも、義政の子義尚が若くして陣没したことで棚ぼた的に将軍に就任する。ところが政権を牛耳っていた日野富子と不仲になり、細川政元らがクーデターを起こし幽閉された。脱出後、大内義興の力を借りて将軍に返り咲いたものの、お人好しの義稙には政権運営能力はなく、かつての腹心細川高国との確執から逐電し逃げ延びた撫養(むや:鳴門市)で病没した。武家で将軍を再任したのは彼だけである。
著者自身が後書きで書いているように、本書に取り上げられた6人のうち義稙を除く5人が法体(ほったい:出家後の姿)で生涯を終えている。しかし専門的宗教家と呼べるのは雪村友梅だけである。中世においては、人は晩年には出家するのが普通だったし、また法体であることに各種の便宜があった時代だったからだという。本書の中心テーマではないが中世における出家の意味を改めて考えさせられた。
また、6人の中で私が最も興味を抱いたのは広義門院。幕府によって担ぎ出されたのにもかかわらず、その権力が実質化した過程を知りたくなった(本書ではごく簡単に書いている)。
歴史書ではあまり語られない人物を題材に、いろいろな角度から中世を知れる良書。
2019年11月24日日曜日
『密教占星術—宿曜道とインド占星術』矢野 道雄 著
密教占星術「宿曜道」の理論を解明する本。
本書は、英語による宿曜道(すくようどう)についての論文を著者自身が一般向けに書き直したものである。よって、宿曜道の概説というよりは研究論文としての内容を持つ。
本書に書かれる宿曜道についての新知見で、私が重要だと思ったのが主に次の3点。第1に、『宿曜経』上下巻は同じ書物の新訳と旧訳(くやく)であるということ。第2に、『宿曜経』和本のみに伝えられた第7章「宿曜経算曜直章第七」は『九執暦』の抜粋であること。第3に、『七曜攘災決』に解説される「羅睺(らこう)」は月の昇交点であり、「計都(けいと)」は月の遠地点であること、を解明したことである。
これだけを読むと、本書がとても専門的で難解なものと思われるかもしれない。しかしその筆致は平明であり、丁寧に解説されるため初学者にも易しい。備忘を兼ねて上記の内容を紹介しよう。
第1:『宿曜経』上下巻は同じ書物の新訳と旧訳(くやく)である
『宿曜経』は、平安時代に空海によって日本に将来された。正式名称は『文殊師利菩薩及諸千所説吉凶時日善悪宿曜経』といい、その表題が示すように「文殊菩薩と諸仙人が日時の吉凶を説いたお経」である(よって仏説ではない)。具体的には、「宿」すなわち月の運行上にある1日ごとの恒星(27宿)と黄道12位の関係、「曜」すなわち惑星の運行から派生した曜日の観念とを組み合わせて日の吉凶を述べるものだ。つまりこれはインド占星術の初歩の概説書である。
これを翻訳したのは、中国において密教を国家的宗教に発展させた不空のチームであるとされるが、著者はこれはインドには原本はなく、不空自身が撰述した(つまり偽作した)ものだと考えている。それはその内容にインド占星術の専門的なテクニックが述べられていないことなどから推測されるのだという。
それはともかく、『宿曜経』は759年に不空の弟子史瑶(しよう)が最初の翻訳を行い、同じく弟子の楊景風が764年に改訳版を作成した。初訳版はインド的な要素を残していたが、中国語の文章もこなれておらず、構成にもまとまりがなかった。そこで不空は5年後、俗人の弟子で史瑶よりもはるかに学があった楊景風に再編集を命じ、より大系的に構成され中国化した『宿曜経』の改訳版を作成した。
ここまでは『宿曜経』序文により明らかだったのであるが、『宿曜経』上下巻の内容を検証したところ、構成や文章は全く異なるが内容的に同一箇所が散見され、上巻が楊景風訳の新訳版、下巻が史瑶訳の旧訳版であることが明らかになったのである。ということは上巻だけあれば十分だったのであるが、『宿曜経』の編纂者は旧訳も捨て去ることはせずに下巻として残したということだ。おかげで、我々はよりインド占星術の原型を留めた旧訳を参照することが可能となり、その内容を正確に理解できるのだという。
第2:『宿曜経』和本のみに伝えられた第7章「宿曜経算曜直章第七」は『九執暦』の抜粋である
『宿曜経』は日本に伝えられ、陰陽道と並んで「暦と吉凶の理論」として発展し、やがて「宿曜道」となっていった。一方、陰陽道が早くから「陰陽寮」という国家機関が設置されたのに、宿曜道の方は密教の一要素となって国家機関化はせず、南北朝期か遅くとも室町所期には衰微してしまった。ところが『宿曜経』は原型に近い形を留めたまま伝承され続け、『宿曜経』に述べられる27宿の理論は「宣明暦(862〜1684年施行)」の間用いられた。
さらに江戸中期に『宿曜経』を研究し頭注を附して出版(1736年)したのが学僧の覚勝である。この覚勝本は中国では失われた部分をも保存した優れたもので、その第7章「宿曜経算曜直章第七」こそは中国の『宿曜経』でも日本の大正大蔵経でも収録されていない失われた部分であったのである。
その内容は、ずばり曜日の計算方法である。『宿曜経』と相前後して中国に伝えられたのが七曜、つまり「日月火水木金土」という曜日の概念であったが、『宿曜経』本体は曜日の吉凶については述べていても、ある特定の日が何曜日であるのかを調べる手法は書いていない。しかし『宿曜道』成立のころ、そもそも曜日の観念が普及していなかったのだから、曜日を求める方法がなくては吉凶自体が占えない。そこで楊景風は新訳を作成する際、曜日の算定方法を述べた「宿曜経算曜直章第七」を付け加えた。そして著者はこの内容を検証し、罌曇悉達(くとんしった)が718年に著した『九執暦』からの抜粋であることを明らかにした。
しかしながらこの「宿曜経算曜直章第七」には決定的な弱点があった。それは『九執暦』にある正確な曜日の計算方法を引き写しながら、楊景風は暦元(暦の起点となる日)を勝手に「2月白分朔日」から「上元の日(1月15日)」に勝手に押し上げてしまった。暦の起点がずらされているので、この章の計算方法自体は正しいのに、結果は間違っているということになる。そのため中国ではこの章は早くに削除されてしまった。だが日本では、中国からきた有り難いお経が間違っているわけがないということでそのまま伝承され、1000年後の僧侶たちが曜日の計算が合わない事に呻吟することになったのである。
第3:『七曜攘災決』に解説される「羅睺」は月の昇交点であり、「計都」は月の遠地点である
既に述べたように、『宿曜経』は「宿」と「曜」により日の吉凶を判断する手法を概説したものだが、ホロスコープでは肝心な情報である惑星の運行については全く述べられていない。これでは、観測に基づいて吉凶を判断することはできても、未来の特定の日の吉凶を占うことには役立たないのである。そこで惑星の運行の計算方法が必要になってくるのであるが、これこそが8世紀末から9世紀初頭に中国で作られた『七曜攘災決』であった。なお日本には宗叡が伝え、中国では失われている。
さて、「攘災決」というのは惑星によってもたらされる災厄を鎮める方法のことで、この本では「七曜」の他に「羅睺(らこう)」・「計都(けいと)」という架空の天体についても論じられている。
なお日月火水木金土+羅睺・計都の9天体を「九曜」または「九執」という。先述の『九執暦』はこの意味であるが、実は『九執暦』では5惑星を論じていない(あくまで「曜日」として扱っている)。『七曜攘災決』はこれを補い、科学的な観測によって5惑星のかなり正確な運行表を作成したものだ。そこに加えられたのが、「羅睺」・「計都」という架空の天体なのだ。
では「羅睺」・「計都」とは何なのだろうか? インドの伝説では、「羅睺(ラーフ)」は日蝕・月蝕を起こす魔物で、「計都(ケートゥ)」はその尻尾であるとか、「計都」は彗星であるとかいう。『宿曜経』の時点ではその存在すらなかったこの架空の2惑星は、『七曜攘災決』の頃には5惑星に並ぶ重要な天体になっていた。
しかしそれは凶事をもたらす魔物だという伝説的存在だったわけではない。というのは、『七曜攘災決』では5惑星と同じように詳細な運行表や計算がなされているからである。それは科学的な観測に基づいたものでしかありえない。そして著者は、『七曜攘災決』と現代の惑星計算の対照に基づいて、羅睺が月の昇交点であり、計都が月の遠地点であることを解明したのである。
月の昇交点とは、月の軌道(白道)が黄道と交わる2つの交点のうち、南半球から北半球に向かって北向きに交差する点のことである。白道と黄道は約5度の角度で交わっている。つまり月が地球を公転している軌道と、太陽が地球の周りを回っているとみなした時の軌道は5度ずれている(ずれていなければ白道と黄道は一致する)。よって2つの軌道をリングとすれば、そのリング同士が交わる点が「交点」であって、片方を昇交点といい、もう片方を降交点と呼び区別する。
この交点は常に同じところにあるわけではなく、月の公転面に歳差運動(軸のブレ回転)があるため移動していき、約19年周期で1周する。リング同士が5度の角度を保ちながらズレていくことをイメージしてみればよい。そして、この交点の天文学的意味は、月と太陽と地球が一直線に並ぶ点になるわけだから、日蝕・月蝕が起こるポイントというわけだ。
ということは、日蝕の計算を行うには、もちろん太陽と月の動きをそれぞれ計算してもよいが、重要なのはその交点のみであるから、昇交点を19年周期で一回転する1つの天体であると見なして計算すれば、それでかなり計算の手間が省けるというわけである。それが架空の天体「羅睺」であったのだ。ということは、天体としての「羅睺」を考え出したインド人がこれを魔物と思っていたというのはありそうもなく、計算上の便宜として導出した架空の天体を、日蝕を起こす魔物になぞらえて呼んだのであろう。
「羅睺」が、日蝕・月蝕を起こすということで月の昇交点と考えられることは、著者が示す以前にも半ば予見されていたのであるが、著者の独創は「計都」の方にある。
「計都」は「羅睺」の尻尾だという伝説があったことから、著者以前には「計都」は昇交点と対になる降交点であると考えられていた。だとすれば、「羅睺」の座標から180度を加えれば「計都」の位置が算出できるはずだ。ところが『七曜攘災決』では「計都」の位置計算はそのようになっていなかった。では何か? ということで著者が現代の惑星計算と照合した結果、「計都」は月の遠地点であることが明らかになったのである。
遠地点にも少し説明が必要かも知れない。月は地球の周りを楕円運動しているから、一番遠くなる位置と近くなる位置があり、それをそれぞれ遠地点と近地点という。そしてこの楕円運動についても、その楕円の膨らみ方は常に地球から見て同じ位置にあるわけではなく、約9年で白道上を一周する。これも厳密には月の楕円運動の計算によって求められるものであるが、遠地点をあたかも1つの天体と見なすことで簡易に計算結果が表現できるのである。
そして「計都」が月の遠地点であるとするなら、観測上、それは月が最も小さく見えるところであることを意味する。「羅睺」は日蝕・月蝕と関係し、「計都」は月が小さくなるということで、この2つの架空の天体はどちらも月の特徴的な位置関係を表すものであったことが解明された。
本書はこの他、インドのホロスコープがどのようにして『宿曜経』に受容されているかを分析している。著者は古代インドの天文学・数学・占星術を専門としており、分析はその面目躍如たるところがある。全体を通じて非常に重厚な学問的内容を持ちながら平易でもあり、特に「羅睺」と「計都」の考察はスリリングですらあった。
本書を読んで気になったのは、陰陽道でも日の吉凶をやかましく云々していたし、暦を作成したりしていたわけだが、陰陽道と宿曜道の暦(特に天体運動)の理論がどう異なっていたのかということだ。陰陽師と宿曜師は対抗関係にあったが、科学的な面において彼らはどちらが勝れていたのか。また九曜の理論が日本にはどのように受容されていたのかということ(例えば「羅睺」=月の昇交点、などということは理解されていたのだろうか?)にも興味を抱いた。
宿曜道を理解する上での必読書。
本書は、英語による宿曜道(すくようどう)についての論文を著者自身が一般向けに書き直したものである。よって、宿曜道の概説というよりは研究論文としての内容を持つ。
本書に書かれる宿曜道についての新知見で、私が重要だと思ったのが主に次の3点。第1に、『宿曜経』上下巻は同じ書物の新訳と旧訳(くやく)であるということ。第2に、『宿曜経』和本のみに伝えられた第7章「宿曜経算曜直章第七」は『九執暦』の抜粋であること。第3に、『七曜攘災決』に解説される「羅睺(らこう)」は月の昇交点であり、「計都(けいと)」は月の遠地点であること、を解明したことである。
これだけを読むと、本書がとても専門的で難解なものと思われるかもしれない。しかしその筆致は平明であり、丁寧に解説されるため初学者にも易しい。備忘を兼ねて上記の内容を紹介しよう。
第1:『宿曜経』上下巻は同じ書物の新訳と旧訳(くやく)である
『宿曜経』は、平安時代に空海によって日本に将来された。正式名称は『文殊師利菩薩及諸千所説吉凶時日善悪宿曜経』といい、その表題が示すように「文殊菩薩と諸仙人が日時の吉凶を説いたお経」である(よって仏説ではない)。具体的には、「宿」すなわち月の運行上にある1日ごとの恒星(27宿)と黄道12位の関係、「曜」すなわち惑星の運行から派生した曜日の観念とを組み合わせて日の吉凶を述べるものだ。つまりこれはインド占星術の初歩の概説書である。
これを翻訳したのは、中国において密教を国家的宗教に発展させた不空のチームであるとされるが、著者はこれはインドには原本はなく、不空自身が撰述した(つまり偽作した)ものだと考えている。それはその内容にインド占星術の専門的なテクニックが述べられていないことなどから推測されるのだという。
それはともかく、『宿曜経』は759年に不空の弟子史瑶(しよう)が最初の翻訳を行い、同じく弟子の楊景風が764年に改訳版を作成した。初訳版はインド的な要素を残していたが、中国語の文章もこなれておらず、構成にもまとまりがなかった。そこで不空は5年後、俗人の弟子で史瑶よりもはるかに学があった楊景風に再編集を命じ、より大系的に構成され中国化した『宿曜経』の改訳版を作成した。
ここまでは『宿曜経』序文により明らかだったのであるが、『宿曜経』上下巻の内容を検証したところ、構成や文章は全く異なるが内容的に同一箇所が散見され、上巻が楊景風訳の新訳版、下巻が史瑶訳の旧訳版であることが明らかになったのである。ということは上巻だけあれば十分だったのであるが、『宿曜経』の編纂者は旧訳も捨て去ることはせずに下巻として残したということだ。おかげで、我々はよりインド占星術の原型を留めた旧訳を参照することが可能となり、その内容を正確に理解できるのだという。
第2:『宿曜経』和本のみに伝えられた第7章「宿曜経算曜直章第七」は『九執暦』の抜粋である
『宿曜経』は日本に伝えられ、陰陽道と並んで「暦と吉凶の理論」として発展し、やがて「宿曜道」となっていった。一方、陰陽道が早くから「陰陽寮」という国家機関が設置されたのに、宿曜道の方は密教の一要素となって国家機関化はせず、南北朝期か遅くとも室町所期には衰微してしまった。ところが『宿曜経』は原型に近い形を留めたまま伝承され続け、『宿曜経』に述べられる27宿の理論は「宣明暦(862〜1684年施行)」の間用いられた。
さらに江戸中期に『宿曜経』を研究し頭注を附して出版(1736年)したのが学僧の覚勝である。この覚勝本は中国では失われた部分をも保存した優れたもので、その第7章「宿曜経算曜直章第七」こそは中国の『宿曜経』でも日本の大正大蔵経でも収録されていない失われた部分であったのである。
その内容は、ずばり曜日の計算方法である。『宿曜経』と相前後して中国に伝えられたのが七曜、つまり「日月火水木金土」という曜日の概念であったが、『宿曜経』本体は曜日の吉凶については述べていても、ある特定の日が何曜日であるのかを調べる手法は書いていない。しかし『宿曜道』成立のころ、そもそも曜日の観念が普及していなかったのだから、曜日を求める方法がなくては吉凶自体が占えない。そこで楊景風は新訳を作成する際、曜日の算定方法を述べた「宿曜経算曜直章第七」を付け加えた。そして著者はこの内容を検証し、罌曇悉達(くとんしった)が718年に著した『九執暦』からの抜粋であることを明らかにした。
しかしながらこの「宿曜経算曜直章第七」には決定的な弱点があった。それは『九執暦』にある正確な曜日の計算方法を引き写しながら、楊景風は暦元(暦の起点となる日)を勝手に「2月白分朔日」から「上元の日(1月15日)」に勝手に押し上げてしまった。暦の起点がずらされているので、この章の計算方法自体は正しいのに、結果は間違っているということになる。そのため中国ではこの章は早くに削除されてしまった。だが日本では、中国からきた有り難いお経が間違っているわけがないということでそのまま伝承され、1000年後の僧侶たちが曜日の計算が合わない事に呻吟することになったのである。
第3:『七曜攘災決』に解説される「羅睺」は月の昇交点であり、「計都」は月の遠地点である
既に述べたように、『宿曜経』は「宿」と「曜」により日の吉凶を判断する手法を概説したものだが、ホロスコープでは肝心な情報である惑星の運行については全く述べられていない。これでは、観測に基づいて吉凶を判断することはできても、未来の特定の日の吉凶を占うことには役立たないのである。そこで惑星の運行の計算方法が必要になってくるのであるが、これこそが8世紀末から9世紀初頭に中国で作られた『七曜攘災決』であった。なお日本には宗叡が伝え、中国では失われている。
さて、「攘災決」というのは惑星によってもたらされる災厄を鎮める方法のことで、この本では「七曜」の他に「羅睺(らこう)」・「計都(けいと)」という架空の天体についても論じられている。
なお日月火水木金土+羅睺・計都の9天体を「九曜」または「九執」という。先述の『九執暦』はこの意味であるが、実は『九執暦』では5惑星を論じていない(あくまで「曜日」として扱っている)。『七曜攘災決』はこれを補い、科学的な観測によって5惑星のかなり正確な運行表を作成したものだ。そこに加えられたのが、「羅睺」・「計都」という架空の天体なのだ。
では「羅睺」・「計都」とは何なのだろうか? インドの伝説では、「羅睺(ラーフ)」は日蝕・月蝕を起こす魔物で、「計都(ケートゥ)」はその尻尾であるとか、「計都」は彗星であるとかいう。『宿曜経』の時点ではその存在すらなかったこの架空の2惑星は、『七曜攘災決』の頃には5惑星に並ぶ重要な天体になっていた。
しかしそれは凶事をもたらす魔物だという伝説的存在だったわけではない。というのは、『七曜攘災決』では5惑星と同じように詳細な運行表や計算がなされているからである。それは科学的な観測に基づいたものでしかありえない。そして著者は、『七曜攘災決』と現代の惑星計算の対照に基づいて、羅睺が月の昇交点であり、計都が月の遠地点であることを解明したのである。
月の昇交点とは、月の軌道(白道)が黄道と交わる2つの交点のうち、南半球から北半球に向かって北向きに交差する点のことである。白道と黄道は約5度の角度で交わっている。つまり月が地球を公転している軌道と、太陽が地球の周りを回っているとみなした時の軌道は5度ずれている(ずれていなければ白道と黄道は一致する)。よって2つの軌道をリングとすれば、そのリング同士が交わる点が「交点」であって、片方を昇交点といい、もう片方を降交点と呼び区別する。
この交点は常に同じところにあるわけではなく、月の公転面に歳差運動(軸のブレ回転)があるため移動していき、約19年周期で1周する。リング同士が5度の角度を保ちながらズレていくことをイメージしてみればよい。そして、この交点の天文学的意味は、月と太陽と地球が一直線に並ぶ点になるわけだから、日蝕・月蝕が起こるポイントというわけだ。
ということは、日蝕の計算を行うには、もちろん太陽と月の動きをそれぞれ計算してもよいが、重要なのはその交点のみであるから、昇交点を19年周期で一回転する1つの天体であると見なして計算すれば、それでかなり計算の手間が省けるというわけである。それが架空の天体「羅睺」であったのだ。ということは、天体としての「羅睺」を考え出したインド人がこれを魔物と思っていたというのはありそうもなく、計算上の便宜として導出した架空の天体を、日蝕を起こす魔物になぞらえて呼んだのであろう。
「羅睺」が、日蝕・月蝕を起こすということで月の昇交点と考えられることは、著者が示す以前にも半ば予見されていたのであるが、著者の独創は「計都」の方にある。
「計都」は「羅睺」の尻尾だという伝説があったことから、著者以前には「計都」は昇交点と対になる降交点であると考えられていた。だとすれば、「羅睺」の座標から180度を加えれば「計都」の位置が算出できるはずだ。ところが『七曜攘災決』では「計都」の位置計算はそのようになっていなかった。では何か? ということで著者が現代の惑星計算と照合した結果、「計都」は月の遠地点であることが明らかになったのである。
遠地点にも少し説明が必要かも知れない。月は地球の周りを楕円運動しているから、一番遠くなる位置と近くなる位置があり、それをそれぞれ遠地点と近地点という。そしてこの楕円運動についても、その楕円の膨らみ方は常に地球から見て同じ位置にあるわけではなく、約9年で白道上を一周する。これも厳密には月の楕円運動の計算によって求められるものであるが、遠地点をあたかも1つの天体と見なすことで簡易に計算結果が表現できるのである。
そして「計都」が月の遠地点であるとするなら、観測上、それは月が最も小さく見えるところであることを意味する。「羅睺」は日蝕・月蝕と関係し、「計都」は月が小さくなるということで、この2つの架空の天体はどちらも月の特徴的な位置関係を表すものであったことが解明された。
本書はこの他、インドのホロスコープがどのようにして『宿曜経』に受容されているかを分析している。著者は古代インドの天文学・数学・占星術を専門としており、分析はその面目躍如たるところがある。全体を通じて非常に重厚な学問的内容を持ちながら平易でもあり、特に「羅睺」と「計都」の考察はスリリングですらあった。
本書を読んで気になったのは、陰陽道でも日の吉凶をやかましく云々していたし、暦を作成したりしていたわけだが、陰陽道と宿曜道の暦(特に天体運動)の理論がどう異なっていたのかということだ。陰陽師と宿曜師は対抗関係にあったが、科学的な面において彼らはどちらが勝れていたのか。また九曜の理論が日本にはどのように受容されていたのかということ(例えば「羅睺」=月の昇交点、などということは理解されていたのだろうか?)にも興味を抱いた。
宿曜道を理解する上での必読書。
2019年10月31日木曜日
『趙州録』秋月 龍珉 訳(西谷啓治・柳田聖山編『世界古典文学全集36A 禅家語録 I』 所収)
趙州従諗(じょうしゅう・じゅうしん)の言行録。
趙州和尚といえば、かの『無門関』の第1則「狗に仏性はあるのか?」で余りにも有名である。また道元の『正法眼蔵』にもたくさん登場するし、『碧巌録』にもその公案が多く集録されている。
彼の禅風は徹頭徹尾語りと問答にあった。ややもすればすぐに「三十棒!(30回棒で打つ)」と実力行使に出る当時の禅にあって、趙州は禅を言葉で説明することにこだわった。であるから、その言行録は禅のテキストとして貴重であり、広く流布した。
ところが多くの禅籍で取り上げられたためか、肝心の『趙州録』そのものはいつしか忘れられ、原典が顧みられなくなってしまった。中国にも日本にも、『趙州録』の注釈と呼べるものは現代に至るまで存在しなかったのである。
では『趙州録』はつまらないものだったのか、というと実はこれが大変に面白いものだったのである。後代(宋代)に編纂され「公案化」された彼の問答よりも、原典はもっとずっとヴィヴィッドであり、わかりやすい。『趙州録』は神秘的な「公案」ではなくて、直接的な生きた教えなのだ(おそらく、そのために却って廃れたのだろう)。
ではその問答の調子はどんなものかというと、例えば代表的な問に「祖師西来意」というものがある。これは「ダルマ(祖師)がインドから中国に来て伝えようとしたその精神はどんなものですか?」という問である。『趙州録』では、たくさんの僧が趙州にこの質問をしている。趙州のお寺では問答の時間(かノルマ?)があって、僧たちは趙州和尚に質問をすることになっていた。それで、気の聞いた質問を思いつかなかった僧が、「思いつかない時はこういう質問をしたらいいよ」という先輩僧の入れ知恵によって定型的な質問をしていたようなのである。「祖師西来意」はそういう定番質問の一つである。
であるから、そもそも「祖師西来意」を尋ねる僧に切実な疑問というか探求心があろうはずもなく、趙州も軽くあしらっているように見える。そしてその答えはいろいろあり、古来有名な答えは「庭前栢樹子——庭先の栢の木だよ」というものなのだが(『無門関』第37則に取り上げられた)、他にも20以上の答えがある。そこから抽出される趙州の答えの核心は、「ダルマのことはさておいて、それを問うオマエはなんなの?」というものである。「ダルマ云々よりも、まず本来の自己に目覚めないことには話にならないよ」と言ってもよい。
趙州の問答は、質問者の切実度合いと理解度と修行度合いによって変幻自在に変わっていた。であるから、彼の問答の意味を表面的な言葉の意味でだけ考えても無意味であり、「庭先の栢の木がどうして祖師西来意なんだろう?」と考えてもあまり実りはないのである(ちょっと庭先の栢の木を見てみろ、とでも理解した方がいい)。
それを象徴するのが『無門関』第1則にも取り上げられた「狗に仏性はあるのか?」で、『無門関』では趙州は「無」とだけ答え、それについての考究がなされる。そしてこの「無」の一字は禅の究極のようなものと捉えられ、それに因んで『無門関』——「無」に至る門への関所——という標題までつけられているのである。
ところが、『趙州録』を見てみると、「狗に仏性はあるのか?」を質問した僧は2人いて、確かに一人への答えでは「無」と答えているが、もう一人には「家々の門前[の道]は長安の都に通じている(=どんな道でも悟りへ至る道=狗にも仏性はある、という意味と思われる)」と答えている。この2つの問答を見れば、狗に仏性はあるのかないのか、どっちやねん! と思うわけだが、趙州にとってみれば、「なんでオマエは狗の仏性の有無をあーだこーだいうわけ?」というところなのだと思う。『趙州録』の全体を通して、そういう観念的な質問をする時点で「こいつわかってねーな」という応対なのである。
逆に、初歩的な質問、定型的な質問であっても、僧の方に切実な問題意識がある(ように見受けられる)場合には趙州は「いい質問だ」と褒めている。他の僧が同じ質問でメタクソにされているようなものであってもである。趙州の禅は、観念的なものを排し、本来の自己に目覚めることを究極の目的として、あくまでも目の前の人物に応じて臨機応変に説かれるものであった。
であるから、例えば「庭前栢樹子」のような一見すると意味不明の答えであっても、その裏に観念的な世界が広がっているというよりは、極めて具体的・即物的な意味合いがあったと考えるべきなのだと思う。しかし宋代になると、『趙州録』から問答の一部が切り出され、まるで暗号のような公案が多々できあがる。『無門関』はその代表で、それはそれで禅の精神の発露であることは否定しないが、趙州和尚の臨機応変の自在の禅とは、かなり違うものになっていたこともまた事実である。
宋代の禅よりも、その原典の唐代の禅の方が、ずっと普遍的で理解しやすく、私にとっては親しみが持てる。『趙州録』はまさに禅の原点となる、忘れられた名著である。
趙州和尚といえば、かの『無門関』の第1則「狗に仏性はあるのか?」で余りにも有名である。また道元の『正法眼蔵』にもたくさん登場するし、『碧巌録』にもその公案が多く集録されている。
彼の禅風は徹頭徹尾語りと問答にあった。ややもすればすぐに「三十棒!(30回棒で打つ)」と実力行使に出る当時の禅にあって、趙州は禅を言葉で説明することにこだわった。であるから、その言行録は禅のテキストとして貴重であり、広く流布した。
ところが多くの禅籍で取り上げられたためか、肝心の『趙州録』そのものはいつしか忘れられ、原典が顧みられなくなってしまった。中国にも日本にも、『趙州録』の注釈と呼べるものは現代に至るまで存在しなかったのである。
では『趙州録』はつまらないものだったのか、というと実はこれが大変に面白いものだったのである。後代(宋代)に編纂され「公案化」された彼の問答よりも、原典はもっとずっとヴィヴィッドであり、わかりやすい。『趙州録』は神秘的な「公案」ではなくて、直接的な生きた教えなのだ(おそらく、そのために却って廃れたのだろう)。
ではその問答の調子はどんなものかというと、例えば代表的な問に「祖師西来意」というものがある。これは「ダルマ(祖師)がインドから中国に来て伝えようとしたその精神はどんなものですか?」という問である。『趙州録』では、たくさんの僧が趙州にこの質問をしている。趙州のお寺では問答の時間(かノルマ?)があって、僧たちは趙州和尚に質問をすることになっていた。それで、気の聞いた質問を思いつかなかった僧が、「思いつかない時はこういう質問をしたらいいよ」という先輩僧の入れ知恵によって定型的な質問をしていたようなのである。「祖師西来意」はそういう定番質問の一つである。
であるから、そもそも「祖師西来意」を尋ねる僧に切実な疑問というか探求心があろうはずもなく、趙州も軽くあしらっているように見える。そしてその答えはいろいろあり、古来有名な答えは「庭前栢樹子——庭先の栢の木だよ」というものなのだが(『無門関』第37則に取り上げられた)、他にも20以上の答えがある。そこから抽出される趙州の答えの核心は、「ダルマのことはさておいて、それを問うオマエはなんなの?」というものである。「ダルマ云々よりも、まず本来の自己に目覚めないことには話にならないよ」と言ってもよい。
趙州の問答は、質問者の切実度合いと理解度と修行度合いによって変幻自在に変わっていた。であるから、彼の問答の意味を表面的な言葉の意味でだけ考えても無意味であり、「庭先の栢の木がどうして祖師西来意なんだろう?」と考えてもあまり実りはないのである(ちょっと庭先の栢の木を見てみろ、とでも理解した方がいい)。
それを象徴するのが『無門関』第1則にも取り上げられた「狗に仏性はあるのか?」で、『無門関』では趙州は「無」とだけ答え、それについての考究がなされる。そしてこの「無」の一字は禅の究極のようなものと捉えられ、それに因んで『無門関』——「無」に至る門への関所——という標題までつけられているのである。
ところが、『趙州録』を見てみると、「狗に仏性はあるのか?」を質問した僧は2人いて、確かに一人への答えでは「無」と答えているが、もう一人には「家々の門前[の道]は長安の都に通じている(=どんな道でも悟りへ至る道=狗にも仏性はある、という意味と思われる)」と答えている。この2つの問答を見れば、狗に仏性はあるのかないのか、どっちやねん! と思うわけだが、趙州にとってみれば、「なんでオマエは狗の仏性の有無をあーだこーだいうわけ?」というところなのだと思う。『趙州録』の全体を通して、そういう観念的な質問をする時点で「こいつわかってねーな」という応対なのである。
逆に、初歩的な質問、定型的な質問であっても、僧の方に切実な問題意識がある(ように見受けられる)場合には趙州は「いい質問だ」と褒めている。他の僧が同じ質問でメタクソにされているようなものであってもである。趙州の禅は、観念的なものを排し、本来の自己に目覚めることを究極の目的として、あくまでも目の前の人物に応じて臨機応変に説かれるものであった。
であるから、例えば「庭前栢樹子」のような一見すると意味不明の答えであっても、その裏に観念的な世界が広がっているというよりは、極めて具体的・即物的な意味合いがあったと考えるべきなのだと思う。しかし宋代になると、『趙州録』から問答の一部が切り出され、まるで暗号のような公案が多々できあがる。『無門関』はその代表で、それはそれで禅の精神の発露であることは否定しないが、趙州和尚の臨機応変の自在の禅とは、かなり違うものになっていたこともまた事実である。
宋代の禅よりも、その原典の唐代の禅の方が、ずっと普遍的で理解しやすく、私にとっては親しみが持てる。『趙州録』はまさに禅の原点となる、忘れられた名著である。
2019年10月23日水曜日
『碧巌録』(西谷啓治・柳田聖山編『世界古典文学全集36B 禅家語録 II』 所収)
日本語訳された『碧巌録』。
『碧巌録』は、「宗門第一の書」と呼ばれ日本の禅宗、特に臨済宗には多大な影響を与えてきた。また難解であることでも有名であり、古来多くの注釈・講釈の本が出版されてきた。しかし意外にも長く日本語訳されることがなく、本書は出版時おそらく初めて日本語全訳された『碧巌録』である。
これは、雪竇(せっちょう)和尚が『伝燈録』から選んだ公案百則に頌(詩)をつけたテキストを作り、それに対して圜悟(えんご)和尚が解説と著語(じゃくご=ツッコミ)をくわえたノートの集録である。
つまり『碧巌録』は雪竇と圜悟の共同執筆なのであるが、ことはそう単純ではない。というのは、雪竇重顕(980年−1052年)と圜悟克勤(1063年−1135年)にはほぼ3世代の開きがあるからだ。
雪竇和尚が編集した公案百則に、3世代経って圜悟和尚が”超編集”を加えて出来たのが『碧巌録』なのである。その”超編集”ぶりを示すため、一則だけ例示しよう(なお、本来は一則につき、垂示(序論)[圜悟]、本則[雪竇]+著語[圜悟]、評唱(参考資料と解説)[圜悟]、頌古[雪竇]+著語[圜悟]、がセットになっているが、今本則+著語のみを引用する。なお本書では評唱は省略され、訳者による短い解説がそれに代わっている)。
第39則 雲門花薬欄 本則
挙。僧問雲門、如何是清浄法身。壒(*1)扱(*2)堆頭見丈六金身。斑斑駁駁是什麽。門云、花楽欄。問処不真答来鹵莽。祝(*3)著磕著。曲不蔵直。僧云、便恁麽去時如何。渾崙呑箇棗。放憨作麽。門云、金毛獅子。也褒也貶。両采一賽。将錯就錯。是什麽心行。
(*本来の漢字がPCで出せないため代字で表現した。*1「艹」不要、*2「扌」の代わりに「土」、*3 「祝」の下に「土」)
※黒字が雪竇による「本則」、青字が圜悟による「著語」。本書では「著語」は本文より小さい活字にすることで区別されている。
(日本語訳)
雲門大師のところへ、一人の僧がやって来て、「宇宙の本体ともいうべきビルシャナ仏とは、どんなかたですか」と尋ねた。ごみ捨て場の中に仏がいらっしゃるよ。きれい、きたない、いろいろなものが入り交じっているやつ、あれは何かね。雲門は、「便所の袖垣だよ」と答えた。質問がいい加減だから、答えもぞんざいだ。打てば響くようにぴったりだ。曲がったものは、曲がったままでよい。「それでは仰せのとおり、花薬欄は花薬欄と承知したら、どうなりましょうか」と、ひねくれた質問をした。こいつ雲門の答えをよく味わってもみず、丸呑みにしたな。うすぼんやりしていて、いい加減なことを問うたな。「獅子中の王者、禅僧中の禅僧とでもいうかな」と、雲門は答えた。上げたり、下げたりだな。花薬欄と金毛の獅子では同じ賽の目だな。雲門も僧もどっちもいかん。どういうつもりでいったのかな。
これを見れば、古来『碧巌録』が難解とされてきた理由が一目瞭然だろう。雪竇の編集した公案本体部分だけを見れば、その趣旨が理解できるかどうかは別として、なんとか読みこなせるものだろう。しかし圜悟がそこにツッコミの嵐を容赦なく加えており、しかもそれが口語調なものだから、ただでさえ文意があっちこっちしている上に日本人にとっては漢文として大変難しいのである。いや、読み下し文でこれを理解するのはほぼ不可能に近い。
しかし『碧巌録』が画期的だったのは、この圜悟のツッコミ部分だった。上の第39則でも、本文だけを見れば常人の理解を超越した何か高遠な問答のように見える。だが圜悟のツッコミも含めてみると、この問答はそれほど立派なものではなく、あまり噛み合っていない話であったことが理解できる。しかも圜悟のツッコミは、単に公案への対し方・味わい方を教えるだけでなく、公案に通底する禅の哲理を仄めかすものとなっているのである。
そもそも公案というものは、過去の偉大な禅匠たちの言行録で、有り難い教えが含まれていると考えられていた。臨済宗が依拠した「看話禅(かんなぜん)」というのは、公案の意味を考究する事によって悟りに至ろうとする禅のことであり、公案を悟りに至った事例と見なし非常に重視した。雪竇和尚が『碧巌録』の元となった公案百則を編集したのも、古来たくさん伝えられてきた公案(『伝燈録』1700則)から決定版的なものを百だけ選んで、その解読のヒントとして詩をつけたのである。
圜悟和尚は、それにツッコミの嵐を加える事によって、公案の意味を丸裸にしてしまった。それは、公案というものは自らの頭で考えることに意味があるのに、圜悟和尚のガイドによって公案が形無しになってしまったとも言えるし、公案集から神秘的なヴェールを剥ぎ、いたずらに公案を至上のものとする一種の思考停止に強烈な鉄槌を加えたとも言える。
そんなことで編集当時から『碧巌録』は毀誉褒貶が激しく、圜悟和尚の弟子大慧は『碧巌録』の版を焼き捨てたと言われる。また編集完成は1125年であったが、これが本格的に刊行されたのはなんと175年後の1300年であった(※1300年以前にも刊行はあったらしいが少部数だったのか残っていない)。そして、中国では『碧巌録』は、あまりにもわかりやす過ぎる禅籍として衝撃をもって迎えられ、大流行したのであった。
ところが日本では、『碧巌録』は難解な禅籍の代表のようになってしまった。先述の通り、『碧巌録』の本質である圜悟のツッコミが、中国語の口語体であるためかえって難しかったのである。そして、あたかも難解であることが『碧巌録』の価値であり、高遠さであると考えられてきた。現代ですら、「『碧巌録』に現代語訳を求めるなど邪道。難解な本文に直にあたってこそ意味がある」と考えている人は多い。しかし中国人がわかりやすい白話文(口語体)で禅を語り理解してきたのに、日本人がわざわざ難解な外国語を通してしか禅を理解できないなんてあるわけがないのである。
『碧巌録』を生き生きとした日本語訳によって表現した本書は画期的な訳業であり、日本の禅籍史に輝くものである。本書の刊行(1974年)より40年以上経過しているが、未だ『碧巌録』の日本語全訳は数えるほどしかない。とはいえ、本書の日本語訳は決定版とはいえない。刊行時点において『碧巌録』研究の集大成であると自負されてはいるものの、多数の訳者の共同作業であり、日本語訳の仕方も統一されていないからだ。読んだ感じとしても、明らかに訳者によって粗密を感じるところである。事実解説にも「歴史的・語学的な課題のすべてを今後に残すこととする。これが禅門の現状である」と記されている。なお分担は以下の通りである。
第1則ー第20則 苧坂光龍(般若道場)
第21則ー第40則 大森曹玄(鉄舟会)
第41則ー第60則 梶谷宗忍(相国僧堂)
第61則ー第80則 勝平宗徹(南禅僧堂)
第81則ー第100則 平田精耕(天龍僧堂)
『碧巌録』の初めての日本語訳として不朽の価値がある名著。
『碧巌録』は、「宗門第一の書」と呼ばれ日本の禅宗、特に臨済宗には多大な影響を与えてきた。また難解であることでも有名であり、古来多くの注釈・講釈の本が出版されてきた。しかし意外にも長く日本語訳されることがなく、本書は出版時おそらく初めて日本語全訳された『碧巌録』である。
これは、雪竇(せっちょう)和尚が『伝燈録』から選んだ公案百則に頌(詩)をつけたテキストを作り、それに対して圜悟(えんご)和尚が解説と著語(じゃくご=ツッコミ)をくわえたノートの集録である。
つまり『碧巌録』は雪竇と圜悟の共同執筆なのであるが、ことはそう単純ではない。というのは、雪竇重顕(980年−1052年)と圜悟克勤(1063年−1135年)にはほぼ3世代の開きがあるからだ。
雪竇和尚が編集した公案百則に、3世代経って圜悟和尚が”超編集”を加えて出来たのが『碧巌録』なのである。その”超編集”ぶりを示すため、一則だけ例示しよう(なお、本来は一則につき、垂示(序論)[圜悟]、本則[雪竇]+著語[圜悟]、評唱(参考資料と解説)[圜悟]、頌古[雪竇]+著語[圜悟]、がセットになっているが、今本則+著語のみを引用する。なお本書では評唱は省略され、訳者による短い解説がそれに代わっている)。
第39則 雲門花薬欄 本則
挙。僧問雲門、如何是清浄法身。壒(*1)扱(*2)堆頭見丈六金身。斑斑駁駁是什麽。門云、花楽欄。問処不真答来鹵莽。祝(*3)著磕著。曲不蔵直。僧云、便恁麽去時如何。渾崙呑箇棗。放憨作麽。門云、金毛獅子。也褒也貶。両采一賽。将錯就錯。是什麽心行。
(*本来の漢字がPCで出せないため代字で表現した。*1「艹」不要、*2「扌」の代わりに「土」、*3 「祝」の下に「土」)
※黒字が雪竇による「本則」、青字が圜悟による「著語」。本書では「著語」は本文より小さい活字にすることで区別されている。
(日本語訳)
雲門大師のところへ、一人の僧がやって来て、「宇宙の本体ともいうべきビルシャナ仏とは、どんなかたですか」と尋ねた。ごみ捨て場の中に仏がいらっしゃるよ。きれい、きたない、いろいろなものが入り交じっているやつ、あれは何かね。雲門は、「便所の袖垣だよ」と答えた。質問がいい加減だから、答えもぞんざいだ。打てば響くようにぴったりだ。曲がったものは、曲がったままでよい。「それでは仰せのとおり、花薬欄は花薬欄と承知したら、どうなりましょうか」と、ひねくれた質問をした。こいつ雲門の答えをよく味わってもみず、丸呑みにしたな。うすぼんやりしていて、いい加減なことを問うたな。「獅子中の王者、禅僧中の禅僧とでもいうかな」と、雲門は答えた。上げたり、下げたりだな。花薬欄と金毛の獅子では同じ賽の目だな。雲門も僧もどっちもいかん。どういうつもりでいったのかな。
これを見れば、古来『碧巌録』が難解とされてきた理由が一目瞭然だろう。雪竇の編集した公案本体部分だけを見れば、その趣旨が理解できるかどうかは別として、なんとか読みこなせるものだろう。しかし圜悟がそこにツッコミの嵐を容赦なく加えており、しかもそれが口語調なものだから、ただでさえ文意があっちこっちしている上に日本人にとっては漢文として大変難しいのである。いや、読み下し文でこれを理解するのはほぼ不可能に近い。
しかし『碧巌録』が画期的だったのは、この圜悟のツッコミ部分だった。上の第39則でも、本文だけを見れば常人の理解を超越した何か高遠な問答のように見える。だが圜悟のツッコミも含めてみると、この問答はそれほど立派なものではなく、あまり噛み合っていない話であったことが理解できる。しかも圜悟のツッコミは、単に公案への対し方・味わい方を教えるだけでなく、公案に通底する禅の哲理を仄めかすものとなっているのである。
そもそも公案というものは、過去の偉大な禅匠たちの言行録で、有り難い教えが含まれていると考えられていた。臨済宗が依拠した「看話禅(かんなぜん)」というのは、公案の意味を考究する事によって悟りに至ろうとする禅のことであり、公案を悟りに至った事例と見なし非常に重視した。雪竇和尚が『碧巌録』の元となった公案百則を編集したのも、古来たくさん伝えられてきた公案(『伝燈録』1700則)から決定版的なものを百だけ選んで、その解読のヒントとして詩をつけたのである。
圜悟和尚は、それにツッコミの嵐を加える事によって、公案の意味を丸裸にしてしまった。それは、公案というものは自らの頭で考えることに意味があるのに、圜悟和尚のガイドによって公案が形無しになってしまったとも言えるし、公案集から神秘的なヴェールを剥ぎ、いたずらに公案を至上のものとする一種の思考停止に強烈な鉄槌を加えたとも言える。
そんなことで編集当時から『碧巌録』は毀誉褒貶が激しく、圜悟和尚の弟子大慧は『碧巌録』の版を焼き捨てたと言われる。また編集完成は1125年であったが、これが本格的に刊行されたのはなんと175年後の1300年であった(※1300年以前にも刊行はあったらしいが少部数だったのか残っていない)。そして、中国では『碧巌録』は、あまりにもわかりやす過ぎる禅籍として衝撃をもって迎えられ、大流行したのであった。
ところが日本では、『碧巌録』は難解な禅籍の代表のようになってしまった。先述の通り、『碧巌録』の本質である圜悟のツッコミが、中国語の口語体であるためかえって難しかったのである。そして、あたかも難解であることが『碧巌録』の価値であり、高遠さであると考えられてきた。現代ですら、「『碧巌録』に現代語訳を求めるなど邪道。難解な本文に直にあたってこそ意味がある」と考えている人は多い。しかし中国人がわかりやすい白話文(口語体)で禅を語り理解してきたのに、日本人がわざわざ難解な外国語を通してしか禅を理解できないなんてあるわけがないのである。
『碧巌録』を生き生きとした日本語訳によって表現した本書は画期的な訳業であり、日本の禅籍史に輝くものである。本書の刊行(1974年)より40年以上経過しているが、未だ『碧巌録』の日本語全訳は数えるほどしかない。とはいえ、本書の日本語訳は決定版とはいえない。刊行時点において『碧巌録』研究の集大成であると自負されてはいるものの、多数の訳者の共同作業であり、日本語訳の仕方も統一されていないからだ。読んだ感じとしても、明らかに訳者によって粗密を感じるところである。事実解説にも「歴史的・語学的な課題のすべてを今後に残すこととする。これが禅門の現状である」と記されている。なお分担は以下の通りである。
第1則ー第20則 苧坂光龍(般若道場)
第21則ー第40則 大森曹玄(鉄舟会)
第41則ー第60則 梶谷宗忍(相国僧堂)
第61則ー第80則 勝平宗徹(南禅僧堂)
第81則ー第100則 平田精耕(天龍僧堂)
『碧巌録』の初めての日本語訳として不朽の価値がある名著。
2019年10月22日火曜日
『八幡神と神仏習合』逵 日出典 著
神仏習合を軸に八幡神の成立過程を述べる。
八幡神社というと、日本中どこでも見られるもので、神社の中では最も多いとも言われる。この八幡神社はどのようにして成立し、発展していったのか。本書はそれをほぼ時系列的に述べるものである。
その流れを大まかにまとめれば、(1)八幡神は新羅からの渡来人が祀った神が日本化してできたもので、(2)宇佐周辺で行われていた山岳信仰と一体となって発展し、(3)隼人の乱への征伐や大仏造立といったことに協力したことから朝廷との持ちつ持たれつの関係となって権威を得、(4)護国的な性格を持つ神社となって、また仏教とも融合して「護国霊験威力神通大自在菩薩」とまで称するようになり、(5)源頼朝が鎌倉に鶴岡八幡宮を勧請したことから武家にとって重要な神社となって全国に広がっていった。となるだろう。
この流れについて、本書は縦横に史料を駆使して述べており説得的である。しかし私が本書を手に取った動機は、宇佐八幡の荘園支配の実態がどのようなものであったのか、というもので、それについては本書はほとんど述べるところがない。
中世初期において、鹿児島の土地は島津庄と八幡宮領(八幡宮の荘園)で2分されており、九州の他の地方でも八幡宮領がかなり多かった。また八幡宮直轄領だけでなく、その神宮寺であった弥勒寺領となっていたところも多い。なぜ八幡宮はこのように広大な荘園を支配することができたのだろうか? 特に九州では、国衙の近くに八幡宮が勧請されることが多かったが、これは何を意味していたのだろうか。
また中世において、九州の二大権門は大宰府と宇佐八幡宮であるが、この二大権門はどのような関係だったのか。例えば、有名な宇佐八幡宮神託事件では、「道鏡を皇位に就けるべき」という最初の神託を伝えたのが大宰府の主神(かんづかさ:諸々の祭司を掌る)習宜阿曾麻呂(すげのあそまろ)であったが、なぜ大宰府の役人が宇佐八幡宮の託宣を表明することができたのか。
さらに宇佐八幡宮神託事件では、「皇族でない人間を皇位に就けるべきではない」という趣旨の第二の神託を持ち帰った和気清麻呂が処分されるわけだが、これは宇佐八幡の神託が恣意的なものと考えられていたことを示しているのではないだろうか。もし実際に神託が出て清麻呂がそれを持ち帰っただけなのであれば、清麻呂自身には責任があろうはずもないからである。つまり宇佐八幡の神託は、作為的なものと考えられていながら、やはり権威を持っていた。それが不思議なのである。宇佐八幡宮神託事件自体が『続日本紀』の作為であるという説もあるが、であるにしても、宇佐八幡が持つ意味について考えさせられる事件である。本書ではこうしたことについて全く考察はないが、非常に気になった。
また本書では、八幡神の発展が日本の神仏習合を先導していたと述べており、神仏習合現象についての説明もかなり丁寧である。事実、八幡神は「八幡大菩薩」として親しまれ、僧形によって表現されるようになったのであるが、ここも疑問に思った。なぜ八幡神は「大菩薩」なのにもかかわらず僧形なのだろうか。素直に考えれば菩薩形であるべきなのに、どうして僧形とされたのか謎で、これも本書には全く考察がない。
本書は、八幡神の思想的発展については丁寧に記述するものの、それに対する考察はあまり充実しておらず、荘園経営や社殿造営などの実務面についてはほとんど触れていない。入門書としては当然かもしれないが、そこは少し残念だった。
八幡神を巡る種々の謎についてはあまり解きほぐされないが、史実を実直に辿れる八幡神入門書。
【関連書籍】
『神仏習合』逵 日出典 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html
神仏習合の概略的な説明。
八幡神社というと、日本中どこでも見られるもので、神社の中では最も多いとも言われる。この八幡神社はどのようにして成立し、発展していったのか。本書はそれをほぼ時系列的に述べるものである。
その流れを大まかにまとめれば、(1)八幡神は新羅からの渡来人が祀った神が日本化してできたもので、(2)宇佐周辺で行われていた山岳信仰と一体となって発展し、(3)隼人の乱への征伐や大仏造立といったことに協力したことから朝廷との持ちつ持たれつの関係となって権威を得、(4)護国的な性格を持つ神社となって、また仏教とも融合して「護国霊験威力神通大自在菩薩」とまで称するようになり、(5)源頼朝が鎌倉に鶴岡八幡宮を勧請したことから武家にとって重要な神社となって全国に広がっていった。となるだろう。
この流れについて、本書は縦横に史料を駆使して述べており説得的である。しかし私が本書を手に取った動機は、宇佐八幡の荘園支配の実態がどのようなものであったのか、というもので、それについては本書はほとんど述べるところがない。
中世初期において、鹿児島の土地は島津庄と八幡宮領(八幡宮の荘園)で2分されており、九州の他の地方でも八幡宮領がかなり多かった。また八幡宮直轄領だけでなく、その神宮寺であった弥勒寺領となっていたところも多い。なぜ八幡宮はこのように広大な荘園を支配することができたのだろうか? 特に九州では、国衙の近くに八幡宮が勧請されることが多かったが、これは何を意味していたのだろうか。
また中世において、九州の二大権門は大宰府と宇佐八幡宮であるが、この二大権門はどのような関係だったのか。例えば、有名な宇佐八幡宮神託事件では、「道鏡を皇位に就けるべき」という最初の神託を伝えたのが大宰府の主神(かんづかさ:諸々の祭司を掌る)習宜阿曾麻呂(すげのあそまろ)であったが、なぜ大宰府の役人が宇佐八幡宮の託宣を表明することができたのか。
さらに宇佐八幡宮神託事件では、「皇族でない人間を皇位に就けるべきではない」という趣旨の第二の神託を持ち帰った和気清麻呂が処分されるわけだが、これは宇佐八幡の神託が恣意的なものと考えられていたことを示しているのではないだろうか。もし実際に神託が出て清麻呂がそれを持ち帰っただけなのであれば、清麻呂自身には責任があろうはずもないからである。つまり宇佐八幡の神託は、作為的なものと考えられていながら、やはり権威を持っていた。それが不思議なのである。宇佐八幡宮神託事件自体が『続日本紀』の作為であるという説もあるが、であるにしても、宇佐八幡が持つ意味について考えさせられる事件である。本書ではこうしたことについて全く考察はないが、非常に気になった。
また本書では、八幡神の発展が日本の神仏習合を先導していたと述べており、神仏習合現象についての説明もかなり丁寧である。事実、八幡神は「八幡大菩薩」として親しまれ、僧形によって表現されるようになったのであるが、ここも疑問に思った。なぜ八幡神は「大菩薩」なのにもかかわらず僧形なのだろうか。素直に考えれば菩薩形であるべきなのに、どうして僧形とされたのか謎で、これも本書には全く考察がない。
本書は、八幡神の思想的発展については丁寧に記述するものの、それに対する考察はあまり充実しておらず、荘園経営や社殿造営などの実務面についてはほとんど触れていない。入門書としては当然かもしれないが、そこは少し残念だった。
八幡神を巡る種々の謎についてはあまり解きほぐされないが、史実を実直に辿れる八幡神入門書。
【関連書籍】
『神仏習合』逵 日出典 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html
神仏習合の概略的な説明。
2019年10月20日日曜日
『一遍と時衆の謎—時宗史を読み解く』桜井 哲夫 著
一遍と時衆についてのこれまでの研究のまとめ。
著者の桜井哲夫は近現代ヨーロッパを主な対象とする社会学者であり、時衆については専門外である。が同時に時宗寺院の住職であって、その立場からまとめたのが本書である。よって本書は、著者自身の研究というよりも、これまでの時衆研究を概観してみようというものである。
本書は2部に分かれており、第1部は時衆とは何かということが様々なトピックから紐解かれている。先行研究が縦横に紹介されているので初学者には有り難いが、一方で「○○はこう言っている」という形で様々なことが雑然と語られているという側面もあり、時衆の全体像はやや摑みにくい。
個人的に気になったのは、時衆僧侶は「陣僧」として戦に同行して戦没者の葬儀を執り行っており、それが賦役として課されていたという点。本書では簡単に書いているが、時衆の性格を考察する上で重要だと思われる。
そもそも私が時衆に興味を抱いたのも、葬送との関連であった。中世の葬制が整っていくにあたり、大きな役割を果たしたのは禅宗であり、またそれを武士階級から一般まで普及させていったのは律宗の影響が大きいらしい。しかしその背景として、時衆の存在が非常に気にかかるのである。葬送は言うまでもなく死体を扱うので、当時(中世初期)には穢れの問題がやかましかった。そんな中で、「浄不浄を問わず」としていた時衆はかなり葬儀に関わっていたらしく、また実際に陣僧として活躍していたことを踏まえると、葬制の確立において時衆の果たした役割は大きいと考えられている。非人と時衆の関係がその核にあるのではないかという気がした。こうしたことについて本書ではほとんど触れられていないが、ここはさらに知りたいところである。
この他にも、江戸時代には時衆は遊行にかなり便宜を与えられていたということ、能などの芸道において時衆(と考えられている人)が活躍していたらしいということ、高野聖は時衆が吸収してしまったらしいということなど、様々な点が興味深かった。また、蓮如による浄土真宗の改革が真宗の時衆化ではなかったのかという指摘は面白かった。中世において時衆は非常に隆盛し、多くの信者を獲得したものの、蓮如によって浄土真宗が興隆してゆくと時衆は不思議と衰微していく。これは時衆の徒が浄土真宗に吸収されていった結果であると考えられる。確かに親鸞の浄土真宗は非常に学理的であるが、蓮如の浄土真宗は明解で庶民的であり、時衆風なのである。
第2部では、『一遍聖絵』に基づいて一遍の生涯を紹介している。『一遍聖絵』の研究と、一遍の伝記的研究が同時に扱われているので、こちらもやや煩瑣な部分があるが、時系列的になっている分、第1部に比べるとすっきりしている。
伝記的部分で気になったのは、一遍は神祇不拝ではなくむしろ積極的に神社等に参拝したということや、往生の際の奇瑞を信用せず、そうした奇跡的な現象を迷信だと退けていたという点である。時衆は教義らしい教義を持たない宗派であるとされることもあり、事実一遍は一冊の著書も残さなかったが(入寂の前に焼き捨てた)、彼が残した和歌を見ると宗教家としての思想が感じられる。
おのづから あひあうときも わかれても ひとりはおなじ ひとりなりけり
時衆は集団で念仏踊りに狂う宗派であったのは事実である。その興奮は時として入水往生(入水自殺)をも伴った。時衆教団はいつも「南無阿弥陀仏」の集団的熱狂を伴っていた。しかしその中心の一遍は、いつでも孤独を抱えていたのかもしれない。
先行研究の紹介は煩瑣でもあるが、中世において大きな存在感のある時衆について手軽に学べる本。
著者の桜井哲夫は近現代ヨーロッパを主な対象とする社会学者であり、時衆については専門外である。が同時に時宗寺院の住職であって、その立場からまとめたのが本書である。よって本書は、著者自身の研究というよりも、これまでの時衆研究を概観してみようというものである。
本書は2部に分かれており、第1部は時衆とは何かということが様々なトピックから紐解かれている。先行研究が縦横に紹介されているので初学者には有り難いが、一方で「○○はこう言っている」という形で様々なことが雑然と語られているという側面もあり、時衆の全体像はやや摑みにくい。
個人的に気になったのは、時衆僧侶は「陣僧」として戦に同行して戦没者の葬儀を執り行っており、それが賦役として課されていたという点。本書では簡単に書いているが、時衆の性格を考察する上で重要だと思われる。
そもそも私が時衆に興味を抱いたのも、葬送との関連であった。中世の葬制が整っていくにあたり、大きな役割を果たしたのは禅宗であり、またそれを武士階級から一般まで普及させていったのは律宗の影響が大きいらしい。しかしその背景として、時衆の存在が非常に気にかかるのである。葬送は言うまでもなく死体を扱うので、当時(中世初期)には穢れの問題がやかましかった。そんな中で、「浄不浄を問わず」としていた時衆はかなり葬儀に関わっていたらしく、また実際に陣僧として活躍していたことを踏まえると、葬制の確立において時衆の果たした役割は大きいと考えられている。非人と時衆の関係がその核にあるのではないかという気がした。こうしたことについて本書ではほとんど触れられていないが、ここはさらに知りたいところである。
この他にも、江戸時代には時衆は遊行にかなり便宜を与えられていたということ、能などの芸道において時衆(と考えられている人)が活躍していたらしいということ、高野聖は時衆が吸収してしまったらしいということなど、様々な点が興味深かった。また、蓮如による浄土真宗の改革が真宗の時衆化ではなかったのかという指摘は面白かった。中世において時衆は非常に隆盛し、多くの信者を獲得したものの、蓮如によって浄土真宗が興隆してゆくと時衆は不思議と衰微していく。これは時衆の徒が浄土真宗に吸収されていった結果であると考えられる。確かに親鸞の浄土真宗は非常に学理的であるが、蓮如の浄土真宗は明解で庶民的であり、時衆風なのである。
第2部では、『一遍聖絵』に基づいて一遍の生涯を紹介している。『一遍聖絵』の研究と、一遍の伝記的研究が同時に扱われているので、こちらもやや煩瑣な部分があるが、時系列的になっている分、第1部に比べるとすっきりしている。
伝記的部分で気になったのは、一遍は神祇不拝ではなくむしろ積極的に神社等に参拝したということや、往生の際の奇瑞を信用せず、そうした奇跡的な現象を迷信だと退けていたという点である。時衆は教義らしい教義を持たない宗派であるとされることもあり、事実一遍は一冊の著書も残さなかったが(入寂の前に焼き捨てた)、彼が残した和歌を見ると宗教家としての思想が感じられる。
おのづから あひあうときも わかれても ひとりはおなじ ひとりなりけり
時衆は集団で念仏踊りに狂う宗派であったのは事実である。その興奮は時として入水往生(入水自殺)をも伴った。時衆教団はいつも「南無阿弥陀仏」の集団的熱狂を伴っていた。しかしその中心の一遍は、いつでも孤独を抱えていたのかもしれない。
先行研究の紹介は煩瑣でもあるが、中世において大きな存在感のある時衆について手軽に学べる本。
2019年10月14日月曜日
『日本宗教史』末木 文美士 著
古代から現代に到る日本宗教史を概観する本。
本書の対象とする範囲は非常に広く、新書という形式で記述するには無謀なほどである。そのため細かいことは省き、梗概のみの記載に留めている事項も散見され、古代から中世にかけては特に簡略である。このあたりは分量的には2倍くらい欲しかったのが正直なところである。
逆に近世以降の神道論の展開には、結構紙幅を割いているようだった。著者の専門は言うまでもなく仏教の方にあるが、神道論の展開を丁寧に扱っているのが意外であり好感を持った。
一方で、七福神信仰とか観音・地蔵信仰、庚申講といった近世の民衆的な宗教ムーブメントについては全く記載がなく、やや物足りなく感じたのも事実である。
要するに、本書は日本宗教史を描くにあたり、年表的な事実を教科書的にまとめているというよりも、著者なりの視点で大胆に取捨選択がなされているのである。そして「選択」された部分については割合に丁寧に描かれる。であるから、事実の羅列的な部分はほとんどなく、宗教史が一筋の流れとして理解でき、非常に平易である。著者自身が後書きで本書を評して「試論」「たたき台」「大胆な挑戦の書」と述べているように、決定版とはいえない本だが、本書を刺激として様々な考察を広げてゆく可能性を感じさせる本である。
なお、本書は「<古層>の形成・発見」を大きなテーマとしている。精神的変革が求められる時代にあたって、日本人は多くの場合<古層>を参照し、<古層>に返るというスタンスで革新を成し遂げてきた。しかしその<古層>自体が、歴史的事実としての古思想・文化ではなくて、「そうあるはずだった過去」として形成されたものであったというのである。これは各時代で検証しなくてはならない主張なので、妥当なのかどうかは私には判断できないが、著者はなんでもかんでも<古層>を牽強付会しようとはしていないので、読んでいてあまり違和感はなかった。とはいえそれが斬新な視点であるとも思えず、テーマとしての「<古層>の形成・発見」にはさほど魅力を感じなかったというのが正直な感想である。
「<古層>の形成・発見」はピンと来ないが、日本宗教史の詩論として価値ある本。
本書の対象とする範囲は非常に広く、新書という形式で記述するには無謀なほどである。そのため細かいことは省き、梗概のみの記載に留めている事項も散見され、古代から中世にかけては特に簡略である。このあたりは分量的には2倍くらい欲しかったのが正直なところである。
逆に近世以降の神道論の展開には、結構紙幅を割いているようだった。著者の専門は言うまでもなく仏教の方にあるが、神道論の展開を丁寧に扱っているのが意外であり好感を持った。
一方で、七福神信仰とか観音・地蔵信仰、庚申講といった近世の民衆的な宗教ムーブメントについては全く記載がなく、やや物足りなく感じたのも事実である。
要するに、本書は日本宗教史を描くにあたり、年表的な事実を教科書的にまとめているというよりも、著者なりの視点で大胆に取捨選択がなされているのである。そして「選択」された部分については割合に丁寧に描かれる。であるから、事実の羅列的な部分はほとんどなく、宗教史が一筋の流れとして理解でき、非常に平易である。著者自身が後書きで本書を評して「試論」「たたき台」「大胆な挑戦の書」と述べているように、決定版とはいえない本だが、本書を刺激として様々な考察を広げてゆく可能性を感じさせる本である。
なお、本書は「<古層>の形成・発見」を大きなテーマとしている。精神的変革が求められる時代にあたって、日本人は多くの場合<古層>を参照し、<古層>に返るというスタンスで革新を成し遂げてきた。しかしその<古層>自体が、歴史的事実としての古思想・文化ではなくて、「そうあるはずだった過去」として形成されたものであったというのである。これは各時代で検証しなくてはならない主張なので、妥当なのかどうかは私には判断できないが、著者はなんでもかんでも<古層>を牽強付会しようとはしていないので、読んでいてあまり違和感はなかった。とはいえそれが斬新な視点であるとも思えず、テーマとしての「<古層>の形成・発見」にはさほど魅力を感じなかったというのが正直な感想である。
「<古層>の形成・発見」はピンと来ないが、日本宗教史の詩論として価値ある本。
2019年10月13日日曜日
『列島を翔ける平安武士—九州・京都・東国』野口 実 著
平安時代から鎌倉時代にかけての武士のネットワークを南九州にフォーカスして述べる。
鎌倉時代の武士というと、開発領主としての性格が強く、「一所懸命」という言葉に象徴されるように土地との結びつきが強固であった。彼らはその本拠地の地名を名字にし、土地を自らのアイデンティティとしていた。その土地のことを「本貫」とか「名字の地」という。それくらい、武士にとって土地は本質的なものであった。しかし一方で、戦国大名などとは違い、中世の武士はその本拠地からかなり遠方にも領地を持ち、遠隔地の荘園経営を行ってもいたのである。
南九州のような僻遠の地も、決して孤立的な地域だったのではなく、むしろ大陸や南島との交易での利益が期待できる有利な土地として武士や貴族たちの手を転がされていた。本書は、藤原保晶、平為賢と平季基、阿多忠景と源為朝、千葉常胤と島津忠久などを中心として、南九州と京都、鎌倉の関係性やネットワークを事例から検証するものである。
武士たちの社会的正統性は天皇(国家)を警護することにあったので、長期間京都に勤務する必要があった。そのため彼らは京都で上級の貴族との結びつきを作ることができ、また京都在勤の他の地域の武士との横の繋がりも持つことができた。そしてもちろん御家人にとっては鎌倉も重要な土地だった。本貫の地、京都、鎌倉、そして遠方の所領と、彼らは意外と活発に移動し、全国規模のネットワークを構築していたのである。
また本書は、島津庄(しまづのしょう)の成立と発展がもう一つのテーマとなっており、それを通して武士たちのネットワークを垣間見させるものとなっている。
島津庄の起源は、大宰府の大監であった平季基(すえもと)が島津院を中心とした地域を宇治関白家(藤原頼道)へ万寿年間(1024〜1028年)に寄進したことにある。それは今の都城市あたりだったが、そこは日向国府から大隅国府に向かう官道が通じ、大陸や南島との交易の拠点であった志布志へも通じる交通の要衝であり、農業生産というよりも当初から交易を念頭にして設置されたものだったらしい。
史料上では、季基は「無主の荒野」を開墾して寄進したとなっているが、実際の立荘の担い手は在地勢力で、彼らが季基の威勢を頼り、さらに季基が上級の権威を頼って摂関家へ寄進したというのが実状と見られる。この頃、大宰府に属する軍事貴族の南九州への進出が顕著であったらしく、島津庄の場合も、大宰府の権威を基盤として立荘されたといえる。
こうして設立された島津庄は、やがて薩摩・大隅にまで拡大され、12世紀後半には8000町歩もの日本最大の荘園に成長する。その領主は摂関家に相伝され、南方交易からもたらされる「夜光貝」「檳榔毛(びんろうげ)」など、並の貴族では手に入れられない贅沢品を手に入れるルートになった。だが、藤原基実(もとざね)が若くして急死したことでその妻が相続。この妻が平清盛の娘の盛子で、こうして島津庄は平家の支配下に入ることになる。
なお平季基の子孫は大宰府に基盤を確保しつつ肥前国で領主的な発展を遂げ、太宰府領を基盤として薩摩国に進出。そして河辺氏、頴娃氏、鹿児島氏といった郡名を姓とする「薩摩平氏」という有力在地勢力の一族に成長した。
その中でも有名なのが阿多忠景(ただかげ)である。阿多忠景は阿多郡(現南さつま市金峰町)の郡司職を梃子に国務に参与して「一国惣領」、つまり薩摩国全体を手中に収めた。その力の源泉となったのが、おそらくは万之瀬川河口を利用した大陸・南島との交易であって、それを裏付けるように河口の持躰松(もったいまつ)遺跡からは博多以外では他に類を見ないほどの大陸製陶磁器や国内産陶磁器が出土している。こうした交易からは莫大な利益が上がったものと見られ、阿多忠景は「成功(じょうごう)」、すなわち売官によって下野権守(しもうさごんのかみ)の官職を手に入れてのし上がったのである。
しかも忠景は、中央政界との結びつきをより強固にする意図があったと思われるが、鎮西(九州)に威を奮った源為朝を娘の婿に迎えている。こうして阿多忠景は為朝とのコンビで南九州に強大な勢力を誇った。しかし源為朝は保元の乱で敗れ、忠景は勅勘を蒙って平家の有力家人である筑後守平家貞(いえさだ)の追討を受けて没落し、その領地も平家の勢力下に入った。
時代が源平合戦の頃に移ると、南九州の勢力図も激変が生じる。鎌倉幕府設立の功労者である千葉常胤(本貫は房総半島)が九州に侵攻し、その侵略範囲を領地化していったからだ。南九州では現薩摩川内市や伊佐市にあたる北薩の地域の地頭が千葉常胤となった。また島津庄には、地頭として惟宗忠久(これむね・ただひさ)が任命される。これが島津氏の祖である。
惟宗忠久は、元来は摂関家たる近衛家の下家司(しもけいし)であり、つまり近衛家の職務に与る一介の京侍に過ぎず、今で言えば単なる下級役人であったと思われ、元来の頼朝の御家人ではなかった。それが島津庄という大荘園の地頭にいきなり抜擢されたのは、どういうわけか。
史料上ではその実状は不明であるが、状況証拠としては、忠久は近衛家の家臣であるとともに、頼朝の乳母(比企尼)の縁者であったと見られる。つまり島津庄という日本一の荘園を領主である近衛家ともめ事を起こさずに幕府の支配下に置くため、双方に関係を有する忠久を京都からスカウトして御家人とし地頭にしたのではないか、というのが著者の考えである。ともかく忠久はこうして本貫を島津庄と定めて「島津」姓とし、南九州の三国(薩摩・大隅・日向)を支配する島津氏の始まりとなったのである。
これまでの島津庄成立史を振り返ってみて思うのは、南九州は僻遠の地でありながら、大宰府や中央勢力の政治的力学が非常に強く影響しているということである。仮に南九州が孤立的地域であれば、そこには中央政府とは何の関係も持たない、力によって支配を打ち立てた勢力が盤踞していてもおかしくないのであるが、実際には中央政府と強いパイプを持つ人物が、公的な力を持って勢力を確立しているという感じが強いのである。中世の南九州は、荒くれ者たちが力で支配を競った無法地帯ではなかった。
中世の武士というと、忠義といった江戸時代的な固定関係の思想がなく、実利によって動く武力を頼みにする存在、といったイメージが強いが、それは物事の一面でしかない。むしろ実利を重視するがゆえに、中央政府の威光や貴顕の人物との縁戚関係を最大限に利用し、最小限の武力によって世を渡り歩いたということだったのかもしれない。事実、鎌倉時代における南九州の覇者である惟宗忠久は、一切軍功がない。彼は一兵をも動かすことなく島津庄を手に入れているのである。
すなわち、武士は意外と「政治的存在」であった。いや、この時代は後世とは違って世襲的階級としての「武士」は存在していないのである。「武士」と呼ばれた人々は、もちろん武力も行使したが、別の面では政治家であり、農地の開発領主であり、また交易を担う商人でもあった。そういう多様な側面を持つ存在として、日本全国にわたるネットワークと政治力を活用していたのである。
島津庄の歴史を繙くことで中世の武士像の修正を促す本。
鎌倉時代の武士というと、開発領主としての性格が強く、「一所懸命」という言葉に象徴されるように土地との結びつきが強固であった。彼らはその本拠地の地名を名字にし、土地を自らのアイデンティティとしていた。その土地のことを「本貫」とか「名字の地」という。それくらい、武士にとって土地は本質的なものであった。しかし一方で、戦国大名などとは違い、中世の武士はその本拠地からかなり遠方にも領地を持ち、遠隔地の荘園経営を行ってもいたのである。
南九州のような僻遠の地も、決して孤立的な地域だったのではなく、むしろ大陸や南島との交易での利益が期待できる有利な土地として武士や貴族たちの手を転がされていた。本書は、藤原保晶、平為賢と平季基、阿多忠景と源為朝、千葉常胤と島津忠久などを中心として、南九州と京都、鎌倉の関係性やネットワークを事例から検証するものである。
武士たちの社会的正統性は天皇(国家)を警護することにあったので、長期間京都に勤務する必要があった。そのため彼らは京都で上級の貴族との結びつきを作ることができ、また京都在勤の他の地域の武士との横の繋がりも持つことができた。そしてもちろん御家人にとっては鎌倉も重要な土地だった。本貫の地、京都、鎌倉、そして遠方の所領と、彼らは意外と活発に移動し、全国規模のネットワークを構築していたのである。
また本書は、島津庄(しまづのしょう)の成立と発展がもう一つのテーマとなっており、それを通して武士たちのネットワークを垣間見させるものとなっている。
島津庄の起源は、大宰府の大監であった平季基(すえもと)が島津院を中心とした地域を宇治関白家(藤原頼道)へ万寿年間(1024〜1028年)に寄進したことにある。それは今の都城市あたりだったが、そこは日向国府から大隅国府に向かう官道が通じ、大陸や南島との交易の拠点であった志布志へも通じる交通の要衝であり、農業生産というよりも当初から交易を念頭にして設置されたものだったらしい。
史料上では、季基は「無主の荒野」を開墾して寄進したとなっているが、実際の立荘の担い手は在地勢力で、彼らが季基の威勢を頼り、さらに季基が上級の権威を頼って摂関家へ寄進したというのが実状と見られる。この頃、大宰府に属する軍事貴族の南九州への進出が顕著であったらしく、島津庄の場合も、大宰府の権威を基盤として立荘されたといえる。
こうして設立された島津庄は、やがて薩摩・大隅にまで拡大され、12世紀後半には8000町歩もの日本最大の荘園に成長する。その領主は摂関家に相伝され、南方交易からもたらされる「夜光貝」「檳榔毛(びんろうげ)」など、並の貴族では手に入れられない贅沢品を手に入れるルートになった。だが、藤原基実(もとざね)が若くして急死したことでその妻が相続。この妻が平清盛の娘の盛子で、こうして島津庄は平家の支配下に入ることになる。
なお平季基の子孫は大宰府に基盤を確保しつつ肥前国で領主的な発展を遂げ、太宰府領を基盤として薩摩国に進出。そして河辺氏、頴娃氏、鹿児島氏といった郡名を姓とする「薩摩平氏」という有力在地勢力の一族に成長した。
その中でも有名なのが阿多忠景(ただかげ)である。阿多忠景は阿多郡(現南さつま市金峰町)の郡司職を梃子に国務に参与して「一国惣領」、つまり薩摩国全体を手中に収めた。その力の源泉となったのが、おそらくは万之瀬川河口を利用した大陸・南島との交易であって、それを裏付けるように河口の持躰松(もったいまつ)遺跡からは博多以外では他に類を見ないほどの大陸製陶磁器や国内産陶磁器が出土している。こうした交易からは莫大な利益が上がったものと見られ、阿多忠景は「成功(じょうごう)」、すなわち売官によって下野権守(しもうさごんのかみ)の官職を手に入れてのし上がったのである。
しかも忠景は、中央政界との結びつきをより強固にする意図があったと思われるが、鎮西(九州)に威を奮った源為朝を娘の婿に迎えている。こうして阿多忠景は為朝とのコンビで南九州に強大な勢力を誇った。しかし源為朝は保元の乱で敗れ、忠景は勅勘を蒙って平家の有力家人である筑後守平家貞(いえさだ)の追討を受けて没落し、その領地も平家の勢力下に入った。
時代が源平合戦の頃に移ると、南九州の勢力図も激変が生じる。鎌倉幕府設立の功労者である千葉常胤(本貫は房総半島)が九州に侵攻し、その侵略範囲を領地化していったからだ。南九州では現薩摩川内市や伊佐市にあたる北薩の地域の地頭が千葉常胤となった。また島津庄には、地頭として惟宗忠久(これむね・ただひさ)が任命される。これが島津氏の祖である。
惟宗忠久は、元来は摂関家たる近衛家の下家司(しもけいし)であり、つまり近衛家の職務に与る一介の京侍に過ぎず、今で言えば単なる下級役人であったと思われ、元来の頼朝の御家人ではなかった。それが島津庄という大荘園の地頭にいきなり抜擢されたのは、どういうわけか。
史料上ではその実状は不明であるが、状況証拠としては、忠久は近衛家の家臣であるとともに、頼朝の乳母(比企尼)の縁者であったと見られる。つまり島津庄という日本一の荘園を領主である近衛家ともめ事を起こさずに幕府の支配下に置くため、双方に関係を有する忠久を京都からスカウトして御家人とし地頭にしたのではないか、というのが著者の考えである。ともかく忠久はこうして本貫を島津庄と定めて「島津」姓とし、南九州の三国(薩摩・大隅・日向)を支配する島津氏の始まりとなったのである。
これまでの島津庄成立史を振り返ってみて思うのは、南九州は僻遠の地でありながら、大宰府や中央勢力の政治的力学が非常に強く影響しているということである。仮に南九州が孤立的地域であれば、そこには中央政府とは何の関係も持たない、力によって支配を打ち立てた勢力が盤踞していてもおかしくないのであるが、実際には中央政府と強いパイプを持つ人物が、公的な力を持って勢力を確立しているという感じが強いのである。中世の南九州は、荒くれ者たちが力で支配を競った無法地帯ではなかった。
中世の武士というと、忠義といった江戸時代的な固定関係の思想がなく、実利によって動く武力を頼みにする存在、といったイメージが強いが、それは物事の一面でしかない。むしろ実利を重視するがゆえに、中央政府の威光や貴顕の人物との縁戚関係を最大限に利用し、最小限の武力によって世を渡り歩いたということだったのかもしれない。事実、鎌倉時代における南九州の覇者である惟宗忠久は、一切軍功がない。彼は一兵をも動かすことなく島津庄を手に入れているのである。
すなわち、武士は意外と「政治的存在」であった。いや、この時代は後世とは違って世襲的階級としての「武士」は存在していないのである。「武士」と呼ばれた人々は、もちろん武力も行使したが、別の面では政治家であり、農地の開発領主であり、また交易を担う商人でもあった。そういう多様な側面を持つ存在として、日本全国にわたるネットワークと政治力を活用していたのである。
島津庄の歴史を繙くことで中世の武士像の修正を促す本。
2019年10月9日水曜日
『死者たちの中世』勝田 至 著
中世、多くの死者が墓地に葬られるようになる背景を説き明かす本。
平安末期、京都には日常的に死体が放置されていた。貴族の屋敷や内裏においてさえ、野犬が死体の一部を置いていくことが珍しくなかった。当時は死の穢れが神経質に避けられていたから、屋敷で死体の一部がみつかれば「五体不具穢(ごたいふぐえ)」となって、7日間の出仕停止(謹慎)が必要であった(※この「五体不具」は、死体の一部によるという意味)。彼らは死体が見つかった気味の悪さや死者への弔いの気持ちよりも、7日間の謹慎を食らうことを気にしており、日記に書き留めた(ちなみに全身死体の場合は30日の謹慎だった)。それが仕事に影響することだったからだ。
よって、貴族の日記にはたびたび遺棄された死体のことが記録された。著者は、その記録を詳細に分析し、12世紀には「五体不具穢」などの記事が頻繁に出てくるのに、13世紀前半にそうした記事が急減することを突き止めた。12世紀の京都では死体放置・遺棄が日常的であったが、13世紀前半にはあまり死体は放置されなくなり、14世紀には稀な出来事になっていた。これはどうしてなのだろうか? それが本書の問題提起であり、この謎解きが本書のテーマである。
そもそも、なぜ死体は放置されていたのだろうか。それにはいくつか理由があった。
第1に、死者の葬送はほとんど親族しか携わることができなかった。その背景には死の穢れへの懼れ・忌みがあったと思われる。このため、肉親が少ない人は死を目前にすると自ら(!)葬所へ赴いたりした。また家の中で家族の死体が放置されていることもよくあった。死体が重すぎて女一人では移動させられなかった場合などだ。つまり葬送は、あくまで家族が自力でやるもので地域社会はこれに協力しなかった。
第2に、当時は鳥葬が行われていた。貴族や財力のある人は火葬を行うことが出来たが、火葬にはかなりお金がかかった。よって河原や山に死体を放置することにはそれほど抵抗感はなかった。鳥葬は山野で行う方が好ましいとは思われていたが、死体をそこまで運んでいくのも一苦労だったので、荒廃した貴族の屋敷地やそのあたりの空き地に死体を置いておくのも珍しくはなかった。そもそも低層の人々にとって、死体の遺棄と鳥葬の間には明確な線がなかったと思われる。
第3に、使用人が病気になり死にそうになると家を追い出すことが一般的に行われていた。もし家の中で使用人が病死すれば、死穢によって30日間の謹慎になるからである。今から見ると非人道的と言うほかないが、こうして死に瀕した病人が追い出され、路傍で死んだ。
こうした理由から、疫病が流行した時には当然河原には死体が溢れ、そうでなくても京都には若干の死体が放置されていることは珍しくなかった。もちろん国家はそれを好ましいものとはせず、検非違使に死体清掃のパトロールをさせることはあったが、それも何か行事がある時に限られ、積極的にこれを対策しようという気はなかったようだ。死の穢れを神経質なまでに気にしていたのに、「開放空間(道路や広場)にある死体の穢れは伝染しない」というような屁理屈で街中の死体を黙認していたのが平安朝であった。
それがなぜ13世紀前半に放置死体は急減するのか。その謎を解くため、本書では当時の葬送がどうであったかをまとめている。死の直前から年忌法要に至るまでの各段階における儀礼がこれまでの研究に基づいて整理されており、この項目は大変参考になり、便覧としても便利である。
その中でも火葬場の様子が興味深い。この頃は常設の火葬場はなく、そのたびごとに火葬場(「山作所」という)をしつらえていたが、上級の人々の場合、その形式は、荒垣で囲んで四方に鳥居で門を設けるものだった。四門はそれぞれ発心門、修行門、菩提門、涅槃門と呼ばれていた。門の名前だけでなく葬送儀礼全体が仏式で行われながら、「鳥居」が使われているのが面白い。やや時代は下るが天文5年(1536年)制作の『日蓮聖人註画讃』にはその様子が描かれており、仏式の場に鳥居が並んでいるのが奇異である。なぜ仏教は葬送の場において鳥居を必要としたのだろうか。大変興味を引かれる。
なお葬儀には死霊を恐れ、その害を避ける儀式が多いが、「貴族はそれを行いつつも「世俗の忌」として否定的に見ているようである(p.123)」という指摘が目を引いた。貴族は死霊を実体として扱うことを迷信的と思っていた節がある。「貴族は葬送のやり方を詳細に日記に書いているが、個々の儀礼について、死霊や魔がどうとかは一言半句も書いていない。(中略)彼らはそういう解釈を系統的に排除しているような感じがする(同)」とのことである。しかし死霊を避ける儀礼(出棺後に竹箒で掃くなど)は徐々に貴族社会にも浸透し、12世紀中期からは「世俗の忌」的儀礼が取り入れられるようになる。普通、文化は上流から下流に伝わっていくが、この時代の葬送儀礼に関しては民衆的な「俗信」が貴族社会に逆流していく感じがする。
葬送儀礼は全体として、鎌倉時代にかけて整備が進んでくる感じである。また散発的・個別的だった墓地(その都度適当な山野を選んで墓を作っていた)が12世紀後半になると全国的に広域の共同墓地が営まれるようになってくる。京都では、「鳥辺野」に加え「蓮台野」という墓地が12世紀中頃に成立している。また墓地が一門の繁栄の源泉という考え方も現れ、一門墓地も形成された。墓地=穢れという感覚が希薄になり、むしろ聖性を帯びてくるのである。共同墓地の場合も、ただ墓をまとめただけというのではなく、そこに葬れば必ず極楽往生できるといった聖性を帯びた「勝地」と捉えられ、実際僧侶によって結界が行われるなど聖域としての性格を有していた。なお平安中〜後期には墓自体が全国的に少なく、どのように葬ったのか謎が大きいそうだ。
このように当時の葬送を外観し、それが13世紀にどう変化していくのかを見るのであるが、その変革の兆しとなったは、「二十五三昧会(にじゅうござんまいえ)」である。これは僧侶が極楽往生するための互助組合のようなもので、恵心僧都源信が寛和2年(986年)に組織した念仏結社である。お互い極楽往生を遂げられるよう念仏を欠かさないようにし、死にそうになったら他のメンバーで面倒を見て葬儀も共同で行うというもので、「寺院内部でさえ葬式互助がなかった当時としてまさに画期的なものだった。(p.179)」
この「二十五三昧会」は12世紀には天台系の寺院で普及し、また死を目前とした貴族がこれに加入して共同の火葬場を利用させてもらうことも出てきた。さらに13世紀後半からは「念仏講」のような形で次第に一般社会にも浸透していき、血縁のない人の葬式の手伝いをするという行為が普及していく。こうして死体が放置される理由の第1は徐々に解消されていくのである。
さらに死者が葬られるべき共同墓地が出現したことで、鳥葬をするにせよ、どこかの空き地に放置するのではなく、「鳥辺野」や「蓮台野」まで持っていくことが期待されるようになった。さらに著者はそうした死体運搬に「坂非人」(清水坂にいた非人)が活躍したのではないかと推測している。
平安時代の「非人」は後の被差別階級とは異なり、ハンセン病患者などによって構成され、救恤の対象と見られていたのであるが、鎌倉時代になると彼らは「葬送得分権」を持つようになり強固な集団となっていく。この「葬送得分権」というのは、死者の葬儀を行う代わりにその衣服や葬具を奪取する権利であり、やがて彼らは京中の葬送に関する権利を持つようになって、南北朝時代(14世紀)には死体を運ぶ輿を独占する権利(輿独占権)を有し、輿の貸しだしで収入を得るようになった。さらに16世紀になると寺院が独自の葬式をする場合に、葬式一回あたりいくらの権利料を非人集団に支払うまでになるのである。
そして著者は、非人集団が「葬送得分権」を持つようになったきっかけが、葬送において鳥辺野や蓮台野まで死体を運ぶサービスを行ったことにあるのではないかと推測する。いくら共同墓地が「勝地」であったにしろ、死体を運ぶのは重労働である。しかし死体の衣類などと引き換えに非人集団が代わりに運んでくれるのであれば、あえて死体をそこらに放置するより運んでもらうことを選ぶだろう。こうして死体が放置される理由の第2が解消されたというのが著者の考えである。
ただし、(1)京中の放置死体の減少するのと歩調をあわせ、(2)蓮台野が大規模共同墓地として成長し、(3)同時期に非人の組織が史料に現れる、という状況証拠はあるものの、非人が棺を運んでいたこと自体を証明する史料は存在しないそうだ。
なお死体が放置される理由の第3については特に変化したとの指摘はないが、行き倒れの死体や極貧で身寄りのないものの死体は川や野山に棄てられるのは中世後期(14〜15世紀)でも続いていたと述べている。
本書は問題設定が極めて明解で、中世の葬儀に関する情報が総動員されており、著者の推測は史料の裏付けはないとはいえ説得的である。放置死体の減少から京都の葬儀事情が繙かれるという構成は読みやすく、葬送という地味な話題を扱っているにもかかわらず引き込まれる。
ただし思想面では若干記載が弱く、13世紀前半に放置死体が減少する背景に思想的な変遷もあったのではないかという気がさせられた。例えば本書には鎌倉新仏教とか浄土教の流行といったものはほとんど触れられていないが、こうしたものは葬送儀礼には影響していないのだろうか。唯一、葬送儀礼の整備には禅宗が積極的だったと簡単な記載があったのみだが、このあたりはもう少し考察が欲しかったところである。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
【関連書籍】
『中世の葬送・墓制—石塔を造立すること』水藤 真 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_4.html
中世の葬式がどうであったか検証する本。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
平安末期、京都には日常的に死体が放置されていた。貴族の屋敷や内裏においてさえ、野犬が死体の一部を置いていくことが珍しくなかった。当時は死の穢れが神経質に避けられていたから、屋敷で死体の一部がみつかれば「五体不具穢(ごたいふぐえ)」となって、7日間の出仕停止(謹慎)が必要であった(※この「五体不具」は、死体の一部によるという意味)。彼らは死体が見つかった気味の悪さや死者への弔いの気持ちよりも、7日間の謹慎を食らうことを気にしており、日記に書き留めた(ちなみに全身死体の場合は30日の謹慎だった)。それが仕事に影響することだったからだ。
よって、貴族の日記にはたびたび遺棄された死体のことが記録された。著者は、その記録を詳細に分析し、12世紀には「五体不具穢」などの記事が頻繁に出てくるのに、13世紀前半にそうした記事が急減することを突き止めた。12世紀の京都では死体放置・遺棄が日常的であったが、13世紀前半にはあまり死体は放置されなくなり、14世紀には稀な出来事になっていた。これはどうしてなのだろうか? それが本書の問題提起であり、この謎解きが本書のテーマである。
そもそも、なぜ死体は放置されていたのだろうか。それにはいくつか理由があった。
第1に、死者の葬送はほとんど親族しか携わることができなかった。その背景には死の穢れへの懼れ・忌みがあったと思われる。このため、肉親が少ない人は死を目前にすると自ら(!)葬所へ赴いたりした。また家の中で家族の死体が放置されていることもよくあった。死体が重すぎて女一人では移動させられなかった場合などだ。つまり葬送は、あくまで家族が自力でやるもので地域社会はこれに協力しなかった。
第2に、当時は鳥葬が行われていた。貴族や財力のある人は火葬を行うことが出来たが、火葬にはかなりお金がかかった。よって河原や山に死体を放置することにはそれほど抵抗感はなかった。鳥葬は山野で行う方が好ましいとは思われていたが、死体をそこまで運んでいくのも一苦労だったので、荒廃した貴族の屋敷地やそのあたりの空き地に死体を置いておくのも珍しくはなかった。そもそも低層の人々にとって、死体の遺棄と鳥葬の間には明確な線がなかったと思われる。
第3に、使用人が病気になり死にそうになると家を追い出すことが一般的に行われていた。もし家の中で使用人が病死すれば、死穢によって30日間の謹慎になるからである。今から見ると非人道的と言うほかないが、こうして死に瀕した病人が追い出され、路傍で死んだ。
こうした理由から、疫病が流行した時には当然河原には死体が溢れ、そうでなくても京都には若干の死体が放置されていることは珍しくなかった。もちろん国家はそれを好ましいものとはせず、検非違使に死体清掃のパトロールをさせることはあったが、それも何か行事がある時に限られ、積極的にこれを対策しようという気はなかったようだ。死の穢れを神経質なまでに気にしていたのに、「開放空間(道路や広場)にある死体の穢れは伝染しない」というような屁理屈で街中の死体を黙認していたのが平安朝であった。
それがなぜ13世紀前半に放置死体は急減するのか。その謎を解くため、本書では当時の葬送がどうであったかをまとめている。死の直前から年忌法要に至るまでの各段階における儀礼がこれまでの研究に基づいて整理されており、この項目は大変参考になり、便覧としても便利である。
その中でも火葬場の様子が興味深い。この頃は常設の火葬場はなく、そのたびごとに火葬場(「山作所」という)をしつらえていたが、上級の人々の場合、その形式は、荒垣で囲んで四方に鳥居で門を設けるものだった。四門はそれぞれ発心門、修行門、菩提門、涅槃門と呼ばれていた。門の名前だけでなく葬送儀礼全体が仏式で行われながら、「鳥居」が使われているのが面白い。やや時代は下るが天文5年(1536年)制作の『日蓮聖人註画讃』にはその様子が描かれており、仏式の場に鳥居が並んでいるのが奇異である。なぜ仏教は葬送の場において鳥居を必要としたのだろうか。大変興味を引かれる。
なお葬儀には死霊を恐れ、その害を避ける儀式が多いが、「貴族はそれを行いつつも「世俗の忌」として否定的に見ているようである(p.123)」という指摘が目を引いた。貴族は死霊を実体として扱うことを迷信的と思っていた節がある。「貴族は葬送のやり方を詳細に日記に書いているが、個々の儀礼について、死霊や魔がどうとかは一言半句も書いていない。(中略)彼らはそういう解釈を系統的に排除しているような感じがする(同)」とのことである。しかし死霊を避ける儀礼(出棺後に竹箒で掃くなど)は徐々に貴族社会にも浸透し、12世紀中期からは「世俗の忌」的儀礼が取り入れられるようになる。普通、文化は上流から下流に伝わっていくが、この時代の葬送儀礼に関しては民衆的な「俗信」が貴族社会に逆流していく感じがする。
葬送儀礼は全体として、鎌倉時代にかけて整備が進んでくる感じである。また散発的・個別的だった墓地(その都度適当な山野を選んで墓を作っていた)が12世紀後半になると全国的に広域の共同墓地が営まれるようになってくる。京都では、「鳥辺野」に加え「蓮台野」という墓地が12世紀中頃に成立している。また墓地が一門の繁栄の源泉という考え方も現れ、一門墓地も形成された。墓地=穢れという感覚が希薄になり、むしろ聖性を帯びてくるのである。共同墓地の場合も、ただ墓をまとめただけというのではなく、そこに葬れば必ず極楽往生できるといった聖性を帯びた「勝地」と捉えられ、実際僧侶によって結界が行われるなど聖域としての性格を有していた。なお平安中〜後期には墓自体が全国的に少なく、どのように葬ったのか謎が大きいそうだ。
このように当時の葬送を外観し、それが13世紀にどう変化していくのかを見るのであるが、その変革の兆しとなったは、「二十五三昧会(にじゅうござんまいえ)」である。これは僧侶が極楽往生するための互助組合のようなもので、恵心僧都源信が寛和2年(986年)に組織した念仏結社である。お互い極楽往生を遂げられるよう念仏を欠かさないようにし、死にそうになったら他のメンバーで面倒を見て葬儀も共同で行うというもので、「寺院内部でさえ葬式互助がなかった当時としてまさに画期的なものだった。(p.179)」
この「二十五三昧会」は12世紀には天台系の寺院で普及し、また死を目前とした貴族がこれに加入して共同の火葬場を利用させてもらうことも出てきた。さらに13世紀後半からは「念仏講」のような形で次第に一般社会にも浸透していき、血縁のない人の葬式の手伝いをするという行為が普及していく。こうして死体が放置される理由の第1は徐々に解消されていくのである。
さらに死者が葬られるべき共同墓地が出現したことで、鳥葬をするにせよ、どこかの空き地に放置するのではなく、「鳥辺野」や「蓮台野」まで持っていくことが期待されるようになった。さらに著者はそうした死体運搬に「坂非人」(清水坂にいた非人)が活躍したのではないかと推測している。
平安時代の「非人」は後の被差別階級とは異なり、ハンセン病患者などによって構成され、救恤の対象と見られていたのであるが、鎌倉時代になると彼らは「葬送得分権」を持つようになり強固な集団となっていく。この「葬送得分権」というのは、死者の葬儀を行う代わりにその衣服や葬具を奪取する権利であり、やがて彼らは京中の葬送に関する権利を持つようになって、南北朝時代(14世紀)には死体を運ぶ輿を独占する権利(輿独占権)を有し、輿の貸しだしで収入を得るようになった。さらに16世紀になると寺院が独自の葬式をする場合に、葬式一回あたりいくらの権利料を非人集団に支払うまでになるのである。
そして著者は、非人集団が「葬送得分権」を持つようになったきっかけが、葬送において鳥辺野や蓮台野まで死体を運ぶサービスを行ったことにあるのではないかと推測する。いくら共同墓地が「勝地」であったにしろ、死体を運ぶのは重労働である。しかし死体の衣類などと引き換えに非人集団が代わりに運んでくれるのであれば、あえて死体をそこらに放置するより運んでもらうことを選ぶだろう。こうして死体が放置される理由の第2が解消されたというのが著者の考えである。
ただし、(1)京中の放置死体の減少するのと歩調をあわせ、(2)蓮台野が大規模共同墓地として成長し、(3)同時期に非人の組織が史料に現れる、という状況証拠はあるものの、非人が棺を運んでいたこと自体を証明する史料は存在しないそうだ。
なお死体が放置される理由の第3については特に変化したとの指摘はないが、行き倒れの死体や極貧で身寄りのないものの死体は川や野山に棄てられるのは中世後期(14〜15世紀)でも続いていたと述べている。
本書は問題設定が極めて明解で、中世の葬儀に関する情報が総動員されており、著者の推測は史料の裏付けはないとはいえ説得的である。放置死体の減少から京都の葬儀事情が繙かれるという構成は読みやすく、葬送という地味な話題を扱っているにもかかわらず引き込まれる。
ただし思想面では若干記載が弱く、13世紀前半に放置死体が減少する背景に思想的な変遷もあったのではないかという気がさせられた。例えば本書には鎌倉新仏教とか浄土教の流行といったものはほとんど触れられていないが、こうしたものは葬送儀礼には影響していないのだろうか。唯一、葬送儀礼の整備には禅宗が積極的だったと簡単な記載があったのみだが、このあたりはもう少し考察が欲しかったところである。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
【関連書籍】
『中世の葬送・墓制—石塔を造立すること』水藤 真 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_4.html
中世の葬式がどうであったか検証する本。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
2019年10月6日日曜日
『畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史—因果応報と悪道』生駒 哲郎 著
中世の畜生・餓鬼・地獄の世界観について述べる。
仏教では殺生は重大な罪である。では戦で人を殺した武士はみな地獄に落ちたのか、狩猟を行った人は地獄に落ちた(と考えられた)のかというと実はそうではない。殺生は罪業であったが、地獄が必定の殺生と、そうでもない殺生があった。
ごく単純化して言えば、わけもなく人を殺した場合が地獄行きで、道理に基づいて人を殺した場合はそうでもないと考えられた。例えば大義名分のある戦の場合や、仇討ちの場合は同じ殺生でも義務を果たした行為と見なされた。そういう場合、地獄には落ちない。中世の仏教において、殺生は決定的な罪業とは考えられていなかった模様である。むしろ道理のなさ、慈悲のなさといったことの方が決定的であった。
また、ひとたび地獄に落ちても、地蔵菩薩が救ってくれるという思想も発達した。本書では、『今昔物語集』に収録された地蔵霊験譚を分析してその変遷を考察している。地蔵菩薩の功徳は、地獄に落ちそうになった人を閻魔庁で救い出してやるというところから始まったようである。地獄に落ちてしまった人には代受苦(地獄の苦しみを代わりに受けてくれる)を提供したが、やがて地獄から人道へ戻すこともやるようになり、人道から西方浄土への往生に導くようになる。地獄に落ちた人を救うという地蔵菩薩の性格が、浄土信仰と結びついているのが興味深い。
また、罪業を冒しても、それを機縁として仏道を修せば地獄落ちを避けることができると考えられた。このように、悪事をきっかけに仏道に入ることを「逆縁」といった(今でいう逆縁とは意味が違う)。地獄に落ちたくないという利己的な心によるものであっても悔過(けか=懺悔みたいなもの)を行い、仏像を安置し、法華経を写せばそれで罪が軽くなったのである。また、自らは仏道を修さずとも、追善供養でも地獄落ちは避けられた。殺人や裏切りといった悪事も地獄落ちの決定打ではなく、各種の「抜け道」があったということだ。こうした「抜け道」があることが、仏教の盛行に一役買っていたに違いない。抜け道のない峻厳な教義であれば、きっと仏教は中世においてそれほど一般化しなかったであろう。
本書ではさらに、畜生道に落ちる場合はどんな時か、そして畜生道に落ちると人はどうなると考えられたかについて述べ、次いで同様に餓鬼道の場合が述べられる。畜生道の場合で、神への供物に肉や魚を使うことの仏教的整合性をどうとったかという説明があるがこれが面白い。例えば神にハマグリを供えるということを考えると、これはハマグリを殺しているわけだから殺生である。これは神が殺生を要求しているということになり、仏教的に考えるとおかしい。当時は神と仏は神仏習合で一体化していたが、この矛盾はどう考えたらよいか。これは、畜生道に落ちてしまっているハマグリを神に供えることで仏道に触れる機縁とし、天人道へ転生する道筋であると考えたのである。ハマグリは畜生道で苦しんでいるわけだから、それを神に供えることによって救う、という話である。
本書にはごく簡単にしか書いていないが、敵方供養が重要であったという指摘も面白い。中世には敵方の妻や子どもまでも一族皆殺しにすることはなかったという。これは温情があったのではなくて、敵方の供養をする人を残すためなのであった。なぜなら、非業の死を遂げた人間は、適切な供養がなければ怨霊となり現世に仇なすと考えられたからである。よって戦の供養塔などでは敵方の供養も重要なこととみなされた。この頃の仏教はさほど倫理的ではないが、これは人道的な考え方だろう。
本書は「中世仏教史」というタイトルになっているが、中身はケーススタディ的なものが多く通史的ではない。畜生・餓鬼・地獄といったものがどのように考えられていたかということを記述するのがメインで、それらの分析や考察もあまりない。私は地獄の観念は中世の仏教に甚大な影響を与えていると感じているが、本書ではそうした思想史的展開がほとんど語られないのは少し残念だった。
事例紹介的で「中世仏教史」は名折れだが、中世の悪道の軽重を知ることができる手軽な本。
仏教では殺生は重大な罪である。では戦で人を殺した武士はみな地獄に落ちたのか、狩猟を行った人は地獄に落ちた(と考えられた)のかというと実はそうではない。殺生は罪業であったが、地獄が必定の殺生と、そうでもない殺生があった。
ごく単純化して言えば、わけもなく人を殺した場合が地獄行きで、道理に基づいて人を殺した場合はそうでもないと考えられた。例えば大義名分のある戦の場合や、仇討ちの場合は同じ殺生でも義務を果たした行為と見なされた。そういう場合、地獄には落ちない。中世の仏教において、殺生は決定的な罪業とは考えられていなかった模様である。むしろ道理のなさ、慈悲のなさといったことの方が決定的であった。
また、ひとたび地獄に落ちても、地蔵菩薩が救ってくれるという思想も発達した。本書では、『今昔物語集』に収録された地蔵霊験譚を分析してその変遷を考察している。地蔵菩薩の功徳は、地獄に落ちそうになった人を閻魔庁で救い出してやるというところから始まったようである。地獄に落ちてしまった人には代受苦(地獄の苦しみを代わりに受けてくれる)を提供したが、やがて地獄から人道へ戻すこともやるようになり、人道から西方浄土への往生に導くようになる。地獄に落ちた人を救うという地蔵菩薩の性格が、浄土信仰と結びついているのが興味深い。
また、罪業を冒しても、それを機縁として仏道を修せば地獄落ちを避けることができると考えられた。このように、悪事をきっかけに仏道に入ることを「逆縁」といった(今でいう逆縁とは意味が違う)。地獄に落ちたくないという利己的な心によるものであっても悔過(けか=懺悔みたいなもの)を行い、仏像を安置し、法華経を写せばそれで罪が軽くなったのである。また、自らは仏道を修さずとも、追善供養でも地獄落ちは避けられた。殺人や裏切りといった悪事も地獄落ちの決定打ではなく、各種の「抜け道」があったということだ。こうした「抜け道」があることが、仏教の盛行に一役買っていたに違いない。抜け道のない峻厳な教義であれば、きっと仏教は中世においてそれほど一般化しなかったであろう。
本書ではさらに、畜生道に落ちる場合はどんな時か、そして畜生道に落ちると人はどうなると考えられたかについて述べ、次いで同様に餓鬼道の場合が述べられる。畜生道の場合で、神への供物に肉や魚を使うことの仏教的整合性をどうとったかという説明があるがこれが面白い。例えば神にハマグリを供えるということを考えると、これはハマグリを殺しているわけだから殺生である。これは神が殺生を要求しているということになり、仏教的に考えるとおかしい。当時は神と仏は神仏習合で一体化していたが、この矛盾はどう考えたらよいか。これは、畜生道に落ちてしまっているハマグリを神に供えることで仏道に触れる機縁とし、天人道へ転生する道筋であると考えたのである。ハマグリは畜生道で苦しんでいるわけだから、それを神に供えることによって救う、という話である。
本書にはごく簡単にしか書いていないが、敵方供養が重要であったという指摘も面白い。中世には敵方の妻や子どもまでも一族皆殺しにすることはなかったという。これは温情があったのではなくて、敵方の供養をする人を残すためなのであった。なぜなら、非業の死を遂げた人間は、適切な供養がなければ怨霊となり現世に仇なすと考えられたからである。よって戦の供養塔などでは敵方の供養も重要なこととみなされた。この頃の仏教はさほど倫理的ではないが、これは人道的な考え方だろう。
本書は「中世仏教史」というタイトルになっているが、中身はケーススタディ的なものが多く通史的ではない。畜生・餓鬼・地獄といったものがどのように考えられていたかということを記述するのがメインで、それらの分析や考察もあまりない。私は地獄の観念は中世の仏教に甚大な影響を与えていると感じているが、本書ではそうした思想史的展開がほとんど語られないのは少し残念だった。
事例紹介的で「中世仏教史」は名折れだが、中世の悪道の軽重を知ることができる手軽な本。
2019年10月4日金曜日
『中世の葬送・墓制—石塔を造立すること』水藤 真 著
中世の葬式がどうであったか検証する本。
江戸時代になると葬送や墓制(火葬し、その後石塔に納骨するなど)は現代とさほど変わらない。しかしその前の中世では、死者に対する態度、死体の扱い方、葬送の仕方、墓の造立、墓参の仕方まで、その基本的態度がだいぶ違うようである。本書は、中世の葬送・墓制がどうであったか、各種の資料に基づいて推測するものである。
「第1 中世の葬送・墓制」では、藤原良通、藤原俊成、中原師右(もろすけ)の死にあたってどのようなことが行われたか記述される。この頃の葬送はこっそり行われ、各種の儀礼がかなりの期間にわたって行われたが、必ずしも造塔は伴わなかった。墓は忘れられていたわけではないし、墓参もあったようだが、後代の常識とは異なって石塔は必須とは考えられていなかったようだ。
「第2 中世的葬送・墓制の淵源」では、平安貴族、後醍醐天皇、貴族・庶民の葬送が検証される。ここでも貴族の日記などから葬儀の様子が述べられているが、後醍醐天皇の葬儀でもほとんど仏式に行われていることが注目される。この時代の葬式は今のように決まった形態がなく、バリエーションが非常に大きい。
「第3 石塔の作り方」は、技術的な意味での石塔の作り方ではなく、どのような思想によって石塔が造立されたかを述べる。この項は基本的なことであるが面白い。石塔を作ることは故人を弔うというよりも、積善・作善の行為であったとし、であるから必ずしも墓に石塔がなくてもいいし、逆に墓以外にも石塔をたくさん建ててもよいのであった。もちろん積善の行為は造塔だけでなく、仏事を修する、仏像を造立する、梵鐘を鋳造する、風呂を施す、罪人を解き放つといったことも積善と見なされていた。また生前に自らの供養をする逆修供養の事例が紹介されているが、文明3年(1471年)の例で、初七日や一周忌、十三回忌までを圧縮した日程で実施しているものがあり、逆修供養で生前に葬式の全課程を終えておく場合があったことを初めて知った。
「第4 中世における葬送・墓制の諸相」では、足利将軍家、僧侶、女性の葬儀について検証される。かつては仏式というだけで特に何宗ということのなかった葬儀が、14世紀、室町時代になると何宗という分化が生じ、時宗の影響を受けた禅宗の葬儀が盛行するようになる。また葬儀の執行が相続の正統性を示すものと受け止められるものとなったという。
「第5 色々な墓」では、文字通り墓にまつわるいろいろな話を列挙している。中でも葬送や石塔の費用について分析した部分が面白い。貴族の葬式では大変な出費があり、例えば母の追善供養のためにその領地を売却した例も紹介されている。なおその中で石塔の造立にかかるコストは比較的小さく、数多くの仏事を修するのが費用のメインである。とにかく葬式を正式に修すると大金がかかったので、逆修供養とは葬式の簡略化によるコスト削減でもあったのかもしれないと思った。
「第6 中世的墳墓の形成と実態」では、14世紀頃から葬送と石塔の造立がセットになっていったことが推測され、それには禅宗が積極的に関与したことが示唆されている。また墓が寺に営まれるようになったことが簡単に指摘されているが、これはさらに詳しく過程を知りたいところである。さらに悉皆調査が行われている埼玉県の板碑についての統計的な分析が行われ、墓の変遷がデータで述べられている。このデータは非常に示唆的で興味を引く。
全体的に葬儀の事例を列挙していく感じの内容であり、普通には退屈な本であるかもしれないが、中世の葬儀への興味を持って読むとどの項目も興味深く、意外と退屈せずに読んだ。ただし、事例の列挙であるためにあまり分析や考察はなされていない。一つひとつの事例についてもう少し突っ込んだ考察が欲しかった。また、副題が「石塔を造立すること」であるにもかかわらず、石塔そのものについての話(どのように制作されたのか、どのような形式の石塔があったのかなど)がほとんどないのは残念だった。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
【関連書籍】
『死者たちの中世』勝田 至 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_9.html
中世、多くの死者が墓地に葬られるようになる背景を説き明かす本。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
江戸時代になると葬送や墓制(火葬し、その後石塔に納骨するなど)は現代とさほど変わらない。しかしその前の中世では、死者に対する態度、死体の扱い方、葬送の仕方、墓の造立、墓参の仕方まで、その基本的態度がだいぶ違うようである。本書は、中世の葬送・墓制がどうであったか、各種の資料に基づいて推測するものである。
「第1 中世の葬送・墓制」では、藤原良通、藤原俊成、中原師右(もろすけ)の死にあたってどのようなことが行われたか記述される。この頃の葬送はこっそり行われ、各種の儀礼がかなりの期間にわたって行われたが、必ずしも造塔は伴わなかった。墓は忘れられていたわけではないし、墓参もあったようだが、後代の常識とは異なって石塔は必須とは考えられていなかったようだ。
「第2 中世的葬送・墓制の淵源」では、平安貴族、後醍醐天皇、貴族・庶民の葬送が検証される。ここでも貴族の日記などから葬儀の様子が述べられているが、後醍醐天皇の葬儀でもほとんど仏式に行われていることが注目される。この時代の葬式は今のように決まった形態がなく、バリエーションが非常に大きい。
「第3 石塔の作り方」は、技術的な意味での石塔の作り方ではなく、どのような思想によって石塔が造立されたかを述べる。この項は基本的なことであるが面白い。石塔を作ることは故人を弔うというよりも、積善・作善の行為であったとし、であるから必ずしも墓に石塔がなくてもいいし、逆に墓以外にも石塔をたくさん建ててもよいのであった。もちろん積善の行為は造塔だけでなく、仏事を修する、仏像を造立する、梵鐘を鋳造する、風呂を施す、罪人を解き放つといったことも積善と見なされていた。また生前に自らの供養をする逆修供養の事例が紹介されているが、文明3年(1471年)の例で、初七日や一周忌、十三回忌までを圧縮した日程で実施しているものがあり、逆修供養で生前に葬式の全課程を終えておく場合があったことを初めて知った。
「第4 中世における葬送・墓制の諸相」では、足利将軍家、僧侶、女性の葬儀について検証される。かつては仏式というだけで特に何宗ということのなかった葬儀が、14世紀、室町時代になると何宗という分化が生じ、時宗の影響を受けた禅宗の葬儀が盛行するようになる。また葬儀の執行が相続の正統性を示すものと受け止められるものとなったという。
「第5 色々な墓」では、文字通り墓にまつわるいろいろな話を列挙している。中でも葬送や石塔の費用について分析した部分が面白い。貴族の葬式では大変な出費があり、例えば母の追善供養のためにその領地を売却した例も紹介されている。なおその中で石塔の造立にかかるコストは比較的小さく、数多くの仏事を修するのが費用のメインである。とにかく葬式を正式に修すると大金がかかったので、逆修供養とは葬式の簡略化によるコスト削減でもあったのかもしれないと思った。
「第6 中世的墳墓の形成と実態」では、14世紀頃から葬送と石塔の造立がセットになっていったことが推測され、それには禅宗が積極的に関与したことが示唆されている。また墓が寺に営まれるようになったことが簡単に指摘されているが、これはさらに詳しく過程を知りたいところである。さらに悉皆調査が行われている埼玉県の板碑についての統計的な分析が行われ、墓の変遷がデータで述べられている。このデータは非常に示唆的で興味を引く。
全体的に葬儀の事例を列挙していく感じの内容であり、普通には退屈な本であるかもしれないが、中世の葬儀への興味を持って読むとどの項目も興味深く、意外と退屈せずに読んだ。ただし、事例の列挙であるためにあまり分析や考察はなされていない。一つひとつの事例についてもう少し突っ込んだ考察が欲しかった。また、副題が「石塔を造立すること」であるにもかかわらず、石塔そのものについての話(どのように制作されたのか、どのような形式の石塔があったのかなど)がほとんどないのは残念だった。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
【関連書籍】
『死者たちの中世』勝田 至 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_9.html
中世、多くの死者が墓地に葬られるようになる背景を説き明かす本。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
『寺社勢力の中世—無縁・有縁・移民』伊藤 正敏 著
中世の寺社勢力の姿を、様々な事例から解き明かす本。
中世において、寺社は幕府からも朝廷からも独立した存在であった。それを象徴するのは、寺社が「検断権」を持っていたということである。これは今の検察・警察権にあたる。たとえ謀反人であったとしても、寺社の境内に逃げ込めば幕府も朝廷も捜査はできなかった。あくまで、謀反人の捜査を寺社に「依頼」することしかできなかった。だから頼朝から追討された義経は比叡山に逃げ込んだ。比叡山に逃げ込めば、積極的な保護を受けられるかどうかは別として、直ちに幕府や朝廷に引き渡されることはなかったのである。
それは、百姓でも、悪党でも同じであった。俗世で行き詰まった人々は寺社を頼ってきた。少なくともそこでは俗世の階級やしがらみは断ち切ったことになっていた。実際には、寺社の中には貴族・武士階級を出自に持つ学侶と、百姓階級の行人・堂衆があり、僧侶としての身分は世襲されていたのであるが、建前としては寺社の境内では俗世をどう過ごしてきたかは不問にされた。これを著者は寺社の「無縁性」と呼ぶ。中世では、寺社は俗世の縁(有縁)を絶ちきり、しがらみのない状態(無縁)になれる唯一の場所であった。
そうして寺社にやってきた人々も、寺社の中で無為徒食できるわけではなかった。彼らは幕府や朝廷から距離を置くことはできたが、逆に言えば朝幕が用意していた社会システムから離れて生活の糧を得る必要があった。彼らは今で言えば「移民」であった。ある人は職人となり、ある人は商人となり、またある人は金融業を営んだ。こうした人々の生きるためのエネルギーによって寺社は最新技術を有し、中世の経済の中心となった。例えば根来寺(真義真言宗)では、武器製造が盛んだった。根来寺は高度な鍛冶技術を有し、鉄砲の三大生産地のひとつであった(他の2つは堺・近江国友)。
故郷を離れ、経済活動に勤しむ「個人」が集積していたところ、しかも国家と別の警察権を持ち、国家から半独立していたところ、それが寺社であった。著者はそうした寺社の様相を「境内都市」という用語で読み解く。中世末期、高野山には7千坊もの子院があったというが、これは宗教施設の集合ではなく、むしろ都市そのものだと考えた方がいいというのである。中世は農業中心の経済ではなく、多くの境内都市(=寺社)が活躍した都市経済の時代であった。
そして中世の京都は、事実都でもあったのだが、それ以上に叡山の門前町という性格が強かった。感神院祇園社は元は興福寺末寺であったが延暦寺(比叡山)が強奪し、祇園社を通じて比叡山は京都の経済を牛耳った。延暦寺の僧侶は、比叡山ではなく京都に住んでいたのである。
朝幕の勢力が、寺社勢力に対して無力だったわけではない。しかし朝廷と寺社勢力が争う場合、常に朝廷の腰は引けていた。神罰・仏罰を恐れたためだ。嗷訴(ごうそ)を行う場合、比叡山の僧侶は日吉社の神輿を持ち出した(神輿動座(しんよどうざ))。神の乗り物である神輿を置き去りにし、神意によって主張を通そうとしたのである。しかし「僧侶」が「神輿」を持ち出すというのが面白い。この頃、仏教と神道は、教義においてはもちろんアイテム的な面でも区別されていなかった。
本書はこうした寺社勢力の特質を、当時の文書(もんじょ)に現れる事例から読み解いている。鎌倉幕府の行政記録はほとんど残っていないし、当時の朝廷の様子も貴族の日記によって窺い知れるのみであるが、寺社の場合かなり寺としての記録が残っている上、貴族の日記にも頻繁に寺社とのもめ事が記述されているため、寺社の動向はこの時代の一次資料によってかなり解明できるんだそうである。
しかし、多くの事例から読み解くというスタイルであるため、本書はあまり体系的ではなく、時系列的でもないためややわかりにくい。さらに、著者はいわゆる「名物教授風」というか、かなりアクの強い書き方をしているため、文体の好みは分かれそうである(私自身はちょっと苦手だった)。
また「無縁性」を大きなキーワードとして寺社勢力の特質を読み解き、寺社に流入する人々を「移民」と捉える視点は面白いが、実際には寺社の中も世襲の僧侶たちによって相続されていたという事実と若干接続しない部分がある。ある面では寺社は「無縁所」であったし、移民が金持ちになれるアメリカン・ドリームな世界であったのは事実である。しかし「無縁」はあくまで寺社勢力の中の一部(特に行人・堂衆と呼ばれた人たち)の成立背景に過ぎず、「無縁」を以て寺社勢力全体を読み解くには無理があるような気がした。
ややアクの強い論ではあるが、「境内都市」という概念で寺社勢力の特質を繙いていく独特な本。
【関連書籍】
『寺社勢力—もう一つの中世社会』黒田 俊雄 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/blog-post_13.html
中世における寺社勢力の勃興と衰退を述べる。
中世の申し子とも言える寺社勢力を通じて当時の社会の内実を考えさせる良書。
中世において、寺社は幕府からも朝廷からも独立した存在であった。それを象徴するのは、寺社が「検断権」を持っていたということである。これは今の検察・警察権にあたる。たとえ謀反人であったとしても、寺社の境内に逃げ込めば幕府も朝廷も捜査はできなかった。あくまで、謀反人の捜査を寺社に「依頼」することしかできなかった。だから頼朝から追討された義経は比叡山に逃げ込んだ。比叡山に逃げ込めば、積極的な保護を受けられるかどうかは別として、直ちに幕府や朝廷に引き渡されることはなかったのである。
それは、百姓でも、悪党でも同じであった。俗世で行き詰まった人々は寺社を頼ってきた。少なくともそこでは俗世の階級やしがらみは断ち切ったことになっていた。実際には、寺社の中には貴族・武士階級を出自に持つ学侶と、百姓階級の行人・堂衆があり、僧侶としての身分は世襲されていたのであるが、建前としては寺社の境内では俗世をどう過ごしてきたかは不問にされた。これを著者は寺社の「無縁性」と呼ぶ。中世では、寺社は俗世の縁(有縁)を絶ちきり、しがらみのない状態(無縁)になれる唯一の場所であった。
そうして寺社にやってきた人々も、寺社の中で無為徒食できるわけではなかった。彼らは幕府や朝廷から距離を置くことはできたが、逆に言えば朝幕が用意していた社会システムから離れて生活の糧を得る必要があった。彼らは今で言えば「移民」であった。ある人は職人となり、ある人は商人となり、またある人は金融業を営んだ。こうした人々の生きるためのエネルギーによって寺社は最新技術を有し、中世の経済の中心となった。例えば根来寺(真義真言宗)では、武器製造が盛んだった。根来寺は高度な鍛冶技術を有し、鉄砲の三大生産地のひとつであった(他の2つは堺・近江国友)。
故郷を離れ、経済活動に勤しむ「個人」が集積していたところ、しかも国家と別の警察権を持ち、国家から半独立していたところ、それが寺社であった。著者はそうした寺社の様相を「境内都市」という用語で読み解く。中世末期、高野山には7千坊もの子院があったというが、これは宗教施設の集合ではなく、むしろ都市そのものだと考えた方がいいというのである。中世は農業中心の経済ではなく、多くの境内都市(=寺社)が活躍した都市経済の時代であった。
そして中世の京都は、事実都でもあったのだが、それ以上に叡山の門前町という性格が強かった。感神院祇園社は元は興福寺末寺であったが延暦寺(比叡山)が強奪し、祇園社を通じて比叡山は京都の経済を牛耳った。延暦寺の僧侶は、比叡山ではなく京都に住んでいたのである。
朝幕の勢力が、寺社勢力に対して無力だったわけではない。しかし朝廷と寺社勢力が争う場合、常に朝廷の腰は引けていた。神罰・仏罰を恐れたためだ。嗷訴(ごうそ)を行う場合、比叡山の僧侶は日吉社の神輿を持ち出した(神輿動座(しんよどうざ))。神の乗り物である神輿を置き去りにし、神意によって主張を通そうとしたのである。しかし「僧侶」が「神輿」を持ち出すというのが面白い。この頃、仏教と神道は、教義においてはもちろんアイテム的な面でも区別されていなかった。
本書はこうした寺社勢力の特質を、当時の文書(もんじょ)に現れる事例から読み解いている。鎌倉幕府の行政記録はほとんど残っていないし、当時の朝廷の様子も貴族の日記によって窺い知れるのみであるが、寺社の場合かなり寺としての記録が残っている上、貴族の日記にも頻繁に寺社とのもめ事が記述されているため、寺社の動向はこの時代の一次資料によってかなり解明できるんだそうである。
しかし、多くの事例から読み解くというスタイルであるため、本書はあまり体系的ではなく、時系列的でもないためややわかりにくい。さらに、著者はいわゆる「名物教授風」というか、かなりアクの強い書き方をしているため、文体の好みは分かれそうである(私自身はちょっと苦手だった)。
また「無縁性」を大きなキーワードとして寺社勢力の特質を読み解き、寺社に流入する人々を「移民」と捉える視点は面白いが、実際には寺社の中も世襲の僧侶たちによって相続されていたという事実と若干接続しない部分がある。ある面では寺社は「無縁所」であったし、移民が金持ちになれるアメリカン・ドリームな世界であったのは事実である。しかし「無縁」はあくまで寺社勢力の中の一部(特に行人・堂衆と呼ばれた人たち)の成立背景に過ぎず、「無縁」を以て寺社勢力全体を読み解くには無理があるような気がした。
ややアクの強い論ではあるが、「境内都市」という概念で寺社勢力の特質を繙いていく独特な本。
【関連書籍】
『寺社勢力—もう一つの中世社会』黒田 俊雄 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/blog-post_13.html
中世における寺社勢力の勃興と衰退を述べる。
中世の申し子とも言える寺社勢力を通じて当時の社会の内実を考えさせる良書。
2019年9月13日金曜日
『寺社勢力—もう一つの中世社会』黒田 俊雄 著
中世における寺社勢力の勃興と衰退を述べる。
本書の副題は「もう一つの中世社会」である。寺社は、天皇を中心とする公家、将軍を中心とする武家と並ぶ、中世社会におけるもう一つの権門であった。しかしその実態は、天皇や将軍のような中心がないからつかみどころがなく、また一般にもその存在が浸透していない。本書はこの謎の第三勢力・寺社勢力の中世史について述べるものである。
寺社、特に仏教寺院については、飛鳥や奈良の頃から現代にまで連綿と続いているように思うのであるが、現代の諸宗派が整備されたのは江戸時代で、それも廃仏毀釈による破壊・改変から復興したものであり、中世のそれとはだいぶ違っている。仏教寺院の多くは、中世の始まりとともに非常なる隆盛を見せ、そして中世の終わりとともに衰微していった。今に残る寺社と、中世における寺社は全く別のものであった。
それを象徴するのは「僧兵」の存在かもしれない。今の宗教の在り方からすると、寺院が兵力を持つということはあってはならぬことのように思える。しかし当時は、「僧兵」という言葉すらなく、僧侶であれひとたびことが起これば武器を持ち戦うことは当然とされていた。「僧兵」とは、寺院が兵士を雇っていたということではないのである。
では寺院は宗教的に堕落していたのか、というとそうとも言い切れない。南都六宗は国家の後ろ盾を失って荒廃していたし(東大寺と興福寺を除く)、仲間内で争いごとばかりする不届きな僧侶はいた。しかし同時に中世——特に鎌倉時代——は宗教的には確かに高潮期であり、今に繋がる主要な宗派の高僧が矢継ぎ早に出現したのである。即ち寺院は、高僧から悪党まで、様々な人間が犇めいた世界であった。公家や武家と、同じように。
当時の寺院を今の社会で譬えてみれば、宗教法人というよりは、大学と企業が一体になったような存在だと言うことができる。寺院は高徳な学僧を有した一方で、広大な荘園を経営してもいた。寺院の中の身分としては、リーダー格(別当・座主・検校など)、執行部(三綱——上座・時主・都維那(ついな))に続いて、哲理を究明する学侶(学衆・学生(がくしょう))、修行を行う行人(ぎょうにん)(行者・禅衆)の他に、僧に仕える身分である堂衆(どうしゅ)・夏衆(げしゅ)・花摘(はなつみ)などと呼ばれた者もたくさん在籍していた。これら様々な身分・階層のものがいたが、しかし建前からいえば、僧伽(僧侶の集団)は和合の精神で運営されており、寺院の中でこれらは同じ「大衆(だいしゅ)」を構成し、ある種の平等的な連帯集団を形作り自治を行っていた。
その具体的装置が「大衆僉議(だいしゅせんぎ)」である。これは、大衆——大寺院ともなれば何千人という規模になる——が一堂に会し、破れた袈裟で頭を裹(つつ)み、誰が誰ともわからない匿名の状況で集団討議と議決を行うものである。10世紀ごろのことだ。権力者が専断して憚らなかった時代に、匿名による討議と多数決による議決によって寺院としての決定を行っていたということは、やはり高く評価されなければならない。世俗とは違う論理によって経営がなされていたということが、寺社勢力の勃興に一役買っていたのだろう。
だが寺社が権門として力を持ってくると、いきおい公家との関係が深まってきた。大衆たちは自らの権威を飾るためにも、貴種を戴くことを当然と考えた。こうして、寺院の中に「門跡」ができるようになった。「門跡(もんぜき)」とは、皇族や摂関家のみに相続を許された寺院内の子院であって、例えば延暦寺における青蓮院(しょうれんいん)、興福寺における一乗院や大乗院といったものがそれに当たる。寺院は、貴族にとって公家社会とは別の居場所として機能するようになった。
12〜13世紀になると、門跡の下に大衆が組み込まれ、匿名平等だったはずの寺院が、門跡という特権階級の下に再組織化されていった。それは門跡だけでなく、寺院内の子院においても規模は違えど同様のことが起こったのである。先ほどの譬えを使うなら、当初は大学全体の自治が教授会によって行われていたが、大学が一部の特権的経営者によって独裁されたことで、研究室ごとの独立性が高まって大学全体の連帯意識が薄くなり、小組織へと分裂していったというようにいえるかもしれない。
このようにして寺院社会は内部から瓦解し、僧たちは武力と銭を蓄える方向へと走っていく。それは寺院勢力の強大な力を示す最後の仇花となり、寺院は繁栄を享受したが、世俗の論理に覆い尽くされた寺院に社会的存在価値はもはやなかった。織田信長・豊臣秀吉の全国統一が始まった時、寺社勢力は最終の没落を迎え、織田信長の比叡山焼き討ちに象徴されるように、新しい時代の権力者によって中世的な寺社勢力は滅亡したのである。
ところで私が本書を手にした興味は2つあった。第1に、寺社が広大な荘園を有したのはなぜかということ。特に寺社は広大な皇室領を持っていたが、なぜ天皇は寺社に荘園を寄進したのか。第2に、天皇をはじめ執権北条氏、室町幕府の足利氏など、時の最高権力者の多くが出家し法体となっているがこれはなぜなのかということ、である。
第1の点に関し、本書では寺院への寄進を「「王家」の(中略)荘園を確保し拡大する方途でもあった」としているが、なぜそうなのか詳しくは書かれていない。
中世、天皇家は広大な荘園を寺院に寄進している。有名なのは、安楽寿院・蓮華王院・長講堂・最勝光院といったものがある。これらは王家の御願寺、菩提寺、持仏堂などに荘園群を寄進し、事実上の王領(皇室領)でありながら、形式的に寺院の荘園としたものである。例えば「長講堂」というのは、後白河法皇の持仏堂であった「法華長講弥陀三昧堂」のことであるが、法皇がこの長講堂に多くの荘園を寄進しておいたのが「長講堂領」という荘園群のことである。鎌倉初期には長講堂領は180箇所の荘園によって構成されていたというが、形式的にはこれらは長講堂という持仏堂が所有しているものの、その長講堂が後白河法皇の所有であったのだから、結局王領なのである。
しかしなぜ後白河法皇は、わざわざ自分の所有地を長講堂という持仏堂の荘園としたのだろうか。長講堂なる持仏堂が天皇以上の権威を持っていたとも思えず、寄進によって荘園の私有が権威付けられたとも思えないのである。本書にその答えは書かれていないが、本書を読みながら私が思ったのは、その裏に相続の事情があったからなのではないか、ということである。
というのは、当時、日本の相続は分割相続がメインである。5人子どもがいれば、土地は(等分かどうかはともかく)5人に分割相続される。しかも女子にも相続権はほぼ同様にある(実際、長講堂領は後白河法皇の娘に相続された)。となると財産は代を進むごとに分割されていってしまう。それを避ける手段が、荘園の寺院への寄進だったのではないか。先ほど述べたように、寺院は門跡と門流の細分化によって相続関係は複雑となっていくが、少なくとも「大衆僉議」が機能していた頃はいわば「法人的」であったし、それでないにしても法統の関係は一括相続的であった。寺院に寄進した荘園は分割されることなく相続されていくものだったのである。それが、皇室直属の荘園との違いであった。分割不能なものとして土地を相続していく手段が寺院への寄進ではなかったのか。
そしてもしかしたら、寺院興隆には、寺院が「法人的」であったことが一役買っていたのかもしれない。中世の社会は「家」を重視してはいたが、実際には個人で活動している意味合いが強かった。そんな中で寺院は「法人的」な安定した存在であった。しかも匿名平等な多数決によって運営されていたから、経営者の交替によって方針が大きく変わるということもそれほどなかったのだろう。その安定性が、財産の維持に利用されたのかもしれない。
さらに寺院は、荘園経営事務に長けているということもあった。寺院は大学のようなものであったから、高度な事務作業ができたのだと思われる。荘園経営というのは、各地の荘園への課税を産出し、布達し、回収し、不達の場合は督促し、問題点があれば改善し…といったようなことが必要になるわけだが、荘園の数が多くなればこの事務は厖大かつ煩瑣なものとなっていく。荘園を寺院に寄進することで、荘園事務に長けた寺院にこれらの作業を丸投げすることができれば、仮に寺院に幾ばくかの分け前を割かなければならないとしても、結果的には安くついたのではないだろうか。荘園事務の「外注」のため、天皇家だけでなく多くの名家が寺院に荘園を寄進したのではないかと思う。
第2の点に関しては、本書にはあまり記載がなかった。足利義満が出家したのは、「ことごとに法皇に準じて威儀を示した(p.191)」ことがその背景にあり、「もはや武家であることをやめて院政を行う法皇の地位についたのである(同)」としているが、これは義満についてはそう言えるとしても、彼に先行する幾多の権力者が出家している以上、より構造的な原因を探る必要があると思った。
中世の申し子とも言える寺社勢力を通じて当時の社会の内実を考えさせる良書。
【関連書籍】
『日本の歴史 (8) 蒙古襲来』黒田 俊雄 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/8.html
蒙古襲来からの鎌倉幕府の滅亡までを描く。
長講堂領や安楽寿院領(八条院領)がたどった波瀾の運命が描かれている。
本書の副題は「もう一つの中世社会」である。寺社は、天皇を中心とする公家、将軍を中心とする武家と並ぶ、中世社会におけるもう一つの権門であった。しかしその実態は、天皇や将軍のような中心がないからつかみどころがなく、また一般にもその存在が浸透していない。本書はこの謎の第三勢力・寺社勢力の中世史について述べるものである。
寺社、特に仏教寺院については、飛鳥や奈良の頃から現代にまで連綿と続いているように思うのであるが、現代の諸宗派が整備されたのは江戸時代で、それも廃仏毀釈による破壊・改変から復興したものであり、中世のそれとはだいぶ違っている。仏教寺院の多くは、中世の始まりとともに非常なる隆盛を見せ、そして中世の終わりとともに衰微していった。今に残る寺社と、中世における寺社は全く別のものであった。
それを象徴するのは「僧兵」の存在かもしれない。今の宗教の在り方からすると、寺院が兵力を持つということはあってはならぬことのように思える。しかし当時は、「僧兵」という言葉すらなく、僧侶であれひとたびことが起これば武器を持ち戦うことは当然とされていた。「僧兵」とは、寺院が兵士を雇っていたということではないのである。
では寺院は宗教的に堕落していたのか、というとそうとも言い切れない。南都六宗は国家の後ろ盾を失って荒廃していたし(東大寺と興福寺を除く)、仲間内で争いごとばかりする不届きな僧侶はいた。しかし同時に中世——特に鎌倉時代——は宗教的には確かに高潮期であり、今に繋がる主要な宗派の高僧が矢継ぎ早に出現したのである。即ち寺院は、高僧から悪党まで、様々な人間が犇めいた世界であった。公家や武家と、同じように。
当時の寺院を今の社会で譬えてみれば、宗教法人というよりは、大学と企業が一体になったような存在だと言うことができる。寺院は高徳な学僧を有した一方で、広大な荘園を経営してもいた。寺院の中の身分としては、リーダー格(別当・座主・検校など)、執行部(三綱——上座・時主・都維那(ついな))に続いて、哲理を究明する学侶(学衆・学生(がくしょう))、修行を行う行人(ぎょうにん)(行者・禅衆)の他に、僧に仕える身分である堂衆(どうしゅ)・夏衆(げしゅ)・花摘(はなつみ)などと呼ばれた者もたくさん在籍していた。これら様々な身分・階層のものがいたが、しかし建前からいえば、僧伽(僧侶の集団)は和合の精神で運営されており、寺院の中でこれらは同じ「大衆(だいしゅ)」を構成し、ある種の平等的な連帯集団を形作り自治を行っていた。
その具体的装置が「大衆僉議(だいしゅせんぎ)」である。これは、大衆——大寺院ともなれば何千人という規模になる——が一堂に会し、破れた袈裟で頭を裹(つつ)み、誰が誰ともわからない匿名の状況で集団討議と議決を行うものである。10世紀ごろのことだ。権力者が専断して憚らなかった時代に、匿名による討議と多数決による議決によって寺院としての決定を行っていたということは、やはり高く評価されなければならない。世俗とは違う論理によって経営がなされていたということが、寺社勢力の勃興に一役買っていたのだろう。
だが寺社が権門として力を持ってくると、いきおい公家との関係が深まってきた。大衆たちは自らの権威を飾るためにも、貴種を戴くことを当然と考えた。こうして、寺院の中に「門跡」ができるようになった。「門跡(もんぜき)」とは、皇族や摂関家のみに相続を許された寺院内の子院であって、例えば延暦寺における青蓮院(しょうれんいん)、興福寺における一乗院や大乗院といったものがそれに当たる。寺院は、貴族にとって公家社会とは別の居場所として機能するようになった。
12〜13世紀になると、門跡の下に大衆が組み込まれ、匿名平等だったはずの寺院が、門跡という特権階級の下に再組織化されていった。それは門跡だけでなく、寺院内の子院においても規模は違えど同様のことが起こったのである。先ほどの譬えを使うなら、当初は大学全体の自治が教授会によって行われていたが、大学が一部の特権的経営者によって独裁されたことで、研究室ごとの独立性が高まって大学全体の連帯意識が薄くなり、小組織へと分裂していったというようにいえるかもしれない。
このようにして寺院社会は内部から瓦解し、僧たちは武力と銭を蓄える方向へと走っていく。それは寺院勢力の強大な力を示す最後の仇花となり、寺院は繁栄を享受したが、世俗の論理に覆い尽くされた寺院に社会的存在価値はもはやなかった。織田信長・豊臣秀吉の全国統一が始まった時、寺社勢力は最終の没落を迎え、織田信長の比叡山焼き討ちに象徴されるように、新しい時代の権力者によって中世的な寺社勢力は滅亡したのである。
ところで私が本書を手にした興味は2つあった。第1に、寺社が広大な荘園を有したのはなぜかということ。特に寺社は広大な皇室領を持っていたが、なぜ天皇は寺社に荘園を寄進したのか。第2に、天皇をはじめ執権北条氏、室町幕府の足利氏など、時の最高権力者の多くが出家し法体となっているがこれはなぜなのかということ、である。
第1の点に関し、本書では寺院への寄進を「「王家」の(中略)荘園を確保し拡大する方途でもあった」としているが、なぜそうなのか詳しくは書かれていない。
中世、天皇家は広大な荘園を寺院に寄進している。有名なのは、安楽寿院・蓮華王院・長講堂・最勝光院といったものがある。これらは王家の御願寺、菩提寺、持仏堂などに荘園群を寄進し、事実上の王領(皇室領)でありながら、形式的に寺院の荘園としたものである。例えば「長講堂」というのは、後白河法皇の持仏堂であった「法華長講弥陀三昧堂」のことであるが、法皇がこの長講堂に多くの荘園を寄進しておいたのが「長講堂領」という荘園群のことである。鎌倉初期には長講堂領は180箇所の荘園によって構成されていたというが、形式的にはこれらは長講堂という持仏堂が所有しているものの、その長講堂が後白河法皇の所有であったのだから、結局王領なのである。
しかしなぜ後白河法皇は、わざわざ自分の所有地を長講堂という持仏堂の荘園としたのだろうか。長講堂なる持仏堂が天皇以上の権威を持っていたとも思えず、寄進によって荘園の私有が権威付けられたとも思えないのである。本書にその答えは書かれていないが、本書を読みながら私が思ったのは、その裏に相続の事情があったからなのではないか、ということである。
というのは、当時、日本の相続は分割相続がメインである。5人子どもがいれば、土地は(等分かどうかはともかく)5人に分割相続される。しかも女子にも相続権はほぼ同様にある(実際、長講堂領は後白河法皇の娘に相続された)。となると財産は代を進むごとに分割されていってしまう。それを避ける手段が、荘園の寺院への寄進だったのではないか。先ほど述べたように、寺院は門跡と門流の細分化によって相続関係は複雑となっていくが、少なくとも「大衆僉議」が機能していた頃はいわば「法人的」であったし、それでないにしても法統の関係は一括相続的であった。寺院に寄進した荘園は分割されることなく相続されていくものだったのである。それが、皇室直属の荘園との違いであった。分割不能なものとして土地を相続していく手段が寺院への寄進ではなかったのか。
そしてもしかしたら、寺院興隆には、寺院が「法人的」であったことが一役買っていたのかもしれない。中世の社会は「家」を重視してはいたが、実際には個人で活動している意味合いが強かった。そんな中で寺院は「法人的」な安定した存在であった。しかも匿名平等な多数決によって運営されていたから、経営者の交替によって方針が大きく変わるということもそれほどなかったのだろう。その安定性が、財産の維持に利用されたのかもしれない。
さらに寺院は、荘園経営事務に長けているということもあった。寺院は大学のようなものであったから、高度な事務作業ができたのだと思われる。荘園経営というのは、各地の荘園への課税を産出し、布達し、回収し、不達の場合は督促し、問題点があれば改善し…といったようなことが必要になるわけだが、荘園の数が多くなればこの事務は厖大かつ煩瑣なものとなっていく。荘園を寺院に寄進することで、荘園事務に長けた寺院にこれらの作業を丸投げすることができれば、仮に寺院に幾ばくかの分け前を割かなければならないとしても、結果的には安くついたのではないだろうか。荘園事務の「外注」のため、天皇家だけでなく多くの名家が寺院に荘園を寄進したのではないかと思う。
第2の点に関しては、本書にはあまり記載がなかった。足利義満が出家したのは、「ことごとに法皇に準じて威儀を示した(p.191)」ことがその背景にあり、「もはや武家であることをやめて院政を行う法皇の地位についたのである(同)」としているが、これは義満についてはそう言えるとしても、彼に先行する幾多の権力者が出家している以上、より構造的な原因を探る必要があると思った。
中世の申し子とも言える寺社勢力を通じて当時の社会の内実を考えさせる良書。
【関連書籍】
『日本の歴史 (8) 蒙古襲来』黒田 俊雄 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/8.html
蒙古襲来からの鎌倉幕府の滅亡までを描く。
長講堂領や安楽寿院領(八条院領)がたどった波瀾の運命が描かれている。
2019年9月7日土曜日
『鎌倉武士の実像―合戦と暮しのおきて』石井 進 著
鎌倉武士の実態を様々な側面から描く本。
本書は、石井 進氏の論文集でありⅠ〜Ⅳの4部構成となっている。
Ⅰでは中世成立期の軍政や、鎌倉幕府成立の通史、相武地方の武士団の成長が述べられる。特に相武地方について取り上げられているのは、当該論文が元々「神奈川県史」の一節であったためで、ややローカルな部分もあるが鎌倉幕府のお膝元であった相武地方の様相が分かるのは興味深い。
Ⅱでは、武士の生活が農業経営の観点から取り上げられる。中世の村落はまず山裾の迫の部分から開発されたが、やがて新しい豪族が入ってくるとその下流の平野の開発が進み、豪族の館も平野部に建てられるようになる。山裾の部分の水田を開発するのは容易であるが、平地に水田を広げていくのはより進んだ水利技術を必要とする。新しい開発領主たちはそういう技術を持っていたのではと簡単に書いてあるが、仮にそうだとしてその技術をどこで手に入れたのか興味が湧いた。
Ⅲでは『蒙古襲来絵詞』と竹崎季長、霜月騒動、金沢文庫と『吾妻鏡』、鎌倉の道についてなど、関連しつつも雑多な論文が収録されている。
Ⅳでは、改めて「中世武士とは何か」という問を立て、短いながら啓発されるところの多い考察が行われている。 武士にとって、「名字の地」(本拠地)を持つことと共に、「祖先」を持つことが必須の条件であったと強調されているが、これについては改めて考えてみたいところである。現代の感覚からすれば本拠地(農業経営)と武力さえあれば武士といえそうなものであるが、なぜ彼らは「先祖」すなわち立派な家系図を持つことが重要だと考えたのだろうか。
鎌倉近郊の武士の実像を考える上で参考になるところが多い本。
【関連書籍】
『日本の歴史 (7) 鎌倉幕府』石井 進 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/7.html
鎌倉幕府成立の意義がよくわかる良書。
本書は、石井 進氏の論文集でありⅠ〜Ⅳの4部構成となっている。
Ⅰでは中世成立期の軍政や、鎌倉幕府成立の通史、相武地方の武士団の成長が述べられる。特に相武地方について取り上げられているのは、当該論文が元々「神奈川県史」の一節であったためで、ややローカルな部分もあるが鎌倉幕府のお膝元であった相武地方の様相が分かるのは興味深い。
Ⅱでは、武士の生活が農業経営の観点から取り上げられる。中世の村落はまず山裾の迫の部分から開発されたが、やがて新しい豪族が入ってくるとその下流の平野の開発が進み、豪族の館も平野部に建てられるようになる。山裾の部分の水田を開発するのは容易であるが、平地に水田を広げていくのはより進んだ水利技術を必要とする。新しい開発領主たちはそういう技術を持っていたのではと簡単に書いてあるが、仮にそうだとしてその技術をどこで手に入れたのか興味が湧いた。
Ⅲでは『蒙古襲来絵詞』と竹崎季長、霜月騒動、金沢文庫と『吾妻鏡』、鎌倉の道についてなど、関連しつつも雑多な論文が収録されている。
Ⅳでは、改めて「中世武士とは何か」という問を立て、短いながら啓発されるところの多い考察が行われている。 武士にとって、「名字の地」(本拠地)を持つことと共に、「祖先」を持つことが必須の条件であったと強調されているが、これについては改めて考えてみたいところである。現代の感覚からすれば本拠地(農業経営)と武力さえあれば武士といえそうなものであるが、なぜ彼らは「先祖」すなわち立派な家系図を持つことが重要だと考えたのだろうか。
鎌倉近郊の武士の実像を考える上で参考になるところが多い本。
【関連書籍】
『日本の歴史 (7) 鎌倉幕府』石井 進 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/7.html
鎌倉幕府成立の意義がよくわかる良書。
2019年9月6日金曜日
『日本の歴史 (7) 鎌倉幕府』石井 進 著
鎌倉幕府の誕生を描く。
源頼朝は貴顕の生まれであり、武家の棟梁にふさわしい家柄ではあったが、現実には大きな武力も後ろ盾も持っていなかった。だが平氏に戦いを挑み惨敗した「石橋山敗戦」からたった40日で、不可解にも関東の大豪族千葉介、上総氏などが味方につき、一気に鎌倉に新政権を打ち立てるのである。
頼朝は、天才的な政治才覚と読みの深さ、外交的バランスに恵まれ、カリスマ的な存在となった。彼は武士社会が抱えていた2つの課題を解決し、それによって広範な支持を得た。その2つとは、土地所有と訴訟である。
平安末期、かつての公地公民制が瓦解して荘園制へと進んだが、これは場当たり的な土地所有制であったために、その制度は複雑怪奇でしかも不確かなものであった。例えば、自らが開発(開墾)した土地の所有を確実なものとするため、土地の権威者に寄進をし、自身はその現地管理者として収まるといったことが多かったが、その権威者はさらに上位の権威者(例えば大寺院)に寄進するといったことが繰り返された。こうして権利関係が網の目のように張り巡らされ、その結果として土地所有は何重に承認された。しかし現代のように法務局があってそこに登記された、というような確実なものではない。「悔返し」と言って、譲渡したはずの土地を取り戻す行為も多かった。そしてひとたび土地の所有者に疑義が起これば、関係者同士の水掛け論へ陥ってしまう危険性を孕んでいたのである。
だから開発領主たる東国武士にとっての大きな課題は、土地所有を確実なものとすることと、訴訟の際に公平公正な裁定を行うことであった。頼朝は、土地所有については頼朝自らが土地の所有権を認める(=所領安堵)という関係に一本化し、所領安堵した者を「御家人」とした。つまり「御家人」とは、単に頼朝の部下であるということではなく、土地を介した主従関係であった。そして訴訟については、全て頼朝の親裁とした上で公平で的確な裁定を下したのである。
頼朝は、土地や訴訟の問題を解決するだけでなく、関東の独立性の高い武士たちを巧妙に編成していった。そして社会の上部構造にほとんど手をつけることなくほぼ政治的手腕のみによってそれら武士の一団を国家の支配構造の中に組み込むことに成功した。頼朝は、いわば国家の執行機関(国衙)を合法的に乗っ取ったのである。その一例が、一種の徴税官である「地頭」であり、また警察・公安・軍事指揮者である「総追捕使」、後の「守護職」である。
しかし頼朝の政権は、頼朝のたぐいまれなカリスマ性に基づいていたし、その基本政策(土地の支配権の保護と公正な裁決)は2代目以降には引き継がれず、頼朝死後には混迷が訪れる。かつての重臣が次々と粛正され、将軍は形骸化、ついに3代将軍実朝は暗殺される。こうして幕府の実権は執権の北条家へと移っていった。それが確定したのが承久の乱である。
承久の乱の台風の目になったのは後鳥羽上皇であったが、それに呼応したのは将軍独裁時代に特権を教授していた重臣であった。この乱が平定されたことで、そうした特権層が解体され、「評定衆」という合議制機関に基づいた、代表としての執権・北条泰時を推戴する武家による武家のための政権が成立するのである。その到達点が「御成敗式目」の制定だ。「御成敗式目」は、律令のように立派であっても理念的な法規とは違い、極めて実践的かつ平易な、武家の生活実態に即した「道理」を表現した画期的なものであった。
そして現実にも泰時は道理を重んじ、強い者が勝つような不公平を廃して温情的な政治を行い、執権政治の黄金時代を作った。ところがこの合議制に基づく執権政治も、やがては得宗専制政治(独裁政治)へと変質してしまうのである。
本書ではこうした政治史の他、鎌倉文芸の到達点としての「平家物語」や貴族文化の革新、特に東大寺再建や慶派(運慶・快慶など)の活躍、鎌倉新仏教の対称的な実践者であった親鸞と道元についてなど文化史的な面についても筆を割いている。
ちなみに私が本書を手に取ったのは、「地頭や守護とはそもそも何か?」という疑問を抱いてのことだった。それについて本書はかなり丁寧に説明しているがその前提として「「守護地頭問題」…(については)…かつての古い通説的見解はもはやまったく色あせ、全面的な改訂を迫られるに至った。だが一方、学説の戦国時代ともいうべき状況のなかで、新しい統一的結論はまだ生みだされていない(p.174)」としており、暫定的な説明であると断っている。これについては最新の学説も確認したいところである。
鎌倉幕府成立の意義がよくわかる良書。
源頼朝は貴顕の生まれであり、武家の棟梁にふさわしい家柄ではあったが、現実には大きな武力も後ろ盾も持っていなかった。だが平氏に戦いを挑み惨敗した「石橋山敗戦」からたった40日で、不可解にも関東の大豪族千葉介、上総氏などが味方につき、一気に鎌倉に新政権を打ち立てるのである。
頼朝は、天才的な政治才覚と読みの深さ、外交的バランスに恵まれ、カリスマ的な存在となった。彼は武士社会が抱えていた2つの課題を解決し、それによって広範な支持を得た。その2つとは、土地所有と訴訟である。
平安末期、かつての公地公民制が瓦解して荘園制へと進んだが、これは場当たり的な土地所有制であったために、その制度は複雑怪奇でしかも不確かなものであった。例えば、自らが開発(開墾)した土地の所有を確実なものとするため、土地の権威者に寄進をし、自身はその現地管理者として収まるといったことが多かったが、その権威者はさらに上位の権威者(例えば大寺院)に寄進するといったことが繰り返された。こうして権利関係が網の目のように張り巡らされ、その結果として土地所有は何重に承認された。しかし現代のように法務局があってそこに登記された、というような確実なものではない。「悔返し」と言って、譲渡したはずの土地を取り戻す行為も多かった。そしてひとたび土地の所有者に疑義が起これば、関係者同士の水掛け論へ陥ってしまう危険性を孕んでいたのである。
だから開発領主たる東国武士にとっての大きな課題は、土地所有を確実なものとすることと、訴訟の際に公平公正な裁定を行うことであった。頼朝は、土地所有については頼朝自らが土地の所有権を認める(=所領安堵)という関係に一本化し、所領安堵した者を「御家人」とした。つまり「御家人」とは、単に頼朝の部下であるということではなく、土地を介した主従関係であった。そして訴訟については、全て頼朝の親裁とした上で公平で的確な裁定を下したのである。
頼朝は、土地や訴訟の問題を解決するだけでなく、関東の独立性の高い武士たちを巧妙に編成していった。そして社会の上部構造にほとんど手をつけることなくほぼ政治的手腕のみによってそれら武士の一団を国家の支配構造の中に組み込むことに成功した。頼朝は、いわば国家の執行機関(国衙)を合法的に乗っ取ったのである。その一例が、一種の徴税官である「地頭」であり、また警察・公安・軍事指揮者である「総追捕使」、後の「守護職」である。
しかし頼朝の政権は、頼朝のたぐいまれなカリスマ性に基づいていたし、その基本政策(土地の支配権の保護と公正な裁決)は2代目以降には引き継がれず、頼朝死後には混迷が訪れる。かつての重臣が次々と粛正され、将軍は形骸化、ついに3代将軍実朝は暗殺される。こうして幕府の実権は執権の北条家へと移っていった。それが確定したのが承久の乱である。
承久の乱の台風の目になったのは後鳥羽上皇であったが、それに呼応したのは将軍独裁時代に特権を教授していた重臣であった。この乱が平定されたことで、そうした特権層が解体され、「評定衆」という合議制機関に基づいた、代表としての執権・北条泰時を推戴する武家による武家のための政権が成立するのである。その到達点が「御成敗式目」の制定だ。「御成敗式目」は、律令のように立派であっても理念的な法規とは違い、極めて実践的かつ平易な、武家の生活実態に即した「道理」を表現した画期的なものであった。
そして現実にも泰時は道理を重んじ、強い者が勝つような不公平を廃して温情的な政治を行い、執権政治の黄金時代を作った。ところがこの合議制に基づく執権政治も、やがては得宗専制政治(独裁政治)へと変質してしまうのである。
本書ではこうした政治史の他、鎌倉文芸の到達点としての「平家物語」や貴族文化の革新、特に東大寺再建や慶派(運慶・快慶など)の活躍、鎌倉新仏教の対称的な実践者であった親鸞と道元についてなど文化史的な面についても筆を割いている。
ちなみに私が本書を手に取ったのは、「地頭や守護とはそもそも何か?」という疑問を抱いてのことだった。それについて本書はかなり丁寧に説明しているがその前提として「「守護地頭問題」…(については)…かつての古い通説的見解はもはやまったく色あせ、全面的な改訂を迫られるに至った。だが一方、学説の戦国時代ともいうべき状況のなかで、新しい統一的結論はまだ生みだされていない(p.174)」としており、暫定的な説明であると断っている。これについては最新の学説も確認したいところである。
鎌倉幕府成立の意義がよくわかる良書。
2019年9月5日木曜日
『日本の歴史 (8) 蒙古襲来』黒田 俊雄 著
蒙古襲来からの鎌倉幕府の滅亡までを描く。
本書は、後に「黒田史学」を打ち立てることになる黒田俊雄が、39歳の時に書いたもので、若い研究者の意気軒昂さと斬新な観点による考察が不思議と統合され、歴史書ながら非常に引き込まれる。
蒙古襲来を基軸にして鎌倉後期を書くというスタイルは、今でこそ多くの日本通史に見られるが、それは本書を嚆矢とすると言う(海津一朗の「解説」より)。蒙古襲来は一時の外圧だったし、偶発的な事件ではあったが、鎌倉幕府の体制のほころびを垣間見せるものだった。
だが本書に占める蒙古襲来の分量は3分の1程度に過ぎない。残りの3分の2は、社会がどのように分裂していったのかということを様々な角度から描いている。
例えば宗教的には、日蓮の預言的な言論と一遍の教団が大きく取り上げられる。世紀末的な色彩を帯びた一遍の教団(のちの時宗)は、社会の終末を強く予感させたものであり、教団内では入水往生(自殺)がたびたび行われた。
さらに農民たちが次第に領主と対決するようになった経緯、地頭と領家(その土地の名義上の持ち主と、現場監督者である雑掌)の対決、封建的主従関係から飛びだして傭兵や独立的開拓領主となった「悪党」の横行、御家人の没落とその救済策の色々、そして天皇家の分裂(大覚寺統と持明院統)などが詳述される。
つまりこの時代、下は農民から上は天皇家に至るまで、既存の制度からこぼれ出て行ったのである。執権北条家は御家人の救済に努めて領地の回復を図り、悪党を取り締まってはいた。そして表面的には安定した治世を実現しているかに見えた。しかし結局それは社会の矛盾を糊塗しているに過ぎず、そのために独裁制へとなだれ込んでいくのである。こうして鎌倉幕府を支えていた各種の基盤はいつのまにか蚕食され、後醍醐天皇を担いだ謀叛が起こり、続いて楠木正成や足利尊氏が挙兵、あっけなく鎌倉幕府は倒れた。
本書は、若書きの作品であり後の「黒田史学」(例えば「権門体制論」:鎌倉幕府は国家ではない、など)と異質な史観によっているため、現在では評価が難しい本だという。しかし前提知識をあまり持っていない人が読んでもわかりやすく、歴史のダイナミックな動きを様々な側面で捉え、しかも退屈させないという点で、非常に優れた歴史書だと私は思った。
蒙古襲来を起点として鎌倉末期の諸相を描いた良書。
本書は、後に「黒田史学」を打ち立てることになる黒田俊雄が、39歳の時に書いたもので、若い研究者の意気軒昂さと斬新な観点による考察が不思議と統合され、歴史書ながら非常に引き込まれる。
蒙古襲来を基軸にして鎌倉後期を書くというスタイルは、今でこそ多くの日本通史に見られるが、それは本書を嚆矢とすると言う(海津一朗の「解説」より)。蒙古襲来は一時の外圧だったし、偶発的な事件ではあったが、鎌倉幕府の体制のほころびを垣間見せるものだった。
だが本書に占める蒙古襲来の分量は3分の1程度に過ぎない。残りの3分の2は、社会がどのように分裂していったのかということを様々な角度から描いている。
例えば宗教的には、日蓮の預言的な言論と一遍の教団が大きく取り上げられる。世紀末的な色彩を帯びた一遍の教団(のちの時宗)は、社会の終末を強く予感させたものであり、教団内では入水往生(自殺)がたびたび行われた。
さらに農民たちが次第に領主と対決するようになった経緯、地頭と領家(その土地の名義上の持ち主と、現場監督者である雑掌)の対決、封建的主従関係から飛びだして傭兵や独立的開拓領主となった「悪党」の横行、御家人の没落とその救済策の色々、そして天皇家の分裂(大覚寺統と持明院統)などが詳述される。
つまりこの時代、下は農民から上は天皇家に至るまで、既存の制度からこぼれ出て行ったのである。執権北条家は御家人の救済に努めて領地の回復を図り、悪党を取り締まってはいた。そして表面的には安定した治世を実現しているかに見えた。しかし結局それは社会の矛盾を糊塗しているに過ぎず、そのために独裁制へとなだれ込んでいくのである。こうして鎌倉幕府を支えていた各種の基盤はいつのまにか蚕食され、後醍醐天皇を担いだ謀叛が起こり、続いて楠木正成や足利尊氏が挙兵、あっけなく鎌倉幕府は倒れた。
本書は、若書きの作品であり後の「黒田史学」(例えば「権門体制論」:鎌倉幕府は国家ではない、など)と異質な史観によっているため、現在では評価が難しい本だという。しかし前提知識をあまり持っていない人が読んでもわかりやすく、歴史のダイナミックな動きを様々な側面で捉え、しかも退屈させないという点で、非常に優れた歴史書だと私は思った。
蒙古襲来を起点として鎌倉末期の諸相を描いた良書。
2019年8月17日土曜日
『神仏習合』逵 日出典 著
神仏習合の概略的な説明。
本書は、いかにして神仏習合が起こり、それが発展していったかを述べるものである。その起源となる奈良時代の動向については詳述されており、なかなか参考になる。
著者は、最初期の神仏習合にあたっては山岳の修行者が大きな役割を果たしたのではないかと推測している。というのは、修行のために山岳に入っていく場合、山の神といった土地神への崇敬を蔑ろにするわけにはいかなかったからである。本書ではそれが論証されるでもなくアイデアとして書かれているが、その後の修験道の発展を考えるとありそうなことである。
また、著者は神宮寺の設立がまず地方から始まっていることを指摘し、神仏習合が地方的な動きであったと述べている。そのケーススタディとして宇佐八幡についてはやや詳述されており参考になった。神宮寺の設立に関しては「神が宿業によって苦悩しているために、それを仏法によって救う」というロジックであったという。神のために仏教を導入するというロジックが興味深い。
こうした神仏習合の動きはやがて中央にも波及し、聖武天皇は大仏鋳造成就のため八幡神に祈願している。そして次第に、神と仏はいろいろなやり方で交錯するようになっていく。
そして10世紀、宇佐八幡宮を中心として「本地垂迹説」が広まり、神の本体は仏であるとさえ考えられるようになる。そのため神社のご神体として本地仏が安置されることも多くなった。神道は教義や宗教理論がなかったため、仏教側がそれを提供するかたちで習合思想が整備されていった。
さらに時代が進み「伊勢神道」や「両部神道」「垂加神道」など、中世の神道理論が様々に案出されていくと、反本地垂迹説(神の方が本体で仏が仮の姿だ、という説)までが生まれた。ただしこのあたりは、本書では理論的なものが書かれるに過ぎず具体例によっては論証されていない。鎌倉時代以降の神仏習合の動向に関してはかなり簡略である。
ところで本書の終わりの方で、著者は「習合は日本の心」として「わが国にあっては、固有の神と伝来の仏がみごとに習合していった。まさに特異な現象といわねばなるまい」と称揚するのであるが、これは残念ながら誤解であろう。
例えば高取正男は『神道の成立』において堀一郎の見解を紹介し、日本の神仏習合においては「シンクレティズムとよべるほどの体系化は、ほとんど進行しなかった」と述べている。「シンクレティズム」とは複数の宗教が接触することで生じる融合現象である。そもそも世界中の宗教を見回してみても、先行する在来宗教を取り込んだり、対立する宗教の要素をアレンジして取り込んだりすることでその内容を豊かにしていくということは散見される。
仏教もヒンドゥー教の諸神をその中に取り込んで、四天王とか弁財天といったような存在を認めていったのだし、そもそも大乗仏教は在来宗教を飲み込んでできた仏教だといえる。中国においても仏教は在来の神仙思想と接近し「老子化胡説」が伝来当初から案出された。これは老子がインドに渡って仏教を唱えた、つまり、ブッダと老子は同一人物だったという一種の習合説である。さらに道観(道教のお寺)では仏像も礼拝されており、観音は最上位の神仙と考えられていたのである。このように、異なる宗教が互いに影響し合い、共存することは、何も「日本の心」ではなくて世界的によくあることだ。
むしろ日本の神仏習合で特徴的だったのは、本地垂迹説など理論面では神仏同体の思想が発展し、仏像を神として拝んだり、逆に神像を僧形に表現したりなど形式的な面でかなり神仏は接近したのに、遂に神道と仏教は教義面でも実体上でも融合しなかったということである。私は、神仏習合を考える上での第一の疑問はこれであるべきだと思う。つまり「なぜ仏教と神道は、互いにさほど大きな影響を及ぼさずに併存したのか。むしろ併存せざるをえなかったのはなぜか?」ということだ。つまり、なぜ神仏は「習合」しなかったのか、ということこそ出発点にすべきだ。
中国でも、儒教と仏教が習合し、その結果「盂蘭盆経」が生まれている。元来の仏教には祖先崇拝の要素が希薄だが、孝(親や祖先への礼)を重んじる中国では、仏教もそれを取り入れることが必要だった。また真に中国化した仏教といえる「禅」は、老荘思想的な面を多く持っている。日本の場合、古来の神祇信仰と仏教が「修験道」において融合したという例外はあるものの、中国に見られるような大規模な習合現象は生じていない。「本地垂迹説」などは、仏教と神道を融合させることなく並立させるため、名目上のつじつまを合わせているという感じが強いのである。
さて、神仏分離以前の神社には、神宮寺や別当寺というものが存在していた。これは、神社の中に設けられた神社で、神社の運営の主体となるものである。例えば宇佐八幡宮には弥勒寺という神宮寺があり、荘園経営においても弥勒寺は宇佐八幡そのものと遜色ない規模を誇っていた。散発的・個別的だった神官たちと比べ、仏教勢力は早くから全国的に本末制度が確立し、教義的にも体系化しやすかったこともあって、僧侶達はずっと組織的に動く術を心得ていた。よって神宮寺は神社本体よりもずっと組織的に行動することができ、やがて神社そのものを凌ぐほどの力を持つようになるのである。
だが、宇佐八幡宮においても、遂に弥勒寺が宇佐八幡から「独立」することはなかった。やはり弥勒寺は、宇佐八幡が社会的に担っているものを自らに取り込むことはできなかったのである。それがなんだったのか、今となってはよくわからない。それは神託機能だったのだろうか。でも仏教でも託宣や夢のお告げはあるのだ。弥勒寺は、どうして宇佐八幡を乗っ取ってしまうことができなかったのだろう。あるいは乗っ取るメリットがなかったのだろうか? そのあたりのことがどうもよくわからないのだ。
仏教は、神道よりもずっと体系的で理論的で、組織的でしかもおそらくは財力もあった。にも関わらず、ある面では神道の力を借りなければならなかった。神道の持つその力を自らに取り込み、より高い立場から統合するというような、スケールの大きな思想的な成長は、遂になされなかったのである。天台本覚思想——山川草木は悉く仏性を持つという思想——はその例外かもしれない。日本の神道的アミニズムが仏教に取り込まれて生まれたのが天台本覚思想であろう。しかし中国人が禅を生みだしたようには、日本人は独自の仏教を創り出さなかった。
ところで備忘として書いておくが、神宮寺・別当寺の宗派と神社の宗派の関係がどうなっているのか気になるので、いつか調べてみたいと思う。例えば八幡社系は真言宗とか、そういう対応関係はあるのだろうか?
奈良時代までの習合現象の説明はそれなりにあるが、それ以降は簡略すぎ、神仏習合を日本独自の優れたものとする誤解が残念な本。
【関連書籍】
『神道の成立』高取 正男 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/07/blog-post_21.html
平安時代の神仏分離について述べられている。
神道成立前夜の動向を、細かい事実を積み重ねて究明した労作。
『道教史』 窪 徳忠 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
道教と仏教の交流・習合について詳しい。
古代から現代に至る中国における道教の歴史を追った本。
本書は、いかにして神仏習合が起こり、それが発展していったかを述べるものである。その起源となる奈良時代の動向については詳述されており、なかなか参考になる。
著者は、最初期の神仏習合にあたっては山岳の修行者が大きな役割を果たしたのではないかと推測している。というのは、修行のために山岳に入っていく場合、山の神といった土地神への崇敬を蔑ろにするわけにはいかなかったからである。本書ではそれが論証されるでもなくアイデアとして書かれているが、その後の修験道の発展を考えるとありそうなことである。
また、著者は神宮寺の設立がまず地方から始まっていることを指摘し、神仏習合が地方的な動きであったと述べている。そのケーススタディとして宇佐八幡についてはやや詳述されており参考になった。神宮寺の設立に関しては「神が宿業によって苦悩しているために、それを仏法によって救う」というロジックであったという。神のために仏教を導入するというロジックが興味深い。
こうした神仏習合の動きはやがて中央にも波及し、聖武天皇は大仏鋳造成就のため八幡神に祈願している。そして次第に、神と仏はいろいろなやり方で交錯するようになっていく。
そして10世紀、宇佐八幡宮を中心として「本地垂迹説」が広まり、神の本体は仏であるとさえ考えられるようになる。そのため神社のご神体として本地仏が安置されることも多くなった。神道は教義や宗教理論がなかったため、仏教側がそれを提供するかたちで習合思想が整備されていった。
さらに時代が進み「伊勢神道」や「両部神道」「垂加神道」など、中世の神道理論が様々に案出されていくと、反本地垂迹説(神の方が本体で仏が仮の姿だ、という説)までが生まれた。ただしこのあたりは、本書では理論的なものが書かれるに過ぎず具体例によっては論証されていない。鎌倉時代以降の神仏習合の動向に関してはかなり簡略である。
ところで本書の終わりの方で、著者は「習合は日本の心」として「わが国にあっては、固有の神と伝来の仏がみごとに習合していった。まさに特異な現象といわねばなるまい」と称揚するのであるが、これは残念ながら誤解であろう。
例えば高取正男は『神道の成立』において堀一郎の見解を紹介し、日本の神仏習合においては「シンクレティズムとよべるほどの体系化は、ほとんど進行しなかった」と述べている。「シンクレティズム」とは複数の宗教が接触することで生じる融合現象である。そもそも世界中の宗教を見回してみても、先行する在来宗教を取り込んだり、対立する宗教の要素をアレンジして取り込んだりすることでその内容を豊かにしていくということは散見される。
仏教もヒンドゥー教の諸神をその中に取り込んで、四天王とか弁財天といったような存在を認めていったのだし、そもそも大乗仏教は在来宗教を飲み込んでできた仏教だといえる。中国においても仏教は在来の神仙思想と接近し「老子化胡説」が伝来当初から案出された。これは老子がインドに渡って仏教を唱えた、つまり、ブッダと老子は同一人物だったという一種の習合説である。さらに道観(道教のお寺)では仏像も礼拝されており、観音は最上位の神仙と考えられていたのである。このように、異なる宗教が互いに影響し合い、共存することは、何も「日本の心」ではなくて世界的によくあることだ。
むしろ日本の神仏習合で特徴的だったのは、本地垂迹説など理論面では神仏同体の思想が発展し、仏像を神として拝んだり、逆に神像を僧形に表現したりなど形式的な面でかなり神仏は接近したのに、遂に神道と仏教は教義面でも実体上でも融合しなかったということである。私は、神仏習合を考える上での第一の疑問はこれであるべきだと思う。つまり「なぜ仏教と神道は、互いにさほど大きな影響を及ぼさずに併存したのか。むしろ併存せざるをえなかったのはなぜか?」ということだ。つまり、なぜ神仏は「習合」しなかったのか、ということこそ出発点にすべきだ。
中国でも、儒教と仏教が習合し、その結果「盂蘭盆経」が生まれている。元来の仏教には祖先崇拝の要素が希薄だが、孝(親や祖先への礼)を重んじる中国では、仏教もそれを取り入れることが必要だった。また真に中国化した仏教といえる「禅」は、老荘思想的な面を多く持っている。日本の場合、古来の神祇信仰と仏教が「修験道」において融合したという例外はあるものの、中国に見られるような大規模な習合現象は生じていない。「本地垂迹説」などは、仏教と神道を融合させることなく並立させるため、名目上のつじつまを合わせているという感じが強いのである。
さて、神仏分離以前の神社には、神宮寺や別当寺というものが存在していた。これは、神社の中に設けられた神社で、神社の運営の主体となるものである。例えば宇佐八幡宮には弥勒寺という神宮寺があり、荘園経営においても弥勒寺は宇佐八幡そのものと遜色ない規模を誇っていた。散発的・個別的だった神官たちと比べ、仏教勢力は早くから全国的に本末制度が確立し、教義的にも体系化しやすかったこともあって、僧侶達はずっと組織的に動く術を心得ていた。よって神宮寺は神社本体よりもずっと組織的に行動することができ、やがて神社そのものを凌ぐほどの力を持つようになるのである。
だが、宇佐八幡宮においても、遂に弥勒寺が宇佐八幡から「独立」することはなかった。やはり弥勒寺は、宇佐八幡が社会的に担っているものを自らに取り込むことはできなかったのである。それがなんだったのか、今となってはよくわからない。それは神託機能だったのだろうか。でも仏教でも託宣や夢のお告げはあるのだ。弥勒寺は、どうして宇佐八幡を乗っ取ってしまうことができなかったのだろう。あるいは乗っ取るメリットがなかったのだろうか? そのあたりのことがどうもよくわからないのだ。
仏教は、神道よりもずっと体系的で理論的で、組織的でしかもおそらくは財力もあった。にも関わらず、ある面では神道の力を借りなければならなかった。神道の持つその力を自らに取り込み、より高い立場から統合するというような、スケールの大きな思想的な成長は、遂になされなかったのである。天台本覚思想——山川草木は悉く仏性を持つという思想——はその例外かもしれない。日本の神道的アミニズムが仏教に取り込まれて生まれたのが天台本覚思想であろう。しかし中国人が禅を生みだしたようには、日本人は独自の仏教を創り出さなかった。
ところで備忘として書いておくが、神宮寺・別当寺の宗派と神社の宗派の関係がどうなっているのか気になるので、いつか調べてみたいと思う。例えば八幡社系は真言宗とか、そういう対応関係はあるのだろうか?
奈良時代までの習合現象の説明はそれなりにあるが、それ以降は簡略すぎ、神仏習合を日本独自の優れたものとする誤解が残念な本。
【関連書籍】
『神道の成立』高取 正男 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/07/blog-post_21.html
平安時代の神仏分離について述べられている。
神道成立前夜の動向を、細かい事実を積み重ねて究明した労作。
『道教史』 窪 徳忠 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
道教と仏教の交流・習合について詳しい。
古代から現代に至る中国における道教の歴史を追った本。
2019年8月13日火曜日
『父の詫び状』向田 邦子 著
幼少期から青年期までの家族との思い出を中心にしたエッセイ。
本書では、戦前戦後の昭和の中流家庭のありさまがユーモアを交えて描かれている。著者向田邦子のみずみずしい感性によって捉えられているからか、戦前戦後といっても今読んでも古びた感じはしない。著者の初めてのエッセイであるため多少荒削りな点はあるが、話題があっちへ行きこっちへ行きしながらも最後にはそれらが不思議に結びつけられ端正なエッセイに仕上がっている。
ところが、私はこのエッセイ集を読みながら、ちょっとその「端正さ」からはみ出たところに目が行ってしまった。それはタイトルにもなっている「父」のことである。
向田邦子の父は、暴君であった。些細なことで怒鳴り、撲った。毎日の食卓は、家族の団欒というような温かい雰囲気ではなく、父の雷がいつ落ちないかとビクビクしながら囲むものだった。そして父はなんでも自分だけ特別扱いを求め、家長としてふんぞり返っていた。家族に対しては「ありがとう」も「ごめんなさい」も、決して言わなかった人間、それが父であった。
著者は幼い時、そういう父を畏怖し、また嫌った。しかし長ずるにつれ、その横暴さの裏に潜む、社会人としての哀しさを感じるようになる。というのは、父は高等小学校卒でありながら、保険会社で異例の出世をし、支店長にもなっていた。その裏には、卑屈なまでに会社に平身低頭し、交際費を大盤振る舞いするという社内政治があったのである。父は、そういう会社でのままならなさを、家庭で暴君として振る舞うことで埋め合わせていたのだ。父の家庭での絶対性は、社会の中での弱い立場の裏返しだった。
であっても、子どもや妻に押しつける不条理や子どもっぽい怒りが、免罪されるわけではない。当時は、こんな「雷親父」はどこにでもいたのだ、ということは言えるかもしれないが、実際その暴力や暴言を受けている子どもや妻にしてみれば、それはたいした慰めにはならないのだ。
このエッセイで、向田邦子は、そこはかとない努力を傾けて、そういう父の思い出も「今になってみれば懐かしい」と昇華させたがっているように見える。しかしそのたびに、「とはいっても、父のこういうところは嫌いだった」と注釈をつけざるをえないような、割り切れなさを抱えるのだ。それが、全体的には端正なこのエッセイにおいて、なんだか切れ味が鈍っているような、そんな印象を与えている。
だがそのために、このエッセイがつまらないものになっているのではない。むしろ話は逆で、テレビ界出身ならではの、毒気なく素材を調理する感じ、手際よく話題を変えていく調子の中にあって、「父」の事になるとなんとなく筆が鈍る感じが、著者の内面を覗かせる窓のような役割になっている。
いや事実、エッセイに描かれる向田邦子は、まさか「向田邦子」本人であるわけがない。ちょっとおっちょこちょいで、人のやらないような失敗をし、いつまでも嫁き遅れていることを自虐し、仕事のできなさをネタにする、というこの向田邦子は、本人の特徴をデフォルメしてエッセイ用にしつらえたキャラクターだろう。しかし父のことになると割り切れない思いを抱える「向田邦子」は、間違いなく本人の心情が吐露されていると感じるのである。
表題作「父の詫び状」は、生涯でたった一度、父が娘に寄せた詫びの手紙が描かれているが、それにしても「此の度は格別の御働き」という一行があり、そこだけ朱筆で傍線が引かれているに過ぎなかった。結局、いつまでも父は娘に詫びることができなかったのである。
仮の話をするのは気が引けるが、仮に、父が生涯でたった一度でも、「お前にはいろいろいろ迷惑を掛けたなあ」とか「好き勝手振る舞って悪かったなあ」といったように本当に詫びたとしたら、本書はだいぶ違った印象のものになったのではないかという気がする。父にまつわるイヤな思い出も昇華して、「今になってみれば懐かしい」と記憶の棚卸しができたのだと思う。本書の表題が『父の詫び状』なのは、偶然以上の意味があると思う。きっと、向田邦子が欲しかったもの、それがちゃんとした「父の詫び状」だったのではないだろうか。
ただひとつ言い添えなくてはならないのは、こういう読み方は、邪道だということである。というのは、これまで述べてきた著者と父との関係性の襞は、本書で著者が表現しようとしたことでも、伝えたかったことでもないのは明らかだからだ。本書はもっと気楽に読むべきものだろうし、この雷親父も、ありがちな父親像として受け取れば十分なのだ。だが私は表題作であり冒頭作である「父の詫び状」に素の「向田邦子」を感じて、以降それを感じることが本書を読む楽しみと思ってしまったのである。
本書では、戦前戦後の昭和の中流家庭のありさまがユーモアを交えて描かれている。著者向田邦子のみずみずしい感性によって捉えられているからか、戦前戦後といっても今読んでも古びた感じはしない。著者の初めてのエッセイであるため多少荒削りな点はあるが、話題があっちへ行きこっちへ行きしながらも最後にはそれらが不思議に結びつけられ端正なエッセイに仕上がっている。
ところが、私はこのエッセイ集を読みながら、ちょっとその「端正さ」からはみ出たところに目が行ってしまった。それはタイトルにもなっている「父」のことである。
向田邦子の父は、暴君であった。些細なことで怒鳴り、撲った。毎日の食卓は、家族の団欒というような温かい雰囲気ではなく、父の雷がいつ落ちないかとビクビクしながら囲むものだった。そして父はなんでも自分だけ特別扱いを求め、家長としてふんぞり返っていた。家族に対しては「ありがとう」も「ごめんなさい」も、決して言わなかった人間、それが父であった。
著者は幼い時、そういう父を畏怖し、また嫌った。しかし長ずるにつれ、その横暴さの裏に潜む、社会人としての哀しさを感じるようになる。というのは、父は高等小学校卒でありながら、保険会社で異例の出世をし、支店長にもなっていた。その裏には、卑屈なまでに会社に平身低頭し、交際費を大盤振る舞いするという社内政治があったのである。父は、そういう会社でのままならなさを、家庭で暴君として振る舞うことで埋め合わせていたのだ。父の家庭での絶対性は、社会の中での弱い立場の裏返しだった。
であっても、子どもや妻に押しつける不条理や子どもっぽい怒りが、免罪されるわけではない。当時は、こんな「雷親父」はどこにでもいたのだ、ということは言えるかもしれないが、実際その暴力や暴言を受けている子どもや妻にしてみれば、それはたいした慰めにはならないのだ。
このエッセイで、向田邦子は、そこはかとない努力を傾けて、そういう父の思い出も「今になってみれば懐かしい」と昇華させたがっているように見える。しかしそのたびに、「とはいっても、父のこういうところは嫌いだった」と注釈をつけざるをえないような、割り切れなさを抱えるのだ。それが、全体的には端正なこのエッセイにおいて、なんだか切れ味が鈍っているような、そんな印象を与えている。
だがそのために、このエッセイがつまらないものになっているのではない。むしろ話は逆で、テレビ界出身ならではの、毒気なく素材を調理する感じ、手際よく話題を変えていく調子の中にあって、「父」の事になるとなんとなく筆が鈍る感じが、著者の内面を覗かせる窓のような役割になっている。
いや事実、エッセイに描かれる向田邦子は、まさか「向田邦子」本人であるわけがない。ちょっとおっちょこちょいで、人のやらないような失敗をし、いつまでも嫁き遅れていることを自虐し、仕事のできなさをネタにする、というこの向田邦子は、本人の特徴をデフォルメしてエッセイ用にしつらえたキャラクターだろう。しかし父のことになると割り切れない思いを抱える「向田邦子」は、間違いなく本人の心情が吐露されていると感じるのである。
表題作「父の詫び状」は、生涯でたった一度、父が娘に寄せた詫びの手紙が描かれているが、それにしても「此の度は格別の御働き」という一行があり、そこだけ朱筆で傍線が引かれているに過ぎなかった。結局、いつまでも父は娘に詫びることができなかったのである。
仮の話をするのは気が引けるが、仮に、父が生涯でたった一度でも、「お前にはいろいろいろ迷惑を掛けたなあ」とか「好き勝手振る舞って悪かったなあ」といったように本当に詫びたとしたら、本書はだいぶ違った印象のものになったのではないかという気がする。父にまつわるイヤな思い出も昇華して、「今になってみれば懐かしい」と記憶の棚卸しができたのだと思う。本書の表題が『父の詫び状』なのは、偶然以上の意味があると思う。きっと、向田邦子が欲しかったもの、それがちゃんとした「父の詫び状」だったのではないだろうか。
ただひとつ言い添えなくてはならないのは、こういう読み方は、邪道だということである。というのは、これまで述べてきた著者と父との関係性の襞は、本書で著者が表現しようとしたことでも、伝えたかったことでもないのは明らかだからだ。本書はもっと気楽に読むべきものだろうし、この雷親父も、ありがちな父親像として受け取れば十分なのだ。だが私は表題作であり冒頭作である「父の詫び状」に素の「向田邦子」を感じて、以降それを感じることが本書を読む楽しみと思ってしまったのである。
2019年7月17日水曜日
『女と刀』中村きい子 著
自我を持った女の、反抗の物語。
権領司キヲは、薩摩藩の外城士の娘として生まれた。外城士とは、武士ではあるが城下士よりも一段下の存在で、キヲはその中では割合によい身分だった。
キヲの父は西南戦争で賊軍として負けたことを終生悔しがり、その恨みのエネルギーはキヲ達への教育へと向けられた。キヲは男同様の教育を施され、おのれの意向を全うさせるという強烈な原則を魂に刻み込まれた。女は男の従属物として考えられていた時代に、キヲは独立自尊の精神と強靱な自我を育んでいた。
ところが、まさにそのような教育を施した父親によって、キヲの精神は打ち砕かれる。キヲに望まない結婚を強いたのである。有無をも言わさぬ決定だった。いくら「おのれの意向を持て」などと言っていても、結局女は家長の命令に従うもの、というのが父親の本音だったのである。
しかし程なくしてキヲは出戻りとなった。嫁ぎ先の姑との折り合いが悪く、キヲは姑から「夜叉」と呼ばれた。父は、それを権領司家への侮辱ととった。そのような侮辱を受けた以上、キヲは取り戻されなければならなかった。ここでもキヲの意向は無視された。ただ家の名誉が傷つけられた、という事情のためにキヲは離縁しなければならなかったのである。
しばらくしてキヲは再婚するが、それも望まない結婚だった。ここでも優先されたのは家の事情である。そして求められて結婚したにもかかわらず、夫の兵衛門はキヲを愛することはなかった。兵衛門は、「出戻り」という「キズ」があれば自分よりも身分が上の女性と結婚できる、という打算によってキヲを求めたに過ぎなかった。愛のない結婚生活は、キヲの自我をさらに先鋭化させていった。
キヲは、自らの意向が蹂躙され、家の従属物として扱われるに過ぎないとしても、そこに情を通わせ、求め合う関係があるならばそこに没入してもよいと思っていた。だが実際には、兵衛門はキヲを無視するどころか愛人さえ作り、そのくせ家では横座(家長としての地位)にあぐらをかき、横柄に振る舞うことで自らの権威を演出するだけが取り柄の男であった。キヲはこのようなつまらない男に従って生きる、などということは我慢がならなかった。やがてキヲは自らの畑仕事と行商によって、兵衛門の収入をアテにせず生活できるようになった。そしてままならぬ中でも自らの意向を貫き通すという戦いをしていくのである。
しかしその一方で、愛のない結婚生活の中でも夜の営みは続けられた。そして虚しい気持ちの中で、キヲは8人の子どもをもうけるのである。女とは、家を維持していくための道具にすぎなかった。女は男にいいように使われ、子を産み育てるだけに価値が置かれていた。女は、「自分」を持つことが許されなかった。女は、「妻」であるか「母」であるか、どちらかでしかなかった。
だが男が自由きままに振る舞っていたのかというと、そうでもなかった。ことあるごとに血族会議が開かれ、「世間がどういうか」「家のメンツを潰す気か」「家の名誉に関わる」などといって、男たちはキヲの意向を踏みにじったが、そこでは常に「家」の世間体が最優先され、誰も自分の考えを持つものはいなかった。女は確かに男に従属していたが、男も「世間」に従属させられており、それに疑問を持つものはいなかった。「自分」よりも「世間」の方が行動を規定していた。
そんな中で、キヲは自我を持つほとんど唯一の人間だった。キヲは近代的な精神に目覚めていた。だからキヲが(現代の人間からみて)当たり前のことをしても、それは家からも社会からも異常な行動として映った。「自分」を独立した価値あるものと見なす考えは、それだけで狂気じみていた。
キヲの戦いは、同じように抑圧されていた女性たちからも理解されなかった。おのれの意向を貫こうと正面衝突を繰り返すキヲを、女性たちは冷ややかに見ていた。表面上は男を立てながら、小ずるく立ち回ってうまく家庭を回すのが賢いやり方で、キヲのようなやり方では事を荒立てるばかりで結局自分のやりたいようには出来なくなるというのだ。 しかしそれは、キヲの戦いを全く理解していないものの見方だった。キヲは目先の決定権を手に入れたいのではなかった。自分を一人の人間として尊重して欲しい、という根源的な要求を主張していたのだ。
それを象徴するのが、強いて父から譲り受けた短刀だ。女が刀を持つ、ということは普通にはありえないことだ。しかしキヲは刀を持ちたがった。それが自らの意向を貫き通すための唯一の力、命のやりとりによって自らの存在を打ち立てるための力の象徴であった。「自分」を承認させることがキヲの戦いだった。
しかしその考えを、男も女も、誰も理解できなかったのだから、キヲの戦いは常に独り相撲に終わっていた。キヲはむしろ正面衝突を望んでいたが、衝突すべきものは空疎だった。「世間」のことばかり気にする小心翼々とした人間達を、キヲは冷笑した。そのような人間の相手をすることが、次第にバカバカしくなってきた。やがてキヲは、兵衛門との愛のない結婚生活、「世間」にしか向かない血族、「自分」のない人生に見切りをつけた。
そして齢七十にして、兵衛門に離婚を突きつけたのである。そのような老婆が、離婚を突きつけるなどということは前代未聞だった。「世間」も「血族」も、非難囂々だった。だがキヲは、それまでの無意味な人生に決別し、これから「自分」を大切にする人生を踏み出したのである。それがキヲが全人生をかけて到達した答えだった。
本書に描かれた権領司キヲは、社会や男に翻弄されるだけの女とはほど遠い。それらに常に戦いを挑み、挫かれても挫かれてもそのたびごとに「自分」を強くしていく反抗する人間である。 しかし同時に、キヲは外城士の娘として、「ザイ」(百姓)に強い差別意識を持っていた。彼女は自分を、誇り高い士族の娘であると考えていた。自らを蹂躙した「血」の論理を、彼女自身乗り越えていなかったのだ。彼女の桎梏となったのも「家」という「血」であったし、彼女がザイを差別したのも「血」であった。
キヲには、もっと徹底的に世間に反抗した叔母がいた。叔母は、「ザイ」の男と恋に落ち、身分も外聞も捨てて愛に生きた。世間からは村八分になっていたが、彼女は幸せだった。「血」の論理を、乗り越えていたからだ。キヲの悲劇は、自らを苦しめた「血」の論理を、自分自身、捨てきれなかったことだった。
著者中村きい子は、自らの母をモデルにこの小説を作ったという。この時代に比べると、今は女性の地位が随分向上した。結婚を無理強いされることは少ないし、あからさまに女を男の奴隷のように扱う態度は問題視される。しかし根本のところでは、本書に描かれる「世間」「家」「女性」の関係が、今とさほど変わっていないことに愕然とせざるを得ない。未だに日本では「世間」が幅をきかし、「家」を維持するために「女性」が道具として利用されている。キヲが苦しんだ構図で、今の日本の女性も苦しんでいないか。
キヲの戦いは、女性差別が激しかった戦前の思い出話ではないのである。女とか男とか、そういうことではない。それは、「世間」よりも「自分」を価値の根本に置くこと、誰であれ一人の人間を意志ある存在として尊重すること、それを社会に対して認めさせるために、未だに続けられなければならない戦いなのだと私は思う。
女性問題を越えて現代でも読み続けられるべき名著。
【関連書籍】
『薩摩の女―兵児大将の祖母の記』大迫 亘 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/07/blog-post_6.html
理想化された「薩摩の女」を描く小説。
権領司キヲは、薩摩藩の外城士の娘として生まれた。外城士とは、武士ではあるが城下士よりも一段下の存在で、キヲはその中では割合によい身分だった。
キヲの父は西南戦争で賊軍として負けたことを終生悔しがり、その恨みのエネルギーはキヲ達への教育へと向けられた。キヲは男同様の教育を施され、おのれの意向を全うさせるという強烈な原則を魂に刻み込まれた。女は男の従属物として考えられていた時代に、キヲは独立自尊の精神と強靱な自我を育んでいた。
ところが、まさにそのような教育を施した父親によって、キヲの精神は打ち砕かれる。キヲに望まない結婚を強いたのである。有無をも言わさぬ決定だった。いくら「おのれの意向を持て」などと言っていても、結局女は家長の命令に従うもの、というのが父親の本音だったのである。
しかし程なくしてキヲは出戻りとなった。嫁ぎ先の姑との折り合いが悪く、キヲは姑から「夜叉」と呼ばれた。父は、それを権領司家への侮辱ととった。そのような侮辱を受けた以上、キヲは取り戻されなければならなかった。ここでもキヲの意向は無視された。ただ家の名誉が傷つけられた、という事情のためにキヲは離縁しなければならなかったのである。
しばらくしてキヲは再婚するが、それも望まない結婚だった。ここでも優先されたのは家の事情である。そして求められて結婚したにもかかわらず、夫の兵衛門はキヲを愛することはなかった。兵衛門は、「出戻り」という「キズ」があれば自分よりも身分が上の女性と結婚できる、という打算によってキヲを求めたに過ぎなかった。愛のない結婚生活は、キヲの自我をさらに先鋭化させていった。
キヲは、自らの意向が蹂躙され、家の従属物として扱われるに過ぎないとしても、そこに情を通わせ、求め合う関係があるならばそこに没入してもよいと思っていた。だが実際には、兵衛門はキヲを無視するどころか愛人さえ作り、そのくせ家では横座(家長としての地位)にあぐらをかき、横柄に振る舞うことで自らの権威を演出するだけが取り柄の男であった。キヲはこのようなつまらない男に従って生きる、などということは我慢がならなかった。やがてキヲは自らの畑仕事と行商によって、兵衛門の収入をアテにせず生活できるようになった。そしてままならぬ中でも自らの意向を貫き通すという戦いをしていくのである。
しかしその一方で、愛のない結婚生活の中でも夜の営みは続けられた。そして虚しい気持ちの中で、キヲは8人の子どもをもうけるのである。女とは、家を維持していくための道具にすぎなかった。女は男にいいように使われ、子を産み育てるだけに価値が置かれていた。女は、「自分」を持つことが許されなかった。女は、「妻」であるか「母」であるか、どちらかでしかなかった。
だが男が自由きままに振る舞っていたのかというと、そうでもなかった。ことあるごとに血族会議が開かれ、「世間がどういうか」「家のメンツを潰す気か」「家の名誉に関わる」などといって、男たちはキヲの意向を踏みにじったが、そこでは常に「家」の世間体が最優先され、誰も自分の考えを持つものはいなかった。女は確かに男に従属していたが、男も「世間」に従属させられており、それに疑問を持つものはいなかった。「自分」よりも「世間」の方が行動を規定していた。
そんな中で、キヲは自我を持つほとんど唯一の人間だった。キヲは近代的な精神に目覚めていた。だからキヲが(現代の人間からみて)当たり前のことをしても、それは家からも社会からも異常な行動として映った。「自分」を独立した価値あるものと見なす考えは、それだけで狂気じみていた。
キヲの戦いは、同じように抑圧されていた女性たちからも理解されなかった。おのれの意向を貫こうと正面衝突を繰り返すキヲを、女性たちは冷ややかに見ていた。表面上は男を立てながら、小ずるく立ち回ってうまく家庭を回すのが賢いやり方で、キヲのようなやり方では事を荒立てるばかりで結局自分のやりたいようには出来なくなるというのだ。 しかしそれは、キヲの戦いを全く理解していないものの見方だった。キヲは目先の決定権を手に入れたいのではなかった。自分を一人の人間として尊重して欲しい、という根源的な要求を主張していたのだ。
それを象徴するのが、強いて父から譲り受けた短刀だ。女が刀を持つ、ということは普通にはありえないことだ。しかしキヲは刀を持ちたがった。それが自らの意向を貫き通すための唯一の力、命のやりとりによって自らの存在を打ち立てるための力の象徴であった。「自分」を承認させることがキヲの戦いだった。
しかしその考えを、男も女も、誰も理解できなかったのだから、キヲの戦いは常に独り相撲に終わっていた。キヲはむしろ正面衝突を望んでいたが、衝突すべきものは空疎だった。「世間」のことばかり気にする小心翼々とした人間達を、キヲは冷笑した。そのような人間の相手をすることが、次第にバカバカしくなってきた。やがてキヲは、兵衛門との愛のない結婚生活、「世間」にしか向かない血族、「自分」のない人生に見切りをつけた。
そして齢七十にして、兵衛門に離婚を突きつけたのである。そのような老婆が、離婚を突きつけるなどということは前代未聞だった。「世間」も「血族」も、非難囂々だった。だがキヲは、それまでの無意味な人生に決別し、これから「自分」を大切にする人生を踏み出したのである。それがキヲが全人生をかけて到達した答えだった。
本書に描かれた権領司キヲは、社会や男に翻弄されるだけの女とはほど遠い。それらに常に戦いを挑み、挫かれても挫かれてもそのたびごとに「自分」を強くしていく反抗する人間である。 しかし同時に、キヲは外城士の娘として、「ザイ」(百姓)に強い差別意識を持っていた。彼女は自分を、誇り高い士族の娘であると考えていた。自らを蹂躙した「血」の論理を、彼女自身乗り越えていなかったのだ。彼女の桎梏となったのも「家」という「血」であったし、彼女がザイを差別したのも「血」であった。
キヲには、もっと徹底的に世間に反抗した叔母がいた。叔母は、「ザイ」の男と恋に落ち、身分も外聞も捨てて愛に生きた。世間からは村八分になっていたが、彼女は幸せだった。「血」の論理を、乗り越えていたからだ。キヲの悲劇は、自らを苦しめた「血」の論理を、自分自身、捨てきれなかったことだった。
著者中村きい子は、自らの母をモデルにこの小説を作ったという。この時代に比べると、今は女性の地位が随分向上した。結婚を無理強いされることは少ないし、あからさまに女を男の奴隷のように扱う態度は問題視される。しかし根本のところでは、本書に描かれる「世間」「家」「女性」の関係が、今とさほど変わっていないことに愕然とせざるを得ない。未だに日本では「世間」が幅をきかし、「家」を維持するために「女性」が道具として利用されている。キヲが苦しんだ構図で、今の日本の女性も苦しんでいないか。
キヲの戦いは、女性差別が激しかった戦前の思い出話ではないのである。女とか男とか、そういうことではない。それは、「世間」よりも「自分」を価値の根本に置くこと、誰であれ一人の人間を意志ある存在として尊重すること、それを社会に対して認めさせるために、未だに続けられなければならない戦いなのだと私は思う。
女性問題を越えて現代でも読み続けられるべき名著。
【関連書籍】
『薩摩の女―兵児大将の祖母の記』大迫 亘 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/07/blog-post_6.html
理想化された「薩摩の女」を描く小説。
2019年7月11日木曜日
『日向国山東河南の攻防—室町時代の伊東氏と島津氏』新名 一仁 著
鎌倉から室町までの日向国山東河南の歴史について、島津氏と伊東氏の関係を軸に語る本。
日向国の「山東河南」とは、宮崎県平野部の大淀川南岸を指す。ここは島津氏、伊東氏の領国の境界に位置していたため、その勢力が激突する場所であった。
鎌倉時代の山東
鎌倉時代の初め、宮崎県の荘園は、島津荘(約45%)・宇佐八幡宮領(25%)・王領(皇室領)国富荘(約20%)の3つで9割を占めていた。
ところが建仁3年(1203年)「比企能員(ひき・よしかず)の乱」が起こると島津氏は縁座(親類として巻き添えになって罰せられること)により薩隅日三カ国の守護職および島津荘惣地頭職を解任させられた。島津氏は後日薩摩の守護職には復帰するものの、日向からは手を引くことになり、広大な島津荘は北条氏が管理するようになった。
宇佐八幡宮領については、実際には様々に分割され、宇佐八幡宮の支配を離れて各荘ごとに領主が存在する状態となっていた。元寇より後、ここに伊東氏の一門、庶子家が下向してくる。伊東氏は静岡の伊東を本拠地とする鎌倉御家人であったが、幕府の依頼を受けて庶子家を下向させたのである。それが、田島伊東氏(田島荘)、門川伊東氏(富田荘)、木脇伊東氏(諸県荘)の3家であった。
国富(くどみ)荘については、鎌倉時代を通じて王領として維持され、鎌倉時代の最後には地頭として北条泰家が支配していた。
戦乱の始まり
鎌倉時代末はこうした状況にあったが、鎌倉幕府が滅亡して建武の新政が敷かれると、こうした土地は後醍醐天皇によって没収され、功績があった家臣達に分配されることとなった。国富荘・島津荘日向方を与えられたのが足利尊氏である。
ところが建武の新政は2年ほどで瓦解、足利尊氏は後醍醐天皇により追討令が出される。こうして国富荘・島津荘はある意味「無主」の状態となって奪い合われるのである。
この混乱に乗じて山東に進出してきたのが、都城盆地の三俣院を本拠地とする肝付兼重(きもつき・かねしげ)と、木脇伊東氏の伊東祐広(すけひろ)であり、これに対立したのが尊氏方を貫いた在地勢力の土持宣栄(のぶひで)である。 一方尊氏は、薩摩・大隅の両国には守護・島津貞久を下向させ、日向国には畠山直顕(ただあき)を「大将」として派遣し、肝付兼重・伊東祐広の討伐を命じた(建武3年(1336年))。
日向に下向した畠山直顕は、穆佐(むかさ)院・国富荘を本拠地として日向国を平定し、追って畠山直顕は日向国守護職に昇格したが、観応元年(1350年)「観応の擾乱」が起こる。「観応の擾乱」では畠山直顕は足利直冬方となって(結果的に)尊氏方・南朝方と対立。そしてこの混乱期に、直冬方として伊東本宗家は日向に下向してくるのである。
伊東本宗家の山東進出
しかし伊東本宗家当主・伊東氏祐は、すんなりとは山東に入っていくことができなかった。畠山直顕の軍門に降ってからも支配権を保持していた伊東祐広の子・守永祐氏が阻んだのだ。そこで伊東氏祐は、守永祐氏の娘を妻とすることで和睦し、その権益を継承する形で都於郡(とのこおり)に入部した。
一方、鎌倉幕府滅亡に際し、後醍醐天皇の下で一時は大隅・日向国の守護職も回復した島津貞久だったが、尊氏配下になるのが遅れたためか日向国守護職は大友氏に奪われる。ところが征西将軍宮懐良(かねよし)親王が下向し九州での勢力が大きくなると、大友氏や島津氏を初めとした多くの武家方国人は宮方に寝返った。そして貞久の三男氏久は畠山直顕を撃破して日向国進出を確固たるものにしていった。
そんな中、武家方の挽回のために九州に派遣されたのが今川了俊である。今川了俊は九州を制圧する勢いだったものの、島津氏と友好関係にあった前筑前国守護の少弐冬資(しょうに・ふゆすけ)を謀殺したため島津氏とは対立。今川了俊は伊東氏、土持氏などを反島津でまとめて国人一揆を主導したがさしたる成果もなく瓦解。やがて今川了俊は京都へ召還された(応永2年(1395年))。
そういうゴタゴタの間に、伊東本宗家の伊東祐安(すけやす)(氏祐の子) は国富荘を実効支配していった。これは違法な占拠だったが、今川了俊は島津氏との対抗上これを黙認。一方で国富荘は幕府にとって重要な経済基盤だったため、幕府は島津氏に国富荘を奪還するよう命じた。こうして国富荘を巡って、島津氏と伊東氏が対立するようになった。
島津家の山東進出
今川了俊の召還後、島津氏は山東に侵攻し加江田城を攻略(応永6年(1399年)頃)。国富荘全域を手に入れることはできなかったが、山東河南の一部を実効支配することとなった。さらに、本来は国富荘を奪還するよう幕府から命じられたことが大義名分だったにもかかわらず、島津氏は強引なロジックによって実効支配を幕府に追認させ、島津元久(氏久の子)は大隅・日向国守護職に命じられ、島津家は薩隅日の三カ国の守護職を手に入れた。
山東が係争の地となったのは、山北にいた島津氏の庶子家(北郷家や樺山家)からの要請もあったが、それよりも大きかったのは山東河南、つまり大淀川周辺が海運の要衝だったからである。内陸の大荘園である島津荘は、収穫物や貢納の運搬のために港を必要とした。であるから、山東の海岸までの領有権を確立することが重要だったのである。
山東河南への進出を果たした島津元久は、その支配のために異母弟の島津久豊を派遣した。そこで思わぬことが起こる。久豊は元久に無断で、伊東祐安の娘を妻に迎えて勝手に伊東氏と和睦してしまったのである(応永8年(1401年))。元久はこれに激怒。また伊東庶子家や山東の在地勢力も本宗家の単独講和を認めなかった。そのため元久と山東国人が結託し、島津久豊・伊東祐安連合との間で紛争が勃発する。この紛争は戦闘にまでは到らず、結局久豊と祐安の娘の間に生まれた虎寿丸を元久の人質にすることで和睦が成立した。
島津家の内訌と伊東祐立の侵攻
島津元久が没すると、島津本宗家の家督は元久の妹と伊集院頼久の間にうまれた犬千代丸に移ることになっていたが、これを阻止する形で久豊がクーデターを起こし家督を奪取した(応永18年(1411年))。伊集院家と島津家旧主流派(総州家)はこれに反発し、久豊方との抗争に突入する。その空隙を塗って、久豊の義兄弟にあたる伊東祐立(すけはる)(祐安の子)は山東河南に進出。北郷氏・樺山氏・佐多氏などを中心とする島津勢は「曽井・源籐合戦」で大敗、さらに久豊の居城だった穆佐城も焼き払われた。こうして伊東祐立は念願だった山東河南の制圧に成功した。
その背景には、かつて伊東本宗家よりも強い立場だった庶子家(田島伊東氏、門川伊東氏、木脇伊東氏)を婚姻政策によって内部に取り込み、伊東家一門の結束を固めつつ本宗家の求心力を高めた地道な「血の結びつき」の構築があった。
さて、当然島津久豊としては奪われた山東河南の奪還を図る。伊東氏は講和を申し込んだが久豊はこれを拒否し侵攻。加江田城を陥落させ同城に居住した。1425年(応永32年)、久豊は病没し、山東制圧の宿願は穆佐城生まれの嫡男忠国に引き継がれた。また庄内国人(北郷氏や樺山氏)にとっても庄内の外港であった山東河南の奪回は宿願だったから、大規模な山東侵攻が行われるが島津勢は大敗を喫する。
しかもその隙を縫って、薩摩国では「国一揆」とよばれる反島津の反乱が起きた(永享4年(1432年))。中心人物は伊集院煕久や渋谷一族である。しかし忠国は山東侵攻を中止せず、伊東・土持連合軍と合戦。決着はつかなかったが伊東氏が領地を割譲することで和睦し、忠国は飯野や穆佐を回復したものの、「国一揆」への対応のまずさのためか失脚し、事実上のクーデターによって庄内末吉に隠居させられ、一躍リーダーとして擁立されたのが弟の持久(もちひさ)だった。こうして島津家は忠国派と持久派の泥沼の抗争に巻き込まれていく。
伊東氏中興の祖、伊東祐堯
そんな中で伊東本宗家の家督を相続した伊東祐堯(すけたか)は、島津氏が内訌で弱体化している間に国人支配(一揆の結成)と一族の結束を高め、山東全域の制圧に乗り出す。次々に山東を制圧すると、島津氏の拠点・加江田城、穆佐城も攻略し、遂に山東全土を統一した。後に「伊東四十八城」と呼ばれる広大な領域が伊東氏の支配下となっていったのである。
同じ時期、島津忠国・持久はようやく和睦し、また追って伊東氏とも和睦した。これにより島津氏は一時的に山東奪回を諦めることになる。 忠国の嫡男立久が忠国を加世田に追放する形で家督を相続すると、政治的には融和路線となり情勢は安定。さらに伊東祐堯とも改めて和睦し、立久は祐堯の娘を妻に迎えて血縁の上でも関係強化を図った。そして伊東氏の山東支配を認める代わりに、島津氏は庄内支配を強化していった。
島津氏が体制を立て直し、伊東氏とまた対決するようになるのは、16世紀に島津忠良・貴久親子が守護家を継承してからのことである。
さて、鎌倉時代から室町時代までの山東の歴史を見て感じることは、最終的に山東統一を成し遂げる伊東本宗家は決して最初から支配的な勢力ではなかったということだ。むしろ先行的に下向していた庶子家や土持氏のような在地勢力の方がずっと強かった。本宗家であるという権威も、ほとんどなかったように思われる。そんな伊東本宗家が結果的に山東の覇者になったのは、伊東祐安とその孫の祐堯の周到な婚姻政策が大きく影響していたのかもしれない。この頃、島津氏と伊東氏は対立しながらも関係を強化しており、久豊とその孫の立久は伊東氏から妻を迎えている。その微妙な距離感は興味がそそられるところである。
ところで正直に言うと、本書はほぼ2回読んだがなかなか歴史が頭に入ってこなかった。記述はわかりやすく簡にして要を得ているが、逆に言うとちょっと「分かっている人向け」の面もある。よりかみ砕いて説明し、人物像のイメージが湧くようなエピソードも添えてもらえると詳しくない人にも楽しめると思う。
やや専門的だが、マイナーな山東の戦乱の歴史がよくまとまった本。
日向国の「山東河南」とは、宮崎県平野部の大淀川南岸を指す。ここは島津氏、伊東氏の領国の境界に位置していたため、その勢力が激突する場所であった。
鎌倉時代の山東
鎌倉時代の初め、宮崎県の荘園は、島津荘(約45%)・宇佐八幡宮領(25%)・王領(皇室領)国富荘(約20%)の3つで9割を占めていた。
ところが建仁3年(1203年)「比企能員(ひき・よしかず)の乱」が起こると島津氏は縁座(親類として巻き添えになって罰せられること)により薩隅日三カ国の守護職および島津荘惣地頭職を解任させられた。島津氏は後日薩摩の守護職には復帰するものの、日向からは手を引くことになり、広大な島津荘は北条氏が管理するようになった。
宇佐八幡宮領については、実際には様々に分割され、宇佐八幡宮の支配を離れて各荘ごとに領主が存在する状態となっていた。元寇より後、ここに伊東氏の一門、庶子家が下向してくる。伊東氏は静岡の伊東を本拠地とする鎌倉御家人であったが、幕府の依頼を受けて庶子家を下向させたのである。それが、田島伊東氏(田島荘)、門川伊東氏(富田荘)、木脇伊東氏(諸県荘)の3家であった。
国富(くどみ)荘については、鎌倉時代を通じて王領として維持され、鎌倉時代の最後には地頭として北条泰家が支配していた。
戦乱の始まり
鎌倉時代末はこうした状況にあったが、鎌倉幕府が滅亡して建武の新政が敷かれると、こうした土地は後醍醐天皇によって没収され、功績があった家臣達に分配されることとなった。国富荘・島津荘日向方を与えられたのが足利尊氏である。
ところが建武の新政は2年ほどで瓦解、足利尊氏は後醍醐天皇により追討令が出される。こうして国富荘・島津荘はある意味「無主」の状態となって奪い合われるのである。
この混乱に乗じて山東に進出してきたのが、都城盆地の三俣院を本拠地とする肝付兼重(きもつき・かねしげ)と、木脇伊東氏の伊東祐広(すけひろ)であり、これに対立したのが尊氏方を貫いた在地勢力の土持宣栄(のぶひで)である。 一方尊氏は、薩摩・大隅の両国には守護・島津貞久を下向させ、日向国には畠山直顕(ただあき)を「大将」として派遣し、肝付兼重・伊東祐広の討伐を命じた(建武3年(1336年))。
日向に下向した畠山直顕は、穆佐(むかさ)院・国富荘を本拠地として日向国を平定し、追って畠山直顕は日向国守護職に昇格したが、観応元年(1350年)「観応の擾乱」が起こる。「観応の擾乱」では畠山直顕は足利直冬方となって(結果的に)尊氏方・南朝方と対立。そしてこの混乱期に、直冬方として伊東本宗家は日向に下向してくるのである。
伊東本宗家の山東進出
しかし伊東本宗家当主・伊東氏祐は、すんなりとは山東に入っていくことができなかった。畠山直顕の軍門に降ってからも支配権を保持していた伊東祐広の子・守永祐氏が阻んだのだ。そこで伊東氏祐は、守永祐氏の娘を妻とすることで和睦し、その権益を継承する形で都於郡(とのこおり)に入部した。
一方、鎌倉幕府滅亡に際し、後醍醐天皇の下で一時は大隅・日向国の守護職も回復した島津貞久だったが、尊氏配下になるのが遅れたためか日向国守護職は大友氏に奪われる。ところが征西将軍宮懐良(かねよし)親王が下向し九州での勢力が大きくなると、大友氏や島津氏を初めとした多くの武家方国人は宮方に寝返った。そして貞久の三男氏久は畠山直顕を撃破して日向国進出を確固たるものにしていった。
そんな中、武家方の挽回のために九州に派遣されたのが今川了俊である。今川了俊は九州を制圧する勢いだったものの、島津氏と友好関係にあった前筑前国守護の少弐冬資(しょうに・ふゆすけ)を謀殺したため島津氏とは対立。今川了俊は伊東氏、土持氏などを反島津でまとめて国人一揆を主導したがさしたる成果もなく瓦解。やがて今川了俊は京都へ召還された(応永2年(1395年))。
そういうゴタゴタの間に、伊東本宗家の伊東祐安(すけやす)(氏祐の子) は国富荘を実効支配していった。これは違法な占拠だったが、今川了俊は島津氏との対抗上これを黙認。一方で国富荘は幕府にとって重要な経済基盤だったため、幕府は島津氏に国富荘を奪還するよう命じた。こうして国富荘を巡って、島津氏と伊東氏が対立するようになった。
島津家の山東進出
今川了俊の召還後、島津氏は山東に侵攻し加江田城を攻略(応永6年(1399年)頃)。国富荘全域を手に入れることはできなかったが、山東河南の一部を実効支配することとなった。さらに、本来は国富荘を奪還するよう幕府から命じられたことが大義名分だったにもかかわらず、島津氏は強引なロジックによって実効支配を幕府に追認させ、島津元久(氏久の子)は大隅・日向国守護職に命じられ、島津家は薩隅日の三カ国の守護職を手に入れた。
山東が係争の地となったのは、山北にいた島津氏の庶子家(北郷家や樺山家)からの要請もあったが、それよりも大きかったのは山東河南、つまり大淀川周辺が海運の要衝だったからである。内陸の大荘園である島津荘は、収穫物や貢納の運搬のために港を必要とした。であるから、山東の海岸までの領有権を確立することが重要だったのである。
山東河南への進出を果たした島津元久は、その支配のために異母弟の島津久豊を派遣した。そこで思わぬことが起こる。久豊は元久に無断で、伊東祐安の娘を妻に迎えて勝手に伊東氏と和睦してしまったのである(応永8年(1401年))。元久はこれに激怒。また伊東庶子家や山東の在地勢力も本宗家の単独講和を認めなかった。そのため元久と山東国人が結託し、島津久豊・伊東祐安連合との間で紛争が勃発する。この紛争は戦闘にまでは到らず、結局久豊と祐安の娘の間に生まれた虎寿丸を元久の人質にすることで和睦が成立した。
島津家の内訌と伊東祐立の侵攻
島津元久が没すると、島津本宗家の家督は元久の妹と伊集院頼久の間にうまれた犬千代丸に移ることになっていたが、これを阻止する形で久豊がクーデターを起こし家督を奪取した(応永18年(1411年))。伊集院家と島津家旧主流派(総州家)はこれに反発し、久豊方との抗争に突入する。その空隙を塗って、久豊の義兄弟にあたる伊東祐立(すけはる)(祐安の子)は山東河南に進出。北郷氏・樺山氏・佐多氏などを中心とする島津勢は「曽井・源籐合戦」で大敗、さらに久豊の居城だった穆佐城も焼き払われた。こうして伊東祐立は念願だった山東河南の制圧に成功した。
その背景には、かつて伊東本宗家よりも強い立場だった庶子家(田島伊東氏、門川伊東氏、木脇伊東氏)を婚姻政策によって内部に取り込み、伊東家一門の結束を固めつつ本宗家の求心力を高めた地道な「血の結びつき」の構築があった。
さて、当然島津久豊としては奪われた山東河南の奪還を図る。伊東氏は講和を申し込んだが久豊はこれを拒否し侵攻。加江田城を陥落させ同城に居住した。1425年(応永32年)、久豊は病没し、山東制圧の宿願は穆佐城生まれの嫡男忠国に引き継がれた。また庄内国人(北郷氏や樺山氏)にとっても庄内の外港であった山東河南の奪回は宿願だったから、大規模な山東侵攻が行われるが島津勢は大敗を喫する。
しかもその隙を縫って、薩摩国では「国一揆」とよばれる反島津の反乱が起きた(永享4年(1432年))。中心人物は伊集院煕久や渋谷一族である。しかし忠国は山東侵攻を中止せず、伊東・土持連合軍と合戦。決着はつかなかったが伊東氏が領地を割譲することで和睦し、忠国は飯野や穆佐を回復したものの、「国一揆」への対応のまずさのためか失脚し、事実上のクーデターによって庄内末吉に隠居させられ、一躍リーダーとして擁立されたのが弟の持久(もちひさ)だった。こうして島津家は忠国派と持久派の泥沼の抗争に巻き込まれていく。
伊東氏中興の祖、伊東祐堯
そんな中で伊東本宗家の家督を相続した伊東祐堯(すけたか)は、島津氏が内訌で弱体化している間に国人支配(一揆の結成)と一族の結束を高め、山東全域の制圧に乗り出す。次々に山東を制圧すると、島津氏の拠点・加江田城、穆佐城も攻略し、遂に山東全土を統一した。後に「伊東四十八城」と呼ばれる広大な領域が伊東氏の支配下となっていったのである。
同じ時期、島津忠国・持久はようやく和睦し、また追って伊東氏とも和睦した。これにより島津氏は一時的に山東奪回を諦めることになる。 忠国の嫡男立久が忠国を加世田に追放する形で家督を相続すると、政治的には融和路線となり情勢は安定。さらに伊東祐堯とも改めて和睦し、立久は祐堯の娘を妻に迎えて血縁の上でも関係強化を図った。そして伊東氏の山東支配を認める代わりに、島津氏は庄内支配を強化していった。
島津氏が体制を立て直し、伊東氏とまた対決するようになるのは、16世紀に島津忠良・貴久親子が守護家を継承してからのことである。
さて、鎌倉時代から室町時代までの山東の歴史を見て感じることは、最終的に山東統一を成し遂げる伊東本宗家は決して最初から支配的な勢力ではなかったということだ。むしろ先行的に下向していた庶子家や土持氏のような在地勢力の方がずっと強かった。本宗家であるという権威も、ほとんどなかったように思われる。そんな伊東本宗家が結果的に山東の覇者になったのは、伊東祐安とその孫の祐堯の周到な婚姻政策が大きく影響していたのかもしれない。この頃、島津氏と伊東氏は対立しながらも関係を強化しており、久豊とその孫の立久は伊東氏から妻を迎えている。その微妙な距離感は興味がそそられるところである。
ところで正直に言うと、本書はほぼ2回読んだがなかなか歴史が頭に入ってこなかった。記述はわかりやすく簡にして要を得ているが、逆に言うとちょっと「分かっている人向け」の面もある。よりかみ砕いて説明し、人物像のイメージが湧くようなエピソードも添えてもらえると詳しくない人にも楽しめると思う。
やや専門的だが、マイナーな山東の戦乱の歴史がよくまとまった本。
登録:
投稿 (Atom)