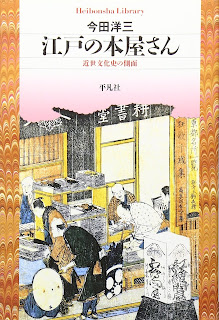江戸時代の出版・流通事情をまとめた本。
「これまでの江戸の文化研究といえば、作品の形式や内容や、作者・思想家についての研究ばかりで、作品を出版し、世の中に送り出し、作品と読者をむすびつける役割を果たす書物屋・出版業の人々について研究することがあまりにもおろそかではないのか」という問題意識から、著者は江戸時代に出版された本の奥付(本の最後にある著者や出版社が記載されたページ)を手当たり次第に捜索し、特別な記録が残されていない、出版業で働いていた人びとの姿を浮かび上がらせ、江戸時代の出版史としてまとめたのが本書である。
江戸初期の出版業の中心は京都である。寛永年間のころ(1620〜40年代)京都の町衆は大寺院と結んで仏典や儒書、日本の古典などを刊行するようになった。武士たちも、武力による統治から次第に文治主義へと移行してきて、行政官にふさわしい教養を身につけなくてはならなかった。この時代の出版業は、こうした特権階級の知識人たちと関係を結ぶことで成立した。こうして京都には「書林十哲」と呼ばれる10の大書商が現れた。
元禄期(1700年代前後)になると、大阪の書商が勃興してくる。当時京都には100軒以上本屋(出版社)があったが、大阪には30軒に満たなかった。しかしこの少数勢力が出版界に新風を入れた。井原西鶴の『好色一代男』を嚆矢とする浮世草子類、すなわち好色本である。『好色一代男』(1663年)の成功でこれに類する好色本がたくさん出版され、本は特権階級・知識階級のみが読むものではなく、大衆的な商品になっていった。
俳諧の本もたくさん出版された。そして都会だけでなく、おそらくは俳諧のネットワークを通じて農村にまで本は流通するようになる。本書に例示される豪農の「読書生活」は驚くべきものだ。田舎にいながら、書物の行商が頻繁に訪ねてきてたくさんの本を借りたり買ったりしている。かつては書商が特権階級と結びついていたのでさして宣伝の必要もなかったが、大衆向けの本が作られるようになると宣伝・流通の方もやらなくてはならない。それまで本が売られていなかったところへ積極的に切り込んでいく書商が現れるのである。江戸時代の農村にここまで知識の流通があったのかと蒙を啓かされる思いであった。
元禄時代の出版文化を象徴する存在に「八文字屋」がある。八文字屋は井原西鶴の成功の2匹目のナマズを狙ったような出版社で、とにかく売れる本をたくさん世に出した。その経営の特徴は、(1)庶民向け、(2)好色性、(3)実用性、(4)教訓性、(5)積極的な販売策、(6)稿本の積極的確保(売れる原稿を仕入れる)といったもので、要するに庶民にとって商品価値の高い本を積極的に販売する、ということである。八文字屋は一つの時代をつくったが、こうした特徴からその場しのぎ的な作品を残したに過ぎず、出版文化を発展させる力はなかった。それどころか、元禄文化をダメにしてしまうようなところすら内在していた。
一方、幕府の方でもこの新興の出版業については厳しい言論統制で臨んだ。既に寛文期(1660年代)にその規制は始まっている。時代が進むにつれ規制はどんどん厳しくなり、元禄の頃には「批判がましい言動をとる者は、あっという間に死刑に処せられ、三宅島・大島に流罪、島流しにする」というくらいになっていた。また幕府は書物屋に組合を作らせ、相互監視させるという策をとった。
享保の頃になると、江戸の書商も次第に形を整えてくる。最初は京都の書商の出店(でみせ)のような系列店が多かったのが、だんだんと江戸生え抜きの出版社の方が(両者抗争しつつ)中心になっていった。こうした江戸の出版文化を象徴する出来事が、杉田玄白の『解体新書』の出版(1775年)である。これを出版したのが江戸の書商を代表する須原屋市兵衛。須原屋市兵衛は、杉田玄白の他、平賀源内、森島中良ら田沼時代に活躍した一流の学者の作品、それも学問史上画期的な作品を矢継ぎ早に出版した。文化人や学者のパーソナルな交流から生まれた学問的成果を出版して公的な場面に送り込んでいく役割を市兵衛は果たしていた。
市兵衛は、学問的成果だけでなく、当時の農村の疲弊や社会の矛盾をえぐり出す『民間備荒録』といった本を採算を度外視して出版。さらに『三国通鑑図説』や『万国一器界万量総図』など世界地図・地理書をも刊行し、世界のありさまを日本人に知らしめようとした。しかし『三国通鑑図説』は幕府から絶版の処分にされ、罰金を払わされた。そして市兵衛の盟友・森島中良は松平定信の家臣に取り立てられ、在野の啓蒙勢力であった市兵衛らのサークルは瓦解させられた。田沼時代の江戸文化の結晶を社会に送り込んできた須原屋市兵衛は、急速に没落して版木も他の出版社に売り払い、誠に寂しい晩年を送ることになった。
須原屋市兵衛についで現れたのが、写楽を世に出したことで有名な「蔦重」こと蔦屋重三郎。重三郎は吉原に生まれ、ちょうど『解体新書』が出版される頃、吉原の案内書である『吉原細見』の出版権を手に入れ、『細見』の序文を一流の知識人に書いてもらい、積極的に販売するという手法で頭角を現した。重三郎は、町人と武士が一体となった江戸っ子文化の創出に、演出家的な役割を果たしつつ出版経営を行った。浄瑠璃本、黄表紙(絵付きの滑稽本)、狂歌本などを次々に出版し、しかも町人・武士といった身分にとらわれず一流の文人に依頼して高水準なものを生みだした。
さらに重三郎は、当局の政策を茶化す『文武二道万石通』といった時事を風刺する作品も世に送り出し大評判を得る。「蔦重」が時事に取材して黄表紙を成功させたことは当時の出版社を驚かせた。それまでの洒落本や狂歌本は売れたとしても所詮は「通」向けのもので流通量も限られていた。ところが重三郎の黄表紙は、いわば漫画本であるから大衆向けのものであった。こうして、江戸の識字層は一気に黄表紙や様々な「読書」へと引きずり込まれていったのである。
しかし重三郎の冒険も、やはり松平定信によって弾圧されることになる。松平定信は寛政2年(1790年)に出版取締りの触書を出した。要するに、幕府にとって都合の悪いことは出版できないという規制だ。重三郎は見せしめとして捉えられ、多額の罰金と刑罰を受けた。重三郎はそれでもめげずに、利益を度外視して写楽の絵を刊行したが、それが最後の出版文化への挑戦で、晩年は寂しく亡くなった。そうした晩年の蔦重の下で手代をしていたのが若き日の滝沢馬琴、寄宿していたのが十返舎一九である。
続く化政期に入ると、中下層の町人にまで文化の受容層が拡大して出版物の数は膨大となり出版文化は興隆の時を迎えたが、質的には停滞していた。そもそも言論統制がさらに厳しくなり、筆禍事件、禁書が頻発したため当たり障りのない本しか出せなくなった。そこで活躍したのが貸本屋だ。出版は難しくても、写本(書き写した本)なら草の根の活動であるため規制をかいくぐりやすい。この時代は貸本屋が「秘本」の流通を担った。貸本屋の店頭はなじみ客たちの文化サロンにもなった。 江戸だけで10万軒に及ぶ貸本屋があったという。
幕末期には、本の需要は地方にも拡大してくる。地方の本屋(出版社)は江戸の本屋と提携して本を出すようになった。幕末には、封建社会の動揺が切実な課題として地方にも迫ってきていた。こうした課題に対応するための本が求められるようになったし、寺子屋での教科書需要も大きくなってきていた。特に、天保の救荒対策のため武士層にかつてない書籍需要が生じたという。それは庶民としても同じで、寺子屋の増加に象徴されるように、この時期に読み書きの必要性を大きく感じるようになったようだ。危機を乗り切るためどうしたらいいか、そういう実用的な知識が書物に期待されるようになっていた。
学術・文化、そして近代的ジャーナリズムを育んだ江戸の出版文化は、厳しい統制によって停滞させられつつも明治維新を準備した。しかしいざ明治期に移ると、江戸時代までの書物屋は、明治の中頃までにほとんど没落し去ってしまった。新しい印刷技術や新聞を代表とする急テンポのジャーナリズムといった新しい時代の情報流通に対応できず、明治の新興出版業者との競争に負けてしまったのである。江戸幕府は、言論を弾圧した出版文化の敵役ではあったが、江戸の出版文化はやはり幕藩体制にその基盤を負っていた。敵対していた江戸幕府の滅亡と共に、江戸の書商たちが消え去ってしまったのは怖ろしい皮肉である。
本書は、そうした消え去った歴史を、奥付などの限られた原資料を基に1ピースずつ再構成した労作であり、江戸の出版文化の豊かさに驚かされるだけでなく、それを弾圧した幕府との対決と敗北、そしてその終焉までも一気に読ませる歴史絵巻でもある。
書商という文化の裏方から見る江戸の文化史。
2017年3月13日月曜日
2017年2月26日日曜日
『日本文化の多重構造―アジア的視野から日本文化を再考する』佐々木 高明 著
日本文化の基層に存在する多様な文化について述べる本。
日本文化が、大まかに言って縄文文化と弥生文化のハイブリッドで形成されたことはよく知られている。しかしもっと細かく見てみると、縄文文化には東部ユーラシアに由来する「ナラ林文化」と、アッサムから東南アジア、雲南に連なる「照葉樹林文化」があるという。さらに、熱帯アジア島嶼部の「南島式耨耕(どうこう)文化」が黒潮を伝って渡ってきている可能性もある。本書は、日本文化がこうした多様な出自を持つ文化が共存することで生まれたものであることを論証するものである。
そのために、著者の専門である民族学の他、民俗学、考古学や歴史学、生態学といった様々な学問分野の成果が総動員されており、特に第Ⅰ部および第Ⅱ部はそうした既存研究の集大成的なものとして書かれている。
著者は、このうちの「照葉樹林文化論」の提唱者の一人であり、本書においてもこの説明の比重が最も大きい。照葉樹林文化の特徴を一つ挙げれば、モチモチした食品への強い志向があることである。餅やチマキ、オコワといったモチモチネバネバした食品は他の文化ではあまり好まれないが、この文化では特別な場面で価値が高いものとして扱われハレの日の儀礼的食品になる。この他、味噌など大豆の発酵食品の使用、飲茶の慣行、麹を使う酒の製造、蚕の繭から絹をつくる技術、漆の使用、ドングリ類を水にさらしてアク抜きする技法、柑橘類やシソやエゴマの栽培といったものも照葉樹林文化圏に共通する特徴である。
また、著者の専門は「焼畑」であるため照葉樹林文化の中でも特に焼畑については詳しく書かれている。焼畑というと遅れた農法のように思われるけれども、東アジアの環境の中では持続可能で完成された農法であり、焼畑による雑穀栽培は早い時期に完成形に達して日本に伝播した。昭和はじめくらいまでは特に西日本の山間部において、焼畑によるアワを中心とした雑穀とイモ類の栽培は普通に見られるものだった。第Ⅲ部では、この「焼畑」の系譜が著者自身のフィールドワークに基づき丁寧に解明されている。
日本文化の基層、すなわち衣食住の基本的技術と慣習を見てみると、この照葉樹林文化によっている部分が非常に大きいという。弥生時代になって大陸から稲作文化が伝来してきても、生活の基本となる技術にはほとんど変更が加えられなかった。例えば、竪穴住居や狩猟・漁撈の技術、石器・土器・木器・骨角器などの製作、植物の採集・畑作農耕の技術などは縄文文化をそのまま引き継いだのである。稲作文化と共にやってきたものは、銅鏡や銅剣などの武器や祭器、卜骨(ぼっこつ:骨占い)や鳥霊信仰、支石墓のような新しい墓制、そして社会的・政治的統合原理というような、非常にシンボリックなもの、「剣と鏡」に象徴される支配原理こそが弥生文化の中心だった。
つまり日本文化は、照葉樹林文化によって形作られた生活基盤の上に稲作が導入され、それによって政治的に統合されて出来たものだと考えることができる。
第Ⅳ部では、この稲作文化についてアジア的視点で考察し、日本に導入された稲作がどのようなものだったかを推測し、稲作文化を再考している。それによれば、稲作の技術は早い時期に完成していたが生産性は低いもので、雑穀栽培や堅果類の採集に頼らなければ生活していけないものだった。しかし稲作自体は、たった2、3世代という短い期間で北部九州から西日本に広まっているのだという。なぜこの新参の技術が素早く広がったかというと、既に西日本には照葉樹林文化式の雑穀栽培の伝統があり、イネ科植物栽培に必要な知識が蓄積されていたからではないかと推測している。
このように、縄文文化的なものと弥生文化的なものは補完し合い、いわばいいとこ取りのような形で日本文化の形成に寄与してきた。しかし近世幕藩体制が確立してくると、山で焼畑をして雑穀栽培で暮らすようなライフスタイルは統治者の論理と合わなくなってくる。石高制=米社会が成立するためには、米以外のものを中心に据える暮らしはあってはならなかった。そこで体制側は、非稲作民の山村の集団に対して武力による大弾圧を強行した。
例えば、椎葉村では1619年に幕府が討伐の大軍を差し向け、山中男女千余人がことごとく捉えられ、140人の首がはねられた。これをみて婦女20人が自殺するなど、合わせて200人以上が死んだ。人口千人ほどの村には潰滅的打撃である。このように、米社会への参画を強要した幕府側に反抗して山村各地で一揆が起こったが、全て幕府側の勝利に終わり、しかも大量の殺戮を伴っているという。日本文化の基層に存在する照葉樹林文化は消え去ることはなかったが、そのライフスタイルはこの時期にかなりの程度矯正されてしまった。
本書の多くは著者がそれまでに発表した論文をまとめたものであるが、若干重複は多いものの構成は散漫ではなく書き下しのようなまとまりがある。著者の主張する日本文化の多重構造は、多くの物証に基づくもので説得的であり、日本文化をアジアの中において理解する上での重要な要素であると感じた。
なお終章では、多元的で多重な構造をもつ日本文化は、多様な文化を柔軟に対応する優れた特色を持っていると主張される。21世紀は多文明が協調していく社会になるはずで、その時代の諸事象に対し、日本文化は容易に適応しうる特性を有しているのだ、としている。「私が本書の結論として言いたかったのは、この事実である(p.326)」ということだが、これについては我田引水の感が否めない。
というのは、近世幕藩体制の成立の産みの苦しみだとしても、山村の非稲作民を弾圧した歴史が存在している以上、日本文化が他文化に対して寛容だという主張は成り立たないはずである。むしろ、稲作文化が照葉樹林文化などの非稲作文化を「基層」に追いやってできたのが日本文化だという見方が正確な気がする。基層に追いやられた文化は消えはしなかったが、稲作とそれを主導する支配階級の原理に屈服していったのが日本の生活文化史ではないのか。雑穀栽培が事実上消滅してしまったことはその証左のように思える。
ちなみに、照葉樹林文化の特質の一つに山上他界や山の神信仰の観念があるという。私には山岳信仰の系譜をしっかり理解したいという思いがあり、この事実は大変興味深かった。
終章のまとめは蛇足だが、それ以外は先行研究を縦横に駆使し、アジアを俯瞰して日本生活文化史を位置づけた非常に内容の濃い本。
【関連書籍】
『日本文化の形成』 宮本 常一 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2012/09/blog-post_3.html
独自の視点から、日本文化の形成に大きな役割を果たした先住民(縄文人)や海洋民、焼畑耕作、秦人などについて語る本。
日本文化が、大まかに言って縄文文化と弥生文化のハイブリッドで形成されたことはよく知られている。しかしもっと細かく見てみると、縄文文化には東部ユーラシアに由来する「ナラ林文化」と、アッサムから東南アジア、雲南に連なる「照葉樹林文化」があるという。さらに、熱帯アジア島嶼部の「南島式耨耕(どうこう)文化」が黒潮を伝って渡ってきている可能性もある。本書は、日本文化がこうした多様な出自を持つ文化が共存することで生まれたものであることを論証するものである。
そのために、著者の専門である民族学の他、民俗学、考古学や歴史学、生態学といった様々な学問分野の成果が総動員されており、特に第Ⅰ部および第Ⅱ部はそうした既存研究の集大成的なものとして書かれている。
著者は、このうちの「照葉樹林文化論」の提唱者の一人であり、本書においてもこの説明の比重が最も大きい。照葉樹林文化の特徴を一つ挙げれば、モチモチした食品への強い志向があることである。餅やチマキ、オコワといったモチモチネバネバした食品は他の文化ではあまり好まれないが、この文化では特別な場面で価値が高いものとして扱われハレの日の儀礼的食品になる。この他、味噌など大豆の発酵食品の使用、飲茶の慣行、麹を使う酒の製造、蚕の繭から絹をつくる技術、漆の使用、ドングリ類を水にさらしてアク抜きする技法、柑橘類やシソやエゴマの栽培といったものも照葉樹林文化圏に共通する特徴である。
また、著者の専門は「焼畑」であるため照葉樹林文化の中でも特に焼畑については詳しく書かれている。焼畑というと遅れた農法のように思われるけれども、東アジアの環境の中では持続可能で完成された農法であり、焼畑による雑穀栽培は早い時期に完成形に達して日本に伝播した。昭和はじめくらいまでは特に西日本の山間部において、焼畑によるアワを中心とした雑穀とイモ類の栽培は普通に見られるものだった。第Ⅲ部では、この「焼畑」の系譜が著者自身のフィールドワークに基づき丁寧に解明されている。
日本文化の基層、すなわち衣食住の基本的技術と慣習を見てみると、この照葉樹林文化によっている部分が非常に大きいという。弥生時代になって大陸から稲作文化が伝来してきても、生活の基本となる技術にはほとんど変更が加えられなかった。例えば、竪穴住居や狩猟・漁撈の技術、石器・土器・木器・骨角器などの製作、植物の採集・畑作農耕の技術などは縄文文化をそのまま引き継いだのである。稲作文化と共にやってきたものは、銅鏡や銅剣などの武器や祭器、卜骨(ぼっこつ:骨占い)や鳥霊信仰、支石墓のような新しい墓制、そして社会的・政治的統合原理というような、非常にシンボリックなもの、「剣と鏡」に象徴される支配原理こそが弥生文化の中心だった。
つまり日本文化は、照葉樹林文化によって形作られた生活基盤の上に稲作が導入され、それによって政治的に統合されて出来たものだと考えることができる。
第Ⅳ部では、この稲作文化についてアジア的視点で考察し、日本に導入された稲作がどのようなものだったかを推測し、稲作文化を再考している。それによれば、稲作の技術は早い時期に完成していたが生産性は低いもので、雑穀栽培や堅果類の採集に頼らなければ生活していけないものだった。しかし稲作自体は、たった2、3世代という短い期間で北部九州から西日本に広まっているのだという。なぜこの新参の技術が素早く広がったかというと、既に西日本には照葉樹林文化式の雑穀栽培の伝統があり、イネ科植物栽培に必要な知識が蓄積されていたからではないかと推測している。
このように、縄文文化的なものと弥生文化的なものは補完し合い、いわばいいとこ取りのような形で日本文化の形成に寄与してきた。しかし近世幕藩体制が確立してくると、山で焼畑をして雑穀栽培で暮らすようなライフスタイルは統治者の論理と合わなくなってくる。石高制=米社会が成立するためには、米以外のものを中心に据える暮らしはあってはならなかった。そこで体制側は、非稲作民の山村の集団に対して武力による大弾圧を強行した。
例えば、椎葉村では1619年に幕府が討伐の大軍を差し向け、山中男女千余人がことごとく捉えられ、140人の首がはねられた。これをみて婦女20人が自殺するなど、合わせて200人以上が死んだ。人口千人ほどの村には潰滅的打撃である。このように、米社会への参画を強要した幕府側に反抗して山村各地で一揆が起こったが、全て幕府側の勝利に終わり、しかも大量の殺戮を伴っているという。日本文化の基層に存在する照葉樹林文化は消え去ることはなかったが、そのライフスタイルはこの時期にかなりの程度矯正されてしまった。
本書の多くは著者がそれまでに発表した論文をまとめたものであるが、若干重複は多いものの構成は散漫ではなく書き下しのようなまとまりがある。著者の主張する日本文化の多重構造は、多くの物証に基づくもので説得的であり、日本文化をアジアの中において理解する上での重要な要素であると感じた。
なお終章では、多元的で多重な構造をもつ日本文化は、多様な文化を柔軟に対応する優れた特色を持っていると主張される。21世紀は多文明が協調していく社会になるはずで、その時代の諸事象に対し、日本文化は容易に適応しうる特性を有しているのだ、としている。「私が本書の結論として言いたかったのは、この事実である(p.326)」ということだが、これについては我田引水の感が否めない。
というのは、近世幕藩体制の成立の産みの苦しみだとしても、山村の非稲作民を弾圧した歴史が存在している以上、日本文化が他文化に対して寛容だという主張は成り立たないはずである。むしろ、稲作文化が照葉樹林文化などの非稲作文化を「基層」に追いやってできたのが日本文化だという見方が正確な気がする。基層に追いやられた文化は消えはしなかったが、稲作とそれを主導する支配階級の原理に屈服していったのが日本の生活文化史ではないのか。雑穀栽培が事実上消滅してしまったことはその証左のように思える。
ちなみに、照葉樹林文化の特質の一つに山上他界や山の神信仰の観念があるという。私には山岳信仰の系譜をしっかり理解したいという思いがあり、この事実は大変興味深かった。
終章のまとめは蛇足だが、それ以外は先行研究を縦横に駆使し、アジアを俯瞰して日本生活文化史を位置づけた非常に内容の濃い本。
【関連書籍】
『日本文化の形成』 宮本 常一 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2012/09/blog-post_3.html
独自の視点から、日本文化の形成に大きな役割を果たした先住民(縄文人)や海洋民、焼畑耕作、秦人などについて語る本。
2017年2月23日木曜日
『国家神道と日本人』島薗 進 著
明治維新から現在に至るまでの「国家神道」を概観する本。
国家神道とは何だったのか? 村上重良の古典的研究(『国家神道』)をはじめ、それを批判した葦津珍彦ら神道側からの反論、これまでも様々な立場からの研究が行われてきた。しかし著者によれば、それらの研究は神社神道、すなわち神社界の動向を中心に据えすぎており、皇室祭祀が十分に取り上げられていなかったという。本書は、こうした点を踏まえ、先行研究を批判しつつより広い視座に立って「国家神道とは何だったのか?」を検証していくものである。
本書第1章および第2章では、国家神道の位置づけや、それがどう捉えられて来たかを解説する。国家神道というと分かったつもりになっているものであるが、改めてそれが何かを説明するのは難しい。例えば、国家神道とは宗教だったのだろうか? その中心に神話から続く万世一系の天皇への崇敬や皇室祭祀といったものがある以上、宗教的な色彩があることは確実だが、その完成形においては国家神道は宗教とは位置づけられなかった。
明治維新では「祭政一致」が志向され、国家は宗教を全て管理し神道を国教化しようとしたが、神道は宗教勢力としては脆弱であり、仏教やキリスト教の反対によりこれは一度は頓挫した。また政教分離や信教の自由といった問題も惹起することから、「神道は宗教ではない」という整理にされてしまった。人びとは、倫理感や死生観といった「私」の領域では仏教やキリスト教を信仰しながら、国家的秩序に関わる「公」の領域では神道に従うという宗教的二重構造を生きることになった。
そうした二重構造を可能にしたのは、神社界の働きかけよりも、記念式典などの国家的行事や学校教育の力が非常に大きかった。特に「教育勅語」の影響は甚大であり、「それが国民自身によって読み上げられ、記憶され、身についた生き方となった」(本書p.39)という意味で、教育勅語は国家神道の教典的な役割を果たした。
第3章では、どうやって国家神道が形作られたか述べる。維新政府は成立当初より国家神道の創出を構想していた。そのため、数々の新たな皇室祭祀体系を考案したり、伊勢神宮を国家の神社として作りかえ、全国の神社を皇室を頂点とするヒエラルキーにまとめたりした。ではそうしたことが明治政府の急ごしらえの思いつきだったかというとそうでもなく、幕末期からの国学の興隆がそれを準備していた。
具体的には、長州藩に隣接する津和野藩の大国隆正の思想が大きく影響しているようだ。津和野藩主の亀井茲監(これみ)は大国の思想に基づき、明治維新前に神仏分離や神葬祭を行っていたが、津和野藩は長州藩の盟友として維新勢力の王政復古のプログラムに携わり、亀井の神社政策は明治政府でも踏襲されることになる。この津和野派はやがて神道行政を牛耳って祭政一致路線を選択していく。伊藤博文など非宗教路線を指向する勢力と妥協しつつも、彼らの思想は後に生みだされる「国家神道」の青写真となった。
第4章と第5章は、教育勅語以降から戦後を取り扱う。国家神道は、それを構想した人も思いも寄らなかったほど強力に発展していった。当初は国家からの強制の意味合いが強かったものが、次第に民衆側からその強化が叫ばれ出す。これを本書では「下からの国家神道」運動と呼んでいる。ところが、ここにも二重構造が存在した。というのは、小学校から続く教育過程において祭祀王としての天皇が徹底的に教え込まれ、民衆のレベルでは天皇は絶対不可侵の存在となっていたが、高等教育以上のエリートには天皇が「天皇機関説」的なものとして捉えられ、実質的には天皇の権力はほとんどなく、官僚機構が自由に操れる存在となっていた。
戦後、GHQは「神道指令」により国家神道を解体したが、天皇の存在そのものが悪いのではなく、天皇を至上としながらそれを恣意的に操作できる政府こそが問題である、との認識の下、皇室と国家の結びつきこそ弱めたものの、皇室祭祀は皇室の私的な宗教行為と整理されてほとんど存続させられた。しかし国家神道の中心に皇室祭祀がある以上、それが廃止させられなかったことは国家神道の命脈を絶つものではなかった。戦後から時間が経つにつれ、神社勢力は国家と神社の結びつきを改めて強化しようと画策し成功するようになった。例えば、建国記念の日の制定(紀元節復活運動)、伊勢神宮と皇位が不可分だと政府に認めさせること(神宮の真姿顕現運動)、そして行幸する天皇に三種の神器を伴わせること(剣璽御動座復古運動)などだ。こうなってくると、国家神道が全く解体されたとは言えなくなってくる。今でも国家神道は存続している、というのが本書における著者の大きな主張である。政府が右傾化し神道的なものが擡頭しつつある現在、本書の主張はより切実に迫ってくる。
国家神道の歴史書であると同時に、現代の社会にまで大きな影響を与え続けている国家神道の動きにも留意した、小著ながら充実した本。
【関連書籍】
『神々の明治維新—神仏分離と廃仏毀釈』安丸 良夫 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/05/blog-post_2.html
明治初年の神仏分離政策を中心とした、明治政府の神祇行政史。
「国家神道」まで繋がる明治初年の宗教的激動を、わかりやすくしかも深く学べる名著。
国家神道とは何だったのか? 村上重良の古典的研究(『国家神道』)をはじめ、それを批判した葦津珍彦ら神道側からの反論、これまでも様々な立場からの研究が行われてきた。しかし著者によれば、それらの研究は神社神道、すなわち神社界の動向を中心に据えすぎており、皇室祭祀が十分に取り上げられていなかったという。本書は、こうした点を踏まえ、先行研究を批判しつつより広い視座に立って「国家神道とは何だったのか?」を検証していくものである。
本書第1章および第2章では、国家神道の位置づけや、それがどう捉えられて来たかを解説する。国家神道というと分かったつもりになっているものであるが、改めてそれが何かを説明するのは難しい。例えば、国家神道とは宗教だったのだろうか? その中心に神話から続く万世一系の天皇への崇敬や皇室祭祀といったものがある以上、宗教的な色彩があることは確実だが、その完成形においては国家神道は宗教とは位置づけられなかった。
明治維新では「祭政一致」が志向され、国家は宗教を全て管理し神道を国教化しようとしたが、神道は宗教勢力としては脆弱であり、仏教やキリスト教の反対によりこれは一度は頓挫した。また政教分離や信教の自由といった問題も惹起することから、「神道は宗教ではない」という整理にされてしまった。人びとは、倫理感や死生観といった「私」の領域では仏教やキリスト教を信仰しながら、国家的秩序に関わる「公」の領域では神道に従うという宗教的二重構造を生きることになった。
そうした二重構造を可能にしたのは、神社界の働きかけよりも、記念式典などの国家的行事や学校教育の力が非常に大きかった。特に「教育勅語」の影響は甚大であり、「それが国民自身によって読み上げられ、記憶され、身についた生き方となった」(本書p.39)という意味で、教育勅語は国家神道の教典的な役割を果たした。
第3章では、どうやって国家神道が形作られたか述べる。維新政府は成立当初より国家神道の創出を構想していた。そのため、数々の新たな皇室祭祀体系を考案したり、伊勢神宮を国家の神社として作りかえ、全国の神社を皇室を頂点とするヒエラルキーにまとめたりした。ではそうしたことが明治政府の急ごしらえの思いつきだったかというとそうでもなく、幕末期からの国学の興隆がそれを準備していた。
具体的には、長州藩に隣接する津和野藩の大国隆正の思想が大きく影響しているようだ。津和野藩主の亀井茲監(これみ)は大国の思想に基づき、明治維新前に神仏分離や神葬祭を行っていたが、津和野藩は長州藩の盟友として維新勢力の王政復古のプログラムに携わり、亀井の神社政策は明治政府でも踏襲されることになる。この津和野派はやがて神道行政を牛耳って祭政一致路線を選択していく。伊藤博文など非宗教路線を指向する勢力と妥協しつつも、彼らの思想は後に生みだされる「国家神道」の青写真となった。
第4章と第5章は、教育勅語以降から戦後を取り扱う。国家神道は、それを構想した人も思いも寄らなかったほど強力に発展していった。当初は国家からの強制の意味合いが強かったものが、次第に民衆側からその強化が叫ばれ出す。これを本書では「下からの国家神道」運動と呼んでいる。ところが、ここにも二重構造が存在した。というのは、小学校から続く教育過程において祭祀王としての天皇が徹底的に教え込まれ、民衆のレベルでは天皇は絶対不可侵の存在となっていたが、高等教育以上のエリートには天皇が「天皇機関説」的なものとして捉えられ、実質的には天皇の権力はほとんどなく、官僚機構が自由に操れる存在となっていた。
戦後、GHQは「神道指令」により国家神道を解体したが、天皇の存在そのものが悪いのではなく、天皇を至上としながらそれを恣意的に操作できる政府こそが問題である、との認識の下、皇室と国家の結びつきこそ弱めたものの、皇室祭祀は皇室の私的な宗教行為と整理されてほとんど存続させられた。しかし国家神道の中心に皇室祭祀がある以上、それが廃止させられなかったことは国家神道の命脈を絶つものではなかった。戦後から時間が経つにつれ、神社勢力は国家と神社の結びつきを改めて強化しようと画策し成功するようになった。例えば、建国記念の日の制定(紀元節復活運動)、伊勢神宮と皇位が不可分だと政府に認めさせること(神宮の真姿顕現運動)、そして行幸する天皇に三種の神器を伴わせること(剣璽御動座復古運動)などだ。こうなってくると、国家神道が全く解体されたとは言えなくなってくる。今でも国家神道は存続している、というのが本書における著者の大きな主張である。政府が右傾化し神道的なものが擡頭しつつある現在、本書の主張はより切実に迫ってくる。
国家神道の歴史書であると同時に、現代の社会にまで大きな影響を与え続けている国家神道の動きにも留意した、小著ながら充実した本。
【関連書籍】
『神々の明治維新—神仏分離と廃仏毀釈』安丸 良夫 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/05/blog-post_2.html
明治初年の神仏分離政策を中心とした、明治政府の神祇行政史。
「国家神道」まで繋がる明治初年の宗教的激動を、わかりやすくしかも深く学べる名著。
2017年2月15日水曜日
『神都物語:伊勢神宮の近現代史』ジョン・ブリーン著
現在の伊勢神宮がどうやって形作られたのかを説明する本。
伊勢神宮というと、天皇家の神話的祖先である天照大神を祀る天皇の神社であり、国家的性格を持つ神社でもある。しかしこうした伊勢神宮の在り方は、伝統的なものとは全く違う。これは明治維新後につくられたものだ。例えば、明治になるまで天皇は伊勢神宮を参拝したことがなかった。
江戸時代において、天皇と伊勢神宮が全く関係なかったかというとそうではない。遷宮の諸儀礼の日取りの宣下、幣史の派遣など、特別な関係にあったことは間違いない。しかし天皇家の宗廟として祀られていたわけではなかった。庶民のレベルにおいても、天照大神を祀る内宮(ないくう)はさほど注目されず、豊受大神を祀る外宮(げくう)の方が参拝客がずっと多かった。
これが劇的に変貌を遂げるのが明治になってからである。明治維新は、王政復古、すなわち天皇が治めていた古代王朝のリバイバルを己のレジティマシー(正統性)の旗印にした。このため、神社政策は国家統一の重要な1ピースであった。徐々に改められて政策自体は世俗的になっていくものの、最初は「神祇官」が置かれ文字通り祭政一致の体制が取られたほどだった。
こうした趨勢の下、伊勢神宮は国家的神社としてまるきり作りかえられる。まず天皇との特別な関係が樹立され、天皇が参拝する神社となった。それを主導したのは、岩倉具視や木戸孝允、そして神社政策を委託されていた津和野藩の亀井茲監(これみ)と福羽美静(ふくば・びせい)らだそうである。そして、自治的・世襲的に運営されていた伊勢神宮は国家の管理化に置かれ、人事が国家政策となり、「浄化」されていった。
具体的には、まず廃仏毀釈が行われ、伊勢から仏教勢力が一掃された。そして神宮大麻(お札)の頒布を担っていた御師(おんし)と呼ばれる世襲職をはじめ神宮の世襲役職が全て廃止され、宮司も中央からの任命になり、祭主も皇族が務めるようになった。また伊勢の街自体が「神都」として作りかえられ、猥雑な妓楼街は主要道路から遠ざけられ、自然消滅させられていった。さらに、天皇との特別な関係の樹立のために、今に続く数々の儀礼が定められ(『神宮明治祭式』)、新しい神道理論も確立していった。この際に26の明治以前の儀礼が廃止され、新しい儀礼が21も取り入れられたという。伊勢神宮は、こうして明治以前のそれとは全く違う神社になっていったのだ。なお、こうした改革を主導したのは、内宮の神職だった浦田長民(ちょうみん)という人物である。
しかしこうした改革は、伊勢神宮がこれまで数百年に渡って培ってきた地域社会や全国の信者との関係性にも大きく変更を迫るものでもあった。交通の改善や伊勢の観光地化、旅館による広報といった数々の策が打たれたが、こうした改革のために参拝者は明治以前よりもむしろ減少してしまった。つまり神宮には矢継ぎ早の改革が行われたが、伊勢という街を見た時には明治初期は停滞の時期であった。
1929年の式年遷宮がこうした停滞を打ち破る画期となる。式年遷宮の当日に、総理大臣はじめ多くの国務大臣など国家の要人だけでなく、軍までも参加した。そして遷宮当日は休日に指定され、文部省は全国の小学校に奉賀式を執り行うよう指示した。文字通り国家儀礼として式年遷宮を行ったのである。こうなるとメディアでも伊勢神宮が多く取り上げられるようになり、国民の間に国家の神社としての認識が浸透してくる。また、小学校では「一生に一度は神宮に参拝した方がいい」と教えられはじめ、遂には「参拝しなくてはならない」に変更された。これを受けて修学旅行での伊勢神宮参拝が広まり、参拝客はどんどん増加していった。特に1935年の「国体明徴声明」(天皇を立憲君主ではなく時空を超越した聖なる君主として位置づける声明)以後はこれに拍車がかかった。開戦により伊勢神宮自体の整備は停滞したが、1941年の参拝客は年間400万人に達し、また神宮大麻の頒布数も1945年には当時の世帯数とほぼ同じ1400万体にも登っている。ただしこの頃、参拝客はまだ内宮ではなく外宮を中心に参拝していた。
戦後、「国家神道」の中心であった伊勢神宮はGHQにより存続の危機に立たされた。天皇の宗廟として細々と存続するのか、それとも単なる神社となるかを迫られた。伊勢神宮側は、当初は天皇の宗廟となる意向であったが、それだと予算的にも限られ宗教活動も制限されるということで、私的宗教法人となる道を選んだ。
しかし伊勢神宮は、単なる神社にはならなかった。GHQの目が光っているうちは表立った活動は控えていたが、徐々に天皇家との特別な関係も復活させていった。さらに、国家的な神社としての性格も獲得していった。本書の用語ではそれを「脱宗教法人化」という。その象徴となったのが1959年の正月、岸信介が総理大臣として参拝した時であった。戦後にも私的に参拝した総理はいた(鳩山一郎、石橋湛山)。しかし岸は、非公式参拝としていたにもかかわらず、随行者60人以上を連ねて明らかに公的行事として参拝を行ったのである。これに続き、池田勇人は神宮にある「八咫(やた)の鏡」が神話に基づくものであり、公的なものであるという答弁書を決定した。こうして、戦後日本でも神話が公認されて、天皇の神的性格は確認されたのである。天照大神は、国家に公認された神になった。
こうして、交通(バイパス)整備という事情もあって、戦後にはついに内宮への参拝者が外宮へのそれを上回るようになった。一度「単なる神社」になりかけた伊勢神宮は、また戦前と同じように国家と皇室の神社として国民に認識されるようになった。2013年、安倍総理大臣は戦後の首相として初めて式年遷宮に参列した。伊勢の式年遷宮は、またしても国家儀礼になりかけている。
伊勢神宮というと、古代より続く伝統の牙城のように思われている。しかしそれは事実とは全く異なる。むしろ国家が民衆支配の道具として創り出した伝統の方が多い。ただし、伊勢神宮は国家に翻弄された存在というわけでもない。積極的に国家と関わり、自らの権威を高めるように働きかけたのも伊勢神宮だった。
本書を読む上での私の興味は、なぜ伊勢神宮だけがこのような特別な存在になれたのかということだった。靖国神社や明治神宮ならば、最初から国家が創ったものだから分かる。しかし伊勢神宮は、最初から国家の神社だったわけではないし、そうならない道もあったように思われる。だが伊勢神宮は国家の神社となった。なぜなのだろうか。その答えは本書にはない。ただ、それは明治政府の誰か偉い人が決めたというより、地元伊勢の人を含めて多くの人の思惑が絡み合っていることだけは確かだ。
その大勢の中の一人に、薩摩出身の田中頼庸(よりつね)という人がいる。田中は明治時代に神宮の大宮司となり、浦田長民と対立しながらも神宮の改革を手がけた上、神社の宗教活動が禁止されると(神道は宗教でないということになり政教分離に抵触しないとされた)神宮を飛び出して「神宮教」という宗教を立ち上げて神宮大麻の配布などを行った異色の人物である。本書は田中の事績を辿るものではないからその全貌はわからなかったが、この人物もより掘り下げて知りたいと思った。
近代に成立した国家の神社としての伊勢神宮の姿に迫る、コンパクトながら内容の濃い歴史書。
伊勢神宮というと、天皇家の神話的祖先である天照大神を祀る天皇の神社であり、国家的性格を持つ神社でもある。しかしこうした伊勢神宮の在り方は、伝統的なものとは全く違う。これは明治維新後につくられたものだ。例えば、明治になるまで天皇は伊勢神宮を参拝したことがなかった。
江戸時代において、天皇と伊勢神宮が全く関係なかったかというとそうではない。遷宮の諸儀礼の日取りの宣下、幣史の派遣など、特別な関係にあったことは間違いない。しかし天皇家の宗廟として祀られていたわけではなかった。庶民のレベルにおいても、天照大神を祀る内宮(ないくう)はさほど注目されず、豊受大神を祀る外宮(げくう)の方が参拝客がずっと多かった。
これが劇的に変貌を遂げるのが明治になってからである。明治維新は、王政復古、すなわち天皇が治めていた古代王朝のリバイバルを己のレジティマシー(正統性)の旗印にした。このため、神社政策は国家統一の重要な1ピースであった。徐々に改められて政策自体は世俗的になっていくものの、最初は「神祇官」が置かれ文字通り祭政一致の体制が取られたほどだった。
こうした趨勢の下、伊勢神宮は国家的神社としてまるきり作りかえられる。まず天皇との特別な関係が樹立され、天皇が参拝する神社となった。それを主導したのは、岩倉具視や木戸孝允、そして神社政策を委託されていた津和野藩の亀井茲監(これみ)と福羽美静(ふくば・びせい)らだそうである。そして、自治的・世襲的に運営されていた伊勢神宮は国家の管理化に置かれ、人事が国家政策となり、「浄化」されていった。
具体的には、まず廃仏毀釈が行われ、伊勢から仏教勢力が一掃された。そして神宮大麻(お札)の頒布を担っていた御師(おんし)と呼ばれる世襲職をはじめ神宮の世襲役職が全て廃止され、宮司も中央からの任命になり、祭主も皇族が務めるようになった。また伊勢の街自体が「神都」として作りかえられ、猥雑な妓楼街は主要道路から遠ざけられ、自然消滅させられていった。さらに、天皇との特別な関係の樹立のために、今に続く数々の儀礼が定められ(『神宮明治祭式』)、新しい神道理論も確立していった。この際に26の明治以前の儀礼が廃止され、新しい儀礼が21も取り入れられたという。伊勢神宮は、こうして明治以前のそれとは全く違う神社になっていったのだ。なお、こうした改革を主導したのは、内宮の神職だった浦田長民(ちょうみん)という人物である。
しかしこうした改革は、伊勢神宮がこれまで数百年に渡って培ってきた地域社会や全国の信者との関係性にも大きく変更を迫るものでもあった。交通の改善や伊勢の観光地化、旅館による広報といった数々の策が打たれたが、こうした改革のために参拝者は明治以前よりもむしろ減少してしまった。つまり神宮には矢継ぎ早の改革が行われたが、伊勢という街を見た時には明治初期は停滞の時期であった。
1929年の式年遷宮がこうした停滞を打ち破る画期となる。式年遷宮の当日に、総理大臣はじめ多くの国務大臣など国家の要人だけでなく、軍までも参加した。そして遷宮当日は休日に指定され、文部省は全国の小学校に奉賀式を執り行うよう指示した。文字通り国家儀礼として式年遷宮を行ったのである。こうなるとメディアでも伊勢神宮が多く取り上げられるようになり、国民の間に国家の神社としての認識が浸透してくる。また、小学校では「一生に一度は神宮に参拝した方がいい」と教えられはじめ、遂には「参拝しなくてはならない」に変更された。これを受けて修学旅行での伊勢神宮参拝が広まり、参拝客はどんどん増加していった。特に1935年の「国体明徴声明」(天皇を立憲君主ではなく時空を超越した聖なる君主として位置づける声明)以後はこれに拍車がかかった。開戦により伊勢神宮自体の整備は停滞したが、1941年の参拝客は年間400万人に達し、また神宮大麻の頒布数も1945年には当時の世帯数とほぼ同じ1400万体にも登っている。ただしこの頃、参拝客はまだ内宮ではなく外宮を中心に参拝していた。
戦後、「国家神道」の中心であった伊勢神宮はGHQにより存続の危機に立たされた。天皇の宗廟として細々と存続するのか、それとも単なる神社となるかを迫られた。伊勢神宮側は、当初は天皇の宗廟となる意向であったが、それだと予算的にも限られ宗教活動も制限されるということで、私的宗教法人となる道を選んだ。
しかし伊勢神宮は、単なる神社にはならなかった。GHQの目が光っているうちは表立った活動は控えていたが、徐々に天皇家との特別な関係も復活させていった。さらに、国家的な神社としての性格も獲得していった。本書の用語ではそれを「脱宗教法人化」という。その象徴となったのが1959年の正月、岸信介が総理大臣として参拝した時であった。戦後にも私的に参拝した総理はいた(鳩山一郎、石橋湛山)。しかし岸は、非公式参拝としていたにもかかわらず、随行者60人以上を連ねて明らかに公的行事として参拝を行ったのである。これに続き、池田勇人は神宮にある「八咫(やた)の鏡」が神話に基づくものであり、公的なものであるという答弁書を決定した。こうして、戦後日本でも神話が公認されて、天皇の神的性格は確認されたのである。天照大神は、国家に公認された神になった。
こうして、交通(バイパス)整備という事情もあって、戦後にはついに内宮への参拝者が外宮へのそれを上回るようになった。一度「単なる神社」になりかけた伊勢神宮は、また戦前と同じように国家と皇室の神社として国民に認識されるようになった。2013年、安倍総理大臣は戦後の首相として初めて式年遷宮に参列した。伊勢の式年遷宮は、またしても国家儀礼になりかけている。
伊勢神宮というと、古代より続く伝統の牙城のように思われている。しかしそれは事実とは全く異なる。むしろ国家が民衆支配の道具として創り出した伝統の方が多い。ただし、伊勢神宮は国家に翻弄された存在というわけでもない。積極的に国家と関わり、自らの権威を高めるように働きかけたのも伊勢神宮だった。
本書を読む上での私の興味は、なぜ伊勢神宮だけがこのような特別な存在になれたのかということだった。靖国神社や明治神宮ならば、最初から国家が創ったものだから分かる。しかし伊勢神宮は、最初から国家の神社だったわけではないし、そうならない道もあったように思われる。だが伊勢神宮は国家の神社となった。なぜなのだろうか。その答えは本書にはない。ただ、それは明治政府の誰か偉い人が決めたというより、地元伊勢の人を含めて多くの人の思惑が絡み合っていることだけは確かだ。
その大勢の中の一人に、薩摩出身の田中頼庸(よりつね)という人がいる。田中は明治時代に神宮の大宮司となり、浦田長民と対立しながらも神宮の改革を手がけた上、神社の宗教活動が禁止されると(神道は宗教でないということになり政教分離に抵触しないとされた)神宮を飛び出して「神宮教」という宗教を立ち上げて神宮大麻の配布などを行った異色の人物である。本書は田中の事績を辿るものではないからその全貌はわからなかったが、この人物もより掘り下げて知りたいと思った。
近代に成立した国家の神社としての伊勢神宮の姿に迫る、コンパクトながら内容の濃い歴史書。
2017年2月12日日曜日
『東シナ海文化圏の民俗—地域研究から比較民俗学へ』下野敏見 著
東シナ海に共通してはいるが様々な地域的変異がある民俗を取り上げ、その伝播や起源を考える論文集。
著者は鹿児島を代表する民俗学者の下野敏見氏。本書は、著者が『隼人文化』と『鹿児島民俗』に提出した論文を中心に、「東シナ海文化圏」にまつわる論文をまとめたもので、「第一章で身近な地域からだんだんひろがった地域の比較をなし、第二章でさらにひろげて近隣の国の資料もとり入れ、第三章では隣国の現地にどっぷりつかって調べあげた資料をもとに、日本の民族を省みて比較するという構成」(あとがきより)である。
個人的に興味を持って読んだのは、「鬼火焚き・門松の意味するもの」(第1章第1節)、「南日本の石神信仰—立神と陰陽石と三ツ石」(第1章第3節)、「南からみたハレ・ケガレ論—エビスと水死体」(第2章第2節)、「十五夜綱引の源流—門ノ浦のヨコビキに寄せて」(第2章第3節)の4編。
著者はこうした材料で「東シナ海文化圏」を構想する。そもそも、民俗学は比較の学である。民俗文化はただその地域の伝統を見ているだけでは見えてこない。隣村とはどう違いがあるか、また隣の地域とはどう違うか、そして隣の国とはどう違うのか、ということを次第に視野を広げてみることで、その民俗伝承の持つ意味が明確になってくる。例えば、綱引き一つとっても、小正月に綱引きをする地域と十五夜に綱引きをする地域がある。だからそれらがどう分布しているかを調べれば、伝達の経路や時期が分かったり、その伝統がどこで生まれたかが分かってくる。
いろいろな民俗現象で著者はそれを考え、文化伝播について調べていく。日本の文化伝播は基本的には畿内を中心とした同心円状になっており、畿内で生まれた文化が次第に広がっていったものが多い。となると、南九州などは日本の端っこなわけだから、最も後進的な地域となってしまう。だが、さらに視野を広げてみれば、違った文化伝播の同心円が見えてくる。それが下の図である(序章より)。
これを見ると、南西諸島、台湾、中国南部沿岸、朝鮮半島南部、そして九州が同じ同心円の中に収まっている。つまり文化は決して畿内中心ばかりではなく、いわば海を中心とした文化伝播も起こっていたわけだ。この、海を中心とした文化伝播によって形作られた地域が「東シナ海文化圏」である。
とはいえ、この図で言われていることがどれほど妥当なのかは、本書だけでは判断することができない。もう少し材料が必要だし、衣食住全般にわたった比較が必要になるだろう。ただし、本書に取り上げられた民俗についていえば、かなりの程度こうした文化圏の存在は肯定できる。
書き下ろしではないので論文ごとの粗密はあるが、郷土研究から出発しより広い視野に誘ってくれる好著。
著者は鹿児島を代表する民俗学者の下野敏見氏。本書は、著者が『隼人文化』と『鹿児島民俗』に提出した論文を中心に、「東シナ海文化圏」にまつわる論文をまとめたもので、「第一章で身近な地域からだんだんひろがった地域の比較をなし、第二章でさらにひろげて近隣の国の資料もとり入れ、第三章では隣国の現地にどっぷりつかって調べあげた資料をもとに、日本の民族を省みて比較するという構成」(あとがきより)である。
個人的に興味を持って読んだのは、「鬼火焚き・門松の意味するもの」(第1章第1節)、「南日本の石神信仰—立神と陰陽石と三ツ石」(第1章第3節)、「南からみたハレ・ケガレ論—エビスと水死体」(第2章第2節)、「十五夜綱引の源流—門ノ浦のヨコビキに寄せて」(第2章第3節)の4編。
著者はこうした材料で「東シナ海文化圏」を構想する。そもそも、民俗学は比較の学である。民俗文化はただその地域の伝統を見ているだけでは見えてこない。隣村とはどう違いがあるか、また隣の地域とはどう違うか、そして隣の国とはどう違うのか、ということを次第に視野を広げてみることで、その民俗伝承の持つ意味が明確になってくる。例えば、綱引き一つとっても、小正月に綱引きをする地域と十五夜に綱引きをする地域がある。だからそれらがどう分布しているかを調べれば、伝達の経路や時期が分かったり、その伝統がどこで生まれたかが分かってくる。
いろいろな民俗現象で著者はそれを考え、文化伝播について調べていく。日本の文化伝播は基本的には畿内を中心とした同心円状になっており、畿内で生まれた文化が次第に広がっていったものが多い。となると、南九州などは日本の端っこなわけだから、最も後進的な地域となってしまう。だが、さらに視野を広げてみれば、違った文化伝播の同心円が見えてくる。それが下の図である(序章より)。
これを見ると、南西諸島、台湾、中国南部沿岸、朝鮮半島南部、そして九州が同じ同心円の中に収まっている。つまり文化は決して畿内中心ばかりではなく、いわば海を中心とした文化伝播も起こっていたわけだ。この、海を中心とした文化伝播によって形作られた地域が「東シナ海文化圏」である。
とはいえ、この図で言われていることがどれほど妥当なのかは、本書だけでは判断することができない。もう少し材料が必要だし、衣食住全般にわたった比較が必要になるだろう。ただし、本書に取り上げられた民俗についていえば、かなりの程度こうした文化圏の存在は肯定できる。
書き下ろしではないので論文ごとの粗密はあるが、郷土研究から出発しより広い視野に誘ってくれる好著。
2017年1月30日月曜日
『バナナと日本人―フィリピン農園と食卓のあいだ』鶴見 良行 著
日本人のバナナ需要に応えるため、フィリピンのバナナ・プランテーションがいかにして成立し、またそこで労働者がいかに苦しんでいるかを告発した本。
フィリピンのバナナ産業は、国際資本4社に完全に支配されている。すなわち、デルモンテ、キャッスル&クック(ドール)、ユナイテッド・ブランズ(チキータ)、住友商事(バナンボ)の4社である(括弧内はブランド名)。住友を除く3社は米国資本であり、この3社でバナナの作付面積のほぼ8割を支配している。フィリピンのバナナ産業は、フィリピンが作ったものというよりは、米国資本が作ったものだ。しかしその背景には、日本人にも大きな関わりがある。
フィリピンのバナナ産業の原型は、戦前日本人が作った「ダバオ麻農園」まで遡る。フィリピンには戦前多くの日本人が入植して「アバカ麻」という植物を育てる農園を経営していた。アバカ麻とは、麻と名はついているがバナナと似た植物で、水に強いことから船に使うロープなどの原料となった。戦争のため海軍がどんどん増強されていった時代であり、アバカ麻は飛ぶように売れた。日本人たちは半ばイカサマのような方法でフィリピンの土着の人から土地を奪って開墾を進め、アバカ農園をミンダナオ島のダバオというところに作ったのである。
日本の敗戦でこの農園は雲散霧消してしまうが、これが戦後のバナナ農園の原型を準備した。
日本が戦争の痛手を克服し高度経済成長期を迎えると、日本のバナナ需要が急激に高まってきた。60年代の話である。1950年には6600トンだったバナナの輸入は、ピークの1972年には106万2900トンになり、実に160倍もの伸びを見せている。バナナはいくらでも売れる商品だった。これに目をつけたのが米国資本の商社である。
フィリピンは米国にとって植民地だったから、強力な権益を持っていた。日本も米国にとって戦後そうした位置づけにあったとも言えるが、米国がフィリピンに対して行ったこと日本に対するそれは随分違う。例えば、日本では農地解放(地主層の解体)をやったがフィリピンではやらなかった。地主の問題は同様に存在していたのにだ。
むしろ、米国商社はフィリピンの地主層と結託して大規模農園を作った。もともと、米国はスペイン統治時代にできた大地主制のプランテーションでフィリピン人が苦しんでいることを知っていたから、1903年には公有地法を定めて法人・個人の土地所有をそれぞれ1024ha、24haに制限していた。しかし米国資本商社にとってはこの制限は障害となる。この法の制限を、あの手この手でかいくぐってバナナ・プランテーションが発達していく。
例えばデルモンテが使った方法は奇抜なものだ。デルモンテは米国海軍に働きかけて、バナナ農園適地の高原を海軍基地(!)として指定させた。そして海軍からその土地を借りるという手段で8000haもの農園を手に入れるのである。1934年にフィリピンが独立するとその土地はフィリピンに返還されたが、デルモンテは超法規的な国有企業の「国立開発公社」をフィリピンに設立させ、今度はその公社から土地を借りるという形をとった。この8000haもの土地に対し、1937年から1956年までの18年間に同社が払った地代はわずか4100ドルである。詐欺的な手段によって、米国資本の商社はフィリピン人から土地を奪っていったのである。
そして土地を奪われたフィリピンの人びとには、バナナ農園で働くという選択しか残っていなかった。
形式的には、契約栽培など地場の農園が自主的に商社と取引するという形が取られたが、実質的にはフィリピンの農民に選択肢はなかった。作付計画から農薬散布、出荷検品にいたるまで、全て商社のいいなりだったからだ。生産性を向上させて、所得を上げようということすら難しかった。なぜなら、形の上ではバナナは全量買取りだったが、商社は相場を調整するために、検品の厳しさを自由自在に変えて買取量を上下させていたからだ。酷いときには、集荷されたバナナの半分が廃棄された。これでは頑張って収量を上げても意味がなかった。
そもそも、バナナ栽培は農民に全く利益が出ないように作られていた。栽培指導、農薬代、生産資材代、手数料…としてバナナの売り上げはどんどん天引きされ、手元に残るのは売り上げの1割ほどしかなかった。当然そんな薄利では生活できようはずもない。農民は、商社の下請けから借金をして生活をせざるを得なかった。こうなると、返すアテのない借金のために、商社の農奴になるのと同じことだった。農民に出来るのは、夜逃げくらいしかなかったが、そうしたとしても、港湾のスラムでのバナナ積み込みの荷役が待っていた。バナナ農園で働くよりももっと厳しい仕事である。
フィリピンのバナナ産業は、まさに「生かさず殺さず」のシステムである。儲けるのは、商社だけになるように巧妙に設計され、そのシステムから逃げることもできないように仕組まれていた。それというのも全ては、日本人のバナナの需要があったからのことだ。
日本のバナナ輸入の業者は、急激に伸びるバナナ需要を前にして、商社に強気の契約を持ちかけた。前もって定めた価格で、全量買い取るという契約である。バナナはいくらでも売れる、と思っていたのだ。だが実際は、日本人がバナナばかりを際限なく食べ続けるなんてことはあるわけがなかった。1972年をピークに消費は漸減していく。それでも全量買取の縛りがあったので日本の輸入業者はバナナを商社のいいなりに輸入せざるを得ない。バナナは「3年に1度当たればいい」というバクチ的商品になっていた。
しかし、結局日本の輸入業者はバナナのバクチには負けてしまう。このバナナ貿易は巨額の赤字を計上して契約を終えた(以後、買取制ではなく入札制に変わる)。ここでも儲けたのは、国際資本の商社だけだったのである。
そしてフィリピンのバナナ産業には、あくどい仕掛けもあった。バナナには、先進国では使用が禁止されているような毒性の強い農薬が大量に使われていたのだ。米国企業は、自国では販売が禁止されている農薬をフィリピンに輸出して使わせていたのである。先進国では厳しい環境基準を守っているように見せかけながら、「植民地」では現地の人の健康被害にも、環境汚染にも全く気にも留めなかった。このために、バナナ農園には体を壊した人がたくさんいるらしい。
こうして、日本人のバナナ需要をアテにしてつくられたフィリピンのバナナ産業は、フィリピンの人びとと環境を搾取し、自生的な成長の機会を奪ってしまった。貧しい人がもっと貧しく、富める人がもっと富むメカニズムが固定化され、フィリピンの農民はどんどん没落していった。自給自足的でのどかな世界に生きていた土着の人びとは、いきなり生き馬の目を抜く国際競争の世界に投げ出され、なすすべなく溺れていったのである。
この悲惨な自体に対し、我々日本人は全くの無罪ではありえない。何しろ、安いバナナを輸入しているのは、他ならぬ我々だからである。一番悪いのは商社なのは間違いないが、我々には、少なくとも道義的責任があるだろう。すなわち、もう少しマシなやり方はできないのか? と問いかける責任はある、と私は思う。
綿密な調査から、国際資本の商社がいかにしてフィリピン人を合法的に搾取する体制を作ったかを克明に記録した名著。
★Amazonページ
https://amzn.to/3Oq5cwj
フィリピンのバナナ産業は、国際資本4社に完全に支配されている。すなわち、デルモンテ、キャッスル&クック(ドール)、ユナイテッド・ブランズ(チキータ)、住友商事(バナンボ)の4社である(括弧内はブランド名)。住友を除く3社は米国資本であり、この3社でバナナの作付面積のほぼ8割を支配している。フィリピンのバナナ産業は、フィリピンが作ったものというよりは、米国資本が作ったものだ。しかしその背景には、日本人にも大きな関わりがある。
フィリピンのバナナ産業の原型は、戦前日本人が作った「ダバオ麻農園」まで遡る。フィリピンには戦前多くの日本人が入植して「アバカ麻」という植物を育てる農園を経営していた。アバカ麻とは、麻と名はついているがバナナと似た植物で、水に強いことから船に使うロープなどの原料となった。戦争のため海軍がどんどん増強されていった時代であり、アバカ麻は飛ぶように売れた。日本人たちは半ばイカサマのような方法でフィリピンの土着の人から土地を奪って開墾を進め、アバカ農園をミンダナオ島のダバオというところに作ったのである。
日本の敗戦でこの農園は雲散霧消してしまうが、これが戦後のバナナ農園の原型を準備した。
日本が戦争の痛手を克服し高度経済成長期を迎えると、日本のバナナ需要が急激に高まってきた。60年代の話である。1950年には6600トンだったバナナの輸入は、ピークの1972年には106万2900トンになり、実に160倍もの伸びを見せている。バナナはいくらでも売れる商品だった。これに目をつけたのが米国資本の商社である。
フィリピンは米国にとって植民地だったから、強力な権益を持っていた。日本も米国にとって戦後そうした位置づけにあったとも言えるが、米国がフィリピンに対して行ったこと日本に対するそれは随分違う。例えば、日本では農地解放(地主層の解体)をやったがフィリピンではやらなかった。地主の問題は同様に存在していたのにだ。
むしろ、米国商社はフィリピンの地主層と結託して大規模農園を作った。もともと、米国はスペイン統治時代にできた大地主制のプランテーションでフィリピン人が苦しんでいることを知っていたから、1903年には公有地法を定めて法人・個人の土地所有をそれぞれ1024ha、24haに制限していた。しかし米国資本商社にとってはこの制限は障害となる。この法の制限を、あの手この手でかいくぐってバナナ・プランテーションが発達していく。
例えばデルモンテが使った方法は奇抜なものだ。デルモンテは米国海軍に働きかけて、バナナ農園適地の高原を海軍基地(!)として指定させた。そして海軍からその土地を借りるという手段で8000haもの農園を手に入れるのである。1934年にフィリピンが独立するとその土地はフィリピンに返還されたが、デルモンテは超法規的な国有企業の「国立開発公社」をフィリピンに設立させ、今度はその公社から土地を借りるという形をとった。この8000haもの土地に対し、1937年から1956年までの18年間に同社が払った地代はわずか4100ドルである。詐欺的な手段によって、米国資本の商社はフィリピン人から土地を奪っていったのである。
そして土地を奪われたフィリピンの人びとには、バナナ農園で働くという選択しか残っていなかった。
形式的には、契約栽培など地場の農園が自主的に商社と取引するという形が取られたが、実質的にはフィリピンの農民に選択肢はなかった。作付計画から農薬散布、出荷検品にいたるまで、全て商社のいいなりだったからだ。生産性を向上させて、所得を上げようということすら難しかった。なぜなら、形の上ではバナナは全量買取りだったが、商社は相場を調整するために、検品の厳しさを自由自在に変えて買取量を上下させていたからだ。酷いときには、集荷されたバナナの半分が廃棄された。これでは頑張って収量を上げても意味がなかった。
そもそも、バナナ栽培は農民に全く利益が出ないように作られていた。栽培指導、農薬代、生産資材代、手数料…としてバナナの売り上げはどんどん天引きされ、手元に残るのは売り上げの1割ほどしかなかった。当然そんな薄利では生活できようはずもない。農民は、商社の下請けから借金をして生活をせざるを得なかった。こうなると、返すアテのない借金のために、商社の農奴になるのと同じことだった。農民に出来るのは、夜逃げくらいしかなかったが、そうしたとしても、港湾のスラムでのバナナ積み込みの荷役が待っていた。バナナ農園で働くよりももっと厳しい仕事である。
フィリピンのバナナ産業は、まさに「生かさず殺さず」のシステムである。儲けるのは、商社だけになるように巧妙に設計され、そのシステムから逃げることもできないように仕組まれていた。それというのも全ては、日本人のバナナの需要があったからのことだ。
日本のバナナ輸入の業者は、急激に伸びるバナナ需要を前にして、商社に強気の契約を持ちかけた。前もって定めた価格で、全量買い取るという契約である。バナナはいくらでも売れる、と思っていたのだ。だが実際は、日本人がバナナばかりを際限なく食べ続けるなんてことはあるわけがなかった。1972年をピークに消費は漸減していく。それでも全量買取の縛りがあったので日本の輸入業者はバナナを商社のいいなりに輸入せざるを得ない。バナナは「3年に1度当たればいい」というバクチ的商品になっていた。
しかし、結局日本の輸入業者はバナナのバクチには負けてしまう。このバナナ貿易は巨額の赤字を計上して契約を終えた(以後、買取制ではなく入札制に変わる)。ここでも儲けたのは、国際資本の商社だけだったのである。
そしてフィリピンのバナナ産業には、あくどい仕掛けもあった。バナナには、先進国では使用が禁止されているような毒性の強い農薬が大量に使われていたのだ。米国企業は、自国では販売が禁止されている農薬をフィリピンに輸出して使わせていたのである。先進国では厳しい環境基準を守っているように見せかけながら、「植民地」では現地の人の健康被害にも、環境汚染にも全く気にも留めなかった。このために、バナナ農園には体を壊した人がたくさんいるらしい。
こうして、日本人のバナナ需要をアテにしてつくられたフィリピンのバナナ産業は、フィリピンの人びとと環境を搾取し、自生的な成長の機会を奪ってしまった。貧しい人がもっと貧しく、富める人がもっと富むメカニズムが固定化され、フィリピンの農民はどんどん没落していった。自給自足的でのどかな世界に生きていた土着の人びとは、いきなり生き馬の目を抜く国際競争の世界に投げ出され、なすすべなく溺れていったのである。
この悲惨な自体に対し、我々日本人は全くの無罪ではありえない。何しろ、安いバナナを輸入しているのは、他ならぬ我々だからである。一番悪いのは商社なのは間違いないが、我々には、少なくとも道義的責任があるだろう。すなわち、もう少しマシなやり方はできないのか? と問いかける責任はある、と私は思う。
綿密な調査から、国際資本の商社がいかにしてフィリピン人を合法的に搾取する体制を作ったかを克明に記録した名著。
★Amazonページ
https://amzn.to/3Oq5cwj
2017年1月20日金曜日
『食事の文明論』石毛直道 著
世界各国の食事の在り方が、近代文明の影響によってどのように変容してきたかを語る本。
著者は文化人類学者の石毛直道。「鉄の胃袋」の異名を持ち、世界各国でフィールドワークして様々な土着の料理を食べてきた人物だ。彼がたくさんの食卓を見るうちに沸き上がってきた「人類の食事の文明はどういう志向性を持つのか」という疑問。本書は、それを学問的というよりもエッセイ風に思索していったものである。
人類の食事を考える際に、最も基本となる単位は「家族」である。というよりも、食事を分け与える最小単位として「家族」というものが成立したのだろう。家族がそのメンバーにどう食物を分配するか(時間的な意味でも。例えば一日3食にするか2食にするか)、そしてそれを取り巻く社会がどう家族ごとに分配するかというのがまず問題になる。それには、宗教や文化や労働の在り方、社会システムなどが影響する。
例えば、一日3食が普及したのはなぜか、という問題。前近代の社会はもともと一日2食が普通だった。それなのに日本でも欧州でも、同じような時期に一日3食の習慣が広まっているのはどうしてか。一般的には、灯火の普及で夜の生活が長くなり3食に分けて食べないと体が持たなかったからと言われているが、著者は近代社会では長時間うんと働かなくてはならなくなったのが最大の原因ではないかと考える。
さらに日本で朝に飯炊きをするという習慣も会社労働や学校などの普及によって導入されたものだ。会社や学校は、昼に帰宅が難しい場合があり弁当を持って行かなくてはならない。よって弁当をつくるために朝に飯炊きをする必要が生じたのだという。
このように、伝統的な食事の在り方は近代文明の波を受けて劇的に変わってきている。その変化はどこへ向かっているのか。それは著者自身にもまだ茫洋としているようだ。しかし社会が豊かになって食物が豊富になり分配のややこしい手続きが省略されるといった傾向はある。そしてそのことは、食事の分配機能の最小単位である家族の在り方にまで影響を及ぼしつつある。
一昔前では、一人で生活してちゃんと3食食べることは不可能に近かったが、電化製品や加工食品の普及で、今ではそんなことは全く難しいことではない。毎日の食事を用意するために「家族」があるのではなく、むしろ共に食事することが「家族」を維持する役目を担うようになってきた。こうなると、「機能集団としての意味が弱くなった家庭生活の運営というものは、大人も参加したママゴト遊びのようなもの」になったのである。
要するに、食事から見れば、我々の文明にはもはや「家族」は不要なのだ。しかしこれはいっときの栄華のなせることなのかもしれない。「ふたたび食物の獲得と分配をめぐって家族が機能する時代がやってくる可能性もある。(中略)そのときまで、フィクションとしてでも家族を存続させるために、われわれはつかの間のママゴト遊びを演じているのかもしれない。」
食事を通じて、姿が見えない社会の基底まで考えさせる好著。
著者は文化人類学者の石毛直道。「鉄の胃袋」の異名を持ち、世界各国でフィールドワークして様々な土着の料理を食べてきた人物だ。彼がたくさんの食卓を見るうちに沸き上がってきた「人類の食事の文明はどういう志向性を持つのか」という疑問。本書は、それを学問的というよりもエッセイ風に思索していったものである。
人類の食事を考える際に、最も基本となる単位は「家族」である。というよりも、食事を分け与える最小単位として「家族」というものが成立したのだろう。家族がそのメンバーにどう食物を分配するか(時間的な意味でも。例えば一日3食にするか2食にするか)、そしてそれを取り巻く社会がどう家族ごとに分配するかというのがまず問題になる。それには、宗教や文化や労働の在り方、社会システムなどが影響する。
例えば、一日3食が普及したのはなぜか、という問題。前近代の社会はもともと一日2食が普通だった。それなのに日本でも欧州でも、同じような時期に一日3食の習慣が広まっているのはどうしてか。一般的には、灯火の普及で夜の生活が長くなり3食に分けて食べないと体が持たなかったからと言われているが、著者は近代社会では長時間うんと働かなくてはならなくなったのが最大の原因ではないかと考える。
さらに日本で朝に飯炊きをするという習慣も会社労働や学校などの普及によって導入されたものだ。会社や学校は、昼に帰宅が難しい場合があり弁当を持って行かなくてはならない。よって弁当をつくるために朝に飯炊きをする必要が生じたのだという。
このように、伝統的な食事の在り方は近代文明の波を受けて劇的に変わってきている。その変化はどこへ向かっているのか。それは著者自身にもまだ茫洋としているようだ。しかし社会が豊かになって食物が豊富になり分配のややこしい手続きが省略されるといった傾向はある。そしてそのことは、食事の分配機能の最小単位である家族の在り方にまで影響を及ぼしつつある。
一昔前では、一人で生活してちゃんと3食食べることは不可能に近かったが、電化製品や加工食品の普及で、今ではそんなことは全く難しいことではない。毎日の食事を用意するために「家族」があるのではなく、むしろ共に食事することが「家族」を維持する役目を担うようになってきた。こうなると、「機能集団としての意味が弱くなった家庭生活の運営というものは、大人も参加したママゴト遊びのようなもの」になったのである。
要するに、食事から見れば、我々の文明にはもはや「家族」は不要なのだ。しかしこれはいっときの栄華のなせることなのかもしれない。「ふたたび食物の獲得と分配をめぐって家族が機能する時代がやってくる可能性もある。(中略)そのときまで、フィクションとしてでも家族を存続させるために、われわれはつかの間のママゴト遊びを演じているのかもしれない。」
食事を通じて、姿が見えない社会の基底まで考えさせる好著。
登録:
コメント (Atom)