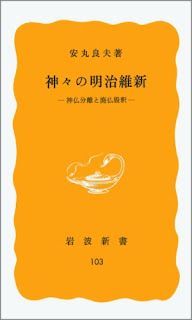その後祖父が「これも読みなさい」といって3冊、本をくれた。
『西郷隆盛のすべて―その思想と革命行動』(濵田尚友)、『首丘の人 大西郷』(平泉 澄)、の2冊は覚えているが、3冊目がなんだったか今や分からなくなってしまった。『南洲翁遺訓』だったか。こちらも曖昧である。
なぜ曖昧かというと、これらの本を読んでも、どうも西郷隆盛という人間が自分の中にスッと入ってこない。だいたい、これらの本はどれも最初から西郷隆盛賛美を決めてかかっているところがあって、大げさに言えば、「西郷はかくも偉大であった」というようなことが結論としてあり、それに枝葉をつけたような書きぶりなのだ。
それで、どうも西郷隆盛は自分にとって謎の存在ということになってしまった。伝記的なことを一応は知っていても、等身大の姿というものが見えなかったのである。
そんな西郷に再び興味を抱いたのはだいぶ後になってからで、西南戦争のことが気になり出してからだった。
そのきっかけは、『近代日本の戦争と宗教』(小川原 正道)という本だ。
↓読書メモ
https://shomotsushuyu.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html
この本で、西南戦争には「不平士族の暴発」だけでない、多様な性格があった事を知った。西南戦争発端の裏側には、鹿児島で布教を進めたい西本願寺と、真宗の教化によって鹿児島の民衆を政府に馴化しようとする大久保利通らの思惑があった。
西南戦争を起こした者たちには、単なる新政府への不平不満だけでなく、思想的な反抗があったということが朧気ながらに見えた。
なぜ、鹿児島の士族たちは、明治維新を主導しながらも反政府的になってしまったのか。西郷はなぜ、その士族たちを抑えることが出来ずに望まない戦争に担ぎ出されたのか。鹿児島の歴史を知るにつれ、それが私の中で大きな疑問となっていった。
もちろん、通り一辺倒の答えならすぐに準備できる。鹿児島の士族たちが反政府的になったのは彼らが廃藩置県で無職になってしまったからだし、西郷が彼らを止められなかったのは、県内各所の温泉など巡っていて現場(城下)にいなかったからだ。
でも私は、もっと深いレベルで西南戦争を理解したいと思った。西南戦争は、「鹿児島の明治維新」を象徴するものであり、いろいろな意味でその後の日本を先取りしている点がある。そしてその中心にいる西郷隆盛を、今までとは違った視角から理解したくなった。
そういう視角を準備してくれたのが、『南洲残影』(江藤 淳)である。
↓読書メモ
https://shomotsushuyu.blogspot.jp/2016/11/blog-post.html
本書は、西郷が残した文学作品(漢詩)や檄(指示)を読み解くことで、西郷の心情に迫ろうとするもので、その内容の多くが西南戦争に費やされている。
本書が用意した視角というのは、西郷を「維新の英雄」としてではなく、むしろ「国賊として討伐された敗者」として描いたことだ。西郷賛美でも西郷否定でもなく、一人の非命の人間として西郷を理解しようとする姿勢が、意外と類書にはない。本書によって初めて、私は西郷という人間がこちらの方へ歩み寄ってくれたような気がした。
だが本書の憾みは、適度な距離感をもって語りはじめたはずの著者が、最後には西郷に飲み込まれ、「日本人はかつて「西郷南洲」以上に強力な思想を持ったことがなかった」といったことを言い出すことである。私には、西郷が「思想」だったとはどうしても思えないのだ。いや、「西郷の思想」が何だったのかさえ、未だ茫洋としてつかみどころがないのである。
一方、猪飼隆明は『西郷隆盛―西南戦争への道』によって、西郷の行動原理が「忠君」であることを主張した。
↓読書メモ
https://shomotsushuyu.blogspot.jp/2015/08/blog-post.html
要するに西郷は古いタイプの人間で、武士としてのあるべき行動原理である「忠」をずっと守っていたというのである。
最初は主君島津斉彬に対し、そしてその後は明治天皇に対して。そして明治天皇も、ことのほか西郷を寵愛したという。それは、他の維新の功臣が形式的にしか天皇を尊重していなかったのと比べ、西郷は天皇を主君として仰いでいたからではないかという気がする。
また、西郷もその胸の内に様々な葛藤を抱えていた。
例えば、斉彬が残した国(鹿児島藩)を解体してしまってよいのかという葛藤だ。700年も続いた島津氏の支配を、「廃藩置県」を行うことで微臣に過ぎぬ自分が終わらせてよいのか。そういった葛藤を、西郷は天皇への忠心によって乗り越えたという。
私は、本書を読んで、西郷は、みずから「時代遅れの男」であることを自覚しつつ、むしろ「時代遅れの男」として死のうと決意した人間であると思うようになった。西南戦争は彼にとっては望まない戦争であったが、彼以上に「時代遅れの男」たちであった鹿児島の士族を見捨てきれなかったのも、西郷の西郷らしい点であった。
このことは、最初期に「藩」という意識を脱却し、日本の「政治家」としての自覚を持った進歩的な人間、大久保利通と全く対照的な点だった。
だがもちろん、西郷はただの「時代遅れの男」ではなかった。
西郷は鹿児島の士族たちとは、全く違う想いを抱いていた。明治政府のやり方が気にくわなかったのは事実であるが、彼の中には「万国公法」と通ずる進歩的思想が旧来の儒教道徳の上に打ち立てられてもいた。
だから、「時代遅れの男」ばかりの鹿児島の不平士族たちの中にあって、西郷は孤独だった。鹿児島の大勢の士族に慕われながら、実のところ西郷は四面楚歌だったのである。
そもそも、士族が失職した原因である「廃藩置県」は西郷が主導したものなのだ。鹿児島の士族は西郷をまつりあげたけれども、内心憤懣やるかたない想いがあったのではないか。そういう空気を感じられるのが、『西南戦争 遠い崖—アーネスト・サトウ日記抄13』(萩原 延壽)に描かれる一場面である。
↓読書メモ
https://shomotsushuyu.blogspot.jp/2015/08/13.html
明治10年2月11日、もうあと数日で薩軍が進軍を開始するというその時、西郷は旧知のサトウを突然訪問した。その時の様子をサトウはこう記す。
「西郷には約二十名の護衛が付き添っていた。かれらは西郷の動きを注意深く監視していた。そのうちの四、五名は、西郷が入るなと命じたにもかかわらず、西郷に付いて家の中へ入ると主張してゆずらず、さらに二階に上がり、ウイリスの居間へ入るとまで言い張った」護衛たちは、他ならぬ西郷を監視していたのであった。そして西郷は、西南戦争のさなかにあっても直接に指揮を執らせてもらえなかった。戦場から隔離され、激しい戦闘が行われている裏側で、西郷は呑気にウサギ刈りなどしていたのである。いや、「させられていた」と言う方が正しいか。彼は西南戦争において、少なくとも戦いの半ばまで蚊帳の外に置かれていた。
しかしながら、西郷がただ士族たちのいいように手玉に取られていたかというと、それはまた違う。
当時イギリスの外交官で日本に赴任していたオーガスタス・マウンジーが『薩摩国反乱記』(安岡 昭男 補注)を書いているが、彼は仕事の外交記録としてではなく、一個人として本書を書きイギリスで公刊した。
↓読書メモ
https://shomotsushuyu.blogspot.jp/2017/09/blog-post_8.html
マウンジーは、イギリスにとっては東洋の遅れた島国の内輪もめにすぎない西南戦争についてなぜ一書をものしたのか。それは、おそらく彼が西郷隆盛を高く評価していたからであり、西郷はイギリス人にとっても知って損はない人間だと信じていたからであろう。
マウンジーは、西南戦争については「封建制度をいくらか復活させようとする最後の真剣な企図であった」としていて、それ自体に進歩的意義は認めていない。しかし西郷については「その波瀾に富んだ生涯とその悲劇的な死とによって、国民の間で、「東洋の偉大な英雄」との称号を得、またイギリスの読者の興味をひくにも事欠かないのである」と述べている。
彼がこうした記述をしたことを考えてみても、西郷が鹿児島の士族にいいように使われていただけということは考えにくく、戦争中はかなり自由を制限されていたとはいえ、西郷が西南戦争の性格に大きな影響を及ぼしていることは確実なのだ。西南戦争は西郷にとって望まない戦だったが、鹿児島ではこの戦いは「せごどんのイッサ(戦)」と呼ばれ、確かに「西郷の戦い」だったのである。
そして、西郷の思想そのものが西南戦争にどう現れているか、ということはさして重要ではない。それよりも、西南戦争において、西郷にどのような思想が付託されていたのか、ということが、この戦争を理解する上でもっと重要だ。
西南戦争は、「時代遅れの男」たちの守旧的な戦いであると同時に、明治維新の精神が骨抜きになっていくなかで、自由と言論をもって権力に対抗し明治維新の大業を貫徹させようとする進歩的な思想を持った人々の戦いでもあった。
そういう西南戦争の二面性を描いたのが、『西南戦争―西郷隆盛と日本最後の内戦』(小川原 正道)である。
↓読書メモ
https://shomotsushuyu.blogspot.jp/2018/04/blog-post_23.html
五箇条のご誓文では「万機公論に決すべし」とされていなかがら、実際には言論が制限され、薩長の政治家たちによる独裁政権(有司専制)が敷かれていたのが明治政府の実態であった。
そのため、いわゆる「民権派」という、自由と言論を重視する勢力が勃興してきたのが明治10年の頃である。そして「民権派」は、政府の横暴なやり方を糺すには武力を使うこともやむなしとさえ考えつつあった。例えば、板垣退助は明治政府の独裁を打破するため西郷を擁した反乱を企図し、島津久光に建言するのである。
後に板垣は西郷に批判的に転じるが、こういう背景があったから、薩軍には民権を求める進歩的な人々が多数参加している。
薩軍には、武士の特権を信じ封建制の復活を目指す人々と、自由と言論を信じ民権の拡大を目指す人々という、全く正反対の勢力が奇妙に同居していた。しかもそれぞれの勢力が、共にその思想を西郷に託していたのである。
どうしてそんなことが起こりえたのか。例えばこれが大久保利通であったなら、こんなことは起こりえなかっただろう。ほとんど共通点がない正反対の思想が西郷その人に付託されたという事実そのものが、西郷という人物を読み解く鍵であるように私には思える。
そして二つの思想の唯一の共通点は、理想の社会を実現するために身命をなげうつ点であったろう。ご一新の世の中に順応しえた人々が薩軍を冷ややかに見つめる中で、「この社会は間違っている」と憤った人々が西郷を旗印に集結した。社会を自分たちの手で変えようとする第2の明治維新を、西郷と共に起こそうとした。
だがこの戦いは、敗北を宿命付けられていたとも言える。なぜなら当の西郷にはその気がなかったからだ。彼は、あくまで明治天皇に忠誠を尽くそうとしていたのだから。
西郷をどう評価するかということは、近代日本の歩みを評価することと等しい。西郷には、古い社会の理想と新しい社会の理想が、両方投影されていた。しかし自分ではそのどちらも選び取ることが出来ず、新しい社会の理想を夢見ながら、「時代遅れの男」として死んだ。
「武士らしく生きることができない世の中なら、せめて武士らしく死なせてくれ」とでも言わんばかりの同胞と共に。
こうして西郷は「神話」となった。彼はあくまで黙して語らない。だから彼をどう評価してよいのか、考えれば考えるほど途方に暮れてしまう。
明治時代を鋭い目で見た橋川文三でさえ、西郷をどう扱えばいいのか悩んだ。『西郷隆盛紀行』(橋川 文三)は、依頼された西郷の評伝を書くために行った対談や小文をまとめたものだが、これを読めば西郷の評価がどうして難しいのかが分かるだろう。
↓読書メモ
https://shomotsushuyu.blogspot.jp/2018/04/blog-post_7.html
だから、こうしていくつかの本を読んできたが、私もまだ「西郷隆盛と西南戦争」をどう考えたらいいのか、正直よく分からないのだ。以前とは違った意味で、西郷隆盛は私にとって謎の存在のままだ。
それにまだまだ知りたいことがいくつかある。西郷が設立したと一般的には思われているが、実はそうではないらしい「私学校」の実態について(例えば徳富蘇峰の『近世日本国民史「西南戦争」第1巻』参照)。西南戦争を始めた戦犯ともいうべき篠原国幹や桐野利秋、別府晋介といった人々の動向。そして私学校を保護して薩軍を支援し、実質的な薩軍の代理人をつとめたといえる県令・大山綱良のこと。
こうしたことを分かった上でないと西南戦争の評価は出来ないし、西郷の評価もできないだろう。近代日本史の分水嶺であった西南戦争は、もっと深く理解されてしかるべき戦いだ。もう少し、書の径(みち)をさまよってみなくてはならない。