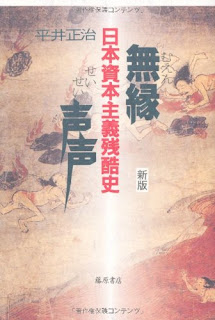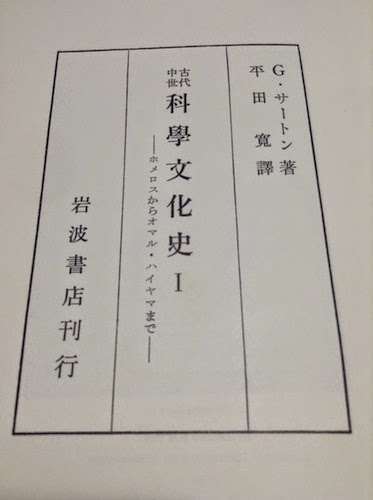2015年6月17日水曜日
『世界史をつくった海賊』竹田 いさみ著
大航海時代、イギリスは後発国家として国際競争に参入した。最も早く国際貿易を確立したポルトガル、そしてそれに続くスペインといった先行者がいる中で、イギリス(正確にはイングランド王国)は不利な競争をせざるをえなかった。イギリスには羊毛や毛皮くらいしか輸出に適した製品はなく資源に乏しかったし、既に世界各国の販路は両国に抑えられていたのである。
そこでイギリスはならずもの集団である海賊を国家として活用するという奇策に出る。スペインやポルトガルの貿易船を略奪すればたくさんの富が手に入る上、スペインやポルトガルの国力を削ぐことも出来、さらには最新式の船まで入手できるからである。
だが表立ってそういうことをすれば国際問題になり弱小国家だったイギリスには分が悪い。そこで裏では海賊組織と手を結び、国家の手として足として海賊を使いながらも、表向きにはスペインやポルトガルとの友好関係を演出していたのであった。このため諜報活動に力を入れ、ある年では国家予算の15%が諜報活動に使われていたという。
私はフランシス・ドレークなどが国家公認海賊として国家の英雄として祭り上げられ、イギリス国民の鼓舞に使われたということは知っていたが、それはあくまで象徴的な意味のことだと思っていた。しかし本書を読むと、イギリスの国家財政を支えていたのはまさに海賊マネーであり、海賊による略奪は象徴的どころか手堅い商売だったのだということがわかった。
一方、私が本書を手に取った動機は本筋とは全く関係ないことで、イギリスの海賊たちはどんなものを食べていたのだろうということにあった。それについては簡素な記載があるだけで(当たり前のことです)詳しくわからなかった。船上ではかなり貧しい食事に耐えていたことは間違いないだろうが。
なお、『世界史をつくった海賊』という表題であるが、本書の主人公はあくまでもイギリス国家であり、国家が海賊をどう利用したか、という観点で書かれている。海賊が主体的に何を望みどう行動したか、ということはあまり明確ではない。それどころか、ある意味ではイギリスの政策にいいように使われたようなところがあり、イギリスが貿易立国として成長し海賊マネーが不要になるとあっさりと切り捨てられている。
だからもうちょっと、海賊たちそのものを描いて欲しかったという気もする。ただ国家に使われたというだけでなく、彼らも国家を使ったのであるから、その駆け引きというか、国家v.s.海賊という視点もありうるのではないかと思った。
とはいえイギリス近代史と海賊の関係がよくわかる本。
2015年6月11日木曜日
『無縁声声 新版―日本資本主義残酷史』平井 正治 著
日本の資本主義の裏側を大阪・釜ヶ崎から語る本。
著者の平井正治は日雇い労働者として釜ヶ崎に30年も住んでいる人物。しかし凡百の日雇い労働者とはワケが違う。数々の労働運動を興すとともに、史資料の渉猟やフィールドワーク(という言葉は本書には出てこないが)によって日本の資本主義発展史を最も凄惨な現場の渦中から紐解いてきた、知る人ぞ知る人物である。
その内容は、基本的には著者の自伝であるが、その実全く自伝の枠を飛び越えている。そこでは当時の社会的事件の背景、そこに至る歴史が縦横に語られ、それはほとんどアナール派の歴史記述を思い起こさせるような重厚さがあり、しかもそれが軽妙な大阪弁で表現されているのだから、唸るしかない。
著者が一環して語るのは、いちばん底辺の労働者がどれだけ置き去りにされてきたかということである。特に港湾労働、土木労働といった景気と国策に左右される産業の労働者たちのことだ。そして彼らがどれだけ日本資本主義の犠牲になってきたかということだ。
例えば新幹線の工事ではこうだ。こういう土木工事は多くの人手がいる。だから広くから労働者を集めてこなければならない。しかし常雇いは出来ない。なぜなら、新幹線が開通してしまった後はその労働力は不要になるからだ。しかも工事中だってそうである。生コンを打つ時は多くの人手がいるが、生コンを打ってしまったら固まるまで次の作業ができないのでその労働力は遊ぶことになる。
だから労働力はその日暮らしの底辺労働者で調整することになる。そこで「手配師」の出番だ。半分ヤクザみたいな斡旋屋である。甘いことをいってその日の金にも困っている労働者を連れてくる。もちろん彼らはただ職場を斡旋するワケではなく、やれ食費だ衣料品費だ衛生費(トイレ使用料)だといって手当をピンハネするのである。それでも立場の弱い日雇い労働者はそれに何も言えない。何よりヤクザに反抗するのも怖い。
そして労働者は危険にさらされる。まともな労働衛生は期待できない。アスベストを扱う仕事でもマスクひとつくれない。そういう日雇いの担当する仕事は、孫請けのさらに下請けがやっているような仕事で、何重にもピンハネされた上に何の保証もないものだからである。元請けの大企業が発注する時は、もちろん労働衛生費まで計上されている。だがそれが下請けに出される度に削られていく。何重もの調整構造の中で、全てのしわ寄せが底辺労働者へいく。
さらに無理な日程で無理な作業をするから事故が起きる。そして労働者が簡単に死んでいく。日雇いで働いているような人の命は軽い。労災ではなく、交通事故として処理されたり、身元を調べることもなく無縁仏として処理されたりする。死んだのが誰かなど、誰も気にしない。過去を捨てた人間がドヤ街に集っているのだから。
こうして、彼らに押しつけられた矛盾はなかったことにされていく。
それに反抗するのが著者の平井である。筋が通らないことは許さない。ただゴネるのではなく、理路整然と、諄々と、そして時に激しい言葉で不正を追求する。ある時は、たった数百円の手当を認めさせるのに4年かかったという。例えば汚れる仕事にはその分手当を上乗せすべき、そういう「公正さ」を追求するのに妥協はしない。そういう男である。
実行力と知力を兼ね備えた人間である。やろうとすれば、日雇いの境遇から抜け出すことなどたやすかっただろう。だが平井は釜ヶ崎でほんの少しの労働環境の改善を成し遂げることに全力を注いだ。どうしてそういう茨の道を歩んだのか、本人にもよくわからないらしい。本書の末尾につけられた対談で一言「黙ってられん」からだと笑っている。
本書を読むと、オリンピック、万博、新幹線といった国策による大規模土木工事がいかに不正と事故の温床になってきたかということに気づかされる。そういった「国の威信」を賭けた工事は遅れるわけにいかない。だから無理なスケジュールが組まれる。十分な安全策をとれなくなる。そして工事が終わって不要になった労働者のことなど知ったことではない。見捨てられた労働者は、やがて街の掃きだめへと追いやられそこが次のドヤ街になる。このように労働者を使い捨てて出来たのがオリンピックや万博の会場であり、新幹線だった。
どうしてそんな不条理がまかり通っているのか? それに対する明確な説明は本書にはない。ただ、行政、政治、産業界とヤクザの馴れ合いと癒着の構造が示唆される。日雇いの弱い労働者を使い捨てることで維持されてきた「国の威信」や「経済成長」。「必要悪」という便利な言葉で温存されてきた古い労働のやり方。こうしたものに向き合わない限り、日本には本当の「経済成長」はありえないのではないか?
そして今、再び東京オリンピックの開催が決まっている。無理な設計によって既に工事は波乱含みだ。だが日本のゼネコンは工期を守るだろう。弱い労働者のおおきな犠牲の上に。今度のオリンピック会場にはいくつの人柱が立つのだろうか。
実は戦前にも東京オリンピックの開催が決まったことがあった。皇紀2600年事業(昭和15年)の一環で政府はオリンピックと万博を誘致したのである。これは古い「東京」をぶち壊して国家にとって都合のよい「東京」に変えるための大規模土木工事だった。オリンピックと万博のためということで東京-下関間に高速鉄道を作ろうとした。いわゆる「弾丸列車」である。
しかしこれは、実際には軍事物資の輸送のためのものだった。太平洋戦争で日本が東南アジア諸国を獲得すると、この高速鉄道の計画は順次延長されてシンガポールまでの延長が構想されたという。
結局オリンピックや万博は戦争のために中止されて、弾丸鉄道も戦争中は実現しなかったが、これが戦後の東海道新幹線へと繋がっていく。そして戦前実現しなかったオリンピックや万博も戦後にはどんどん開催され、その裏で日雇い労働者たちは都合よく使われ、そして押し潰されていったのであった。
そしてこの構造は、今でも全く変わっていない。派遣労働者という新たな日雇い人夫の置かれた状況はますます厳しくなっていく。その一方で「過去最高益」を記録する大企業。どこかおかしい。日本がほんとうの意味で「経済成長」するためには、あと百人の平井正治が必要だろう。
横山源之助『日本の下層社会』や鎌田慧氏の一連の著作に連なる、日本の社会を考える上での必読書。
2015年5月19日火曜日
『神話の力』 ジョーゼフ・キャンベル&ビル・モイヤーズ(対談)、飛田 茂雄 訳
ジョージ・ルーカスに大きな影響を与えたことで有名な比較神話学者のジョーゼフ・キャンベルが、晩年にテレビの企画でジャーナリストのビル・モイヤーズと対談を行った。本書はその書き起こしである。
その内容は、神話そのものについてというよりも、神話を通じて何を学ぶかということである。そして、キャンベルが神話を通じて学んだ人生哲学へと話が進んでいく。その人生哲学は、私にとって大変共感できるものであった。例えばこういう調子である。
「しかし、そうすることであなたは世界を救うことになります。いきいきとした人間が世界に生気を与える。(中略)人々は、物事を動かしたり、制度を変えたり、指導者を選んだり、そういうことで世界を救えると考えている。ノー、違うんです! (中略)必要なのは世界に生命をもたらすこと、そのためのただひとつの道は、自分自身にとっての生命のありかを見つけ、自分がいきいきと生きることです。」キャンベルの語り口は簡潔でありまた軽妙でもある。対談ゆえに断片的なところは否めないが、「あなたの至福に従いなさい」(自分自身の内なる声に従え)というメッセージがよく伝わってくる。
しかし問題なのは聞き手のモイヤーズで、話があっちに飛びこっちに飛び、「えー、そこで話題変えちゃうの?」というところがたくさんある。聞きたいことがたくさんあって節操なく質問しているのか、キャンベルの言わんとしていることを表面的にしか理解していないのか、あるいは断片的な警句をたくさん引き出そうとしているのか、よくわからない。
巻末の冲方 丁による解説ではモイヤーズを「希代の聞き手」と称揚しているが、これは皮肉なのだろうか? キャンベルの話を落ちついてよく聴き、無闇に質問攻めにすることなくその思想を開陳してもらう対談にすればもっと実りあるものになったと思う。
キャンベルの話は興味深いが、聞き手の軽率な感じが残念な本。
2015年5月14日木曜日
『チベット旅行記』河口 慧海 著
ヴェルヌの『八十日間世界一周』のように面白い。著者はチベットまで仏教の原典を求めに行ったので、私としては当時のチベット仏教の現状に興味があって本書を手に取ったのだが、それがどうでもよくなるほど本書はエンターテインメントとしてよくできている。
誰の紹介もなく独力でチベットを目指し、大した装備もないままヒマラヤを越えて当時鎖国状態だったチベットに密入国するという下りは、ハラハラドキドキの連続である。途中強盗に身ぐるみ剥がされたり、迷ったり、死にかけたりするがそれを乗り越えていく強い決意と知恵が素晴らしい。自分も何か困難な物事に立ち向かってゆくぞ、という気概が湧いてくるような内容である。
チベットの首府ラサに行くまでが全体の分量の半分程度で、次のラサ編では今度は聴き知った医学の知識が役立ち、法王にも認められ医師として活躍することになる。本来求めに行った仏教の仏典についての記載はあまりないが(たぶん余りに専門的なので省いたのだと思う)当時のチベットの風俗、外交、行政システムなどの記述は詳細である。
最後の1/4は帰国編であるが、ここに著者は大きな問題に直面する。というのは、密入国で入ったチベットでは、己をチベット人と偽って活躍していたのであるが、これが脱出後に露見し、のみならず英国の秘密探偵であったとの風評が立ち、ラサで世話になった人びとが探偵への協力の廉で投獄されるという事態に陥ったのであった。著者はこれをなんとか救出すべく手をつくすのであるが、それが最後のハラハラドキドキである。
本書の文体は生き生きしていて読みやすく、明治の作品であることを感じさせない。一部人種的な記述(例えば、チベット人は怠惰だ、とする部分など)、日本人や皇室への過度な自信が窺える部分などは今日的には問題があるが、チベット人は怠惰だ、という場合にもチベット人の長所についても述べており、バランスを取ろうとする意識がある。
また著者は「文明的に遅れた国を探検しよう」というような傲岸な気持ちではなくて、むしろチベットに留学しにいったのであるから(事実大学に入学している)、チベットの文化をなるだけ尊重しようという気持ちが感じられる。
ちなみに、私は本書をiBooks(by iPod touch)で読んだのだが、これはiBooksで読んだ始めての本であった。画面が小さいので4000ページ近くあったがとにかく面白く見づらさも気にならなかった。
チベットに興味があろうがなかろうが、エンターテインメントとして読める第一級の旅行記。
2015年5月4日月曜日
『古代中世 科学文化史 Ⅰ <ホメロスからオマル・ハイヤマまで>』 G.サートン著、平田 寛 訳
著者のジョージ・サートンは「科学史」を独立した学科として構築することを企図して本書を構想した。「科学史」は、例えば数学史であれば数学研究の一分野(しかもほとんどオマケのような一分野)でしかなかったし、或いは文化史の中の一つのトピックに過ぎない面があった。そういう歴史学の付属物としてではなく、「科学史」自体に学問としての固有の価値があることを信じ、 サートンは大規模な叢書をつくり上げることによって「科学史」そのものを打ち立てようとしたのである。
その叢書は次のような構成として計画された。
第一叢書:編年的に構成された、地域横断型の科学史の概観(7〜8巻)。
第二叢書:例えばユダヤ文明、イスラーム文明、中国文明といったように、種々の文明における科学発展の概観(7〜8巻)。
第三叢書:数学、物理学など分野ごとの発展の概観(8〜9巻)。
つまり、サートンは科学史を縦糸的(年代記)、横糸的(地域的)、分野的という3方向から編むことにより、科学史の目でしか見ることの出来ない人間学を確立しようとした。もちろんこのような大規模で百科全書的な構想はサートン一人の手に負えないことは自身がよくわかっていた。ただサートンは、自らが出来るところまでやってみよう、という決意でこの仕事を始めたのである。
そして結果的に成し遂げられたのは、第一叢書の最初の3巻(古代・中世)だけであった。全体の構想の、ほぼ1/8にあたる量である。しかし、この3巻だけでもサートンの名は科学史史に永久に記される価値がある。 それくらい、科学史において画期的な業績であった。
この3巻(日本語訳では5分冊)の特色は、西洋中心だったそれまでの科学史から脱却し、東洋(特にイスラーム圏、中国、日本)の業績を詳しく紹介するという、世界史的な視座に立った科学史となっていることである。特にイスラーム圏の科学を詳細に研究したサートンは、イスラーム圏の科学がどれだけ大きく科学の発展に寄与したか熱をこめて記述しており、仮に本書がイスラーム圏のみの記述しかなかったとしてもその価値は非常に大きい。
その内容を紹介することは科学史の無様な要約になってしまうし、関心のある人は自ら目を通すであろうから辞めるが、科学史について深く知ろうという人でなくても、この第1巻の序章だけでも面白い。
例えばサートンはこの序章で、中世期には東洋の方が科学の水準が進んでいたのに、近代になってなぜ西洋がそれを追い越し、圧倒的な差がついてしまったのか、という疑問を提示する。そしてそれに対し、「西洋人と東洋人とはスコラ学の大きな試練を受けたが、西洋人はそれを突破し、東洋人はそれを突破しそこなったのである」との回答を与えている。
スコラ学という病理の唯一の治療法は実証的経験に基づいて知識を再構成しなおしてくことだったが、東洋では遂にその大事業をする人間が現れなかったのであった。この回答の含蓄の深さは、実際に本書を手にとっていただかないとなかなか伝わらない。科学の発展の歴史というある意味では無味乾燥な事実の羅列であるにもかかわらず、ここには確かに新たな人間学・文明史学が誕生していると思う。
なお、日本語訳は5分冊あるが、原書3巻の抄訳である。原書では、(1)その時代の主な科学的事績の概説、(2)批判的書肆解題(その時代の科学書の紹介)、(3)それらに対するサートンの覚書、の3つの部分を年代記的に並べていく構成が取られているが、日本語訳ではその(1)の部分のみを訳出しているのである。これは、サートン自身が(1)の部分を通史的に読めるように意図して著述しているため無理な抄訳ではなく、(2)や(3)まで目を通したいという専門的な向きはどのみち原書で読むと思われるのでやむない処置であろう。
ちなみに、日本語の書名は「科学文化史」を銘打っているがこれは不可解である。サートンは、文化の一様態としての科学というより「科学史」そのものを記述したかったわけであるから、単に「科学史」とすべきであった。本書ではそれまでの科学史の範疇に収まらない歴史学、言語学なども含まれているから「文化」をつけたのだろうが蛇足だ。原題は "Introduction to the History of Science"(科学史概説)であり、素直にこれを直訳する方がよかったと思う。
なお、本書が切り拓いた地平には、サートンに続いて新たな科学史がどんどんと打ち立てられていくことになる。例えばその嚆矢はニーダムの『中国の科学技術』(全14巻)であろう。科学史の分野で顕著な業績をあげた人に送られる賞がジョージ・サートン・メダルという名前なのも納得である。
そういう独立した学科としての「科学史」を打ち立てた不朽の名著。
2015年4月19日日曜日
『茶の世界史―緑茶の文化と紅茶の社会』角山 栄 著
茶の近代貿易のありさまを通じて歴史のダイナミズムを感じる本。
本書はいわゆる「物が語る世界史」であり、茶という商材を題材にして近代西洋の資本主義(特に英国のそれ)の様子を描き出している。
第1部は、茶と西洋人との出会い。西洋人が茶に出会ったとき、それは緑茶であった。日本の茶の湯は深い精神性と芸術性に基づいており、単なる飲料ではない喫茶文化に魅了されたのだという。 西欧人が東洋に到達した頃は、まだ西洋の力が絶対的に優位にあるという自信はなかったし、むしろ東洋の豊かさ、歴史と文化に嫉妬している部分すらあった。
そこで、茶の文化は進んだ文化として西洋に移入されることになる。しかし緑茶は西欧の食文化との相性が悪かったためか、緑茶であってもミルクや砂糖を入れて飲まれていたし、次第に紅茶へとその重心が移っていく。
その重心移動と並行にして、生産力の増大を背景に西洋の(東洋に対する)絶対的優位性が揺るがないものになってくると、茶は進んだ文化などではなく、単なる消費財になっていく。そしてそれが大衆に茶を飲む習慣を浸透させることにもなり、より消費量も増加していった。こうして茶(特に紅茶)は西欧諸国(特にイギリス)になくてはならないものとなり、茶を手に入れるために歴史が動いていくのである。
第2部は、その茶の輸出入の動向に対し日本がどのように動いたか。かつて日本の輸出品は第1に生糸、第2に茶であり、茶は主要輸出品であった。しかし世界の消費動向が次第に紅茶へと移っていく中で、日本も紅茶製造の取り組みはしたけれども、基本的には緑茶の販売をし続けた。もちろんこれは世界の動向に沿わないものであったために次第に茶の輸入は低減していく。
なぜ世界の動向に沿わない輸出を続けたのか、ということに関して、本書では外交文書等を引いて具体的にその情報収集能力のなさを指摘しているが、今も当時も変わらない、日本人の「世界的な空気を読めない」感が多分に出ていて暗鬱な気持ちになった。だがその背景にはもちろん日本にとって茶が重要な生産品ではなくなり、徐々に工業国家として立ち上がってくるということがあるわけなので、これは歴史の必然でもあったろう。
ところで本書は少し看板に偽りありで、「世界史」を銘打っている割には西洋近代史しか取り扱っていない。茶と世界史と言えば、例えば中国の「茶馬貿易」も重要かつ面白いトピックであるし、この内容を「世界史」と言い切るのは少し弱い感じがした。
しかしその内容は具体的な資料に基づいて考証を行っていて堅実であり、端正で読みやすくまとめられている。それこそお茶でも飲みながら読みたいような手軽で知的な本。
2015年4月8日水曜日
『ニッポン景観論』アレックス・カー 著
日本の都市・農村の景観が高度経済成長期以降に大変劣化したことを嘆く本。
著者はイェール大で日本文化を学び、渡日して書、古典演劇、古美術などを研究、さらに京都の町屋が壊されていくことを危惧して修復し宿泊施設として開業。その経験を元に古民家再生コンサルティングなどを行っている人物である。
その論旨は痛快である。
第1章では、日本には細かな建築規制などがあるのに枝葉末節を規定しているばかりで、景観に大きな影響を及ぼす電線・鉄塔・携帯基地局などが無秩序に乱立することを嘆く。
第2章は、街に無意味な広告看板が溢れていることについて。「消費税納税完納推進の街」といったような、無意味なスローガンから品のない巨大な看板まで。しかもそれらは何の広告効果も持っていないようである。
第3章は、他国に比べて圧倒的に多い公共工事とその「前衛的」な景観について。予算を消化するために必要性の低い土木工事が行われ、かつそれが周囲の環境と調和していない前衛的・近未来的なものとなっている。必要な土木工事を、周囲と調和させて行うのが先進国の公共事業の常識である。
第4章は、奇抜なデザインを尊ぶ建築界の悪弊について。権威あるデザイン賞を取るのが奇抜なデザインの建築ばかりなのはなぜなのか?周囲の景観に融け込んだ、落ちついたデザインは日本ではなぜ尊ばれないのか。
第5章は、ピカピカにしなければ気が済まないという「工業思想」について。景観への愛着がなく、単にキレイに管理できさえすればよいという悪習のもたらすもの。
第6章は、町中に溢れる「スローガン」について。特に「ふれあい」「環境に優しい」といった言葉がなぜ多用され、しかも何の意味もなしていないのかという考察。
第7章は、古い街並みに誇りを持たず、奇抜な建物や周囲と調和しない建物の建設を許してきてしまった住民のメンタリティについて。
第8章は、日本の貧弱な観光産業について。大型バスで観光客を周遊させ、凡庸なシティホテルが乱立しているだけの残念な観光地の多いこと。
終章では、それまでの議論を踏まえて、景観の面について今後日本人が進むべき方向を提言する。既存の公共工事で行われた無様な土木建築物の撤去やメンテナンスなど、公共工事の中身を改善していく必要性などについて。
どこをとっても膝を打つ内容で、「街は私たち住民のものだ」という意識が全くない日本人の内向きでお役所依存のメンタリティを見せつけられる思いがした。また、文章はとても皮肉が効いていて、単なる現状の批判に終わっていない。
公共工事の担当者はもちろん、建築家、商店主、いや街の景観を形作る全ての人に読んで欲しい本。
【関連書籍の読書メモ】
『犬と鬼—知られざる日本の肖像』アレックス・カー 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2015/07/blog-post_21.html
日本の政治・行政機構への痛烈なダメ出しの書。
日本の姿を率直に捉えて、これを改善していこうじゃないか、そういう気持ちにさせられる重要な本。『ニッポン景観論』は、本書を下敷きにして書かれたもの。