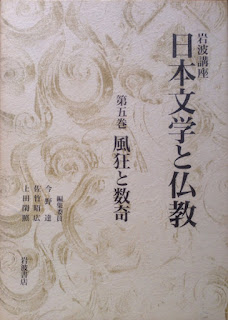徳富蘇峰(猪一郎)がその交友した人物について語った本。
徳富蘇峰は反体制派のジャーナリストとして頭角を現すも、やがて体制に取り込まれて一種の御用記者となり、それは「蘇峰の変節」と批判されるのであるが、これは体制を内部から眺めるという機会を得ることにもなった。
本書は、そういう蘇峰の体制内部における交友、すなわち山県有朋、井上毅、伊藤博文、大隈重信などの要人との個人的な思い出やその人物評を語るものである(口述筆記)。
私自身は、これらの人々についてはあまり詳しくなく、ここに語られている内幕の話にどれほどの価値があるのか判断ができないけれども、面白かったのは勝海舟と新島襄の話。
私も本書によって初めて知ったのだが、徳富蘇峰は若い頃に勝海舟の家に借家していた。同じ家に住んでいたのではなくて、勝海舟の屋敷内にあり本宅と隣接していた別宅を借家していたのだがその書斎が隣同士で、同じ敷地内に住んでいたのだから勝海舟とはかなり濃密な付き合いがあった模様である。勝海舟の人柄については多くの人が述べているが、これほど近しかった蘇峰の論評には独自の価値があるだろう。
新島襄については、蘇峰が生涯で心酔したただ独りの先生であったようだ。蘇峰は新島に会ったその日に強く惹かれた模様である。そして、政府の要人と親しく付き合うようになって、偉人とされる人と親炙するようになっても、新島以上に尊敬した人はいなかったように思われる。彼は、新島の能力や知識に感服していたのではなくて、ひたすらに人柄に惹かれていた。
当時学生であった蘇峰は、キリスト教のことはよくわからないまま、新島の勧めに従って洗礼を受けている。蘇峰は一時期キリスト教徒だったのである。しかも記者としての出発は、キリスト教系の新聞社への就職にあった(しかしこれはすぐに辞職している)。ところが次第にキリスト教への抑えがたい疑問が湧いてきて、やがて棄教する。それでも新島への敬慕は持ち続け、新島が同志社大学を設立せんとするやそれに熱心に協力したのである。
私にとって蘇峰といえば『近世日本国民史』の作家という存在感が大きいのであるが、本書ではそれ以外の、どちらかというと私的な面での蘇峰を知ることができた。
2018年10月30日火曜日
2018年10月24日水曜日
『三つの棺』ジョン・ディスクン・カー 著、三田村 裕 訳
カーの不可能犯罪の最高峰とされる作品。
訳者三田村 裕は「ミステリ・ファンならば、ミステリを語ろうという者ならば、必ず読まなければならない作品なのだ」と本書を評している(あとがき)。
これは訳者の我田引水ではない。実際、アメリカ探偵作家クラブの関係者17人が選んだ不可能犯罪のオールタイム・ベストにおいて、2位以下を大きく引き離して1位となったのが本書であり、また本書17章「密室講義」は、密室殺人ものの理論として独立した価値があり、本書はこの「密室講義」を読むためだけでも読むべき作品とされている(らしい)。
私自身の読書体験としても、かなり面白く読ませてもらった。不可解な密室殺人とだけ思われていたものが、やがて消し去られた過去の犯罪を暴く端緒となり、まるで霧の中から姿が現れるように怪奇的な全貌が紐解かれていく。しかし肝心なところは最後の謎解きまで読者には謎であり、最後まで一気に読ませる作品である。
しかも本書がミステリとして優れているところは、名探偵フェル博士が、作中に描かれないものからは推理していないということである。つまり、謎解きに必要な材料はほぼ全て作中にしっかり描かれており、読者も超人的な推理力がありさえすれば、フェル博士と同じ推理が可能となるように仕組まれているのだ。しかも、それでありながら読者にはその材料がどう組み立てられるのか最後の最後までわからないわけで、これがカーの絢爛豪華な小説技法だといえよう。
とはいえ、「不可能犯罪の最高峰」とされる作品であるだけに批判も多い。実際、あまりにも事件に手が込みすぎていてわかりにくい部分があるし、ありそうもないような偶然や、「そんなの普通できないでしょ」という無理矢理な行動(死にかけの男が自分で歩いて家に帰るなど)に頼った部分が確かにある。リアリズムを求める向きには少し「やりすぎ」な小説かもしれない。しかし、ディスクン・カー自身が、これは事実ではなくてあくまでも小説だ、というスタンスで書いているので、私としてはあまり気にならなかった。
なお、本書には新訳がありそちらの方が優れているようである(未読)。実際、本書には(日本語的に)やや頭に入って来づらい箇所がある。
訳者三田村 裕は「ミステリ・ファンならば、ミステリを語ろうという者ならば、必ず読まなければならない作品なのだ」と本書を評している(あとがき)。
これは訳者の我田引水ではない。実際、アメリカ探偵作家クラブの関係者17人が選んだ不可能犯罪のオールタイム・ベストにおいて、2位以下を大きく引き離して1位となったのが本書であり、また本書17章「密室講義」は、密室殺人ものの理論として独立した価値があり、本書はこの「密室講義」を読むためだけでも読むべき作品とされている(らしい)。
私自身の読書体験としても、かなり面白く読ませてもらった。不可解な密室殺人とだけ思われていたものが、やがて消し去られた過去の犯罪を暴く端緒となり、まるで霧の中から姿が現れるように怪奇的な全貌が紐解かれていく。しかし肝心なところは最後の謎解きまで読者には謎であり、最後まで一気に読ませる作品である。
しかも本書がミステリとして優れているところは、名探偵フェル博士が、作中に描かれないものからは推理していないということである。つまり、謎解きに必要な材料はほぼ全て作中にしっかり描かれており、読者も超人的な推理力がありさえすれば、フェル博士と同じ推理が可能となるように仕組まれているのだ。しかも、それでありながら読者にはその材料がどう組み立てられるのか最後の最後までわからないわけで、これがカーの絢爛豪華な小説技法だといえよう。
とはいえ、「不可能犯罪の最高峰」とされる作品であるだけに批判も多い。実際、あまりにも事件に手が込みすぎていてわかりにくい部分があるし、ありそうもないような偶然や、「そんなの普通できないでしょ」という無理矢理な行動(死にかけの男が自分で歩いて家に帰るなど)に頼った部分が確かにある。リアリズムを求める向きには少し「やりすぎ」な小説かもしれない。しかし、ディスクン・カー自身が、これは事実ではなくてあくまでも小説だ、というスタンスで書いているので、私としてはあまり気にならなかった。
なお、本書には新訳がありそちらの方が優れているようである(未読)。実際、本書には(日本語的に)やや頭に入って来づらい箇所がある。
2018年10月18日木曜日
『日本文学と仏教思想』浜千代 清、渡辺 貞麿 編
仏教思想が日本文学にどう表現されてきたかを考察する論考集。
本書は、「仏教文学会」のメンバーがそれぞれの論考を持ち寄ったもので、「日本文学と仏教思想」という壮大なテーマを掲げてはいるものの、これを真正面から体系的に考察するというよりは、主に平安時代を対象とし、それぞれのメンバーなりの視角から話題提供をしたという体裁の本である。
「序章」(渡辺貞麿)では、そもそも仏教では執着を断つということが求められるのに、文学という営みはいろんな意味で執着がなければ成り立たないわけだから、そこに緊張関係があるという認識を述べ、その緊張関係を解きほぐすことを本書の問題意識としたいとしている(ただし、この問題意識はあまり掘り下げられない)。
「第1章 因果の具現」(寺川真知夫)では、『日本霊異記』が取り上げられ、仏教説話が述べる新しい理倫理観について考察される。『日本霊異記』では、因果応報の原則を貫徹させようとする意識が強いあまり、倫理や人の内面についてはほとんど問題とされないという指摘は面白かった。また、僧を敬わないことが大きな罪とされたことは、逆に言えば僧を排撃する勢力が当時もあったことを示唆する。そうした勢力を掣肘するためにも、ほとんど残酷とも言える因果応報譚が述べられたのであった。
「第2章 『法華経と国文学』」(広田哲通)は、本書のメンバー全員の中心的な関心事である法華経の仏教説話についての考察である。法華経が日本文学に及ぼしている影響は他の教典に比べかなり大きいようだ。
「第3章 欣求浄土」(石橋義秀・渡辺貞麿)は、本書中で一番面白かった。まず平安末期の往生思想を『往生要集』などを取り上げて考察し、続いて「悪人往生思想」が法然・親鸞の思想(悪人正機説)と対置されている。往生—つまり浄土への転生ということについては、平安末期から大流行を見せるのだが、この思想の限界を文学作品(『今昔物語集』など)から探っている。本章の白眉は「入水往生」についてで、これは非常に面白い切り口の論考だった。なぜ自主的な往生(要するに自殺)をするのに入水往生が流行したのか。そこを探ることにより、当時の人の「往生」観が見えてくるのである。
「第4章 末法到来」(渡辺貞麿)は、『平家物語』についてのやや部分的な(かなり限定的なテーマの)考察。有名な「盛者必衰のことわり」の文辞的解釈や、『平家物語』作者の仏教理解についての推測など。
「第5章 自己を二つに裂くもの」(浜千代 清)では、西行、鴨長明、『閑居友』の作者という3人をケーススタディ的に取り上げている。
全体として、浄土思想・往生思想の平安期文学における巨大な存在感に改めて注目させられた。平安以来、往生伝の類は陸続と書かれたのであるが、これは日本仏教を理解する上での欠くべからざる水脈であると感じた。
日本文学における往生思想の重要性を感じさせる本。
【関連書籍】
『岩波講座 日本文学と仏教<第5巻> 風狂と数寄』今野 達 ほか編集
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/09/5.html
日本文学における仏教思想の展開を探るシリーズの第5巻。
本書は、「仏教文学会」のメンバーがそれぞれの論考を持ち寄ったもので、「日本文学と仏教思想」という壮大なテーマを掲げてはいるものの、これを真正面から体系的に考察するというよりは、主に平安時代を対象とし、それぞれのメンバーなりの視角から話題提供をしたという体裁の本である。
「序章」(渡辺貞麿)では、そもそも仏教では執着を断つということが求められるのに、文学という営みはいろんな意味で執着がなければ成り立たないわけだから、そこに緊張関係があるという認識を述べ、その緊張関係を解きほぐすことを本書の問題意識としたいとしている(ただし、この問題意識はあまり掘り下げられない)。
「第1章 因果の具現」(寺川真知夫)では、『日本霊異記』が取り上げられ、仏教説話が述べる新しい理倫理観について考察される。『日本霊異記』では、因果応報の原則を貫徹させようとする意識が強いあまり、倫理や人の内面についてはほとんど問題とされないという指摘は面白かった。また、僧を敬わないことが大きな罪とされたことは、逆に言えば僧を排撃する勢力が当時もあったことを示唆する。そうした勢力を掣肘するためにも、ほとんど残酷とも言える因果応報譚が述べられたのであった。
「第2章 『法華経と国文学』」(広田哲通)は、本書のメンバー全員の中心的な関心事である法華経の仏教説話についての考察である。法華経が日本文学に及ぼしている影響は他の教典に比べかなり大きいようだ。
「第3章 欣求浄土」(石橋義秀・渡辺貞麿)は、本書中で一番面白かった。まず平安末期の往生思想を『往生要集』などを取り上げて考察し、続いて「悪人往生思想」が法然・親鸞の思想(悪人正機説)と対置されている。往生—つまり浄土への転生ということについては、平安末期から大流行を見せるのだが、この思想の限界を文学作品(『今昔物語集』など)から探っている。本章の白眉は「入水往生」についてで、これは非常に面白い切り口の論考だった。なぜ自主的な往生(要するに自殺)をするのに入水往生が流行したのか。そこを探ることにより、当時の人の「往生」観が見えてくるのである。
「第4章 末法到来」(渡辺貞麿)は、『平家物語』についてのやや部分的な(かなり限定的なテーマの)考察。有名な「盛者必衰のことわり」の文辞的解釈や、『平家物語』作者の仏教理解についての推測など。
「第5章 自己を二つに裂くもの」(浜千代 清)では、西行、鴨長明、『閑居友』の作者という3人をケーススタディ的に取り上げている。
全体として、浄土思想・往生思想の平安期文学における巨大な存在感に改めて注目させられた。平安以来、往生伝の類は陸続と書かれたのであるが、これは日本仏教を理解する上での欠くべからざる水脈であると感じた。
日本文学における往生思想の重要性を感じさせる本。
【関連書籍】
『岩波講座 日本文学と仏教<第5巻> 風狂と数寄』今野 達 ほか編集
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/09/5.html
日本文学における仏教思想の展開を探るシリーズの第5巻。
2018年10月5日金曜日
『遊女の文化史―ハレの女たち』佐伯 順子 著
文学作品に描かれた遊女—娼婦について述べた本。
著者は、かつての遊女は春をひさぐというまさにそのことのために、神聖視されたという。つまり「性」は「聖」として受け取られたというのだ。さらに、彼女らは菩薩と同一視されることもあった。
遊女は罪深い職業であるという観念は次第に芽生えてくるが、罪深いがゆえにかえって深い仏道に帰依する因縁を持つとも考えられた。
また、遊女は芸能や文化の担い手でもあり、ただ男に体を許すだけでなく、舞や歌を献げるという高遠な「遊び」を神に捧げる役割も果たした。
しかしこうした遊女像は次第に零落してゆく。本来漂白の旅人だった遊女が遊郭に固定され、遊興の場と日常生活が裁断されてしまうと、遊女は聖なるものではなく、むしろ俗世の中でもさらに俗っぽいものと考えられるようになった。「性」は「俗」となったのである。
さらに近代になると、遊女から文化や聖性は全くはぎ取られ、単純に性的サービスを提供する娼婦となってゆく。娼婦たちはもはや高度な遊芸を身につけることなく、いっときの安逸を感じさせるだけの存在となったのだった。
著者は、こうしたことを文学作品(和歌、浄瑠璃など)を紐解くことで明らかにしている。しかし、全体を通じてみると納得できないところも多い。文学作品の主な担い手であり、また受け手でもあった男性の視点を解体するという作業が欠落しているためだ。
つまり、文学作品では、「そうあって欲しい遊女」や「理想の遊女」が描かれているわけで、現実の遊女がそうであったとは限らない。いくら遊女が「聖なるもの」として描かれたとしても、現実の男性が現実の遊女を聖なるものとして扱ったかどうかは別問題だ。本書は、男性の「理想の遊女像」が崩壊していった過程として読むことは出来るが、遊女が社会的にどう受容されてきたかという全体像ではない。
遊女に対するやや一方的な見方が気になるが、一つの遊女観としては参考になる本。
著者は、かつての遊女は春をひさぐというまさにそのことのために、神聖視されたという。つまり「性」は「聖」として受け取られたというのだ。さらに、彼女らは菩薩と同一視されることもあった。
遊女は罪深い職業であるという観念は次第に芽生えてくるが、罪深いがゆえにかえって深い仏道に帰依する因縁を持つとも考えられた。
また、遊女は芸能や文化の担い手でもあり、ただ男に体を許すだけでなく、舞や歌を献げるという高遠な「遊び」を神に捧げる役割も果たした。
しかしこうした遊女像は次第に零落してゆく。本来漂白の旅人だった遊女が遊郭に固定され、遊興の場と日常生活が裁断されてしまうと、遊女は聖なるものではなく、むしろ俗世の中でもさらに俗っぽいものと考えられるようになった。「性」は「俗」となったのである。
さらに近代になると、遊女から文化や聖性は全くはぎ取られ、単純に性的サービスを提供する娼婦となってゆく。娼婦たちはもはや高度な遊芸を身につけることなく、いっときの安逸を感じさせるだけの存在となったのだった。
著者は、こうしたことを文学作品(和歌、浄瑠璃など)を紐解くことで明らかにしている。しかし、全体を通じてみると納得できないところも多い。文学作品の主な担い手であり、また受け手でもあった男性の視点を解体するという作業が欠落しているためだ。
つまり、文学作品では、「そうあって欲しい遊女」や「理想の遊女」が描かれているわけで、現実の遊女がそうであったとは限らない。いくら遊女が「聖なるもの」として描かれたとしても、現実の男性が現実の遊女を聖なるものとして扱ったかどうかは別問題だ。本書は、男性の「理想の遊女像」が崩壊していった過程として読むことは出来るが、遊女が社会的にどう受容されてきたかという全体像ではない。
遊女に対するやや一方的な見方が気になるが、一つの遊女観としては参考になる本。
2018年9月29日土曜日
『岩波講座 日本文学と仏教<第5巻> 風狂と数寄』今野 達 ほか編集
日本文学における仏教思想の展開を探るシリーズの第5巻。
本巻には、「芸能」として『新猿楽記』(三隅治雄)、仏教歌謡(武石彰夫)、世阿弥の能楽論(三﨑義泉)、「風狂」として『狂雲集』(柳田聖山)、『おくのほそ道』(尾形 仂)、良寛詩集(飯田利行)、「数寄」として『ささめごと』(島津忠夫)、『南方録』(倉沢行洋)が取り上げられ、その他柳田聖山による総論、西村惠信、大橋良介等の論考を収める。
私はハンドルネームを「風狂」としているように、昔から風狂の人物に興味があり、特に一休宗純(『狂雲集』)は人生の手本としての極北だと思っている。松尾芭蕉や良寛については、これまで風狂という観点からは見ていなかったが、こうして紹介されてみると一種の風狂人として共感した。
風狂という言葉には、風雅という意味合いもあるが、やはり狂うというところに意味の重点があり、一休や松尾芭蕉などは、一生悟りなどには到達せずに煩悩のままに己の道を歩んだところがある。漂白の歌人という意味では西行も似たような面があるが、西行は人生の最後には「和歌は陀羅尼に等しい」という境地に到達し、清澄に入滅を果たした。こういう悟った立派な人には、「風狂」という称号は似合わないのであり、西行を風狂という人はいない。
私が風狂の人に惹かれるのも、それが立派な人ではなく、おのれの煩悩に一生つきあい、この狂った世の中で真っ直ぐに生きようと思えば、自らが狂うしかない、というやむにやまれぬ生き方をした人が多いからである。
ところで本書には、『新猿楽記』を記した藤原明衡(あきひら)が登場するが、この人のことは本書にて初めて詳しく知った。明衡は身分と姻戚関係で全てが決まってしまう貴族社会の停滞の中で、才能はありながらも家柄がよくないために長く不遇の時を過ごし、かといって遁世することも出来ず、下級官職に甘んじて長く勤めあげ、晩年になって官位にこだわりながらも官位を得られずに死んだ人物である。
本書では、この明衡が慶滋保胤(よししげのやすたね)と対照的に描かれているが、彼は陰陽師としてよい家柄と才能に恵まれ栄達したが、しかし世間の汚辱を嫌悪して出家し、清浄な境地へと至っている。一方の明衡は、不遇の鬱を払いつつも、老いて若い妻を得、青年にまさる強い精力で二子を得て、その子らのためにも力の続く限り働かねばという執着から離れることはなかった。出家して心を清浄にするなど、全く念頭にないのである。
私はそういう、おのれの煩悩と世間の泥濘にのたうち回りながら、最後まで無駄なあがきを続ける人間が好きだし、私自身がそうなりたいと思っている。
本書には面白い論考もあるが、全体としてみるとやや散漫で、「文学における仏教思想の展開」については真正面からは論じていないものが多い。「風狂と数寄」という緩やかなテーマの下、 必要に応じて仏教的な要素に触れるという調子である。
あまり体系的な考察はないが、風狂と数寄に生きたいろいろな人とその作品を知ることが出来る本。
【関連書籍】
『連環記』幸田 露伴 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/07/blog-post.html
幸田露伴、最晩年の中編。慶滋保胤が主人公。
露伴の到達した言語世界の精華。
本巻には、「芸能」として『新猿楽記』(三隅治雄)、仏教歌謡(武石彰夫)、世阿弥の能楽論(三﨑義泉)、「風狂」として『狂雲集』(柳田聖山)、『おくのほそ道』(尾形 仂)、良寛詩集(飯田利行)、「数寄」として『ささめごと』(島津忠夫)、『南方録』(倉沢行洋)が取り上げられ、その他柳田聖山による総論、西村惠信、大橋良介等の論考を収める。
私はハンドルネームを「風狂」としているように、昔から風狂の人物に興味があり、特に一休宗純(『狂雲集』)は人生の手本としての極北だと思っている。松尾芭蕉や良寛については、これまで風狂という観点からは見ていなかったが、こうして紹介されてみると一種の風狂人として共感した。
風狂という言葉には、風雅という意味合いもあるが、やはり狂うというところに意味の重点があり、一休や松尾芭蕉などは、一生悟りなどには到達せずに煩悩のままに己の道を歩んだところがある。漂白の歌人という意味では西行も似たような面があるが、西行は人生の最後には「和歌は陀羅尼に等しい」という境地に到達し、清澄に入滅を果たした。こういう悟った立派な人には、「風狂」という称号は似合わないのであり、西行を風狂という人はいない。
私が風狂の人に惹かれるのも、それが立派な人ではなく、おのれの煩悩に一生つきあい、この狂った世の中で真っ直ぐに生きようと思えば、自らが狂うしかない、というやむにやまれぬ生き方をした人が多いからである。
ところで本書には、『新猿楽記』を記した藤原明衡(あきひら)が登場するが、この人のことは本書にて初めて詳しく知った。明衡は身分と姻戚関係で全てが決まってしまう貴族社会の停滞の中で、才能はありながらも家柄がよくないために長く不遇の時を過ごし、かといって遁世することも出来ず、下級官職に甘んじて長く勤めあげ、晩年になって官位にこだわりながらも官位を得られずに死んだ人物である。
本書では、この明衡が慶滋保胤(よししげのやすたね)と対照的に描かれているが、彼は陰陽師としてよい家柄と才能に恵まれ栄達したが、しかし世間の汚辱を嫌悪して出家し、清浄な境地へと至っている。一方の明衡は、不遇の鬱を払いつつも、老いて若い妻を得、青年にまさる強い精力で二子を得て、その子らのためにも力の続く限り働かねばという執着から離れることはなかった。出家して心を清浄にするなど、全く念頭にないのである。
私はそういう、おのれの煩悩と世間の泥濘にのたうち回りながら、最後まで無駄なあがきを続ける人間が好きだし、私自身がそうなりたいと思っている。
本書には面白い論考もあるが、全体としてみるとやや散漫で、「文学における仏教思想の展開」については真正面からは論じていないものが多い。「風狂と数寄」という緩やかなテーマの下、 必要に応じて仏教的な要素に触れるという調子である。
あまり体系的な考察はないが、風狂と数寄に生きたいろいろな人とその作品を知ることが出来る本。
【関連書籍】
『連環記』幸田 露伴 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/07/blog-post.html
幸田露伴、最晩年の中編。慶滋保胤が主人公。
露伴の到達した言語世界の精華。
2018年9月23日日曜日
『神の旅人—パウロの道を行く』森本 哲郎 著
パウロの辿った道を追体験する紀行文。
キリスト教を創始したのはイエス・キリストであるが、キリスト教をイスラエルの地方的新興宗教から「世界宗教」へと脱皮させたのはパウロであった。
しかしパウロはイエスから直接教えを聞いたこともなく、それどころかイエスの一派を熱心に迫害していたパリサイ派に属していた。そんなパウロがキリスト教の伝道者となったのは、伝説では天からの光ととともにイエスの声を聞いたからだという(パウロの回心)。
イエスの教えが「キリスト教」として発展したのは、直弟子たちよりもこの神がかり的な体験によって信者に生まれ変わったパウロに負うところが大きく、パウロの思想はキリスト教の要諦をなすものだ。私は、この奇妙な聖人パウロに興味を持って、本書を手に取った。
本書は、基本的には紀行文である。世界各地を旅することをライフワークとした著者が、パウロが生まれてから死ぬまでの、3回の伝道の旅を中心とした、その由来の地を訪ね、パウロの思想を追体験していく。その旅は考証や研究のためでなく、いわばパウロの雰囲気を感じるためのものである。
そして、パウロの思想が進んでいくと同時に、紀行文的な部分が徐々に少なくなっていき、終焉の地ローマについては、ほとんど紀行文は書かれていない。著者は本当にローマに行ったのだろうかと訝しむほどである。それほど、最後はパウロの人生そのものに思いを致す部分が巨大化するのである。
であるから、本書を紀行文だと思って読むと肩すかしを食う。しかし本書は研究書でもない。著者は「旅をしながら考える」という紀行的エッセイをよく書いているが、本書もその一つで、旅のリズムでパウロの思想に肉薄しようとした本である。
キリスト教を創始したのはイエス・キリストであるが、キリスト教をイスラエルの地方的新興宗教から「世界宗教」へと脱皮させたのはパウロであった。
しかしパウロはイエスから直接教えを聞いたこともなく、それどころかイエスの一派を熱心に迫害していたパリサイ派に属していた。そんなパウロがキリスト教の伝道者となったのは、伝説では天からの光ととともにイエスの声を聞いたからだという(パウロの回心)。
イエスの教えが「キリスト教」として発展したのは、直弟子たちよりもこの神がかり的な体験によって信者に生まれ変わったパウロに負うところが大きく、パウロの思想はキリスト教の要諦をなすものだ。私は、この奇妙な聖人パウロに興味を持って、本書を手に取った。
本書は、基本的には紀行文である。世界各地を旅することをライフワークとした著者が、パウロが生まれてから死ぬまでの、3回の伝道の旅を中心とした、その由来の地を訪ね、パウロの思想を追体験していく。その旅は考証や研究のためでなく、いわばパウロの雰囲気を感じるためのものである。
そして、パウロの思想が進んでいくと同時に、紀行文的な部分が徐々に少なくなっていき、終焉の地ローマについては、ほとんど紀行文は書かれていない。著者は本当にローマに行ったのだろうかと訝しむほどである。それほど、最後はパウロの人生そのものに思いを致す部分が巨大化するのである。
であるから、本書を紀行文だと思って読むと肩すかしを食う。しかし本書は研究書でもない。著者は「旅をしながら考える」という紀行的エッセイをよく書いているが、本書もその一つで、旅のリズムでパウロの思想に肉薄しようとした本である。
2018年9月12日水曜日
『私はどのようにして作家となったか』アラン・シリトー著、出口 保夫 訳
イギリスの小説家アラン・シリトーのエッセイ集。
表題作「私はどのようにして作家となったか」「山脈と洞窟」など自伝的なもの、「スポーツとナショナリズム」「政府の調査書」など時事評論的なもの、「北から来た男、アーノルド・ベネット」「ロバート・トレッセル」など文芸評論的なものなど。
私が本書を手に取ったのは、ロクに本が置かれてもいないような下層の労働者階級に育ったシリトーが、どうして文学に親しみ、作家にまでなったのかに興味が湧いてである。戦後イギリスでは「怒れる若者たち」と呼ばれる一群の作家が簇生したが、社会の矛盾や格差に怒っていた彼らも、その実はインテリの出身だったのに、シリトーは本当の下層階級出身だった。
シリトーの家は貧乏だったので、学校教育も14歳で終了しなければならなかった。しかし彼は頭はよい方だったらしい。本も僅かだが読んでいた。彼は上の学校に進む希望を持ちながらも働くことになり、やがて従軍する。そして従軍生活の中で文学に徐々に親しんでいった。そして退役にあたって肺病に罹る。これがシリトーの運命を変えた。療養中には何もすることができないため読書に勤しんだのである。
そして18ヶ月の療養を終えると、今度は傷痍軍人の年金(とは書いていないが日本でいえばそういう年金にあたるのだと思う)が出た。そしてその年金をアテにして、新婚の女性と共にフランスとマジョルカ島に滞在して執筆に明け暮れる生活を送る。その中で名のある詩人から「故郷のノッティンガムについて書きなさい」とアドバイスを受け、それにしたがって出世作『日曜の夜と月曜の朝』が書かれ、シリトーは作家として大成していった。
シリトーにとって、戦争とはアンビヴァレントな意味を持っていた。それは青春時代を奪い、暗く貧しい生活に甘んじなければならなかった面もあれば、階級を飛び越える機会や学習の機会、広い世界に飛び出すチャンスでもあった。戦争がなかったら、もしかしたらシリトーは一生を工場労働者として過ごしたのかもしれないのだ。
シリトーにとっての戦争と、文学の意味を考えさせられる本。
【関連書籍】
『長距離走者の孤独』アラン・シリトー著、丸谷才一/河野一郎 訳
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/07/blog-post_19.html
シリトーの第一短編集。底辺の生活を共感の眼差しで描写している。
表題作「私はどのようにして作家となったか」「山脈と洞窟」など自伝的なもの、「スポーツとナショナリズム」「政府の調査書」など時事評論的なもの、「北から来た男、アーノルド・ベネット」「ロバート・トレッセル」など文芸評論的なものなど。
私が本書を手に取ったのは、ロクに本が置かれてもいないような下層の労働者階級に育ったシリトーが、どうして文学に親しみ、作家にまでなったのかに興味が湧いてである。戦後イギリスでは「怒れる若者たち」と呼ばれる一群の作家が簇生したが、社会の矛盾や格差に怒っていた彼らも、その実はインテリの出身だったのに、シリトーは本当の下層階級出身だった。
シリトーの家は貧乏だったので、学校教育も14歳で終了しなければならなかった。しかし彼は頭はよい方だったらしい。本も僅かだが読んでいた。彼は上の学校に進む希望を持ちながらも働くことになり、やがて従軍する。そして従軍生活の中で文学に徐々に親しんでいった。そして退役にあたって肺病に罹る。これがシリトーの運命を変えた。療養中には何もすることができないため読書に勤しんだのである。
そして18ヶ月の療養を終えると、今度は傷痍軍人の年金(とは書いていないが日本でいえばそういう年金にあたるのだと思う)が出た。そしてその年金をアテにして、新婚の女性と共にフランスとマジョルカ島に滞在して執筆に明け暮れる生活を送る。その中で名のある詩人から「故郷のノッティンガムについて書きなさい」とアドバイスを受け、それにしたがって出世作『日曜の夜と月曜の朝』が書かれ、シリトーは作家として大成していった。
シリトーにとって、戦争とはアンビヴァレントな意味を持っていた。それは青春時代を奪い、暗く貧しい生活に甘んじなければならなかった面もあれば、階級を飛び越える機会や学習の機会、広い世界に飛び出すチャンスでもあった。戦争がなかったら、もしかしたらシリトーは一生を工場労働者として過ごしたのかもしれないのだ。
シリトーにとっての戦争と、文学の意味を考えさせられる本。
【関連書籍】
『長距離走者の孤独』アラン・シリトー著、丸谷才一/河野一郎 訳
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2018/07/blog-post_19.html
シリトーの第一短編集。底辺の生活を共感の眼差しで描写している。
登録:
コメント (Atom)