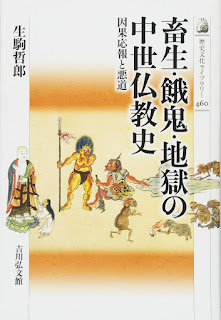趙州従諗(じょうしゅう・じゅうしん)の言行録。
趙州和尚といえば、かの『無門関』の第1則「狗に仏性はあるのか?」で余りにも有名である。また道元の『正法眼蔵』にもたくさん登場するし、『碧巌録』にもその公案が多く集録されている。
彼の禅風は徹頭徹尾語りと問答にあった。ややもすればすぐに「三十棒!(30回棒で打つ)」と実力行使に出る当時の禅にあって、趙州は禅を言葉で説明することにこだわった。であるから、その言行録は禅のテキストとして貴重であり、広く流布した。
ところが多くの禅籍で取り上げられたためか、肝心の『趙州録』そのものはいつしか忘れられ、原典が顧みられなくなってしまった。中国にも日本にも、『趙州録』の注釈と呼べるものは現代に至るまで存在しなかったのである。
では『趙州録』はつまらないものだったのか、というと実はこれが大変に面白いものだったのである。後代(宋代)に編纂され「公案化」された彼の問答よりも、原典はもっとずっとヴィヴィッドであり、わかりやすい。『趙州録』は神秘的な「公案」ではなくて、直接的な生きた教えなのだ(おそらく、そのために却って廃れたのだろう)。
ではその問答の調子はどんなものかというと、例えば代表的な問に「祖師西来意」というものがある。これは「ダルマ(祖師)がインドから中国に来て伝えようとしたその精神はどんなものですか?」という問である。『趙州録』では、たくさんの僧が趙州にこの質問をしている。趙州のお寺では問答の時間(かノルマ?)があって、僧たちは趙州和尚に質問をすることになっていた。それで、気の聞いた質問を思いつかなかった僧が、「思いつかない時はこういう質問をしたらいいよ」という先輩僧の入れ知恵によって定型的な質問をしていたようなのである。「祖師西来意」はそういう定番質問の一つである。
であるから、そもそも「祖師西来意」を尋ねる僧に切実な疑問というか探求心があろうはずもなく、趙州も軽くあしらっているように見える。そしてその答えはいろいろあり、古来有名な答えは「庭前栢樹子——庭先の栢の木だよ」というものなのだが(『無門関』第37則に取り上げられた)、他にも20以上の答えがある。そこから抽出される趙州の答えの核心は、「ダルマのことはさておいて、それを問うオマエはなんなの?」というものである。「ダルマ云々よりも、まず本来の自己に目覚めないことには話にならないよ」と言ってもよい。
趙州の問答は、質問者の切実度合いと理解度と修行度合いによって変幻自在に変わっていた。であるから、彼の問答の意味を表面的な言葉の意味でだけ考えても無意味であり、「庭先の栢の木がどうして祖師西来意なんだろう?」と考えてもあまり実りはないのである(ちょっと庭先の栢の木を見てみろ、とでも理解した方がいい)。
それを象徴するのが『無門関』第1則にも取り上げられた「狗に仏性はあるのか?」で、『無門関』では趙州は「無」とだけ答え、それについての考究がなされる。そしてこの「無」の一字は禅の究極のようなものと捉えられ、それに因んで『無門関』——「無」に至る門への関所——という標題までつけられているのである。
ところが、『趙州録』を見てみると、「狗に仏性はあるのか?」を質問した僧は2人いて、確かに一人への答えでは「無」と答えているが、もう一人には「家々の門前[の道]は長安の都に通じている(=どんな道でも悟りへ至る道=狗にも仏性はある、という意味と思われる)」と答えている。この2つの問答を見れば、狗に仏性はあるのかないのか、どっちやねん! と思うわけだが、趙州にとってみれば、「なんでオマエは狗の仏性の有無をあーだこーだいうわけ?」というところなのだと思う。『趙州録』の全体を通して、そういう観念的な質問をする時点で「こいつわかってねーな」という応対なのである。
逆に、初歩的な質問、定型的な質問であっても、僧の方に切実な問題意識がある(ように見受けられる)場合には趙州は「いい質問だ」と褒めている。他の僧が同じ質問でメタクソにされているようなものであってもである。趙州の禅は、観念的なものを排し、本来の自己に目覚めることを究極の目的として、あくまでも目の前の人物に応じて臨機応変に説かれるものであった。
であるから、例えば「庭前栢樹子」のような一見すると意味不明の答えであっても、その裏に観念的な世界が広がっているというよりは、極めて具体的・即物的な意味合いがあったと考えるべきなのだと思う。しかし宋代になると、『趙州録』から問答の一部が切り出され、まるで暗号のような公案が多々できあがる。『無門関』はその代表で、それはそれで禅の精神の発露であることは否定しないが、趙州和尚の臨機応変の自在の禅とは、かなり違うものになっていたこともまた事実である。
宋代の禅よりも、その原典の唐代の禅の方が、ずっと普遍的で理解しやすく、私にとっては親しみが持てる。『趙州録』はまさに禅の原点となる、忘れられた名著である。
2019年10月31日木曜日
2019年10月23日水曜日
『碧巌録』(西谷啓治・柳田聖山編『世界古典文学全集36B 禅家語録 II』 所収)
日本語訳された『碧巌録』。
『碧巌録』は、「宗門第一の書」と呼ばれ日本の禅宗、特に臨済宗には多大な影響を与えてきた。また難解であることでも有名であり、古来多くの注釈・講釈の本が出版されてきた。しかし意外にも長く日本語訳されることがなく、本書は出版時おそらく初めて日本語全訳された『碧巌録』である。
これは、雪竇(せっちょう)和尚が『伝燈録』から選んだ公案百則に頌(詩)をつけたテキストを作り、それに対して圜悟(えんご)和尚が解説と著語(じゃくご=ツッコミ)をくわえたノートの集録である。
つまり『碧巌録』は雪竇と圜悟の共同執筆なのであるが、ことはそう単純ではない。というのは、雪竇重顕(980年−1052年)と圜悟克勤(1063年−1135年)にはほぼ3世代の開きがあるからだ。
雪竇和尚が編集した公案百則に、3世代経って圜悟和尚が”超編集”を加えて出来たのが『碧巌録』なのである。その”超編集”ぶりを示すため、一則だけ例示しよう(なお、本来は一則につき、垂示(序論)[圜悟]、本則[雪竇]+著語[圜悟]、評唱(参考資料と解説)[圜悟]、頌古[雪竇]+著語[圜悟]、がセットになっているが、今本則+著語のみを引用する。なお本書では評唱は省略され、訳者による短い解説がそれに代わっている)。
第39則 雲門花薬欄 本則
挙。僧問雲門、如何是清浄法身。壒(*1)扱(*2)堆頭見丈六金身。斑斑駁駁是什麽。門云、花楽欄。問処不真答来鹵莽。祝(*3)著磕著。曲不蔵直。僧云、便恁麽去時如何。渾崙呑箇棗。放憨作麽。門云、金毛獅子。也褒也貶。両采一賽。将錯就錯。是什麽心行。
(*本来の漢字がPCで出せないため代字で表現した。*1「艹」不要、*2「扌」の代わりに「土」、*3 「祝」の下に「土」)
※黒字が雪竇による「本則」、青字が圜悟による「著語」。本書では「著語」は本文より小さい活字にすることで区別されている。
(日本語訳)
雲門大師のところへ、一人の僧がやって来て、「宇宙の本体ともいうべきビルシャナ仏とは、どんなかたですか」と尋ねた。ごみ捨て場の中に仏がいらっしゃるよ。きれい、きたない、いろいろなものが入り交じっているやつ、あれは何かね。雲門は、「便所の袖垣だよ」と答えた。質問がいい加減だから、答えもぞんざいだ。打てば響くようにぴったりだ。曲がったものは、曲がったままでよい。「それでは仰せのとおり、花薬欄は花薬欄と承知したら、どうなりましょうか」と、ひねくれた質問をした。こいつ雲門の答えをよく味わってもみず、丸呑みにしたな。うすぼんやりしていて、いい加減なことを問うたな。「獅子中の王者、禅僧中の禅僧とでもいうかな」と、雲門は答えた。上げたり、下げたりだな。花薬欄と金毛の獅子では同じ賽の目だな。雲門も僧もどっちもいかん。どういうつもりでいったのかな。
これを見れば、古来『碧巌録』が難解とされてきた理由が一目瞭然だろう。雪竇の編集した公案本体部分だけを見れば、その趣旨が理解できるかどうかは別として、なんとか読みこなせるものだろう。しかし圜悟がそこにツッコミの嵐を容赦なく加えており、しかもそれが口語調なものだから、ただでさえ文意があっちこっちしている上に日本人にとっては漢文として大変難しいのである。いや、読み下し文でこれを理解するのはほぼ不可能に近い。
しかし『碧巌録』が画期的だったのは、この圜悟のツッコミ部分だった。上の第39則でも、本文だけを見れば常人の理解を超越した何か高遠な問答のように見える。だが圜悟のツッコミも含めてみると、この問答はそれほど立派なものではなく、あまり噛み合っていない話であったことが理解できる。しかも圜悟のツッコミは、単に公案への対し方・味わい方を教えるだけでなく、公案に通底する禅の哲理を仄めかすものとなっているのである。
そもそも公案というものは、過去の偉大な禅匠たちの言行録で、有り難い教えが含まれていると考えられていた。臨済宗が依拠した「看話禅(かんなぜん)」というのは、公案の意味を考究する事によって悟りに至ろうとする禅のことであり、公案を悟りに至った事例と見なし非常に重視した。雪竇和尚が『碧巌録』の元となった公案百則を編集したのも、古来たくさん伝えられてきた公案(『伝燈録』1700則)から決定版的なものを百だけ選んで、その解読のヒントとして詩をつけたのである。
圜悟和尚は、それにツッコミの嵐を加える事によって、公案の意味を丸裸にしてしまった。それは、公案というものは自らの頭で考えることに意味があるのに、圜悟和尚のガイドによって公案が形無しになってしまったとも言えるし、公案集から神秘的なヴェールを剥ぎ、いたずらに公案を至上のものとする一種の思考停止に強烈な鉄槌を加えたとも言える。
そんなことで編集当時から『碧巌録』は毀誉褒貶が激しく、圜悟和尚の弟子大慧は『碧巌録』の版を焼き捨てたと言われる。また編集完成は1125年であったが、これが本格的に刊行されたのはなんと175年後の1300年であった(※1300年以前にも刊行はあったらしいが少部数だったのか残っていない)。そして、中国では『碧巌録』は、あまりにもわかりやす過ぎる禅籍として衝撃をもって迎えられ、大流行したのであった。
ところが日本では、『碧巌録』は難解な禅籍の代表のようになってしまった。先述の通り、『碧巌録』の本質である圜悟のツッコミが、中国語の口語体であるためかえって難しかったのである。そして、あたかも難解であることが『碧巌録』の価値であり、高遠さであると考えられてきた。現代ですら、「『碧巌録』に現代語訳を求めるなど邪道。難解な本文に直にあたってこそ意味がある」と考えている人は多い。しかし中国人がわかりやすい白話文(口語体)で禅を語り理解してきたのに、日本人がわざわざ難解な外国語を通してしか禅を理解できないなんてあるわけがないのである。
『碧巌録』を生き生きとした日本語訳によって表現した本書は画期的な訳業であり、日本の禅籍史に輝くものである。本書の刊行(1974年)より40年以上経過しているが、未だ『碧巌録』の日本語全訳は数えるほどしかない。とはいえ、本書の日本語訳は決定版とはいえない。刊行時点において『碧巌録』研究の集大成であると自負されてはいるものの、多数の訳者の共同作業であり、日本語訳の仕方も統一されていないからだ。読んだ感じとしても、明らかに訳者によって粗密を感じるところである。事実解説にも「歴史的・語学的な課題のすべてを今後に残すこととする。これが禅門の現状である」と記されている。なお分担は以下の通りである。
第1則ー第20則 苧坂光龍(般若道場)
第21則ー第40則 大森曹玄(鉄舟会)
第41則ー第60則 梶谷宗忍(相国僧堂)
第61則ー第80則 勝平宗徹(南禅僧堂)
第81則ー第100則 平田精耕(天龍僧堂)
『碧巌録』の初めての日本語訳として不朽の価値がある名著。
『碧巌録』は、「宗門第一の書」と呼ばれ日本の禅宗、特に臨済宗には多大な影響を与えてきた。また難解であることでも有名であり、古来多くの注釈・講釈の本が出版されてきた。しかし意外にも長く日本語訳されることがなく、本書は出版時おそらく初めて日本語全訳された『碧巌録』である。
これは、雪竇(せっちょう)和尚が『伝燈録』から選んだ公案百則に頌(詩)をつけたテキストを作り、それに対して圜悟(えんご)和尚が解説と著語(じゃくご=ツッコミ)をくわえたノートの集録である。
つまり『碧巌録』は雪竇と圜悟の共同執筆なのであるが、ことはそう単純ではない。というのは、雪竇重顕(980年−1052年)と圜悟克勤(1063年−1135年)にはほぼ3世代の開きがあるからだ。
雪竇和尚が編集した公案百則に、3世代経って圜悟和尚が”超編集”を加えて出来たのが『碧巌録』なのである。その”超編集”ぶりを示すため、一則だけ例示しよう(なお、本来は一則につき、垂示(序論)[圜悟]、本則[雪竇]+著語[圜悟]、評唱(参考資料と解説)[圜悟]、頌古[雪竇]+著語[圜悟]、がセットになっているが、今本則+著語のみを引用する。なお本書では評唱は省略され、訳者による短い解説がそれに代わっている)。
第39則 雲門花薬欄 本則
挙。僧問雲門、如何是清浄法身。壒(*1)扱(*2)堆頭見丈六金身。斑斑駁駁是什麽。門云、花楽欄。問処不真答来鹵莽。祝(*3)著磕著。曲不蔵直。僧云、便恁麽去時如何。渾崙呑箇棗。放憨作麽。門云、金毛獅子。也褒也貶。両采一賽。将錯就錯。是什麽心行。
(*本来の漢字がPCで出せないため代字で表現した。*1「艹」不要、*2「扌」の代わりに「土」、*3 「祝」の下に「土」)
※黒字が雪竇による「本則」、青字が圜悟による「著語」。本書では「著語」は本文より小さい活字にすることで区別されている。
(日本語訳)
雲門大師のところへ、一人の僧がやって来て、「宇宙の本体ともいうべきビルシャナ仏とは、どんなかたですか」と尋ねた。ごみ捨て場の中に仏がいらっしゃるよ。きれい、きたない、いろいろなものが入り交じっているやつ、あれは何かね。雲門は、「便所の袖垣だよ」と答えた。質問がいい加減だから、答えもぞんざいだ。打てば響くようにぴったりだ。曲がったものは、曲がったままでよい。「それでは仰せのとおり、花薬欄は花薬欄と承知したら、どうなりましょうか」と、ひねくれた質問をした。こいつ雲門の答えをよく味わってもみず、丸呑みにしたな。うすぼんやりしていて、いい加減なことを問うたな。「獅子中の王者、禅僧中の禅僧とでもいうかな」と、雲門は答えた。上げたり、下げたりだな。花薬欄と金毛の獅子では同じ賽の目だな。雲門も僧もどっちもいかん。どういうつもりでいったのかな。
これを見れば、古来『碧巌録』が難解とされてきた理由が一目瞭然だろう。雪竇の編集した公案本体部分だけを見れば、その趣旨が理解できるかどうかは別として、なんとか読みこなせるものだろう。しかし圜悟がそこにツッコミの嵐を容赦なく加えており、しかもそれが口語調なものだから、ただでさえ文意があっちこっちしている上に日本人にとっては漢文として大変難しいのである。いや、読み下し文でこれを理解するのはほぼ不可能に近い。
しかし『碧巌録』が画期的だったのは、この圜悟のツッコミ部分だった。上の第39則でも、本文だけを見れば常人の理解を超越した何か高遠な問答のように見える。だが圜悟のツッコミも含めてみると、この問答はそれほど立派なものではなく、あまり噛み合っていない話であったことが理解できる。しかも圜悟のツッコミは、単に公案への対し方・味わい方を教えるだけでなく、公案に通底する禅の哲理を仄めかすものとなっているのである。
そもそも公案というものは、過去の偉大な禅匠たちの言行録で、有り難い教えが含まれていると考えられていた。臨済宗が依拠した「看話禅(かんなぜん)」というのは、公案の意味を考究する事によって悟りに至ろうとする禅のことであり、公案を悟りに至った事例と見なし非常に重視した。雪竇和尚が『碧巌録』の元となった公案百則を編集したのも、古来たくさん伝えられてきた公案(『伝燈録』1700則)から決定版的なものを百だけ選んで、その解読のヒントとして詩をつけたのである。
圜悟和尚は、それにツッコミの嵐を加える事によって、公案の意味を丸裸にしてしまった。それは、公案というものは自らの頭で考えることに意味があるのに、圜悟和尚のガイドによって公案が形無しになってしまったとも言えるし、公案集から神秘的なヴェールを剥ぎ、いたずらに公案を至上のものとする一種の思考停止に強烈な鉄槌を加えたとも言える。
そんなことで編集当時から『碧巌録』は毀誉褒貶が激しく、圜悟和尚の弟子大慧は『碧巌録』の版を焼き捨てたと言われる。また編集完成は1125年であったが、これが本格的に刊行されたのはなんと175年後の1300年であった(※1300年以前にも刊行はあったらしいが少部数だったのか残っていない)。そして、中国では『碧巌録』は、あまりにもわかりやす過ぎる禅籍として衝撃をもって迎えられ、大流行したのであった。
ところが日本では、『碧巌録』は難解な禅籍の代表のようになってしまった。先述の通り、『碧巌録』の本質である圜悟のツッコミが、中国語の口語体であるためかえって難しかったのである。そして、あたかも難解であることが『碧巌録』の価値であり、高遠さであると考えられてきた。現代ですら、「『碧巌録』に現代語訳を求めるなど邪道。難解な本文に直にあたってこそ意味がある」と考えている人は多い。しかし中国人がわかりやすい白話文(口語体)で禅を語り理解してきたのに、日本人がわざわざ難解な外国語を通してしか禅を理解できないなんてあるわけがないのである。
『碧巌録』を生き生きとした日本語訳によって表現した本書は画期的な訳業であり、日本の禅籍史に輝くものである。本書の刊行(1974年)より40年以上経過しているが、未だ『碧巌録』の日本語全訳は数えるほどしかない。とはいえ、本書の日本語訳は決定版とはいえない。刊行時点において『碧巌録』研究の集大成であると自負されてはいるものの、多数の訳者の共同作業であり、日本語訳の仕方も統一されていないからだ。読んだ感じとしても、明らかに訳者によって粗密を感じるところである。事実解説にも「歴史的・語学的な課題のすべてを今後に残すこととする。これが禅門の現状である」と記されている。なお分担は以下の通りである。
第1則ー第20則 苧坂光龍(般若道場)
第21則ー第40則 大森曹玄(鉄舟会)
第41則ー第60則 梶谷宗忍(相国僧堂)
第61則ー第80則 勝平宗徹(南禅僧堂)
第81則ー第100則 平田精耕(天龍僧堂)
『碧巌録』の初めての日本語訳として不朽の価値がある名著。
2019年10月22日火曜日
『八幡神と神仏習合』逵 日出典 著
神仏習合を軸に八幡神の成立過程を述べる。
八幡神社というと、日本中どこでも見られるもので、神社の中では最も多いとも言われる。この八幡神社はどのようにして成立し、発展していったのか。本書はそれをほぼ時系列的に述べるものである。
その流れを大まかにまとめれば、(1)八幡神は新羅からの渡来人が祀った神が日本化してできたもので、(2)宇佐周辺で行われていた山岳信仰と一体となって発展し、(3)隼人の乱への征伐や大仏造立といったことに協力したことから朝廷との持ちつ持たれつの関係となって権威を得、(4)護国的な性格を持つ神社となって、また仏教とも融合して「護国霊験威力神通大自在菩薩」とまで称するようになり、(5)源頼朝が鎌倉に鶴岡八幡宮を勧請したことから武家にとって重要な神社となって全国に広がっていった。となるだろう。
この流れについて、本書は縦横に史料を駆使して述べており説得的である。しかし私が本書を手に取った動機は、宇佐八幡の荘園支配の実態がどのようなものであったのか、というもので、それについては本書はほとんど述べるところがない。
中世初期において、鹿児島の土地は島津庄と八幡宮領(八幡宮の荘園)で2分されており、九州の他の地方でも八幡宮領がかなり多かった。また八幡宮直轄領だけでなく、その神宮寺であった弥勒寺領となっていたところも多い。なぜ八幡宮はこのように広大な荘園を支配することができたのだろうか? 特に九州では、国衙の近くに八幡宮が勧請されることが多かったが、これは何を意味していたのだろうか。
また中世において、九州の二大権門は大宰府と宇佐八幡宮であるが、この二大権門はどのような関係だったのか。例えば、有名な宇佐八幡宮神託事件では、「道鏡を皇位に就けるべき」という最初の神託を伝えたのが大宰府の主神(かんづかさ:諸々の祭司を掌る)習宜阿曾麻呂(すげのあそまろ)であったが、なぜ大宰府の役人が宇佐八幡宮の託宣を表明することができたのか。
さらに宇佐八幡宮神託事件では、「皇族でない人間を皇位に就けるべきではない」という趣旨の第二の神託を持ち帰った和気清麻呂が処分されるわけだが、これは宇佐八幡の神託が恣意的なものと考えられていたことを示しているのではないだろうか。もし実際に神託が出て清麻呂がそれを持ち帰っただけなのであれば、清麻呂自身には責任があろうはずもないからである。つまり宇佐八幡の神託は、作為的なものと考えられていながら、やはり権威を持っていた。それが不思議なのである。宇佐八幡宮神託事件自体が『続日本紀』の作為であるという説もあるが、であるにしても、宇佐八幡が持つ意味について考えさせられる事件である。本書ではこうしたことについて全く考察はないが、非常に気になった。
また本書では、八幡神の発展が日本の神仏習合を先導していたと述べており、神仏習合現象についての説明もかなり丁寧である。事実、八幡神は「八幡大菩薩」として親しまれ、僧形によって表現されるようになったのであるが、ここも疑問に思った。なぜ八幡神は「大菩薩」なのにもかかわらず僧形なのだろうか。素直に考えれば菩薩形であるべきなのに、どうして僧形とされたのか謎で、これも本書には全く考察がない。
本書は、八幡神の思想的発展については丁寧に記述するものの、それに対する考察はあまり充実しておらず、荘園経営や社殿造営などの実務面についてはほとんど触れていない。入門書としては当然かもしれないが、そこは少し残念だった。
八幡神を巡る種々の謎についてはあまり解きほぐされないが、史実を実直に辿れる八幡神入門書。
【関連書籍】
『神仏習合』逵 日出典 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html
神仏習合の概略的な説明。
八幡神社というと、日本中どこでも見られるもので、神社の中では最も多いとも言われる。この八幡神社はどのようにして成立し、発展していったのか。本書はそれをほぼ時系列的に述べるものである。
その流れを大まかにまとめれば、(1)八幡神は新羅からの渡来人が祀った神が日本化してできたもので、(2)宇佐周辺で行われていた山岳信仰と一体となって発展し、(3)隼人の乱への征伐や大仏造立といったことに協力したことから朝廷との持ちつ持たれつの関係となって権威を得、(4)護国的な性格を持つ神社となって、また仏教とも融合して「護国霊験威力神通大自在菩薩」とまで称するようになり、(5)源頼朝が鎌倉に鶴岡八幡宮を勧請したことから武家にとって重要な神社となって全国に広がっていった。となるだろう。
この流れについて、本書は縦横に史料を駆使して述べており説得的である。しかし私が本書を手に取った動機は、宇佐八幡の荘園支配の実態がどのようなものであったのか、というもので、それについては本書はほとんど述べるところがない。
中世初期において、鹿児島の土地は島津庄と八幡宮領(八幡宮の荘園)で2分されており、九州の他の地方でも八幡宮領がかなり多かった。また八幡宮直轄領だけでなく、その神宮寺であった弥勒寺領となっていたところも多い。なぜ八幡宮はこのように広大な荘園を支配することができたのだろうか? 特に九州では、国衙の近くに八幡宮が勧請されることが多かったが、これは何を意味していたのだろうか。
また中世において、九州の二大権門は大宰府と宇佐八幡宮であるが、この二大権門はどのような関係だったのか。例えば、有名な宇佐八幡宮神託事件では、「道鏡を皇位に就けるべき」という最初の神託を伝えたのが大宰府の主神(かんづかさ:諸々の祭司を掌る)習宜阿曾麻呂(すげのあそまろ)であったが、なぜ大宰府の役人が宇佐八幡宮の託宣を表明することができたのか。
さらに宇佐八幡宮神託事件では、「皇族でない人間を皇位に就けるべきではない」という趣旨の第二の神託を持ち帰った和気清麻呂が処分されるわけだが、これは宇佐八幡の神託が恣意的なものと考えられていたことを示しているのではないだろうか。もし実際に神託が出て清麻呂がそれを持ち帰っただけなのであれば、清麻呂自身には責任があろうはずもないからである。つまり宇佐八幡の神託は、作為的なものと考えられていながら、やはり権威を持っていた。それが不思議なのである。宇佐八幡宮神託事件自体が『続日本紀』の作為であるという説もあるが、であるにしても、宇佐八幡が持つ意味について考えさせられる事件である。本書ではこうしたことについて全く考察はないが、非常に気になった。
また本書では、八幡神の発展が日本の神仏習合を先導していたと述べており、神仏習合現象についての説明もかなり丁寧である。事実、八幡神は「八幡大菩薩」として親しまれ、僧形によって表現されるようになったのであるが、ここも疑問に思った。なぜ八幡神は「大菩薩」なのにもかかわらず僧形なのだろうか。素直に考えれば菩薩形であるべきなのに、どうして僧形とされたのか謎で、これも本書には全く考察がない。
本書は、八幡神の思想的発展については丁寧に記述するものの、それに対する考察はあまり充実しておらず、荘園経営や社殿造営などの実務面についてはほとんど触れていない。入門書としては当然かもしれないが、そこは少し残念だった。
八幡神を巡る種々の謎についてはあまり解きほぐされないが、史実を実直に辿れる八幡神入門書。
【関連書籍】
『神仏習合』逵 日出典 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html
神仏習合の概略的な説明。
2019年10月20日日曜日
『一遍と時衆の謎—時宗史を読み解く』桜井 哲夫 著
一遍と時衆についてのこれまでの研究のまとめ。
著者の桜井哲夫は近現代ヨーロッパを主な対象とする社会学者であり、時衆については専門外である。が同時に時宗寺院の住職であって、その立場からまとめたのが本書である。よって本書は、著者自身の研究というよりも、これまでの時衆研究を概観してみようというものである。
本書は2部に分かれており、第1部は時衆とは何かということが様々なトピックから紐解かれている。先行研究が縦横に紹介されているので初学者には有り難いが、一方で「○○はこう言っている」という形で様々なことが雑然と語られているという側面もあり、時衆の全体像はやや摑みにくい。
個人的に気になったのは、時衆僧侶は「陣僧」として戦に同行して戦没者の葬儀を執り行っており、それが賦役として課されていたという点。本書では簡単に書いているが、時衆の性格を考察する上で重要だと思われる。
そもそも私が時衆に興味を抱いたのも、葬送との関連であった。中世の葬制が整っていくにあたり、大きな役割を果たしたのは禅宗であり、またそれを武士階級から一般まで普及させていったのは律宗の影響が大きいらしい。しかしその背景として、時衆の存在が非常に気にかかるのである。葬送は言うまでもなく死体を扱うので、当時(中世初期)には穢れの問題がやかましかった。そんな中で、「浄不浄を問わず」としていた時衆はかなり葬儀に関わっていたらしく、また実際に陣僧として活躍していたことを踏まえると、葬制の確立において時衆の果たした役割は大きいと考えられている。非人と時衆の関係がその核にあるのではないかという気がした。こうしたことについて本書ではほとんど触れられていないが、ここはさらに知りたいところである。
この他にも、江戸時代には時衆は遊行にかなり便宜を与えられていたということ、能などの芸道において時衆(と考えられている人)が活躍していたらしいということ、高野聖は時衆が吸収してしまったらしいということなど、様々な点が興味深かった。また、蓮如による浄土真宗の改革が真宗の時衆化ではなかったのかという指摘は面白かった。中世において時衆は非常に隆盛し、多くの信者を獲得したものの、蓮如によって浄土真宗が興隆してゆくと時衆は不思議と衰微していく。これは時衆の徒が浄土真宗に吸収されていった結果であると考えられる。確かに親鸞の浄土真宗は非常に学理的であるが、蓮如の浄土真宗は明解で庶民的であり、時衆風なのである。
第2部では、『一遍聖絵』に基づいて一遍の生涯を紹介している。『一遍聖絵』の研究と、一遍の伝記的研究が同時に扱われているので、こちらもやや煩瑣な部分があるが、時系列的になっている分、第1部に比べるとすっきりしている。
伝記的部分で気になったのは、一遍は神祇不拝ではなくむしろ積極的に神社等に参拝したということや、往生の際の奇瑞を信用せず、そうした奇跡的な現象を迷信だと退けていたという点である。時衆は教義らしい教義を持たない宗派であるとされることもあり、事実一遍は一冊の著書も残さなかったが(入寂の前に焼き捨てた)、彼が残した和歌を見ると宗教家としての思想が感じられる。
おのづから あひあうときも わかれても ひとりはおなじ ひとりなりけり
時衆は集団で念仏踊りに狂う宗派であったのは事実である。その興奮は時として入水往生(入水自殺)をも伴った。時衆教団はいつも「南無阿弥陀仏」の集団的熱狂を伴っていた。しかしその中心の一遍は、いつでも孤独を抱えていたのかもしれない。
先行研究の紹介は煩瑣でもあるが、中世において大きな存在感のある時衆について手軽に学べる本。
著者の桜井哲夫は近現代ヨーロッパを主な対象とする社会学者であり、時衆については専門外である。が同時に時宗寺院の住職であって、その立場からまとめたのが本書である。よって本書は、著者自身の研究というよりも、これまでの時衆研究を概観してみようというものである。
本書は2部に分かれており、第1部は時衆とは何かということが様々なトピックから紐解かれている。先行研究が縦横に紹介されているので初学者には有り難いが、一方で「○○はこう言っている」という形で様々なことが雑然と語られているという側面もあり、時衆の全体像はやや摑みにくい。
個人的に気になったのは、時衆僧侶は「陣僧」として戦に同行して戦没者の葬儀を執り行っており、それが賦役として課されていたという点。本書では簡単に書いているが、時衆の性格を考察する上で重要だと思われる。
そもそも私が時衆に興味を抱いたのも、葬送との関連であった。中世の葬制が整っていくにあたり、大きな役割を果たしたのは禅宗であり、またそれを武士階級から一般まで普及させていったのは律宗の影響が大きいらしい。しかしその背景として、時衆の存在が非常に気にかかるのである。葬送は言うまでもなく死体を扱うので、当時(中世初期)には穢れの問題がやかましかった。そんな中で、「浄不浄を問わず」としていた時衆はかなり葬儀に関わっていたらしく、また実際に陣僧として活躍していたことを踏まえると、葬制の確立において時衆の果たした役割は大きいと考えられている。非人と時衆の関係がその核にあるのではないかという気がした。こうしたことについて本書ではほとんど触れられていないが、ここはさらに知りたいところである。
この他にも、江戸時代には時衆は遊行にかなり便宜を与えられていたということ、能などの芸道において時衆(と考えられている人)が活躍していたらしいということ、高野聖は時衆が吸収してしまったらしいということなど、様々な点が興味深かった。また、蓮如による浄土真宗の改革が真宗の時衆化ではなかったのかという指摘は面白かった。中世において時衆は非常に隆盛し、多くの信者を獲得したものの、蓮如によって浄土真宗が興隆してゆくと時衆は不思議と衰微していく。これは時衆の徒が浄土真宗に吸収されていった結果であると考えられる。確かに親鸞の浄土真宗は非常に学理的であるが、蓮如の浄土真宗は明解で庶民的であり、時衆風なのである。
第2部では、『一遍聖絵』に基づいて一遍の生涯を紹介している。『一遍聖絵』の研究と、一遍の伝記的研究が同時に扱われているので、こちらもやや煩瑣な部分があるが、時系列的になっている分、第1部に比べるとすっきりしている。
伝記的部分で気になったのは、一遍は神祇不拝ではなくむしろ積極的に神社等に参拝したということや、往生の際の奇瑞を信用せず、そうした奇跡的な現象を迷信だと退けていたという点である。時衆は教義らしい教義を持たない宗派であるとされることもあり、事実一遍は一冊の著書も残さなかったが(入寂の前に焼き捨てた)、彼が残した和歌を見ると宗教家としての思想が感じられる。
おのづから あひあうときも わかれても ひとりはおなじ ひとりなりけり
時衆は集団で念仏踊りに狂う宗派であったのは事実である。その興奮は時として入水往生(入水自殺)をも伴った。時衆教団はいつも「南無阿弥陀仏」の集団的熱狂を伴っていた。しかしその中心の一遍は、いつでも孤独を抱えていたのかもしれない。
先行研究の紹介は煩瑣でもあるが、中世において大きな存在感のある時衆について手軽に学べる本。
2019年10月14日月曜日
『日本宗教史』末木 文美士 著
古代から現代に到る日本宗教史を概観する本。
本書の対象とする範囲は非常に広く、新書という形式で記述するには無謀なほどである。そのため細かいことは省き、梗概のみの記載に留めている事項も散見され、古代から中世にかけては特に簡略である。このあたりは分量的には2倍くらい欲しかったのが正直なところである。
逆に近世以降の神道論の展開には、結構紙幅を割いているようだった。著者の専門は言うまでもなく仏教の方にあるが、神道論の展開を丁寧に扱っているのが意外であり好感を持った。
一方で、七福神信仰とか観音・地蔵信仰、庚申講といった近世の民衆的な宗教ムーブメントについては全く記載がなく、やや物足りなく感じたのも事実である。
要するに、本書は日本宗教史を描くにあたり、年表的な事実を教科書的にまとめているというよりも、著者なりの視点で大胆に取捨選択がなされているのである。そして「選択」された部分については割合に丁寧に描かれる。であるから、事実の羅列的な部分はほとんどなく、宗教史が一筋の流れとして理解でき、非常に平易である。著者自身が後書きで本書を評して「試論」「たたき台」「大胆な挑戦の書」と述べているように、決定版とはいえない本だが、本書を刺激として様々な考察を広げてゆく可能性を感じさせる本である。
なお、本書は「<古層>の形成・発見」を大きなテーマとしている。精神的変革が求められる時代にあたって、日本人は多くの場合<古層>を参照し、<古層>に返るというスタンスで革新を成し遂げてきた。しかしその<古層>自体が、歴史的事実としての古思想・文化ではなくて、「そうあるはずだった過去」として形成されたものであったというのである。これは各時代で検証しなくてはならない主張なので、妥当なのかどうかは私には判断できないが、著者はなんでもかんでも<古層>を牽強付会しようとはしていないので、読んでいてあまり違和感はなかった。とはいえそれが斬新な視点であるとも思えず、テーマとしての「<古層>の形成・発見」にはさほど魅力を感じなかったというのが正直な感想である。
「<古層>の形成・発見」はピンと来ないが、日本宗教史の詩論として価値ある本。
本書の対象とする範囲は非常に広く、新書という形式で記述するには無謀なほどである。そのため細かいことは省き、梗概のみの記載に留めている事項も散見され、古代から中世にかけては特に簡略である。このあたりは分量的には2倍くらい欲しかったのが正直なところである。
逆に近世以降の神道論の展開には、結構紙幅を割いているようだった。著者の専門は言うまでもなく仏教の方にあるが、神道論の展開を丁寧に扱っているのが意外であり好感を持った。
一方で、七福神信仰とか観音・地蔵信仰、庚申講といった近世の民衆的な宗教ムーブメントについては全く記載がなく、やや物足りなく感じたのも事実である。
要するに、本書は日本宗教史を描くにあたり、年表的な事実を教科書的にまとめているというよりも、著者なりの視点で大胆に取捨選択がなされているのである。そして「選択」された部分については割合に丁寧に描かれる。であるから、事実の羅列的な部分はほとんどなく、宗教史が一筋の流れとして理解でき、非常に平易である。著者自身が後書きで本書を評して「試論」「たたき台」「大胆な挑戦の書」と述べているように、決定版とはいえない本だが、本書を刺激として様々な考察を広げてゆく可能性を感じさせる本である。
なお、本書は「<古層>の形成・発見」を大きなテーマとしている。精神的変革が求められる時代にあたって、日本人は多くの場合<古層>を参照し、<古層>に返るというスタンスで革新を成し遂げてきた。しかしその<古層>自体が、歴史的事実としての古思想・文化ではなくて、「そうあるはずだった過去」として形成されたものであったというのである。これは各時代で検証しなくてはならない主張なので、妥当なのかどうかは私には判断できないが、著者はなんでもかんでも<古層>を牽強付会しようとはしていないので、読んでいてあまり違和感はなかった。とはいえそれが斬新な視点であるとも思えず、テーマとしての「<古層>の形成・発見」にはさほど魅力を感じなかったというのが正直な感想である。
「<古層>の形成・発見」はピンと来ないが、日本宗教史の詩論として価値ある本。
2019年10月13日日曜日
『列島を翔ける平安武士—九州・京都・東国』野口 実 著
平安時代から鎌倉時代にかけての武士のネットワークを南九州にフォーカスして述べる。
鎌倉時代の武士というと、開発領主としての性格が強く、「一所懸命」という言葉に象徴されるように土地との結びつきが強固であった。彼らはその本拠地の地名を名字にし、土地を自らのアイデンティティとしていた。その土地のことを「本貫」とか「名字の地」という。それくらい、武士にとって土地は本質的なものであった。しかし一方で、戦国大名などとは違い、中世の武士はその本拠地からかなり遠方にも領地を持ち、遠隔地の荘園経営を行ってもいたのである。
南九州のような僻遠の地も、決して孤立的な地域だったのではなく、むしろ大陸や南島との交易での利益が期待できる有利な土地として武士や貴族たちの手を転がされていた。本書は、藤原保晶、平為賢と平季基、阿多忠景と源為朝、千葉常胤と島津忠久などを中心として、南九州と京都、鎌倉の関係性やネットワークを事例から検証するものである。
武士たちの社会的正統性は天皇(国家)を警護することにあったので、長期間京都に勤務する必要があった。そのため彼らは京都で上級の貴族との結びつきを作ることができ、また京都在勤の他の地域の武士との横の繋がりも持つことができた。そしてもちろん御家人にとっては鎌倉も重要な土地だった。本貫の地、京都、鎌倉、そして遠方の所領と、彼らは意外と活発に移動し、全国規模のネットワークを構築していたのである。
また本書は、島津庄(しまづのしょう)の成立と発展がもう一つのテーマとなっており、それを通して武士たちのネットワークを垣間見させるものとなっている。
島津庄の起源は、大宰府の大監であった平季基(すえもと)が島津院を中心とした地域を宇治関白家(藤原頼道)へ万寿年間(1024〜1028年)に寄進したことにある。それは今の都城市あたりだったが、そこは日向国府から大隅国府に向かう官道が通じ、大陸や南島との交易の拠点であった志布志へも通じる交通の要衝であり、農業生産というよりも当初から交易を念頭にして設置されたものだったらしい。
史料上では、季基は「無主の荒野」を開墾して寄進したとなっているが、実際の立荘の担い手は在地勢力で、彼らが季基の威勢を頼り、さらに季基が上級の権威を頼って摂関家へ寄進したというのが実状と見られる。この頃、大宰府に属する軍事貴族の南九州への進出が顕著であったらしく、島津庄の場合も、大宰府の権威を基盤として立荘されたといえる。
こうして設立された島津庄は、やがて薩摩・大隅にまで拡大され、12世紀後半には8000町歩もの日本最大の荘園に成長する。その領主は摂関家に相伝され、南方交易からもたらされる「夜光貝」「檳榔毛(びんろうげ)」など、並の貴族では手に入れられない贅沢品を手に入れるルートになった。だが、藤原基実(もとざね)が若くして急死したことでその妻が相続。この妻が平清盛の娘の盛子で、こうして島津庄は平家の支配下に入ることになる。
なお平季基の子孫は大宰府に基盤を確保しつつ肥前国で領主的な発展を遂げ、太宰府領を基盤として薩摩国に進出。そして河辺氏、頴娃氏、鹿児島氏といった郡名を姓とする「薩摩平氏」という有力在地勢力の一族に成長した。
その中でも有名なのが阿多忠景(ただかげ)である。阿多忠景は阿多郡(現南さつま市金峰町)の郡司職を梃子に国務に参与して「一国惣領」、つまり薩摩国全体を手中に収めた。その力の源泉となったのが、おそらくは万之瀬川河口を利用した大陸・南島との交易であって、それを裏付けるように河口の持躰松(もったいまつ)遺跡からは博多以外では他に類を見ないほどの大陸製陶磁器や国内産陶磁器が出土している。こうした交易からは莫大な利益が上がったものと見られ、阿多忠景は「成功(じょうごう)」、すなわち売官によって下野権守(しもうさごんのかみ)の官職を手に入れてのし上がったのである。
しかも忠景は、中央政界との結びつきをより強固にする意図があったと思われるが、鎮西(九州)に威を奮った源為朝を娘の婿に迎えている。こうして阿多忠景は為朝とのコンビで南九州に強大な勢力を誇った。しかし源為朝は保元の乱で敗れ、忠景は勅勘を蒙って平家の有力家人である筑後守平家貞(いえさだ)の追討を受けて没落し、その領地も平家の勢力下に入った。
時代が源平合戦の頃に移ると、南九州の勢力図も激変が生じる。鎌倉幕府設立の功労者である千葉常胤(本貫は房総半島)が九州に侵攻し、その侵略範囲を領地化していったからだ。南九州では現薩摩川内市や伊佐市にあたる北薩の地域の地頭が千葉常胤となった。また島津庄には、地頭として惟宗忠久(これむね・ただひさ)が任命される。これが島津氏の祖である。
惟宗忠久は、元来は摂関家たる近衛家の下家司(しもけいし)であり、つまり近衛家の職務に与る一介の京侍に過ぎず、今で言えば単なる下級役人であったと思われ、元来の頼朝の御家人ではなかった。それが島津庄という大荘園の地頭にいきなり抜擢されたのは、どういうわけか。
史料上ではその実状は不明であるが、状況証拠としては、忠久は近衛家の家臣であるとともに、頼朝の乳母(比企尼)の縁者であったと見られる。つまり島津庄という日本一の荘園を領主である近衛家ともめ事を起こさずに幕府の支配下に置くため、双方に関係を有する忠久を京都からスカウトして御家人とし地頭にしたのではないか、というのが著者の考えである。ともかく忠久はこうして本貫を島津庄と定めて「島津」姓とし、南九州の三国(薩摩・大隅・日向)を支配する島津氏の始まりとなったのである。
これまでの島津庄成立史を振り返ってみて思うのは、南九州は僻遠の地でありながら、大宰府や中央勢力の政治的力学が非常に強く影響しているということである。仮に南九州が孤立的地域であれば、そこには中央政府とは何の関係も持たない、力によって支配を打ち立てた勢力が盤踞していてもおかしくないのであるが、実際には中央政府と強いパイプを持つ人物が、公的な力を持って勢力を確立しているという感じが強いのである。中世の南九州は、荒くれ者たちが力で支配を競った無法地帯ではなかった。
中世の武士というと、忠義といった江戸時代的な固定関係の思想がなく、実利によって動く武力を頼みにする存在、といったイメージが強いが、それは物事の一面でしかない。むしろ実利を重視するがゆえに、中央政府の威光や貴顕の人物との縁戚関係を最大限に利用し、最小限の武力によって世を渡り歩いたということだったのかもしれない。事実、鎌倉時代における南九州の覇者である惟宗忠久は、一切軍功がない。彼は一兵をも動かすことなく島津庄を手に入れているのである。
すなわち、武士は意外と「政治的存在」であった。いや、この時代は後世とは違って世襲的階級としての「武士」は存在していないのである。「武士」と呼ばれた人々は、もちろん武力も行使したが、別の面では政治家であり、農地の開発領主であり、また交易を担う商人でもあった。そういう多様な側面を持つ存在として、日本全国にわたるネットワークと政治力を活用していたのである。
島津庄の歴史を繙くことで中世の武士像の修正を促す本。
鎌倉時代の武士というと、開発領主としての性格が強く、「一所懸命」という言葉に象徴されるように土地との結びつきが強固であった。彼らはその本拠地の地名を名字にし、土地を自らのアイデンティティとしていた。その土地のことを「本貫」とか「名字の地」という。それくらい、武士にとって土地は本質的なものであった。しかし一方で、戦国大名などとは違い、中世の武士はその本拠地からかなり遠方にも領地を持ち、遠隔地の荘園経営を行ってもいたのである。
南九州のような僻遠の地も、決して孤立的な地域だったのではなく、むしろ大陸や南島との交易での利益が期待できる有利な土地として武士や貴族たちの手を転がされていた。本書は、藤原保晶、平為賢と平季基、阿多忠景と源為朝、千葉常胤と島津忠久などを中心として、南九州と京都、鎌倉の関係性やネットワークを事例から検証するものである。
武士たちの社会的正統性は天皇(国家)を警護することにあったので、長期間京都に勤務する必要があった。そのため彼らは京都で上級の貴族との結びつきを作ることができ、また京都在勤の他の地域の武士との横の繋がりも持つことができた。そしてもちろん御家人にとっては鎌倉も重要な土地だった。本貫の地、京都、鎌倉、そして遠方の所領と、彼らは意外と活発に移動し、全国規模のネットワークを構築していたのである。
また本書は、島津庄(しまづのしょう)の成立と発展がもう一つのテーマとなっており、それを通して武士たちのネットワークを垣間見させるものとなっている。
島津庄の起源は、大宰府の大監であった平季基(すえもと)が島津院を中心とした地域を宇治関白家(藤原頼道)へ万寿年間(1024〜1028年)に寄進したことにある。それは今の都城市あたりだったが、そこは日向国府から大隅国府に向かう官道が通じ、大陸や南島との交易の拠点であった志布志へも通じる交通の要衝であり、農業生産というよりも当初から交易を念頭にして設置されたものだったらしい。
史料上では、季基は「無主の荒野」を開墾して寄進したとなっているが、実際の立荘の担い手は在地勢力で、彼らが季基の威勢を頼り、さらに季基が上級の権威を頼って摂関家へ寄進したというのが実状と見られる。この頃、大宰府に属する軍事貴族の南九州への進出が顕著であったらしく、島津庄の場合も、大宰府の権威を基盤として立荘されたといえる。
こうして設立された島津庄は、やがて薩摩・大隅にまで拡大され、12世紀後半には8000町歩もの日本最大の荘園に成長する。その領主は摂関家に相伝され、南方交易からもたらされる「夜光貝」「檳榔毛(びんろうげ)」など、並の貴族では手に入れられない贅沢品を手に入れるルートになった。だが、藤原基実(もとざね)が若くして急死したことでその妻が相続。この妻が平清盛の娘の盛子で、こうして島津庄は平家の支配下に入ることになる。
なお平季基の子孫は大宰府に基盤を確保しつつ肥前国で領主的な発展を遂げ、太宰府領を基盤として薩摩国に進出。そして河辺氏、頴娃氏、鹿児島氏といった郡名を姓とする「薩摩平氏」という有力在地勢力の一族に成長した。
その中でも有名なのが阿多忠景(ただかげ)である。阿多忠景は阿多郡(現南さつま市金峰町)の郡司職を梃子に国務に参与して「一国惣領」、つまり薩摩国全体を手中に収めた。その力の源泉となったのが、おそらくは万之瀬川河口を利用した大陸・南島との交易であって、それを裏付けるように河口の持躰松(もったいまつ)遺跡からは博多以外では他に類を見ないほどの大陸製陶磁器や国内産陶磁器が出土している。こうした交易からは莫大な利益が上がったものと見られ、阿多忠景は「成功(じょうごう)」、すなわち売官によって下野権守(しもうさごんのかみ)の官職を手に入れてのし上がったのである。
しかも忠景は、中央政界との結びつきをより強固にする意図があったと思われるが、鎮西(九州)に威を奮った源為朝を娘の婿に迎えている。こうして阿多忠景は為朝とのコンビで南九州に強大な勢力を誇った。しかし源為朝は保元の乱で敗れ、忠景は勅勘を蒙って平家の有力家人である筑後守平家貞(いえさだ)の追討を受けて没落し、その領地も平家の勢力下に入った。
時代が源平合戦の頃に移ると、南九州の勢力図も激変が生じる。鎌倉幕府設立の功労者である千葉常胤(本貫は房総半島)が九州に侵攻し、その侵略範囲を領地化していったからだ。南九州では現薩摩川内市や伊佐市にあたる北薩の地域の地頭が千葉常胤となった。また島津庄には、地頭として惟宗忠久(これむね・ただひさ)が任命される。これが島津氏の祖である。
惟宗忠久は、元来は摂関家たる近衛家の下家司(しもけいし)であり、つまり近衛家の職務に与る一介の京侍に過ぎず、今で言えば単なる下級役人であったと思われ、元来の頼朝の御家人ではなかった。それが島津庄という大荘園の地頭にいきなり抜擢されたのは、どういうわけか。
史料上ではその実状は不明であるが、状況証拠としては、忠久は近衛家の家臣であるとともに、頼朝の乳母(比企尼)の縁者であったと見られる。つまり島津庄という日本一の荘園を領主である近衛家ともめ事を起こさずに幕府の支配下に置くため、双方に関係を有する忠久を京都からスカウトして御家人とし地頭にしたのではないか、というのが著者の考えである。ともかく忠久はこうして本貫を島津庄と定めて「島津」姓とし、南九州の三国(薩摩・大隅・日向)を支配する島津氏の始まりとなったのである。
これまでの島津庄成立史を振り返ってみて思うのは、南九州は僻遠の地でありながら、大宰府や中央勢力の政治的力学が非常に強く影響しているということである。仮に南九州が孤立的地域であれば、そこには中央政府とは何の関係も持たない、力によって支配を打ち立てた勢力が盤踞していてもおかしくないのであるが、実際には中央政府と強いパイプを持つ人物が、公的な力を持って勢力を確立しているという感じが強いのである。中世の南九州は、荒くれ者たちが力で支配を競った無法地帯ではなかった。
中世の武士というと、忠義といった江戸時代的な固定関係の思想がなく、実利によって動く武力を頼みにする存在、といったイメージが強いが、それは物事の一面でしかない。むしろ実利を重視するがゆえに、中央政府の威光や貴顕の人物との縁戚関係を最大限に利用し、最小限の武力によって世を渡り歩いたということだったのかもしれない。事実、鎌倉時代における南九州の覇者である惟宗忠久は、一切軍功がない。彼は一兵をも動かすことなく島津庄を手に入れているのである。
すなわち、武士は意外と「政治的存在」であった。いや、この時代は後世とは違って世襲的階級としての「武士」は存在していないのである。「武士」と呼ばれた人々は、もちろん武力も行使したが、別の面では政治家であり、農地の開発領主であり、また交易を担う商人でもあった。そういう多様な側面を持つ存在として、日本全国にわたるネットワークと政治力を活用していたのである。
島津庄の歴史を繙くことで中世の武士像の修正を促す本。
2019年10月9日水曜日
『死者たちの中世』勝田 至 著
中世、多くの死者が墓地に葬られるようになる背景を説き明かす本。
平安末期、京都には日常的に死体が放置されていた。貴族の屋敷や内裏においてさえ、野犬が死体の一部を置いていくことが珍しくなかった。当時は死の穢れが神経質に避けられていたから、屋敷で死体の一部がみつかれば「五体不具穢(ごたいふぐえ)」となって、7日間の出仕停止(謹慎)が必要であった(※この「五体不具」は、死体の一部によるという意味)。彼らは死体が見つかった気味の悪さや死者への弔いの気持ちよりも、7日間の謹慎を食らうことを気にしており、日記に書き留めた(ちなみに全身死体の場合は30日の謹慎だった)。それが仕事に影響することだったからだ。
よって、貴族の日記にはたびたび遺棄された死体のことが記録された。著者は、その記録を詳細に分析し、12世紀には「五体不具穢」などの記事が頻繁に出てくるのに、13世紀前半にそうした記事が急減することを突き止めた。12世紀の京都では死体放置・遺棄が日常的であったが、13世紀前半にはあまり死体は放置されなくなり、14世紀には稀な出来事になっていた。これはどうしてなのだろうか? それが本書の問題提起であり、この謎解きが本書のテーマである。
そもそも、なぜ死体は放置されていたのだろうか。それにはいくつか理由があった。
第1に、死者の葬送はほとんど親族しか携わることができなかった。その背景には死の穢れへの懼れ・忌みがあったと思われる。このため、肉親が少ない人は死を目前にすると自ら(!)葬所へ赴いたりした。また家の中で家族の死体が放置されていることもよくあった。死体が重すぎて女一人では移動させられなかった場合などだ。つまり葬送は、あくまで家族が自力でやるもので地域社会はこれに協力しなかった。
第2に、当時は鳥葬が行われていた。貴族や財力のある人は火葬を行うことが出来たが、火葬にはかなりお金がかかった。よって河原や山に死体を放置することにはそれほど抵抗感はなかった。鳥葬は山野で行う方が好ましいとは思われていたが、死体をそこまで運んでいくのも一苦労だったので、荒廃した貴族の屋敷地やそのあたりの空き地に死体を置いておくのも珍しくはなかった。そもそも低層の人々にとって、死体の遺棄と鳥葬の間には明確な線がなかったと思われる。
第3に、使用人が病気になり死にそうになると家を追い出すことが一般的に行われていた。もし家の中で使用人が病死すれば、死穢によって30日間の謹慎になるからである。今から見ると非人道的と言うほかないが、こうして死に瀕した病人が追い出され、路傍で死んだ。
こうした理由から、疫病が流行した時には当然河原には死体が溢れ、そうでなくても京都には若干の死体が放置されていることは珍しくなかった。もちろん国家はそれを好ましいものとはせず、検非違使に死体清掃のパトロールをさせることはあったが、それも何か行事がある時に限られ、積極的にこれを対策しようという気はなかったようだ。死の穢れを神経質なまでに気にしていたのに、「開放空間(道路や広場)にある死体の穢れは伝染しない」というような屁理屈で街中の死体を黙認していたのが平安朝であった。
それがなぜ13世紀前半に放置死体は急減するのか。その謎を解くため、本書では当時の葬送がどうであったかをまとめている。死の直前から年忌法要に至るまでの各段階における儀礼がこれまでの研究に基づいて整理されており、この項目は大変参考になり、便覧としても便利である。
その中でも火葬場の様子が興味深い。この頃は常設の火葬場はなく、そのたびごとに火葬場(「山作所」という)をしつらえていたが、上級の人々の場合、その形式は、荒垣で囲んで四方に鳥居で門を設けるものだった。四門はそれぞれ発心門、修行門、菩提門、涅槃門と呼ばれていた。門の名前だけでなく葬送儀礼全体が仏式で行われながら、「鳥居」が使われているのが面白い。やや時代は下るが天文5年(1536年)制作の『日蓮聖人註画讃』にはその様子が描かれており、仏式の場に鳥居が並んでいるのが奇異である。なぜ仏教は葬送の場において鳥居を必要としたのだろうか。大変興味を引かれる。
なお葬儀には死霊を恐れ、その害を避ける儀式が多いが、「貴族はそれを行いつつも「世俗の忌」として否定的に見ているようである(p.123)」という指摘が目を引いた。貴族は死霊を実体として扱うことを迷信的と思っていた節がある。「貴族は葬送のやり方を詳細に日記に書いているが、個々の儀礼について、死霊や魔がどうとかは一言半句も書いていない。(中略)彼らはそういう解釈を系統的に排除しているような感じがする(同)」とのことである。しかし死霊を避ける儀礼(出棺後に竹箒で掃くなど)は徐々に貴族社会にも浸透し、12世紀中期からは「世俗の忌」的儀礼が取り入れられるようになる。普通、文化は上流から下流に伝わっていくが、この時代の葬送儀礼に関しては民衆的な「俗信」が貴族社会に逆流していく感じがする。
葬送儀礼は全体として、鎌倉時代にかけて整備が進んでくる感じである。また散発的・個別的だった墓地(その都度適当な山野を選んで墓を作っていた)が12世紀後半になると全国的に広域の共同墓地が営まれるようになってくる。京都では、「鳥辺野」に加え「蓮台野」という墓地が12世紀中頃に成立している。また墓地が一門の繁栄の源泉という考え方も現れ、一門墓地も形成された。墓地=穢れという感覚が希薄になり、むしろ聖性を帯びてくるのである。共同墓地の場合も、ただ墓をまとめただけというのではなく、そこに葬れば必ず極楽往生できるといった聖性を帯びた「勝地」と捉えられ、実際僧侶によって結界が行われるなど聖域としての性格を有していた。なお平安中〜後期には墓自体が全国的に少なく、どのように葬ったのか謎が大きいそうだ。
このように当時の葬送を外観し、それが13世紀にどう変化していくのかを見るのであるが、その変革の兆しとなったは、「二十五三昧会(にじゅうござんまいえ)」である。これは僧侶が極楽往生するための互助組合のようなもので、恵心僧都源信が寛和2年(986年)に組織した念仏結社である。お互い極楽往生を遂げられるよう念仏を欠かさないようにし、死にそうになったら他のメンバーで面倒を見て葬儀も共同で行うというもので、「寺院内部でさえ葬式互助がなかった当時としてまさに画期的なものだった。(p.179)」
この「二十五三昧会」は12世紀には天台系の寺院で普及し、また死を目前とした貴族がこれに加入して共同の火葬場を利用させてもらうことも出てきた。さらに13世紀後半からは「念仏講」のような形で次第に一般社会にも浸透していき、血縁のない人の葬式の手伝いをするという行為が普及していく。こうして死体が放置される理由の第1は徐々に解消されていくのである。
さらに死者が葬られるべき共同墓地が出現したことで、鳥葬をするにせよ、どこかの空き地に放置するのではなく、「鳥辺野」や「蓮台野」まで持っていくことが期待されるようになった。さらに著者はそうした死体運搬に「坂非人」(清水坂にいた非人)が活躍したのではないかと推測している。
平安時代の「非人」は後の被差別階級とは異なり、ハンセン病患者などによって構成され、救恤の対象と見られていたのであるが、鎌倉時代になると彼らは「葬送得分権」を持つようになり強固な集団となっていく。この「葬送得分権」というのは、死者の葬儀を行う代わりにその衣服や葬具を奪取する権利であり、やがて彼らは京中の葬送に関する権利を持つようになって、南北朝時代(14世紀)には死体を運ぶ輿を独占する権利(輿独占権)を有し、輿の貸しだしで収入を得るようになった。さらに16世紀になると寺院が独自の葬式をする場合に、葬式一回あたりいくらの権利料を非人集団に支払うまでになるのである。
そして著者は、非人集団が「葬送得分権」を持つようになったきっかけが、葬送において鳥辺野や蓮台野まで死体を運ぶサービスを行ったことにあるのではないかと推測する。いくら共同墓地が「勝地」であったにしろ、死体を運ぶのは重労働である。しかし死体の衣類などと引き換えに非人集団が代わりに運んでくれるのであれば、あえて死体をそこらに放置するより運んでもらうことを選ぶだろう。こうして死体が放置される理由の第2が解消されたというのが著者の考えである。
ただし、(1)京中の放置死体の減少するのと歩調をあわせ、(2)蓮台野が大規模共同墓地として成長し、(3)同時期に非人の組織が史料に現れる、という状況証拠はあるものの、非人が棺を運んでいたこと自体を証明する史料は存在しないそうだ。
なお死体が放置される理由の第3については特に変化したとの指摘はないが、行き倒れの死体や極貧で身寄りのないものの死体は川や野山に棄てられるのは中世後期(14〜15世紀)でも続いていたと述べている。
本書は問題設定が極めて明解で、中世の葬儀に関する情報が総動員されており、著者の推測は史料の裏付けはないとはいえ説得的である。放置死体の減少から京都の葬儀事情が繙かれるという構成は読みやすく、葬送という地味な話題を扱っているにもかかわらず引き込まれる。
ただし思想面では若干記載が弱く、13世紀前半に放置死体が減少する背景に思想的な変遷もあったのではないかという気がさせられた。例えば本書には鎌倉新仏教とか浄土教の流行といったものはほとんど触れられていないが、こうしたものは葬送儀礼には影響していないのだろうか。唯一、葬送儀礼の整備には禅宗が積極的だったと簡単な記載があったのみだが、このあたりはもう少し考察が欲しかったところである。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
【関連書籍】
『中世の葬送・墓制—石塔を造立すること』水藤 真 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_4.html
中世の葬式がどうであったか検証する本。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
平安末期、京都には日常的に死体が放置されていた。貴族の屋敷や内裏においてさえ、野犬が死体の一部を置いていくことが珍しくなかった。当時は死の穢れが神経質に避けられていたから、屋敷で死体の一部がみつかれば「五体不具穢(ごたいふぐえ)」となって、7日間の出仕停止(謹慎)が必要であった(※この「五体不具」は、死体の一部によるという意味)。彼らは死体が見つかった気味の悪さや死者への弔いの気持ちよりも、7日間の謹慎を食らうことを気にしており、日記に書き留めた(ちなみに全身死体の場合は30日の謹慎だった)。それが仕事に影響することだったからだ。
よって、貴族の日記にはたびたび遺棄された死体のことが記録された。著者は、その記録を詳細に分析し、12世紀には「五体不具穢」などの記事が頻繁に出てくるのに、13世紀前半にそうした記事が急減することを突き止めた。12世紀の京都では死体放置・遺棄が日常的であったが、13世紀前半にはあまり死体は放置されなくなり、14世紀には稀な出来事になっていた。これはどうしてなのだろうか? それが本書の問題提起であり、この謎解きが本書のテーマである。
そもそも、なぜ死体は放置されていたのだろうか。それにはいくつか理由があった。
第1に、死者の葬送はほとんど親族しか携わることができなかった。その背景には死の穢れへの懼れ・忌みがあったと思われる。このため、肉親が少ない人は死を目前にすると自ら(!)葬所へ赴いたりした。また家の中で家族の死体が放置されていることもよくあった。死体が重すぎて女一人では移動させられなかった場合などだ。つまり葬送は、あくまで家族が自力でやるもので地域社会はこれに協力しなかった。
第2に、当時は鳥葬が行われていた。貴族や財力のある人は火葬を行うことが出来たが、火葬にはかなりお金がかかった。よって河原や山に死体を放置することにはそれほど抵抗感はなかった。鳥葬は山野で行う方が好ましいとは思われていたが、死体をそこまで運んでいくのも一苦労だったので、荒廃した貴族の屋敷地やそのあたりの空き地に死体を置いておくのも珍しくはなかった。そもそも低層の人々にとって、死体の遺棄と鳥葬の間には明確な線がなかったと思われる。
第3に、使用人が病気になり死にそうになると家を追い出すことが一般的に行われていた。もし家の中で使用人が病死すれば、死穢によって30日間の謹慎になるからである。今から見ると非人道的と言うほかないが、こうして死に瀕した病人が追い出され、路傍で死んだ。
こうした理由から、疫病が流行した時には当然河原には死体が溢れ、そうでなくても京都には若干の死体が放置されていることは珍しくなかった。もちろん国家はそれを好ましいものとはせず、検非違使に死体清掃のパトロールをさせることはあったが、それも何か行事がある時に限られ、積極的にこれを対策しようという気はなかったようだ。死の穢れを神経質なまでに気にしていたのに、「開放空間(道路や広場)にある死体の穢れは伝染しない」というような屁理屈で街中の死体を黙認していたのが平安朝であった。
それがなぜ13世紀前半に放置死体は急減するのか。その謎を解くため、本書では当時の葬送がどうであったかをまとめている。死の直前から年忌法要に至るまでの各段階における儀礼がこれまでの研究に基づいて整理されており、この項目は大変参考になり、便覧としても便利である。
その中でも火葬場の様子が興味深い。この頃は常設の火葬場はなく、そのたびごとに火葬場(「山作所」という)をしつらえていたが、上級の人々の場合、その形式は、荒垣で囲んで四方に鳥居で門を設けるものだった。四門はそれぞれ発心門、修行門、菩提門、涅槃門と呼ばれていた。門の名前だけでなく葬送儀礼全体が仏式で行われながら、「鳥居」が使われているのが面白い。やや時代は下るが天文5年(1536年)制作の『日蓮聖人註画讃』にはその様子が描かれており、仏式の場に鳥居が並んでいるのが奇異である。なぜ仏教は葬送の場において鳥居を必要としたのだろうか。大変興味を引かれる。
なお葬儀には死霊を恐れ、その害を避ける儀式が多いが、「貴族はそれを行いつつも「世俗の忌」として否定的に見ているようである(p.123)」という指摘が目を引いた。貴族は死霊を実体として扱うことを迷信的と思っていた節がある。「貴族は葬送のやり方を詳細に日記に書いているが、個々の儀礼について、死霊や魔がどうとかは一言半句も書いていない。(中略)彼らはそういう解釈を系統的に排除しているような感じがする(同)」とのことである。しかし死霊を避ける儀礼(出棺後に竹箒で掃くなど)は徐々に貴族社会にも浸透し、12世紀中期からは「世俗の忌」的儀礼が取り入れられるようになる。普通、文化は上流から下流に伝わっていくが、この時代の葬送儀礼に関しては民衆的な「俗信」が貴族社会に逆流していく感じがする。
葬送儀礼は全体として、鎌倉時代にかけて整備が進んでくる感じである。また散発的・個別的だった墓地(その都度適当な山野を選んで墓を作っていた)が12世紀後半になると全国的に広域の共同墓地が営まれるようになってくる。京都では、「鳥辺野」に加え「蓮台野」という墓地が12世紀中頃に成立している。また墓地が一門の繁栄の源泉という考え方も現れ、一門墓地も形成された。墓地=穢れという感覚が希薄になり、むしろ聖性を帯びてくるのである。共同墓地の場合も、ただ墓をまとめただけというのではなく、そこに葬れば必ず極楽往生できるといった聖性を帯びた「勝地」と捉えられ、実際僧侶によって結界が行われるなど聖域としての性格を有していた。なお平安中〜後期には墓自体が全国的に少なく、どのように葬ったのか謎が大きいそうだ。
このように当時の葬送を外観し、それが13世紀にどう変化していくのかを見るのであるが、その変革の兆しとなったは、「二十五三昧会(にじゅうござんまいえ)」である。これは僧侶が極楽往生するための互助組合のようなもので、恵心僧都源信が寛和2年(986年)に組織した念仏結社である。お互い極楽往生を遂げられるよう念仏を欠かさないようにし、死にそうになったら他のメンバーで面倒を見て葬儀も共同で行うというもので、「寺院内部でさえ葬式互助がなかった当時としてまさに画期的なものだった。(p.179)」
この「二十五三昧会」は12世紀には天台系の寺院で普及し、また死を目前とした貴族がこれに加入して共同の火葬場を利用させてもらうことも出てきた。さらに13世紀後半からは「念仏講」のような形で次第に一般社会にも浸透していき、血縁のない人の葬式の手伝いをするという行為が普及していく。こうして死体が放置される理由の第1は徐々に解消されていくのである。
さらに死者が葬られるべき共同墓地が出現したことで、鳥葬をするにせよ、どこかの空き地に放置するのではなく、「鳥辺野」や「蓮台野」まで持っていくことが期待されるようになった。さらに著者はそうした死体運搬に「坂非人」(清水坂にいた非人)が活躍したのではないかと推測している。
平安時代の「非人」は後の被差別階級とは異なり、ハンセン病患者などによって構成され、救恤の対象と見られていたのであるが、鎌倉時代になると彼らは「葬送得分権」を持つようになり強固な集団となっていく。この「葬送得分権」というのは、死者の葬儀を行う代わりにその衣服や葬具を奪取する権利であり、やがて彼らは京中の葬送に関する権利を持つようになって、南北朝時代(14世紀)には死体を運ぶ輿を独占する権利(輿独占権)を有し、輿の貸しだしで収入を得るようになった。さらに16世紀になると寺院が独自の葬式をする場合に、葬式一回あたりいくらの権利料を非人集団に支払うまでになるのである。
そして著者は、非人集団が「葬送得分権」を持つようになったきっかけが、葬送において鳥辺野や蓮台野まで死体を運ぶサービスを行ったことにあるのではないかと推測する。いくら共同墓地が「勝地」であったにしろ、死体を運ぶのは重労働である。しかし死体の衣類などと引き換えに非人集団が代わりに運んでくれるのであれば、あえて死体をそこらに放置するより運んでもらうことを選ぶだろう。こうして死体が放置される理由の第2が解消されたというのが著者の考えである。
ただし、(1)京中の放置死体の減少するのと歩調をあわせ、(2)蓮台野が大規模共同墓地として成長し、(3)同時期に非人の組織が史料に現れる、という状況証拠はあるものの、非人が棺を運んでいたこと自体を証明する史料は存在しないそうだ。
なお死体が放置される理由の第3については特に変化したとの指摘はないが、行き倒れの死体や極貧で身寄りのないものの死体は川や野山に棄てられるのは中世後期(14〜15世紀)でも続いていたと述べている。
本書は問題設定が極めて明解で、中世の葬儀に関する情報が総動員されており、著者の推測は史料の裏付けはないとはいえ説得的である。放置死体の減少から京都の葬儀事情が繙かれるという構成は読みやすく、葬送という地味な話題を扱っているにもかかわらず引き込まれる。
ただし思想面では若干記載が弱く、13世紀前半に放置死体が減少する背景に思想的な変遷もあったのではないかという気がさせられた。例えば本書には鎌倉新仏教とか浄土教の流行といったものはほとんど触れられていないが、こうしたものは葬送儀礼には影響していないのだろうか。唯一、葬送儀礼の整備には禅宗が積極的だったと簡単な記載があったのみだが、このあたりはもう少し考察が欲しかったところである。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
【関連書籍】
『中世の葬送・墓制—石塔を造立すること』水藤 真 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_4.html
中世の葬式がどうであったか検証する本。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
2019年10月6日日曜日
『畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史—因果応報と悪道』生駒 哲郎 著
中世の畜生・餓鬼・地獄の世界観について述べる。
仏教では殺生は重大な罪である。では戦で人を殺した武士はみな地獄に落ちたのか、狩猟を行った人は地獄に落ちた(と考えられた)のかというと実はそうではない。殺生は罪業であったが、地獄が必定の殺生と、そうでもない殺生があった。
ごく単純化して言えば、わけもなく人を殺した場合が地獄行きで、道理に基づいて人を殺した場合はそうでもないと考えられた。例えば大義名分のある戦の場合や、仇討ちの場合は同じ殺生でも義務を果たした行為と見なされた。そういう場合、地獄には落ちない。中世の仏教において、殺生は決定的な罪業とは考えられていなかった模様である。むしろ道理のなさ、慈悲のなさといったことの方が決定的であった。
また、ひとたび地獄に落ちても、地蔵菩薩が救ってくれるという思想も発達した。本書では、『今昔物語集』に収録された地蔵霊験譚を分析してその変遷を考察している。地蔵菩薩の功徳は、地獄に落ちそうになった人を閻魔庁で救い出してやるというところから始まったようである。地獄に落ちてしまった人には代受苦(地獄の苦しみを代わりに受けてくれる)を提供したが、やがて地獄から人道へ戻すこともやるようになり、人道から西方浄土への往生に導くようになる。地獄に落ちた人を救うという地蔵菩薩の性格が、浄土信仰と結びついているのが興味深い。
また、罪業を冒しても、それを機縁として仏道を修せば地獄落ちを避けることができると考えられた。このように、悪事をきっかけに仏道に入ることを「逆縁」といった(今でいう逆縁とは意味が違う)。地獄に落ちたくないという利己的な心によるものであっても悔過(けか=懺悔みたいなもの)を行い、仏像を安置し、法華経を写せばそれで罪が軽くなったのである。また、自らは仏道を修さずとも、追善供養でも地獄落ちは避けられた。殺人や裏切りといった悪事も地獄落ちの決定打ではなく、各種の「抜け道」があったということだ。こうした「抜け道」があることが、仏教の盛行に一役買っていたに違いない。抜け道のない峻厳な教義であれば、きっと仏教は中世においてそれほど一般化しなかったであろう。
本書ではさらに、畜生道に落ちる場合はどんな時か、そして畜生道に落ちると人はどうなると考えられたかについて述べ、次いで同様に餓鬼道の場合が述べられる。畜生道の場合で、神への供物に肉や魚を使うことの仏教的整合性をどうとったかという説明があるがこれが面白い。例えば神にハマグリを供えるということを考えると、これはハマグリを殺しているわけだから殺生である。これは神が殺生を要求しているということになり、仏教的に考えるとおかしい。当時は神と仏は神仏習合で一体化していたが、この矛盾はどう考えたらよいか。これは、畜生道に落ちてしまっているハマグリを神に供えることで仏道に触れる機縁とし、天人道へ転生する道筋であると考えたのである。ハマグリは畜生道で苦しんでいるわけだから、それを神に供えることによって救う、という話である。
本書にはごく簡単にしか書いていないが、敵方供養が重要であったという指摘も面白い。中世には敵方の妻や子どもまでも一族皆殺しにすることはなかったという。これは温情があったのではなくて、敵方の供養をする人を残すためなのであった。なぜなら、非業の死を遂げた人間は、適切な供養がなければ怨霊となり現世に仇なすと考えられたからである。よって戦の供養塔などでは敵方の供養も重要なこととみなされた。この頃の仏教はさほど倫理的ではないが、これは人道的な考え方だろう。
本書は「中世仏教史」というタイトルになっているが、中身はケーススタディ的なものが多く通史的ではない。畜生・餓鬼・地獄といったものがどのように考えられていたかということを記述するのがメインで、それらの分析や考察もあまりない。私は地獄の観念は中世の仏教に甚大な影響を与えていると感じているが、本書ではそうした思想史的展開がほとんど語られないのは少し残念だった。
事例紹介的で「中世仏教史」は名折れだが、中世の悪道の軽重を知ることができる手軽な本。
仏教では殺生は重大な罪である。では戦で人を殺した武士はみな地獄に落ちたのか、狩猟を行った人は地獄に落ちた(と考えられた)のかというと実はそうではない。殺生は罪業であったが、地獄が必定の殺生と、そうでもない殺生があった。
ごく単純化して言えば、わけもなく人を殺した場合が地獄行きで、道理に基づいて人を殺した場合はそうでもないと考えられた。例えば大義名分のある戦の場合や、仇討ちの場合は同じ殺生でも義務を果たした行為と見なされた。そういう場合、地獄には落ちない。中世の仏教において、殺生は決定的な罪業とは考えられていなかった模様である。むしろ道理のなさ、慈悲のなさといったことの方が決定的であった。
また、ひとたび地獄に落ちても、地蔵菩薩が救ってくれるという思想も発達した。本書では、『今昔物語集』に収録された地蔵霊験譚を分析してその変遷を考察している。地蔵菩薩の功徳は、地獄に落ちそうになった人を閻魔庁で救い出してやるというところから始まったようである。地獄に落ちてしまった人には代受苦(地獄の苦しみを代わりに受けてくれる)を提供したが、やがて地獄から人道へ戻すこともやるようになり、人道から西方浄土への往生に導くようになる。地獄に落ちた人を救うという地蔵菩薩の性格が、浄土信仰と結びついているのが興味深い。
また、罪業を冒しても、それを機縁として仏道を修せば地獄落ちを避けることができると考えられた。このように、悪事をきっかけに仏道に入ることを「逆縁」といった(今でいう逆縁とは意味が違う)。地獄に落ちたくないという利己的な心によるものであっても悔過(けか=懺悔みたいなもの)を行い、仏像を安置し、法華経を写せばそれで罪が軽くなったのである。また、自らは仏道を修さずとも、追善供養でも地獄落ちは避けられた。殺人や裏切りといった悪事も地獄落ちの決定打ではなく、各種の「抜け道」があったということだ。こうした「抜け道」があることが、仏教の盛行に一役買っていたに違いない。抜け道のない峻厳な教義であれば、きっと仏教は中世においてそれほど一般化しなかったであろう。
本書ではさらに、畜生道に落ちる場合はどんな時か、そして畜生道に落ちると人はどうなると考えられたかについて述べ、次いで同様に餓鬼道の場合が述べられる。畜生道の場合で、神への供物に肉や魚を使うことの仏教的整合性をどうとったかという説明があるがこれが面白い。例えば神にハマグリを供えるということを考えると、これはハマグリを殺しているわけだから殺生である。これは神が殺生を要求しているということになり、仏教的に考えるとおかしい。当時は神と仏は神仏習合で一体化していたが、この矛盾はどう考えたらよいか。これは、畜生道に落ちてしまっているハマグリを神に供えることで仏道に触れる機縁とし、天人道へ転生する道筋であると考えたのである。ハマグリは畜生道で苦しんでいるわけだから、それを神に供えることによって救う、という話である。
本書にはごく簡単にしか書いていないが、敵方供養が重要であったという指摘も面白い。中世には敵方の妻や子どもまでも一族皆殺しにすることはなかったという。これは温情があったのではなくて、敵方の供養をする人を残すためなのであった。なぜなら、非業の死を遂げた人間は、適切な供養がなければ怨霊となり現世に仇なすと考えられたからである。よって戦の供養塔などでは敵方の供養も重要なこととみなされた。この頃の仏教はさほど倫理的ではないが、これは人道的な考え方だろう。
本書は「中世仏教史」というタイトルになっているが、中身はケーススタディ的なものが多く通史的ではない。畜生・餓鬼・地獄といったものがどのように考えられていたかということを記述するのがメインで、それらの分析や考察もあまりない。私は地獄の観念は中世の仏教に甚大な影響を与えていると感じているが、本書ではそうした思想史的展開がほとんど語られないのは少し残念だった。
事例紹介的で「中世仏教史」は名折れだが、中世の悪道の軽重を知ることができる手軽な本。
2019年10月4日金曜日
『中世の葬送・墓制—石塔を造立すること』水藤 真 著
中世の葬式がどうであったか検証する本。
江戸時代になると葬送や墓制(火葬し、その後石塔に納骨するなど)は現代とさほど変わらない。しかしその前の中世では、死者に対する態度、死体の扱い方、葬送の仕方、墓の造立、墓参の仕方まで、その基本的態度がだいぶ違うようである。本書は、中世の葬送・墓制がどうであったか、各種の資料に基づいて推測するものである。
「第1 中世の葬送・墓制」では、藤原良通、藤原俊成、中原師右(もろすけ)の死にあたってどのようなことが行われたか記述される。この頃の葬送はこっそり行われ、各種の儀礼がかなりの期間にわたって行われたが、必ずしも造塔は伴わなかった。墓は忘れられていたわけではないし、墓参もあったようだが、後代の常識とは異なって石塔は必須とは考えられていなかったようだ。
「第2 中世的葬送・墓制の淵源」では、平安貴族、後醍醐天皇、貴族・庶民の葬送が検証される。ここでも貴族の日記などから葬儀の様子が述べられているが、後醍醐天皇の葬儀でもほとんど仏式に行われていることが注目される。この時代の葬式は今のように決まった形態がなく、バリエーションが非常に大きい。
「第3 石塔の作り方」は、技術的な意味での石塔の作り方ではなく、どのような思想によって石塔が造立されたかを述べる。この項は基本的なことであるが面白い。石塔を作ることは故人を弔うというよりも、積善・作善の行為であったとし、であるから必ずしも墓に石塔がなくてもいいし、逆に墓以外にも石塔をたくさん建ててもよいのであった。もちろん積善の行為は造塔だけでなく、仏事を修する、仏像を造立する、梵鐘を鋳造する、風呂を施す、罪人を解き放つといったことも積善と見なされていた。また生前に自らの供養をする逆修供養の事例が紹介されているが、文明3年(1471年)の例で、初七日や一周忌、十三回忌までを圧縮した日程で実施しているものがあり、逆修供養で生前に葬式の全課程を終えておく場合があったことを初めて知った。
「第4 中世における葬送・墓制の諸相」では、足利将軍家、僧侶、女性の葬儀について検証される。かつては仏式というだけで特に何宗ということのなかった葬儀が、14世紀、室町時代になると何宗という分化が生じ、時宗の影響を受けた禅宗の葬儀が盛行するようになる。また葬儀の執行が相続の正統性を示すものと受け止められるものとなったという。
「第5 色々な墓」では、文字通り墓にまつわるいろいろな話を列挙している。中でも葬送や石塔の費用について分析した部分が面白い。貴族の葬式では大変な出費があり、例えば母の追善供養のためにその領地を売却した例も紹介されている。なおその中で石塔の造立にかかるコストは比較的小さく、数多くの仏事を修するのが費用のメインである。とにかく葬式を正式に修すると大金がかかったので、逆修供養とは葬式の簡略化によるコスト削減でもあったのかもしれないと思った。
「第6 中世的墳墓の形成と実態」では、14世紀頃から葬送と石塔の造立がセットになっていったことが推測され、それには禅宗が積極的に関与したことが示唆されている。また墓が寺に営まれるようになったことが簡単に指摘されているが、これはさらに詳しく過程を知りたいところである。さらに悉皆調査が行われている埼玉県の板碑についての統計的な分析が行われ、墓の変遷がデータで述べられている。このデータは非常に示唆的で興味を引く。
全体的に葬儀の事例を列挙していく感じの内容であり、普通には退屈な本であるかもしれないが、中世の葬儀への興味を持って読むとどの項目も興味深く、意外と退屈せずに読んだ。ただし、事例の列挙であるためにあまり分析や考察はなされていない。一つひとつの事例についてもう少し突っ込んだ考察が欲しかった。また、副題が「石塔を造立すること」であるにもかかわらず、石塔そのものについての話(どのように制作されたのか、どのような形式の石塔があったのかなど)がほとんどないのは残念だった。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
【関連書籍】
『死者たちの中世』勝田 至 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_9.html
中世、多くの死者が墓地に葬られるようになる背景を説き明かす本。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
江戸時代になると葬送や墓制(火葬し、その後石塔に納骨するなど)は現代とさほど変わらない。しかしその前の中世では、死者に対する態度、死体の扱い方、葬送の仕方、墓の造立、墓参の仕方まで、その基本的態度がだいぶ違うようである。本書は、中世の葬送・墓制がどうであったか、各種の資料に基づいて推測するものである。
「第1 中世の葬送・墓制」では、藤原良通、藤原俊成、中原師右(もろすけ)の死にあたってどのようなことが行われたか記述される。この頃の葬送はこっそり行われ、各種の儀礼がかなりの期間にわたって行われたが、必ずしも造塔は伴わなかった。墓は忘れられていたわけではないし、墓参もあったようだが、後代の常識とは異なって石塔は必須とは考えられていなかったようだ。
「第2 中世的葬送・墓制の淵源」では、平安貴族、後醍醐天皇、貴族・庶民の葬送が検証される。ここでも貴族の日記などから葬儀の様子が述べられているが、後醍醐天皇の葬儀でもほとんど仏式に行われていることが注目される。この時代の葬式は今のように決まった形態がなく、バリエーションが非常に大きい。
「第3 石塔の作り方」は、技術的な意味での石塔の作り方ではなく、どのような思想によって石塔が造立されたかを述べる。この項は基本的なことであるが面白い。石塔を作ることは故人を弔うというよりも、積善・作善の行為であったとし、であるから必ずしも墓に石塔がなくてもいいし、逆に墓以外にも石塔をたくさん建ててもよいのであった。もちろん積善の行為は造塔だけでなく、仏事を修する、仏像を造立する、梵鐘を鋳造する、風呂を施す、罪人を解き放つといったことも積善と見なされていた。また生前に自らの供養をする逆修供養の事例が紹介されているが、文明3年(1471年)の例で、初七日や一周忌、十三回忌までを圧縮した日程で実施しているものがあり、逆修供養で生前に葬式の全課程を終えておく場合があったことを初めて知った。
「第4 中世における葬送・墓制の諸相」では、足利将軍家、僧侶、女性の葬儀について検証される。かつては仏式というだけで特に何宗ということのなかった葬儀が、14世紀、室町時代になると何宗という分化が生じ、時宗の影響を受けた禅宗の葬儀が盛行するようになる。また葬儀の執行が相続の正統性を示すものと受け止められるものとなったという。
「第5 色々な墓」では、文字通り墓にまつわるいろいろな話を列挙している。中でも葬送や石塔の費用について分析した部分が面白い。貴族の葬式では大変な出費があり、例えば母の追善供養のためにその領地を売却した例も紹介されている。なおその中で石塔の造立にかかるコストは比較的小さく、数多くの仏事を修するのが費用のメインである。とにかく葬式を正式に修すると大金がかかったので、逆修供養とは葬式の簡略化によるコスト削減でもあったのかもしれないと思った。
「第6 中世的墳墓の形成と実態」では、14世紀頃から葬送と石塔の造立がセットになっていったことが推測され、それには禅宗が積極的に関与したことが示唆されている。また墓が寺に営まれるようになったことが簡単に指摘されているが、これはさらに詳しく過程を知りたいところである。さらに悉皆調査が行われている埼玉県の板碑についての統計的な分析が行われ、墓の変遷がデータで述べられている。このデータは非常に示唆的で興味を引く。
全体的に葬儀の事例を列挙していく感じの内容であり、普通には退屈な本であるかもしれないが、中世の葬儀への興味を持って読むとどの項目も興味深く、意外と退屈せずに読んだ。ただし、事例の列挙であるためにあまり分析や考察はなされていない。一つひとつの事例についてもう少し突っ込んだ考察が欲しかった。また、副題が「石塔を造立すること」であるにもかかわらず、石塔そのものについての話(どのように制作されたのか、どのような形式の石塔があったのかなど)がほとんどないのは残念だった。
葬儀事例を数多く紹介することで中世の葬送を知る真面目な本。
【関連書籍】
『死者たちの中世』勝田 至 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/10/blog-post_9.html
中世、多くの死者が墓地に葬られるようになる背景を説き明かす本。
思想面は手薄だが、中世の葬送観について総合的に理解できる良書。
『寺社勢力の中世—無縁・有縁・移民』伊藤 正敏 著
中世の寺社勢力の姿を、様々な事例から解き明かす本。
中世において、寺社は幕府からも朝廷からも独立した存在であった。それを象徴するのは、寺社が「検断権」を持っていたということである。これは今の検察・警察権にあたる。たとえ謀反人であったとしても、寺社の境内に逃げ込めば幕府も朝廷も捜査はできなかった。あくまで、謀反人の捜査を寺社に「依頼」することしかできなかった。だから頼朝から追討された義経は比叡山に逃げ込んだ。比叡山に逃げ込めば、積極的な保護を受けられるかどうかは別として、直ちに幕府や朝廷に引き渡されることはなかったのである。
それは、百姓でも、悪党でも同じであった。俗世で行き詰まった人々は寺社を頼ってきた。少なくともそこでは俗世の階級やしがらみは断ち切ったことになっていた。実際には、寺社の中には貴族・武士階級を出自に持つ学侶と、百姓階級の行人・堂衆があり、僧侶としての身分は世襲されていたのであるが、建前としては寺社の境内では俗世をどう過ごしてきたかは不問にされた。これを著者は寺社の「無縁性」と呼ぶ。中世では、寺社は俗世の縁(有縁)を絶ちきり、しがらみのない状態(無縁)になれる唯一の場所であった。
そうして寺社にやってきた人々も、寺社の中で無為徒食できるわけではなかった。彼らは幕府や朝廷から距離を置くことはできたが、逆に言えば朝幕が用意していた社会システムから離れて生活の糧を得る必要があった。彼らは今で言えば「移民」であった。ある人は職人となり、ある人は商人となり、またある人は金融業を営んだ。こうした人々の生きるためのエネルギーによって寺社は最新技術を有し、中世の経済の中心となった。例えば根来寺(真義真言宗)では、武器製造が盛んだった。根来寺は高度な鍛冶技術を有し、鉄砲の三大生産地のひとつであった(他の2つは堺・近江国友)。
故郷を離れ、経済活動に勤しむ「個人」が集積していたところ、しかも国家と別の警察権を持ち、国家から半独立していたところ、それが寺社であった。著者はそうした寺社の様相を「境内都市」という用語で読み解く。中世末期、高野山には7千坊もの子院があったというが、これは宗教施設の集合ではなく、むしろ都市そのものだと考えた方がいいというのである。中世は農業中心の経済ではなく、多くの境内都市(=寺社)が活躍した都市経済の時代であった。
そして中世の京都は、事実都でもあったのだが、それ以上に叡山の門前町という性格が強かった。感神院祇園社は元は興福寺末寺であったが延暦寺(比叡山)が強奪し、祇園社を通じて比叡山は京都の経済を牛耳った。延暦寺の僧侶は、比叡山ではなく京都に住んでいたのである。
朝幕の勢力が、寺社勢力に対して無力だったわけではない。しかし朝廷と寺社勢力が争う場合、常に朝廷の腰は引けていた。神罰・仏罰を恐れたためだ。嗷訴(ごうそ)を行う場合、比叡山の僧侶は日吉社の神輿を持ち出した(神輿動座(しんよどうざ))。神の乗り物である神輿を置き去りにし、神意によって主張を通そうとしたのである。しかし「僧侶」が「神輿」を持ち出すというのが面白い。この頃、仏教と神道は、教義においてはもちろんアイテム的な面でも区別されていなかった。
本書はこうした寺社勢力の特質を、当時の文書(もんじょ)に現れる事例から読み解いている。鎌倉幕府の行政記録はほとんど残っていないし、当時の朝廷の様子も貴族の日記によって窺い知れるのみであるが、寺社の場合かなり寺としての記録が残っている上、貴族の日記にも頻繁に寺社とのもめ事が記述されているため、寺社の動向はこの時代の一次資料によってかなり解明できるんだそうである。
しかし、多くの事例から読み解くというスタイルであるため、本書はあまり体系的ではなく、時系列的でもないためややわかりにくい。さらに、著者はいわゆる「名物教授風」というか、かなりアクの強い書き方をしているため、文体の好みは分かれそうである(私自身はちょっと苦手だった)。
また「無縁性」を大きなキーワードとして寺社勢力の特質を読み解き、寺社に流入する人々を「移民」と捉える視点は面白いが、実際には寺社の中も世襲の僧侶たちによって相続されていたという事実と若干接続しない部分がある。ある面では寺社は「無縁所」であったし、移民が金持ちになれるアメリカン・ドリームな世界であったのは事実である。しかし「無縁」はあくまで寺社勢力の中の一部(特に行人・堂衆と呼ばれた人たち)の成立背景に過ぎず、「無縁」を以て寺社勢力全体を読み解くには無理があるような気がした。
ややアクの強い論ではあるが、「境内都市」という概念で寺社勢力の特質を繙いていく独特な本。
【関連書籍】
『寺社勢力—もう一つの中世社会』黒田 俊雄 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/blog-post_13.html
中世における寺社勢力の勃興と衰退を述べる。
中世の申し子とも言える寺社勢力を通じて当時の社会の内実を考えさせる良書。
中世において、寺社は幕府からも朝廷からも独立した存在であった。それを象徴するのは、寺社が「検断権」を持っていたということである。これは今の検察・警察権にあたる。たとえ謀反人であったとしても、寺社の境内に逃げ込めば幕府も朝廷も捜査はできなかった。あくまで、謀反人の捜査を寺社に「依頼」することしかできなかった。だから頼朝から追討された義経は比叡山に逃げ込んだ。比叡山に逃げ込めば、積極的な保護を受けられるかどうかは別として、直ちに幕府や朝廷に引き渡されることはなかったのである。
それは、百姓でも、悪党でも同じであった。俗世で行き詰まった人々は寺社を頼ってきた。少なくともそこでは俗世の階級やしがらみは断ち切ったことになっていた。実際には、寺社の中には貴族・武士階級を出自に持つ学侶と、百姓階級の行人・堂衆があり、僧侶としての身分は世襲されていたのであるが、建前としては寺社の境内では俗世をどう過ごしてきたかは不問にされた。これを著者は寺社の「無縁性」と呼ぶ。中世では、寺社は俗世の縁(有縁)を絶ちきり、しがらみのない状態(無縁)になれる唯一の場所であった。
そうして寺社にやってきた人々も、寺社の中で無為徒食できるわけではなかった。彼らは幕府や朝廷から距離を置くことはできたが、逆に言えば朝幕が用意していた社会システムから離れて生活の糧を得る必要があった。彼らは今で言えば「移民」であった。ある人は職人となり、ある人は商人となり、またある人は金融業を営んだ。こうした人々の生きるためのエネルギーによって寺社は最新技術を有し、中世の経済の中心となった。例えば根来寺(真義真言宗)では、武器製造が盛んだった。根来寺は高度な鍛冶技術を有し、鉄砲の三大生産地のひとつであった(他の2つは堺・近江国友)。
故郷を離れ、経済活動に勤しむ「個人」が集積していたところ、しかも国家と別の警察権を持ち、国家から半独立していたところ、それが寺社であった。著者はそうした寺社の様相を「境内都市」という用語で読み解く。中世末期、高野山には7千坊もの子院があったというが、これは宗教施設の集合ではなく、むしろ都市そのものだと考えた方がいいというのである。中世は農業中心の経済ではなく、多くの境内都市(=寺社)が活躍した都市経済の時代であった。
そして中世の京都は、事実都でもあったのだが、それ以上に叡山の門前町という性格が強かった。感神院祇園社は元は興福寺末寺であったが延暦寺(比叡山)が強奪し、祇園社を通じて比叡山は京都の経済を牛耳った。延暦寺の僧侶は、比叡山ではなく京都に住んでいたのである。
朝幕の勢力が、寺社勢力に対して無力だったわけではない。しかし朝廷と寺社勢力が争う場合、常に朝廷の腰は引けていた。神罰・仏罰を恐れたためだ。嗷訴(ごうそ)を行う場合、比叡山の僧侶は日吉社の神輿を持ち出した(神輿動座(しんよどうざ))。神の乗り物である神輿を置き去りにし、神意によって主張を通そうとしたのである。しかし「僧侶」が「神輿」を持ち出すというのが面白い。この頃、仏教と神道は、教義においてはもちろんアイテム的な面でも区別されていなかった。
本書はこうした寺社勢力の特質を、当時の文書(もんじょ)に現れる事例から読み解いている。鎌倉幕府の行政記録はほとんど残っていないし、当時の朝廷の様子も貴族の日記によって窺い知れるのみであるが、寺社の場合かなり寺としての記録が残っている上、貴族の日記にも頻繁に寺社とのもめ事が記述されているため、寺社の動向はこの時代の一次資料によってかなり解明できるんだそうである。
しかし、多くの事例から読み解くというスタイルであるため、本書はあまり体系的ではなく、時系列的でもないためややわかりにくい。さらに、著者はいわゆる「名物教授風」というか、かなりアクの強い書き方をしているため、文体の好みは分かれそうである(私自身はちょっと苦手だった)。
また「無縁性」を大きなキーワードとして寺社勢力の特質を読み解き、寺社に流入する人々を「移民」と捉える視点は面白いが、実際には寺社の中も世襲の僧侶たちによって相続されていたという事実と若干接続しない部分がある。ある面では寺社は「無縁所」であったし、移民が金持ちになれるアメリカン・ドリームな世界であったのは事実である。しかし「無縁」はあくまで寺社勢力の中の一部(特に行人・堂衆と呼ばれた人たち)の成立背景に過ぎず、「無縁」を以て寺社勢力全体を読み解くには無理があるような気がした。
ややアクの強い論ではあるが、「境内都市」という概念で寺社勢力の特質を繙いていく独特な本。
【関連書籍】
『寺社勢力—もう一つの中世社会』黒田 俊雄 著
http://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/09/blog-post_13.html
中世における寺社勢力の勃興と衰退を述べる。
中世の申し子とも言える寺社勢力を通じて当時の社会の内実を考えさせる良書。
登録:
投稿 (Atom)