中世の畜生・餓鬼・地獄の世界観について述べる。
仏教では殺生は重大な罪である。では戦で人を殺した武士はみな地獄に落ちたのか、狩猟を行った人は地獄に落ちた(と考えられた)のかというと実はそうではない。殺生は罪業であったが、地獄が必定の殺生と、そうでもない殺生があった。
ごく単純化して言えば、わけもなく人を殺した場合が地獄行きで、道理に基づいて人を殺した場合はそうでもないと考えられた。例えば大義名分のある戦の場合や、仇討ちの場合は同じ殺生でも義務を果たした行為と見なされた。そういう場合、地獄には落ちない。中世の仏教において、殺生は決定的な罪業とは考えられていなかった模様である。むしろ道理のなさ、慈悲のなさといったことの方が決定的であった。
また、ひとたび地獄に落ちても、地蔵菩薩が救ってくれるという思想も発達した。本書では、『今昔物語集』に収録された地蔵霊験譚を分析してその変遷を考察している。地蔵菩薩の功徳は、地獄に落ちそうになった人を閻魔庁で救い出してやるというところから始まったようである。地獄に落ちてしまった人には代受苦(地獄の苦しみを代わりに受けてくれる)を提供したが、やがて地獄から人道へ戻すこともやるようになり、人道から西方浄土への往生に導くようになる。地獄に落ちた人を救うという地蔵菩薩の性格が、浄土信仰と結びついているのが興味深い。
また、罪業を冒しても、それを機縁として仏道を修せば地獄落ちを避けることができると考えられた。このように、悪事をきっかけに仏道に入ることを「逆縁」といった(今でいう逆縁とは意味が違う)。地獄に落ちたくないという利己的な心によるものであっても悔過(けか=懺悔みたいなもの)を行い、仏像を安置し、法華経を写せばそれで罪が軽くなったのである。また、自らは仏道を修さずとも、追善供養でも地獄落ちは避けられた。殺人や裏切りといった悪事も地獄落ちの決定打ではなく、各種の「抜け道」があったということだ。こうした「抜け道」があることが、仏教の盛行に一役買っていたに違いない。抜け道のない峻厳な教義であれば、きっと仏教は中世においてそれほど一般化しなかったであろう。
本書ではさらに、畜生道に落ちる場合はどんな時か、そして畜生道に落ちると人はどうなると考えられたかについて述べ、次いで同様に餓鬼道の場合が述べられる。畜生道の場合で、神への供物に肉や魚を使うことの仏教的整合性をどうとったかという説明があるがこれが面白い。例えば神にハマグリを供えるということを考えると、これはハマグリを殺しているわけだから殺生である。これは神が殺生を要求しているということになり、仏教的に考えるとおかしい。当時は神と仏は神仏習合で一体化していたが、この矛盾はどう考えたらよいか。これは、畜生道に落ちてしまっているハマグリを神に供えることで仏道に触れる機縁とし、天人道へ転生する道筋であると考えたのである。ハマグリは畜生道で苦しんでいるわけだから、それを神に供えることによって救う、という話である。
本書にはごく簡単にしか書いていないが、敵方供養が重要であったという指摘も面白い。中世には敵方の妻や子どもまでも一族皆殺しにすることはなかったという。これは温情があったのではなくて、敵方の供養をする人を残すためなのであった。なぜなら、非業の死を遂げた人間は、適切な供養がなければ怨霊となり現世に仇なすと考えられたからである。よって戦の供養塔などでは敵方の供養も重要なこととみなされた。この頃の仏教はさほど倫理的ではないが、これは人道的な考え方だろう。
本書は「中世仏教史」というタイトルになっているが、中身はケーススタディ的なものが多く通史的ではない。畜生・餓鬼・地獄といったものがどのように考えられていたかということを記述するのがメインで、それらの分析や考察もあまりない。私は地獄の観念は中世の仏教に甚大な影響を与えていると感じているが、本書ではそうした思想史的展開がほとんど語られないのは少し残念だった。
事例紹介的で「中世仏教史」は名折れだが、中世の悪道の軽重を知ることができる手軽な本。
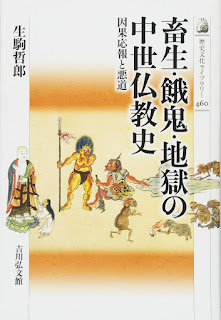
0 件のコメント:
コメントを投稿