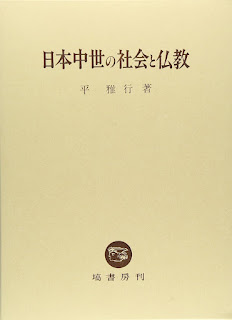本書は、光華女子大学/短大の公開講座をまとめたものである。その基本的な視座は、「仏教において女性はどう扱われてきたか」ということではなく、「女性は仏教をどう信仰してきたのか」というものだ。登壇したのは、吉田一彦、勝浦令子、西口順子の各氏であり、それぞれ2回ずつで計6回の講演がある。
講演に先立つ「はじめに」(西口順子)では、伝統的な仏教の女性観が差別的なものであったことを述べている。「仏教は女性をいつも被救済者の位置においてきた(p.1)」。
そうした女性観を批判し、女性と仏教をめぐる研究を進展させたのが「研究会・日本の女性と仏教」と牛山佳幸氏の一連の研究だった。なお研究会の方では、その成果としてシリーズ『女性と仏教』全4巻が刊行されている。こうした研究によって女性と仏教の研究は新たな展開を迎えた。
「第1章 女性と仏教をめぐる諸問題」(吉田一彦)では、女性と仏教の研究史が概説され、問題点が指摘される。
女性と仏教の研究の基調を作ったのが笠原一男氏である(『女人往生思想の系譜』等)。ところがそれは鎌倉仏教をひいき目に見て、「女性と民衆を救済の対象としたのは鎌倉新仏教が初めてだ」など実証的でない部分が多い。むしろ、古代から女性は深く仏教に関与してきた。最初の出家者は尼だし、持統天皇は7日おきの法要を始めているし、行基は尼院を多く造立している(その3分の1が尼院だ)。また民衆も、古代から仏教を信仰してきたことが『日本霊異記』などに窺える。
続く時期には、桜井徳太郎氏が古代の尼とシャーマンを関連付けて理解し(ただしこの主張は検証が必要。後述)、初期仏教には尼が多いと指摘した。そして、その後の研究に決定的な影響を与えたのが牛山佳幸氏の研究で、それによれば、①寺院における女性の差別待遇は8世紀中頃からで、国家的法会からの排除から始まっている(初見は727年)。②9世紀初頭からの年分度者制では尼が外されている、③8世紀に諸寺に「鎮」が設置されるが、尼の鎮にも僧が任命されている、といったことが明らかになった。
なぜそのような差別が仏教界に広まっていったか。牛山氏は儒教倫理と家父長制家族の成立が理由と考えたが、著者はそれに懐疑的である。そうではなく「国家は男性が運営するという思想による(p.27)」のではないか。つまり仏教が国家的なものになったことで女性が排除されたというのだ。逆にいえば、民衆の世界では仏教もそれほど女性差別はしていなかったということだ。次に著者は牛山氏の女人禁制の研究についても紹介し批判を加えているが、これについては割愛する。
そして1984年、「研究会・日本の女性と仏教」が大隅和雄氏と西口順子氏を発起人としてスタートすると、それまでの研究が総合的に批判された。また、「五障三従」とか「変成男子」のような説が、一見女性を救済するように見せかけながら、女性を差別する「いかがわしい教え(平雅行)」だとされたことは画期的な見解であった。しかしながら、未だに女性と仏教の通史を書ける段階には至っていない。
さらに著者は、後半でケーススタディとして日本で初めて出家した(とされる)善信尼の出家について取り上げている。著者は『日本書紀』等の史料批判を行い、当該記述は道慈の作文である部分も大きいとしつつも、出家自体は事実とし、またそれが倭国のごく初期の出家者であったことや、倭国の初期仏教では尼が多かったことは史実と認めてよいと結論している。
「第2章 『日本霊異記』を題材に」(吉田一彦)では、『日本霊異記』に見える古代の仏教信仰について述べる。
『日本霊異記』は平安時代初めにまとめられた仏教説話集。これに続く9世紀の『日本感霊録』(逸文が伝わる)においても、女性の信仰者は数多く登場し、また女性差別的な要素は見られない。この頃には仏教は女性を差別していなかった。
著者は『霊異記』からいくつかの説話に注目し、当時の仏教の在り方について再考を促している。例えば中-28(中巻第28話という意味。以下同じ)では、国家の大寺が人々に開かれ、僧寺に女性も自由に参詣できたことがわかる。仏教は国家・男性に独占されていたわけではない。「すでに古代仏教の段階で、貴族にも、地方豪族にも、民衆にも、一定程度仏教は広まっており、女性の信仰も集めていた(p.55)」。
また家族で信心をしている家庭も描写される。貴族層では上-31、中下級官人では中-20、地方豪族層では下-16だ。下-16では夫妻で仏教を信仰するという、夫婦を単位とした仏教信仰が見られる。仏教が家族単位で信仰されたのは意外に古いことのようだ(家制度の成立前である)。民衆階層では下-13。この話では古代から民衆が仏教を信仰し、家族も仏教の使者供養をしていたことがわかる。「七日ごとの死者供養は、すでに8世紀に民衆階層にも流通していたよう(p.59)」だ。
また下-25では、漂流した漁民が「南無…釈迦牟尼仏」ととなえている。名号を称えることは意外と古い。下-25では酒を薬として貸し出し、その利息を取っている寺が出てくる。これはなかなか面白い経営である。そしてさらに面白いことに、その責任者が女性であったというのだ。
中-29と中-30には行基が登場するが、行基の法会には女性がたくさん参加していた。中-8では小さい子供を連れた尼も出てくる。子連れで出家したようだ。下-16は、身持ちの悪い女性を諭す話で、ここで死後業罰に苦しめられた霊が追善によって安らかになるという、日本的「成仏」の原型が語られていることが興味深い。
なお下-19の「舎利菩薩説話」が女性差別的であるかについて議論がある。これは、異形の誕生をした障害者らしき女性が「舎利菩薩」として敬われる話だが、途中、法会から排除される場面があるのだ。これは古代でも女性差別が行われていた証拠だろうか? 詳細は省くが、この場合は女性であるより異形であることが差別の要因であると考えらえる。むしろ、「女性で「菩薩」と呼ばれ、「化主(けしゅ)」と仰がれた仏教者がいたらしい(p.82)」ことが注目される。
「第3章 古代の尼と尼寺」(勝浦令子)では、尼と尼寺が古代にどう変遷したかを述べる。
まず、東アジアにおいて尼=比丘尼は、比丘(僧)に服従すべきものとされていた。著者は中国における尼の歴史を簡略に述べているが、それによれば、古代中国では比丘尼はいなかったのではないが数が少なく、また受戒の制度(10人の尼〈三師七証〉の承認が必要)の不備からその位置づけが曖昧だった。しかし宋代には尼の地位が確立し、比丘尼は皇帝からも厚遇された。一方、高句麗での尼の様子はよくわからない(全くいなかったわけではないと思う、としている)。新羅では尼がいて、日本と同じく一番古い出家は尼ということになっている。百済では、最初に作った寺は僧寺で、最初の出家も僧だったが、尼も少なくなく、日本には百済の尼が多く渡来している。
ここで著者は先述の桜井徳太郎氏の尼=シャーマン説を批判し、古代の尼は日本固有の存在ではないのだから、尼を日本のシャーマニズムの流れで理解するのは早計としている。
では、古代における日本の尼は実際どのような存在だったか。『万葉集』巻3-460・461に見える尼理願(あまりがん)は新羅の尼で大納言の家に寄住していた。8世紀では外国人僧尼が一家と共に生活することがあったらしい。邸宅に僧や尼が活動している例は木簡の研究からも明らかになり、特に尼には日常的に米を支給されている例がある。官衙にも尼や僧が配されていたようだ。つまり僧や尼は多様な活動を担い、また貴族の生活にも密着していた。
ところが僧尼令によって活動の幅が狭められ、尼の国家的な役割も失われた。僧尼令は唐令にはなく、道僧格(道教と仏教に関する臨時法)を日本でアレンジして作られたと見られる。ここでは僧尼がほとんど区別されずに扱われており、条文上は男女差別的ではなかったが、尼は僧綱になれないなど、実質的には僧が尼の上に立つ体制があった(尼の勤務評定を僧が行うなど)。また、僧位(師位、半位、複位など)については僧尼が平等の建前であったが、天平宝字4年の僧位制改正案で現れる最上の僧位「大法師位」が男性のみに与えられるものと考えられることから、「この時期に男性を基準とした僧位制というものが確立してきていることがうかがわれる(p.109)」。称徳天皇は尼の地位を上げようとし、「大尼」という尼位が作られたものの、称徳天皇後はそうした尼の優遇処置は一気になくなってしまった。
次に尼寺についてであるが、8世紀の尼寺の史料はたいへん乏しい。国分寺・国分尼寺がセットで建立されたように、僧寺と尼寺はセットであるのが望ましいという観念があったようだ。しかし寺の規模は僧寺の方が大きいのが通念であり、国庫からの給付も尼寺の方が少なかった。東大寺と法華寺(総国分尼寺)の墾田開発の許可を見ると、4対1の面積になっているのはその象徴である。このように、観念的には尼寺と僧寺は平等であったが実態上は差別されており、尼寺は徐々に退縮していった。ただ「格差がありながらも国分尼寺一緒に並立することの意味の方が大きかった(p.117)」と著者は考える。
こうして9世紀の桓武天皇の頃には尼はほとんど重要視されなくなった。古代の常識からすれば平安京の東寺・西寺のいずれかは尼寺であるべきだが、両方僧寺なのだ。しかし、このように国家機構から尼は排除されていったものの、その後女性の出家者は増え、また多様な活動を行っていくというのが面白いところである。
「第4章 女性の出家と家族関係」(勝浦令子)では、9世紀以降摂関・院政期までを中心に女性の出家について述べる。
平安時代の女性の出家には、「尼削ぎ」(当時の言葉)と「完全剃髪」(著者による歴史用語)の2段階があった(なお幼少の頃に行う専業尼になるための出家はこの頃はない)。「尼削ぎ」とは、剃髪ではなく髪を短くするだけのものである。ちなみにインドでは「比丘尼」「式叉摩那尼(しきしゃまなに)」「沙弥尼」の3段階があった。「式叉摩那尼」とは、出家後の2年間の猶予期間のようなもので、日本の僧尼令では規定がなかった。ところが9世紀に「尼削ぎ」=「式叉摩那尼」という観念が形成されてきた模様である。こうして「尼削ぎ」→「完全剃髪」と、女性の場合は2段階を踏んで出家が行われるようになったのである。
なお、藤原詮子の死を目前とした出家=「完全剃髪」を『小右記』では「比丘尼」になるというのではなく、「僧」「法師」になるといっている。あたかも男性になるかのような表現をしているのである。ともかく、髪の毛を中途半端に切っただけでは完全な出家ではないのはもちろん、受戒も必要だ。その意味で、法成寺の無量寿院に尼戒壇ができているのは注目される。
女性は出家して家政と関わったか。もちろん俗事を遠ざけるのが基本だったが、やむを得ない場合は月の半分で仏道を行い、半分は家政に携わる半出家のようなものもあったらしい。次に家族関係だが、まず出家しても同じ家で暮らし続けるということも一般的であった(尼寺がなかったことも関係しているのだろう)。だが夫婦関係は切れたと考えられていた。一方、親子関係は切れないとされていたようだ。自分の子供ともそうだし、自分の親との関係もそうである。こうなると、離縁のために出家をしたり髪を切ったりする場合もあった。
では、寡婦(未亡人)の出家はいつからあるか。出家で夫との縁が切れると考えていたら、夫を弔うための寡婦の出家はありえない。結論を言えば、夫の死後四九日あたりに出家する事例が10世紀以降に見られるようになる。これは「家」の成立と関係がありそうだ。寡婦の出家は「一生夫婦関係を継続していくために夫の菩提を弔う」という意味になっている。つまり、再婚して新たな「家」に移ることはしない、という意思が込められているようだ。この場合、出家しても明らかに夫婦関係は切れていない。
ただし、家族関係を完全に断ち切った出家というものもある。鎌倉時代になると戦乱が多く寡婦がたくさん生じたが、それらのうち夫の菩提を弔うのではなくて尼寺に入るという女性も多かった。こうして鎌倉時代には尼寺が復興されていくのである。
最後に、著者は尼になることで地位が少し上昇する現象について指摘している。「女性が男性と伍して活動している例は、官位をもった女性か、尼が目立(p.157)」つのだ。ただ面白いことに、女性の髪を切った姿は、刑罰を受けた姿と類似しているのだ。女性の場合、髪が長いことは身分を標示するもので、短い髪は身分の低さや刑罰を表象していた。にもかかわらず尼になることが身分上昇をもたらすとは奇妙である。
「第5章 尼と「家」」(西口順子)では、鎌倉から南北朝期にかけての尼や尼寺、家の追善供養などについてまとめている。
「尼と尼寺をもたない教団と、尼・尼寺をもつ教団が中世には存在(p.161)」した。ただ尼寺を完全に持っていないのは、浄土真宗に限られる。恵信尼や覚信尼は「尼」とついてはいるが正式に出家得度した尼ではない。「坊守(ぼうもり)」(住職の妻)も女性宗教者ではあるが職業的宗教者ではなく尼とはいえない。浄土真宗といえば、親鸞が妻帯していたために女性の役割が非常に大きいという印象があったのだが、この指摘が私には新鮮だった。
牛山佳幸氏は尼・尼寺の研究を行い、特に中世には尼寺が次々と再興されたことを指摘した。新しく建立された尼寺は父や夫を弔うための「菩提寺」が多い。これは宗派に組み込まれないものだが、禅宗や浄土宗でも尼寺が建立され、天皇家や貴族・上流武士の女性が入寺するようになった。こうして室町時代には「尼五山」「比丘尼御所」(近代以後の名称)が成立していく。なお「尼門跡」は近代になってできた言葉で「尼門跡制」などというものはなかった。ちなみに時衆には、尼寺ではなく道場に僧衆とともに生活する尼がいた。
次に、南北朝期の尼について中原師守の日記『師守記』を題材に述べる。師守の叔母の経仏房が時宗の六条道場で活動しているが、週に一度くらい実家に帰ってきて忌日供養をしている。一族のうち誰かが尼になり、先祖祭祀をする(家の仏事をする)役割を担っていた、という気配が濃厚だ。
忌日供養をするのは尼だけでなく僧も来るのだが、尼と僧で役割分担があったようだ。さらに、男性が亡くなった時と、女性が亡くなった時では、仏事を執行する寺が違うという指摘(伊藤唯真)が面白い。今の菩提寺・檀家寺の在り方とはちょっと違うのである。ちなみに、女性との関係ではないが、師守は父母の肖像を地蔵堂に持って行って毎月供養をしている。これも面白いことである。
中原家だけでなく、吉田神社の吉田家も肖像画を描かせていた。現在、遺影が先祖祭祀に重要な役割を果たしているのは、この頃の習慣が影響している。なお、時宗系では夫婦の肖像をどちらかが存命中に描かせていたらしい。
「第6章 真宗史のなかの女性」(西口順子)では、恵信尼と絵系図を取り上げている。
ここでは親鸞の行状を伝える「恵信尼書状」を分析しているが、彼女は「転女成仏・変成男子」のような考えが全くなく、むしろ女性のままで極楽に生まれると期待していたらしい。そして彼女は書状の文字から、専門的な教育を受けていない女性であったと考えられ、それが民間レベルで信じられていた極楽往生の姿であったと思われる。
次に「絵系図」を題材にして民衆がどのように忌日供養したかを述べる。「絵系図」とは、14世紀後半から真宗仏光寺派で制作された、絵付きの指導者・信者のリスト・系図である。これは門徒の統制・組織化のための実用的なものだったと考えられるが、なぜ名前のリストではなくわざわざ絵が必要だったのか。細かい議論は省くが、仏光寺派で本尊になっていた光明本尊とセットになるように絵が必要だったのではというのが著者の考えだ。特に光明本尊から出た光の筋が、系譜を繋ぐ朱線になっていることに象徴的な意味があると著者は考える。
そして「絵系図」は当初は住職の相承を示すものだったが、入信者リストとしての門徒絵系図、さらには門徒の絵過去帳へと展開していった。門徒絵系図には、門徒(村の人たち)が僧尼として描かれている。もちろん彼らは普通の門徒で僧尼ではなかったのだが(しかも真宗には尼はいなかったのに)、僧尼として描かれたのは、ある種の「理想化」がされていたのかもしれない。「生きているうちに絵系図に描いてもらうんだ」という気持ちもあったらしい。これは逆修の一種のようである。ただ、江戸時代になると没後に描かれることが一般化し、絵過去帳となっていった。
また絵系図は、個人単位でなく家族が描かれているのが興味深い。そして家族単位の絵系図(つまり家族の系譜が描いてある巻物)もあった。「夫も妻も、亡くなった家族のために絵像を依頼し、自分のその一員として描かせた(p.202)」。現代で、遺影をずらずら並べていくようなものかもしれない。しかし、村落寺院の成立とともに多くの絵系図は姿を消した。門徒と寺院が直接かかわるようになると、絵系図に描いてもらう意味合いが薄れたためである。ただ、現代でも絵系図が作られ続けている寺院も存在する。面白いことに、絵系図の制作は墓の代わりなのだという。
***
第6章はほかの章と少し毛色が違うが、1~5章の内容をまとめると次のようになるだろう。「古代においては僧尼は平等という建前で、僧寺と尼寺はセットという観念があり、人々の意識としても仏教が女性差別しているとは思っていなかった。ところが、僧綱など国家の仏教制度が整えられる中で、女性は仏教教団の中で男性の下に置かれ、また国家的な法会から排除されることで従属的な立場となった。こうして尼寺は衰退し、専業宗教者となる女性はいなくなった。しかし摂関期になると女性の出家は広がりだし、「家」制度の確立に伴って、一族の菩提を弔うという役割を負うようになった。そして戦乱の時代には尼寺が復興し「尼五山」などにつながっていった。」
なお本書では、仏教が女性差別的になっていったのはなぜかという問題についてはあまり触れていない。それは概ね東アジアに共通しており、日本特有のものではなかったらしいが、しかし古代においては男女を区別していなかった仏教が、中世ではすっかり女性差別的なものになっていたとすると、それはやはり社会の変化に対応していたに違いない。そこに家父長制成立が関係することは間違いないが、それだけで説明できるほど単純ではない、というのが本書の主張の一つである。
女性と仏教の関わりを学術的かつ平易にまとめた良書。
【関連書籍の読書メモ】
『家族と女性(シリーズ 中世を考える)』峰岸 純夫 編
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2021/03/blog-post_9.html
中世における家族の様相を女性の在り方を中心として述べる論文集。
『仏と女(シリーズ 中世を考える)』西口 順子 編https://shomotsushuyu.blogspot.com/2019/12/blog-post_21.html
仏教における女性のあり方を考える論文集。
『もう一つの中世像――比丘尼・御伽草子・来世』バーバラ・ルーシュ 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2024/07/blog-post_10.html
女性や絵解きなど、看過されがちだったものに光を当てる論文集。傑出した尼である無外如大が取り上げられている。
『日本女性史』脇田 晴子、林 玲子、永原 和子 編
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2022/08/blog-post.html
女性によって書かれた日本女性史。日本における女性の立場の変遷を平易に学べる良書。
『信仰と愛と死と(人物日本の女性史 7)』円地 文子 監修
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2023/01/blog-post_2.html
信仰に生きた女性を江戸時代中心に述べる本。尼となった女の生き方を考えさせる価値の高い本。