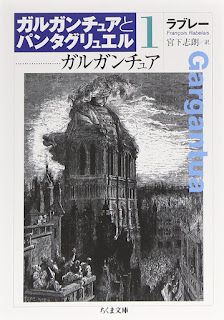この本を初めて見たのは神保町の古本屋だった。古びた岩波文庫の5冊揃い。渡辺一夫訳の伝説的な作品。
当時は絶版の岩波版がほとんど唯一の『ガルガンチュア』だったから、確か9000円くらいしたと思う。お金がない時で、当然買えなかった。神保町へ行くたび、もうちょっと安いセットはないものかと一時期は探していた。
ちくま文庫から宮下志朗訳が出版されたのが2005年。もちろんすぐに購入した。この世界文学史に燦然と輝く作品が、一体どのようなものなのか期待してページをめくったのを覚えている。
それは、期待以上の読書体験だった。この本は、とにかく、笑える。荒唐無稽な巨人王の生涯! ナンセンスと言葉遊びの嵐! 下品なことも高尚なこともごった煮にした、百科全書的で無秩序な物語。
鋭い社会風刺、文明批判、そういうものもあるが、それは横に措いてもとにかく面白い(もちろん理解すればもっと面白い)。16世紀のユマニスム——つまり「人間中心主義」が作品のありとあらゆるところに横溢している。「ガルガンチュア伝説」という中世的な素材を扱いながら、教条主義に凝り固まった無益な規矩から解き放たれた人間が「自由」を存分に謳歌する。ここでは優等生的な人間でなく、ありのままの人間そのもの(巨人だからスケールは桁外れだが)が主人公である。
ぜひ紹介したいのが第13章「グラングジェ、ある尻拭き方法を考案したガルガンチュアのすばらしいひらめきを知る」。主人公たる巨人のガルガンチュアは、この章では「何を使ったら一番気持ちよくお尻が拭けるか」を父上のグラングジェに講釈する。
ビロードのスカーフ、深紅のサテンでできた頭巾の耳当て、母上の手袋、で拭くのもまずまず宜しいそうである。逆にカボチャやほうれん草の葉っぱ、レタスやバラは気持ちよくないらしい。カーテン、クッション、ゲーム台、そういうものは気持ちよい。
最上のお尻拭きを明らかにする前に、ガルガンチュアは「脱糞人に雪隠が話しかける歌」をグラングジェに聞かせる。
うんち之助に、すばらしい「世界文学」! 下品なものを下品なままで文学に表現出来るようになったのが、16世紀のユマニスムであるような気がする。ユマニスム万歳!
びちぐそくん、
ぶう太郎に、
糞野まみれちゃん、
きみたちのきたないうんこが、
ぼたぼたと、
ぼくらの上に、
落ちてくる。
ばっちくて、
うんちだらけの、
おもらし野郎、
あんたの穴がなにもかも
ぱかんとお口を開けたのに、
ふかずに退散するなんて、
聖アントニウス熱で焼けちまえ!
さらにガルガンチュアの試行錯誤は続く。おんどりやめんどり、子牛の皮、ウサギ、ハト、弁護士の書類袋などでも尻を拭いてみた。が、「しかしながら、結論として申しますれば、うぶ毛でおおわれたガチョウのひなにまさる尻拭き紙はないと主張いしたしたいのであります」とのことである!
フランソワ・ラブレー先生の世界文学上に名だたる作品が、こういう調子なのだから、これはもう驚きというより痛快な読書体験であった。ありのままの人間を描こうとするなら、その最も汚い部分、つまり排泄だって描く必要がある。人は誰でも食べてそして排泄する。我々は誰でも「うんち之助」であり「糞野まみれちゃん」なのである。
こういうテーマをそれまでの文学ではあまり扱ってこなかった。というより、未だにそうである。
でも世の中にはやっぱりそういうテーマで文学を書いてみようという人もいるもので、安岡章太郎はそういう作品だけを集めた『ウィタ・フンニョアリス』というアンソロジーを編んだ(これも題名が洒落ている。「ウィタ・フンニョアリス」はもちろん森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』のもじりだ)。
この本では、主に日本近代文学の書き手による糞尿やトイレを題材にした短編が集められており、芥川龍之介、谷崎潤一郎、吉行淳之介、北 杜夫、遠藤周作といった名前が並ぶ(『ガルガンチュア』の第13章も渡辺一夫訳で所収)。全体を通じて意外に思うのは、糞尿が汚いものという観念が薄く、厠の匂い(当然昔は水洗便所ではなかった)には一種の情緒すらあるという考えである。作家たちには、世の中が水洗便所に変わっていき、清潔第一になってしまったことが何か寂しいという郷愁があるようだ。
私などは水洗トイレの方がいいだろ! という現代人で、汲み取り式便所の匂いにどんな情緒があるのか理解できないが、明治や大正の文豪たちにとっては、糞尿は現代の人に比べてずっと身近なものだった。何しろ、昔(といってもそんなに昔ではない)は人糞は肥料として使われていたので、それは大切に集められていた。
以前、江戸時代の農書の勉強をしていたとき、「上農(上手な農家)はあたりかまわず小便をしない」というようなことが書かれていて、何のこっちゃと思ったら、小便はちゃんと溜めておいて肥料に使うべきで、畑の隅で立ち小便をしているようではダメだ、という意味だった。汚いからとか、はしたないから立ち小便をしてはダメということではないのである。
そういう次第だから、化学肥料と水洗便所以前の人たちにとっての糞尿は、今の私たちとは全然違うものとして認識されていた。だが化学肥料が利用できるようになると、自ずから糞尿は役立たずとなり、ただ穢らしいもの、処分すべきもの、できれば目にしたくないものに変わっていった。
そうした風潮に真っ向から異議申し立てをし、糞尿こそ世界を救うとのたまった学者がいる。中村 浩という人だ。
この人の『糞尿博士・世界漫遊記』という本は、めっぽう面白い。中村 浩は幼少の頃よりなぜか糞尿に心惹かれ、微生物学者となってからも「ウンコ博士」として糞尿の研究を続け、ついに糞尿からクロレラを培養して直接的に食糧生産する方法を編み出す。妖気漂う臭気芬々たる研究室から、「緑のパン」が生みだされたのだ。
この功績により、中村はソ連から招聘される。宇宙空間では糞尿はたくさん溜めておけないので、その水分を浄化し、栄養分を食糧生産に使えるなら、宇宙での長期滞在の役に立つ。そういうわけで、日本では奇人・変人扱いされていたウンコ博士が、ソ連へは重要人物として招聘されたのだった。このほか中村は、香港、インド、エジプト、イタリア、スイス、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカと巡り、各地で糞尿談義をふっかけるのである。
中村の夢は、糞尿という毎日生ずる大量の有機物を有効活用し、クロレラを中心とした食糧生産をすることで地球から飢えの心配をなくすという「食糧革命」なのだが、世界各地での彼の興味関心は、糞尿をどうやって排泄し、利用し、処分するかという実務的な面だけでなく、糞尿をどう語り、どう扱うかという文化的側面にまで渡っている。それどころか、本書には「糞尿からの文明批評」というべき風采があって、「糞尿をキタナイもの、イヤラシイものと目のかたきにしていては、人類の進歩はのぞみえない」とか、「人間は糞をひる葦である」といった面白い警句が並ぶ。しかもユーモアいっぱいの!
本書の白眉は、水と太陽と糞尿さえあれば人は自給自足できるんだ! という「食糧革命」の理論を証明するために、自らアリゾナ砂漠で「人体実験」をするくだり。砂漠の朽ちた一軒家に身を寄せて、小さな池を掘り、そこに糞尿を栄養としてクロレラや水草を培養、それらを食べて3ヶ月生きるという何ともワイルドな実験である。
そして中村は池を掘ってから3週間で自給自足の体制を整えた。農業だったらこうはいかない。自給自足できるのに1年はかかるし、その上かなりの面積が必要だ。たった5坪の池で大人一人が生きていくというのは、ものすごい生産性である。中村の夢見る「食糧革命」も絵空事ではないのだろう。
本書のエピローグにはこういう言葉がある。「人間の生活をみてみても、食べることには熱中するが、フンベンなどは口にするもいやらしいこととして葬りさっている。この誤った観念が今日の公害問題を引き起こしたのである。近代工業においても、生産品を高く売りつけて儲けることには熱中するが、工業廃棄物などはコッソリ始末してしまえという安易な考えがあった」その通りであると思う。
ところで、糞尿が社会から隠されてしまうと、逆にそれを覗き観たいと思う人が現れてくる。隠されたものを愛でる行為はそれだけで淫靡なものである。この世界にはそういう、糞尿をなぜだか偏愛している人たちがいて、スカトロジストと呼ばれている。
ある種のポルノビデオには、そういう人たちのための過激な排泄や糞尿表現があるだけでなく、糞便を食べることすらする。ちょっとここまでくると、厠の匂いの情緒とかそういう文学的なものから離れて、ただのゲテモノ趣味のようにも見える。
でも、知り合いからホンモノのスカトロジストの話を聞いてみたら、その活動(?)は結構真面目で、まず彼らはご飯をいただくというところからするそうだ。そのご飯が体内を通って、そして糞便になって出てくる。それをまたいただく——というのが私には全く理解できないが、そういう行為を通じて「生の営み」を実感するんだとかなんとか。
その話を聞いて、最高のスカトロ文学というのが何かひらめいた。それは、『Dr.スランプ(アラレちゃん)』である。アラレちゃんはいつもうんちを持って走り回っているが、それはアラレちゃんがロボットであるため自分には絶対にうんちができないからで、要するにアラレちゃんにとっての生命の象徴がうんちなのだ(と鳥山 明が実際に考えたのかどうか知らないがそういうことにしておく)。
うんちは汚いが、その汚さは人工的に生み出せるものではなく、生命にしか生み出しえない汚さなのである。だからアラレちゃんはうんちに憧れている。かつて、これほど純粋に糞尿に憧れる主人公を登場させた文学作品があっただろうか。
ラブレーが『アラレちゃん』を読んだら歯ぎしりするに違いない。糞尿への憧れが、ロボットによって表現されるなんて、なんて文学的なんだろうか!