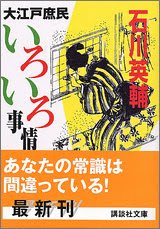島津氏の琉球侵攻について述べる本。
江戸幕府の開創間もない1609年、島津氏は琉球に攻め込み、琉球を実質的に属国化した。本書は、その際に琉球が抵抗らしい抵抗もせずに服属したという通説を覆し、それなりの武力を持ち戦ったということを示すことを目的の一つとして執筆されたものである。
著者は、島津氏の琉球侵攻を「琉日戦争」と位置付ける。それは琉球は独立国であったのであり、また島津氏の侵攻は江戸幕府の許可の下に行われたものであったので、これは日本と琉球国の戦争であった、と見なすからである。そしてそれが一方的な侵攻ではなかった(琉球は抵抗し、島津氏側にも損害があった)ことを含意して「戦争」という言葉が使われている。
私が本書を手に取ったのは、「そもそもなぜ島津氏は琉球に侵攻したのだろうか」という疑問からである。それはしばしば「琉球との貿易の利益を独占するため」と説明されるが、そもそも琉球侵攻以前から島津氏は(大名としては)琉球交易の利益を独占していたし、琉球侵攻が明にバレると大きな国際問題に発展する可能性があった。後述するように明との国際関係が微妙だったこの時期に、あえてリスクを冒して琉球を属国化する理由がよくわからなかったのである。本書を読み終えた今でも、その理由には不明確な点が残っているが、私なりに理解したことをメモしておこうと思う。
「第1章 独立国家、琉球王国」では、琉球王国の成立とその繁栄・衰退が述べられる。琉球国はもともと3つの国(三山)からなり、それが尚氏により統一されて琉球王国となった。特筆すべきことに、統一前から琉球三山は明から貿易を優遇され、閔人三十六姓の派遣、無制限の朝貢回数許可などを得ていた。1458年に鋳造された「万国津梁の鐘」はその繁栄を物語っている。琉球は「万国の架け橋」として中継貿易で栄えた。
しかしその繁栄は、あくまで明からの優遇措置に基づいていた。明から供与された大型船とそれを動かす人材がなくては琉球は東南アジアまでの長距離航海をすることができなかった。よって中国沿岸の倭寇問題が沈静化していく15世紀中頃、明が優遇をやめ琉球との貿易を制限すると琉球の優位は失われた。「朝貢貿易の全盛期は三山時代から琉球王国が成立した頃まで(p.23)」であった。
こうした状況で1470年、琉球ではクーデターが起こり第二尚氏王朝が成立。奄美大島から与那国島までが琉球王国の版図となった。この版図拡大の背景には、貿易の衰退を埋め合わせる必要があったことが考えられる。またこの頃、東アジアの交易世界は「銀」をめぐっての新たな局面を迎える。日本では石見銀山の開発と新たな精錬法によって世界の3分の1ともいわれる莫大な銀が算出。逆に中国では銀が貨幣として用いられるようになり大きな需要が生まれた。よって民間の商人が銀を運んだのである。明は海禁政策を実施し、民間貿易を禁止していたから、これは違法な交易だった。すなわち16世紀からの新たな倭寇=違法海商の登場である(倭寇といえども中国人が多かった)。特に暴徒化した倭寇が沿岸を荒らしまわった「嘉靖の大倭寇」は、琉球の那覇まで押し入っていた。
こうした倭寇被害が大きくなったのは厳格すぎる海禁政策の帰結だったとし、明は約200年続いた海禁政策を一部緩和。これによって倭寇出現の根本原因が取り除かれた。日本と琉球は引き続き渡航禁止の対象であったものの、民間交易が認められた漳州の月港は空前の活況を呈する。これは、琉球が中継貿易で担っていた役割が漳州の月港に移ったことを意味した。この頃、(倭寇でない)日本人も東南アジアへ貿易に乗り出し、各地に日本人町が作られた。琉球自体が、日本人町の一つのような存在になっていた。
「第2章 九州の覇者・島津氏と琉球」では、島津氏が琉球とのいびつな関係を築いていく道程が語られる。島津氏・薩摩が琉球といつごろから交易をしていたのかは不明だが、15世紀後半、管領細川氏は日本国として琉球との通商を求め、その取次役として島津氏が活躍するようになった。その背景には細川氏のライバルである大内氏(山口)の交易活動もあったが、島津氏はこちらの取次も行っていた。16世紀前半には細川氏が衰微し、大内氏が琉球交易の中心となった(なお日明貿易は1547年の大内氏の遣明船を最後に途絶した)。
一方島津氏は、同じく16世紀前半頃から南九州から琉球へ向かう商船を印判制度を用いて統制しようとした。1508年、奥州家島津忠治は琉球王に「印判状を持っていない商船の積み荷は没収してかまわない」という島津奥州家が琉球交易を独占できる制度を提案している(『旧記雑録』)。このような提案がされたのは、私貿易の商船が少なからず琉球へ渡海していたからに他ならない。同時期、南九州と朝鮮との交易は途絶し、対琉球交易の比重が高まっていた。しかし琉球にとっては島津氏へ貿易を一本化する理由はなにもなく、この提案は受け入れられることはなかった。
16世紀前半、南九州は島津氏の本家争いである「三国大乱」が起こり、16世紀中頃にそれに勝利し南九州を統一したのが島津忠良である。その子貴久に琉球は「あや船」という正式な通交船を送り、倭寇対策として島津氏の印判制度が適用されることになった。琉球では尚元王の冊封が直前に迫っており、(交易品を売りさばく必要があるため)外来の商船や治安維持を必要としていたから、一時的な措置として印判制度を認めたものと思われる。ところが、当然のことながら、島津氏ではこれを恒常的制度として確立しようとした。ただし、島津氏直轄領と服属した国人領主の港では発給が確認されているが、どの範囲で印判制度が機能したのかはわからないそうだ。島津氏は印判(朱印状)を持たずに渡航する商船の取り締まりを琉球へ求めるようになる。
島津氏は琉球が思うように違反商船を取り締まらないことを咎め、円覚寺を通じての外交ルートも使い、圧力をかけた(この頃の琉球では禅僧たちが派遣され外交を担っていた)。これに応じる意味もあったのか、1575年、琉球はあや船を島津義久の家督相続を祝賀するために派遣。すると島津氏は印判のない船の入港をはじめ、数々の琉球の「非礼」を問いただした。これは「琉球側にしてみれば理不尽な話(p.83)」であったが、琉球の国力が低下していたことから、これらには琉球側が大きく譲歩して決着した。
またその10年後、琉球から天王寺の祖庭和尚が鹿児島へ派遣されたが、その際も使者の派遣が途絶えていることや進上物が軽微なことなどを非難された。この頃から島津氏は明らかに琉球を意図的に一段低いものとして扱うようになっている。かつてとは違い、島津氏は九州の大部分を手中に収め、強大な戦国大名となっていた。その軍事力・政治力を背景に印判制度は領国外にまで機能した。1852年に堺から琉球に渡海した商人川崎利兵衛はわざわざ鹿児島に立ち寄って家老の「添状」を取得している。おそらく「添状」のみならず印判状も発給されたのだろう。境の民間人にまで印判制度が浸透していることがわかる。
「第3章 豊臣秀吉の東アジア征服戦争」では、豊臣政権下における琉日関係の変化が述べられる。島津氏は九州統一の一歩手前まで行きながら、豊臣秀吉の圧倒的な力の前に全面的な戦争を経ることなく降伏。当主の島津義久は剃髪して龍伯と名乗った。ここに琉球への外交権は秀吉に移り、島津氏はその取次役となった。秀吉は琉球を日本の属国であるとみなしており、琉球の入貢が行われなければ島津氏を亡ぼすとまで恫喝した。しかし島津氏の家臣は秀吉へ反発しており、義久は秀吉に面従腹背の態度をとった。それでも義久は、1588年、秀吉へ服属するようハッタリを交えて勧める使節を送った。
折悪しくその頃、琉球では尚永王が30歳の若さで死去。世継ぎがいなかったため、傍系の浦添尚家より26歳の尚寧王が即位した。こうして1589年、尚寧王の使節は京都を訪れ秀吉に謁見した。琉球が日本の中央政権と接触するのは約100年ぶりのことであった。琉球は、秀吉の恫喝に屈した面もあるが、それ以外の事情もあった。尚寧王の即位は、明に冊封のための入貢を行う必要があることを意味していた(明に王として認めてもらうため)。そのために多額の費用が必要で、それに日本の銀を当て込んでいたのだ。明への冊封を見据えて、明に敵対的だった秀吉に従属したのは皮肉というほかない。
このあたりから秀吉・島津氏・琉球・明の外交は怒涛の勢いで進んでいく。秀吉は明を征服することを表明。島津氏にも軍役の負担を求めた。島津氏は琉球を属国扱いとしてその軍役の一部(兵糧)を琉球に割り振った。著者は、この割り振りの背景に亀井茲矩(これのり)の存在を推測している。というのは、秀吉は茲矩に琉球国を褒美として与えており、茲矩は「琉球守」(!)を名乗っていたのである。つまり名目上は琉球は改易され茲矩に与えられるのが筋であった。島津氏としてはそれは困る。そこで軍役の一部を琉球に負担させ、実質的に琉球が島津氏に従属していることを示し、琉球の改易を阻止しようとしたのではないかという。これは功を奏し、1592年、秀吉より琉球が島津氏の「与力(従属国)」であると公式に認められた。ちなみに茲矩には、まだ征服してもいない明の台州(浙江省)が代わりに与えられ「亀井台州守」を名乗った。
このような緊迫した状況で、同年、琉球はようやく正式な国交船「あや船」を関東平定を祝賀するという名目で秀吉に送った。しかし進上物は粗略で、割り当てられた兵糧についても無回答の状態であった。結局、秀吉に会うこともないまま「あや船」は帰され、義久のメンツはつぶされた。「与力」の失態は主である義久の責任だからである。それでなくても島津氏は失点続きだった。朝鮮出兵には割り当てられた人数を供出せずしかも出兵が遅れた(義久が後ろ向きだった)。その上、反秀吉の性格がある梅北国兼の乱が起こって義久の弟の歳久は自刃させられていた。
一方、琉球は明に秀吉の計画を裏で通報していた。しかもその背後には、義久の周辺にいた明人の存在もあった。琉球も薩摩も、表向きには秀吉に従いながら、背後では反秀吉の動きが蠢動していたのである。しかしながら表立って秀吉に歯向かえば滅ぼされる。そこで琉球は、薩摩藩に指定された兵糧は求められた半額であるが供出した。薩摩藩でも、義久は一貫して秀吉に面従腹背だったものの、朝鮮に渡海した島津義弘(義久の弟)は奮戦し、泗川の戦いでは少ない手兵で獅子奮迅の働きをした。しかしその裏で、薩摩在住明人や禅僧のネットワークによって、明と琉球・薩摩の間で停戦(反秀吉)工作が続けられたようである。そんな中、秀吉が死去。秀吉以外、誰も日明間の戦争は望んでいなかったので戦争は即刻終結したが、問題はその戦後処理であった。
「第4章 徳川政権の成立と対明交渉」では、琉球が対明戦後処理に巻き込まれていく次第が語られる。家康は、明との講和交渉を島津氏に命じた。泗川の戦いで島津氏が捕虜にしていた茅国科を明に送還し、それにあわせて交渉しろというのだ。しかし家康が提示した条件は、秀吉のそれを引き継いで高圧的なものだったので交渉は決裂。一方、琉球はそれまで「国方多事」を理由に明に尚寧王の冊封を求めていなかったが、戦争が終結してようやく明に冊封の要望を行った。明は治安の懸念などを理由にこれまで通りの冊封には難色を示したものの、琉球の必死の説得によって尚寧王の冊封が決まった(実際の冊封は後述)。もちろんこれには、これまでの反秀吉の蠢動が効いていた。琉球は、徳川政権とは距離を取ろうとしていた。
ところで、この時期の琉球の交易船には難破や漂着などの事故が多かった。先述の通り、明からの技術支援(閔人三十六姓、大型船の供与)なしでは、琉球の造船・操舵の技術は未熟であったためである。1602年、琉球船が東北伊達領へ漂着。家康はこれを手厚く送還した。薩摩藩は琉球にその返礼を送るように諭したが琉球はそれを無視。1604年には琉球の進貢船が平戸に漂着。続いて甑島(鹿児島)にも琉球船が漂着した。これが琉球を窮地に追い込んでいく。
薩摩藩からすれば、従属国である琉球の船が他藩領に漂着した場合、それを監督する責任は薩摩藩にあると解釈される。よって平戸に漂着した琉球船の交易品を回収した。が、琉球船は薩摩藩の監督なく勝手に帰国してしまう。島津側はこれに対する報復として甑島の漂着船とその船員を抑留。義久は琉球の非礼を難詰した。他方、徳川幕府としては漂着物の管理は公儀の権利として平戸の琉球船の積み荷を回収しようと試みた。島津氏としてはこの介入は無視できない。またこの頃、琉球は室町時代に島津氏に与えられたものだとする「嘉吉附傭説」を義久は主張し、琉球に従属を求めた。しかしいつまでも琉球は家康に聘礼を行わず、無回答状態を続けていた。
この間、島津氏の当主は島津忠恒(義弘の息子、義久の甥)に移り、忠恒は奄美大島への侵攻を計画した。これは唐突な感じが否めない。本書ではその理由を、(1)忠恒の家督相続を祝賀する使節を琉球が送らなかった、(2)家康に聘礼しない、(3)平戸漂着問題、(4)朝鮮軍役や亀井茲矩の件の無視、としているがここはよくわからない。徳川政権・島津氏と距離を取ろうとしている琉球を力によって属国の地位に留めるための出兵ということなのだろうか。なお義久としては大島侵攻は反対で、その協議をボイコットしている。また、この大島侵攻には財政上の理由もあったという。江戸城普請のために島津氏には石材運搬船300隻の建造が命じられ、また義弘養女の結婚など出費が重なっていた。1606年、島津忠恒は経済的な問題を後年に持ち越さないためには大島出兵の断行が必要だと表明している。要するに、侵攻を理由に領内に軍役(人・物・金)を負担させ、これから京都伏見藩邸の費用などを捻出しようというのである。
同じ頃、忠恒は家康より「家」の偏諱をもらい「家久」と改名(本稿では以下も忠恒で統一)。また徳川家康は島津氏の琉球侵攻を許可したという。そして1606年秋、島津氏は大島出兵を計画していたが中止する。明からの冊封使・夏子陽が来琉したからである。これによりようやく尚寧王は正式に王となった。この際、夏子陽は、茅国科を送還した海商(坊津の鳥原宗安)の接見を求めた。このため、琉球は薩摩に「あや船」を送り忠恒の家督相続を祝賀し、あわせて夏子陽の要求を伝えた。島津氏はこの機会をとらえ、夏子陽への外交文書と琉球王への外交文書の2通を琉球に渡した。夏子陽宛は、明の商船の薩摩へ毎年来航するよう求めるもの、琉球王宛ては、家康への聘礼を求めるとともに、明との交易の仲介を求めるものであった。これには家康の意向があった。家康は明との国交正常化が難しいことを踏まえ、琉球を通じて日明貿易を行う考えだったのである。これもよくわからない点である。琉球を通じた日明貿易をするならば、島津氏の琉球侵攻はむしろ止めた方がよいと思われる(実際、家康は琉球侵攻には積極的ではなかったという)。
ともかく、この時点で琉球の命脈は日明貿易の仲介を担えるかどうかにかかっていた。それができれば家康の目的は達せられるため、島津氏の琉球侵攻には大義名分がなくなるからである。琉球は明に国書を送り、漳州月港の民間商船が琉球に来航できる制度(文引制度)を設けることや、閔人三十六姓再下賜などを求めた。琉球は貿易体制の再構築を図ったのである。ところがこの要求は受け入れられなかった。明は、「琉球に民間商船を往来させることは、実態は陰で倭と交易すること(p.220)」であるから、密貿易勢力を増長させるとして痛切に批判した。
「第5章 島津氏、琉球へ侵攻」では、琉球侵攻の具体的な経過が述べられる。1607年には具体的な動きはあまりないが、島津氏は琉球侵攻を準備していたようだ。しかし1608年には、幕府は琉球出兵を中止するよう島津氏に連絡した。対明の講和交渉に支障をきたすおそれを考えてのことと著者は推測している。これを受け、島津氏としても外交交渉による解決を目指してはいた。
しかし1609年2月、義弘から尚寧王へ最後通牒的な書状が届けられた。それは「亀井茲矩の件、朝鮮軍役の不履行、聘礼使者派遣の遅滞、日明講和の仲介に同意しながらそれを守らなかったことを糾問(p.225)」し、家康からの琉球誅罰の朱印状が出されているとするものであったが(真偽不明)、あわせて、日明交易を仲介するならば侵攻しない、という趣旨のことを述べている。しかし先述の通り、琉球の交易の要求は明に拒絶されており、これは土台無理な話であった。こうして島津氏は琉球への侵攻を開始したのである。
以下、本書では侵攻の具体的な経過が描かれており、琉球側が無抵抗ではなかったということを立証しているが、詳細は割愛する。一つだけ述べれば、薩摩側には200名程度の戦死者が出ていることから琉球もある程度反撃したのは確かとのことである。
しかしながら全体としてみれば、琉球国はかなり一方的に負けている。といっても島津氏の軍が圧倒的に強かったとはいえない。また、彼らは軍規が徹底されていなかった。本当は琉球側に講和の意思があれば即時講和することを命じられていたのに、軍功を優先してどんどん進撃したり、軍の内部で対立を抱えていたことは、島津軍が軍隊としては未熟だったことを示している。それでも琉球側は海側の防御のみに気を取られ、陸からの進撃を想定していなかったことも仇となって敗北した。
「第6章 国破れて」では、侵攻後の琉球国がどうなったかが述べられる。島津軍は首里城を接収し、その宝物を運び出した。勝手に持ち出すものがないよう、慎重を期して点検・運搬し全部で10日間もかかったという。家康は琉球を打ち取ったことを「比類なき働き」と喜び、忠恒に琉球の仕置(支配)を仰せつけた。
一方、琉球は日本が攻め入ったことをすでに明に密書を送っていた。琉球が明に引き続き朝貢することを望んでいた島津氏は、これをもみ消すため「島津氏が攻め込んできたが彼らは慈悲深く信頼に足る国である」とする明への報告を琉球に行わせるとともに、問題の密書のありかを突き止め公銀100両で民間人より買収した(実際に買収したのは琉球の朝貢使節)。
また琉球はついに家康に聘礼を行った。尚寧王は明朝の装束で家康に対面。「家康は尚寧を捕虜としてではなく、一国の王として丁重に待遇(p.307)」した。
その後、琉球国には石高制が導入され、また奄美地域が分離されて後に島津氏による直轄地となった。また王家(尚家)は島津家の家臣となり、名実共に島津氏に従属する存在へと変わっていったのである。その一方で、明には引き続き独立国であるという体裁をとり続けることになった。というのは、家康や島津氏にとっての琉球の価値は、明との交易ができるという点が大きかったし、家康としても琉球を通じての明との講和交渉を期待していた。
そこで忠恒の圧力の下、琉球は明に対し使節を送り、日明貿易をできるようにするよう求めた。しかし明は異例の使節派遣を問題視するとともに、使節の中に「畜髪の倭人(=禅僧ではない)」がいたことなどから、交渉の背景に日本がいることを見抜き、逆に琉球の朝貢間隔を10年に1回へと減じた(元々は2年に1回)。事実上の朝貢停止である。
この強硬な措置に驚いた琉球は、以後さまざまに交渉して明との関係改善に努め、1623年に5年に1度へと緩和されている。
一方島津氏は琉球征服以降、渡航許可証による本格的な統制を試みている。征服後にも、民間の商船は盛んに琉球に渡海していた。島津氏の統制を受けない民間商人たちは琉球との交易を行っていたのである。島津氏の統制がどこまで有効に機能したかは不明だそうだ。
対して、幕府の方は貿易から手を引いていく。1611年には大名による朱印船派遣を停止。「島津氏は琉球を利用してルソン貿易を行おうと、琉球国王に対する朱印状を幕府に申請し、認められた(p.324)」。「琉球がフィリピンとの交易を行うのは約20年ぶりであった(同)」。しかしこれは最後の仇花というべきものだったかもしれない。1616年に家康が死ぬと、徳川秀忠は日明関係の回復を諦め、徐々に海外への門戸を閉ざしていくからである。
「第7章 「黄金の箍」を次代へ」では、さらにその後日譚が語られ、羽地按司朝秀(はねじあじちょうしゅう)の改革によって筆が擱かれている。これは最後に少し語られるに過ぎないが、「我々が「伝統」と考える沖縄のさまざまな仕組みや文化・風習は「古琉球」の次代から連綿と伝わったのではなく、その多くが羽地の改革路線のうえに誕生・成立したものなのである(p.339)」と書かれており興味深い。
全体として、本書は書きぶりは平易で読みやすいが、編年的に書かれておらず、年代が行ったり来たりするので経過の理解は困難だった。このメモを書くことでようやく見えてきた感じである。そして当初の疑問だった「そもそもなぜ島津氏は琉球に侵攻したのだろうか」については、はっきりとした解答が得られなかった。
「貿易の利益を独占するため」とはいえ、侵攻後も民間商船は往来しているし、朝貢を通じた交易については10年に1回という大打撃を被り、侵攻前に比べて却って不利になっている。侵攻後に島津氏はどのような点で得をしているのだろうか。長い目で見れば、琉球国は薩摩藩の「植民地」として徐々に搾取されていくのであるが、短期的には損失の方が大きかったように読めた(本書の記述でははっきりしない)。
ただし、名目的な面では侵攻は理解できる。属国扱いしてきた琉球が、秀吉の死後、急に距離を取り始めたので、このまま独立国の顔をされては「外聞」が悪いと島津氏が考えたとしても無理はない。また軍功なく初代藩主となった島津忠恒にとって、琉球征伐が自らの求心力を高める軍事イベントとして捉えられたであろう。こうした政治的な面の方が、貿易云々の実利面よりも琉球侵攻の真因であったのかもしれない。
ともかく、独立国であった琉球が日本の版図に組み込まれ、やがては沖縄県となっていく契機が島津氏の琉球侵攻であり、これは近代日本の成立にも大きく影響してくる事件であった。にもかかわらず、琉球侵攻はこれまであまり語られてこなかった。近年、多くの研究が進展し、それを踏まえてまとめたのが本書だということだが、未だ不鮮明なところが多く残されている。
琉球侵攻に関する現時点での研究を総合的にまとめた本。
【関連書籍の読書メモ】
『「不屈の両殿」島津義久・義弘—関ヶ原後も生き抜いた才智と武勇』新名 一仁 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2021/12/blog-post_20.html
島津義久・義弘を中心とした歴史書。琉球侵攻に至る薩摩側の動向については本書が参考になる。