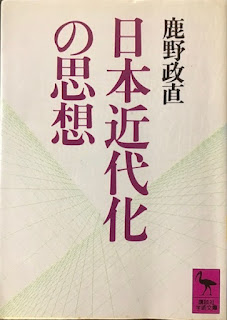神社というと、古代から連綿と続いてきたもののように思われている。しかし明治政府の神仏分離政策によって、近世と現代では神社や神道の在り方は大きく変貌している。では江戸時代の神社はどのようなものだったのか。本書はそれをわかりやすく述べたものである。
「現代と古代・中世の神社」では、近世の前提となる古代・中世の神社について手短にまとめている。古代には神社を統括する役所として神祇官が設けられた。『延喜式』の「神名帳」によれば、神祇官に召集された官幣社737座、それに準じる国幣社2395座が記載されており、これらを合わせて式内社という。また伊勢神宮・石清水・賀茂など、奉幣使を発遣する22社も永保元年(1081)に定まった。これらには国家とつながった神社であったが、摂関政治期や院政期には神祇官が各社に奉幣使を遣わして行う「祈年祭」が断絶、応仁の乱以降は国家との関係は廃絶した。天皇の即位に伴う大嘗祭も応仁の乱以降は挙行されず、戦国時代には朝廷や大神社は荘園領主としても衰退した。
「江戸時代の神社」では、朝廷から地域の中小神社までを概説する。徳川政権は厳格な宗教統制をもって臨んだが、自らは「国家安全・五穀豊穣の祈祷のための装置をもたずに、この役割を古代から伝統的に担ってきた天皇・朝廷や大神社に委託した(p.12)」。国家祭祀の仕組みは3段階で行われていた。
第1に、天皇みずからが行う「毎朝御拝(まいちょうのぎょはい)」といった国家祭祀である。天皇みずから行えない時は関白もしくは白川家が代官を務めた。白川家は神祇官の長官である神祇伯を世襲した家である。幕府は白川家に対し家領として200石を安堵したうえに役料を支給した。幕府が公家に役料を与えたのは他に武家伝奏・議奏があるが、幕府としては白川家にこれと並ぶ不可欠の役割を認めていたということになる。
第2に、四方拝・新嘗祭・大嘗祭など朝廷の公式行事として挙行される神事である。新嘗祭・大嘗祭(即位後に初めて行う新嘗祭)は、現在の朝廷の中心であるが、新嘗祭は寛正4年(1463)に後花園天皇が行って以来中絶していた。大嘗祭は綱吉政権下で、朝廷復古を目指す霊元上皇の強い意志によって再興された(東山天皇即位後)。大嘗祭が行われたのは後土御門天皇以来、221年ぶりのことであった。その後大嘗祭は中断したが、吉宗は朝廷側に働きかけて桜町天皇の即位後の大嘗祭が行われた。「吉宗政権は、幕府による国家統治のために制度充実をはかる一環として、朝廷儀式の再興を実現させ(p.21)」、新嘗祭についても朝廷の正式行事として再興したのである。とはいえ、幕府は「祈年祭」は朝廷が要望したにも関わらずそれを再興させず、また諸社に国家安寧を祈らせる「月次(つきなみ)祭」も認めなかった。これらは神祇官の存在を前提にした神事であり、幕府は神祇官を再興するつもりはなかったからだという。
第3に、大神社に勅使(奉幣使)を遣わすことである。22社に随時発遣された奉幣使も応仁・文明の乱で廃絶していた。江戸時代に奉幣使が遣わされた最初は家光の奏請によってなされた正保3年(1646)の日光東照宮へのそれである(→日光例幣使)。家光は幕府を宗教的に支えるものとして日光東照宮の権威を高めようとしたのである。輪王寺門跡が創設されるのが明暦元年(1655)。輪王寺門跡は天台座主を兼ねて天台宗の最上位とされた。 また日光例幣使開始の翌年(1646)、伊勢神宮への奉幣使が約250年ぶりに再興された。幕府が日光東照宮を伊勢神宮に並ぶものとすべく再興を進めたものと考えられる。
東照宮と伊勢の他は定例の奉幣使はなかったが特別の機会に各社に奉幣使が発遣され、それらも300〜450年ぶりのものだった。なお朝廷は22社への毎年の祈年穀幣使を望んだものの、幕府は認めなかった。各社への奉幣使で注目されるのは、1744年に発遣された宇佐・香椎宮奉幣使である。これにあたって朝廷は「大宰府山陽道諸国司と大宰府」に宛てて「太政官符」を発し、路地の国役・潔斎などを命じたのである。またそれに合わせて幕府は触れを出し、寺院を旅宿に使わないように命じている。これを受けて、例えば広島藩では僧尼は物見に出てはいけないといった神仏分離の考えが命じられた。さらに1804年の宇佐・香椎宮奉幣使では「前回にも増して廃仏や死・穢れを避ける命令が領主から命じられた(p.31)」。
この3重の国家祭祀の外側に、地域の大神社がそれぞれ独特な位置づけで存在し、それは22社に劣らぬ由緒や地域的権力・信仰圏を持っていた。さらにその周辺には地域の中小神社が存在していた。これらは、太閤検地による領地の没収、武士の俸禄制への移行に伴う武士団の紐帯としての神社の役割の変化によって、近世では土地により密着したものとなり、村落や百姓に支えられていた。しかし中小神社では専門の神職がいないところが多かったので、鍵取と呼ばれる百姓が神社の管理人になり、神事の時だけ専業神主を呼んだ。この場合呼ばれる専業神主は何ヵ村もその氏子圏にしていたということになる。
「江戸幕府の神社統制」では、「諸社禰宜神主法度」によって神社がどのような影響を受けたかが述べられる。江戸幕府は寛文5年(1665)、諸宗寺院法度と同時に「諸社禰宜神主法度」(江戸時代には「神社条目」と言われた)五カ条を発布した。江戸幕府は、武威に替わり儀礼によって身分秩序を確立することを企図し、武士・公家・百姓などの基幹身分の外にあった宗教者を身分集団化しようとしたのである。なおその前年、諸大名219人への領知判物・朱印状等の宛行を一斉に行っており(→寛文印知)、当年には公家に97通、仁和寺など門跡に27通、尼門跡に27通、院家に12通、寺院に1076通、神社に365通が発給されている。現状を是認し、秩序を固定化する意図と思われる。
この「諸社禰宜神主法度」の内容は、(1)神職は専ら神祇道を学ぶべし、(2)前々から伝奏に昇進の取次を頼んでいたのは従前の通りとする、(3)装束は吉田の許状が必要、(4)神領は売買禁止、(5)神社が壊れたら修理すること、といったものである。
第3条で全国の神社を統べる存在とされた吉田家は、22社のひとつ吉田神社の神職である。吉田家では、室町時代の吉田兼俱が唯一神道を創始して「大元宮」という場所を文明16年(1484)につくって天神地祇を祀り、また天正18年(1590)に吉田兼右は大元宮の裏に「神祇官八神殿」を設けて「神祇官代」と称していた。そして「吉田家は地方の神社に神号・社号を独自の宣旨(宗源宣旨)であたえ、神職に神道裁許状を発給してきた(p.51)」。幕府はこうした権威を追認、さらに「神祇管領長上職」に任じ、許状を発給する権利を保障したのである。この動きには、吉田神道を学んでいた吉川惟足の影響がある(惟足は天和2年(1682)に神道方に任じられている)。
しかしこれには地方の大社から反発が起こった。例えば出雲大社は吉田家の支配を受けるいわれはなく、国造家が惣検校職として装束の許可を出していたとして朝廷に訴え、霊元天皇から永宣旨を受けた。また肥後国阿蘇宮では摂家の鷹司家に官位執奏を依頼していたことから、「諸社禰宜神主法度」の第2条と第3条の解釈を巡って吉田家と鷹司家で争論となった。そのゴタゴタの結果、吉田家は22社のほか出雲・鹿島・宇佐・阿蘇などの大社の執奏は行わないことになった。さらに延宝2年(1674)幕府はこれを整理し、(2)執奏は必ずしも吉田家に限らない、(3)無位無官の社人装束は吉田家に委ねる、と「諸社禰宜神主法度」の解釈を確定させた。
これに伴い、吉田家の他に白川家や他の公家は神社の執奏を担うようになった。神社としては公家の権威を借りることが出来、公家としても執奏料の収入が期待できたからである。しかしながら全体として見れば、吉田家は「諸社禰宜神主法度」の効力を背景に、時間をかけてかなりの程度全国に影響を及ぼした。
ところで「諸社禰宜神主法度」の第1条「専ら神祇道を云々」も影響が大きかった。そもそも「神祇道」なるものが当時あったのかどうか定かでないが、これは神社の形式を神仏習合から吉田家の唯一神道に改める効力を持ったからである。おそらく装束の許状などを与える際に指導していったのだろう。また唯一神道でなくても、例えば出雲大社では境内にあった大日堂や三重塔を社外に移築し、別当寺の天台宗鰐淵寺との関係を切った。本書ではこの動きを「プレ神仏分離」と呼んでいる。
「吉田家と白川家の支配」では、神社の支配を争った吉田・白川両家の競争と神葬祭の動向について述べている。前章にあったように、幕府からお墨付きを得た吉田家は積極的に神社・神職の組織化を行った。吉田家から神道裁許状を得るには当然に上納金が必要であり、これは吉田家のビジネスでもあった。吉田家では四家老の下に役人が十数人いて、雑掌や社人(吉田社に仕える)もいたので大所帯だったようである。ところが元文4年(1739)、これに水を差す動きがあった。吉宗政権と朝廷(桜町天皇)は官位叙任について制度の見直しをはかり、吉田家が神位階(正一位稲荷大明神など)を「宗源宣旨」によって発給する形をなくしたのである。以後の神位階は勅裁に限られる。
一方の白川家では、宝暦元年(1751)に屋敷内に「八神殿」を再興した。かつて京都内野にあった八神殿が焼亡した際にその御正体を守って白川家が伝存してきたのだという。これが時の関白一条道香(とその親の兼香)によって本物だと確認され、朝廷の公認を得て「八神殿」を再興したのである。吉田家の「神祇官八神殿」と白川家の「八神殿」が併存していたわけだ。「この頃から、白川家に神祇伯としての自覚が目覚め(p.73)」たのだろう。白川家では弟子達を諸国の神社に派遣するようになり、それが吉田家の活動とバッティングした。
天明2年(1782)、幕府は再び「諸社禰宜神主法度」を触れた。これは専業の神職がない村で、村長が「宮座諸座」などと称して神事を営むのを問題視して行われたものだ。幕府としては素人神官が神事を行うことをよしとしなかったのである。これによって神事を担ってきた百姓(鍵取)や御師などは本来の百姓身分から神職身分へと身分を上昇させていく機運が生まれた。そして、その身分上昇には吉田家や白川家の許状が必須であった。本書では富士山信仰の須走村御師が吉田家の許状を受けて百姓から専業神職に移行した例と、別の富士山信仰の村で吉田家の許状を受けていた神職と白川家の許状を受けていた御師の対立が述べられている。
そういう吉田家と白川家の陣取り合戦的な各地での争いは幕府・朝廷に持ち込まれ、「伯卜論争」と呼ばれる争論となった。光格天皇を中心とする朝廷は吉田家に有利な官裁を行い一件落着かと思われたが、白川家はこれに控訴し、その後、先の官裁が撤回されるなど決着がつかず、結局天保11年(1840)に寺社奉行松平伊賀守によって決定した(その内容は本書には述べられていない)。ただし全国的には幕末まで両家は各地域での競争を続けた。
こうした動きと並行して、1700年代後半から各地の神職は神葬際を志向し始めた。幕府の寺請制度により、神職も必ず檀家寺を持ち葬式を仏式で行っていたのであるが、この寺壇関係を解消し、僧侶に依存せず葬儀を行うことが目指されてくる。「神職」としてのアイデンティティが芽生えていったと見なせる。これは「諸社禰宜神主法度」第1条の「専ら神祇道を云々」を盾にとって主張され、幕末になると幕府も神職とその家族の神葬際を認める判断をするようになった。
また幕末では、朝廷は社会の動揺を受け止めて各社への祈願を積極的に行うようになり、神祇にかかる行事が頻繁に行われた。こうした行事は、幕末になって復古されたものが多かった。しかしやはり祈年祭や月次祭は再興されることはなかった。その前提となる神祇官がなかったからである。
「明治から現代にいたる神社」では、明治維新以降の神社の変転がごく簡単に述べられる。明治政府は「神祇官」を再興し、全ての神社を神祇官の下に置いた。江戸時代に吉田家・白川家などが担っていた役割は否定され、国家が一元的に神社を管理する体制になったのである。また神仏分離を行い、神社から仏教的要素を取り除いた。本書では日光東照宮での神仏分離がケーススタディ的に述べられている。日光では神仏分離を不可能として一度は拒絶したが、新政府は輪王寺門跡を廃止し、明治3年には政府からの指示によって神仏分離させられた。しかしそれは廃仏毀釈のような暴力的なものではなく、日光山(東照宮)と日光県と政府の間で申請と許可が繰り返され、全面的な破壊を免れた。
最後に、靖国神社と明治神宮の創建、敗戦の影響などが簡潔に述べられ、未だに万世一系などの観念が天皇家や宮内庁が否定していないことを憂えて擱筆している。
本書は全体として、簡潔ではあるが非常に濃密であり、江戸時代の神社についてかなり見通しよく記述している。ただし、「諸社禰宜神主法度」や吉田家・白川家といった制度面にフォーカスしているため、主立った神社がどのようなものであったかという点についてはあまり記載がない。 本書はあくまで江戸幕府の神社政策について述べるものである。
江戸幕府の神社政策の概略がまとまった良書。
【関連書籍の読書メモ】
『江戸幕府の宗教統制(日本人の行動と思想 16)』圭室 文雄 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2022/05/16.html
江戸時代における仏教の在り方の一端を述べる本。仏教が蒙った江戸幕府の宗教統制を述べるものであり、本書と合わせて読めば江戸幕府の宗教政策がかなり理解できる。