あり得たかもしれない「もう一つの近代」を探る本。
明治維新は、日本の近代化の起点として高く評価されがちだ。しかしその後の歴史を見てみれば、明治政府は江戸幕府以上に専制的になって民衆を弾圧し、また天皇制を狂信的なまでに高めて海外を侵略することになった。
しかしそうした動きに抵抗した人々たちがいなかったわけではない。彼らは、もっと民主的で、自由で、人々の暮らしに立脚した社会を希求した。本書はそうした人々を取り上げ、あり得たかもしれない「もう一つの近代」を浮かび上がらせるものである。
「序章」では、鹿鳴館と地方の窮乏が対比して描かれる。鹿鳴館に象徴される欧化政策華やかな頃、明治政府は富国強兵の政策を推し進めるために民衆からの収奪を強化していた。さらに日露戦争が勃発すると戦費調達のために一層増税される。そして日本は、「開化」されて豊かな生活を送る上級国民と、貧民に二極分化していくのである。農民の収奪を進めたことは、民権運動の担い手だった地方の豪農層が掘り崩されることとなり、民権運動敗北の遠因とさえなった。
「1 近代化と伝統」では、幕末からの民衆側の思想が象徴的ないくつかの事例から述べられる。
豊後国日田(大分県)の広瀬淡窓には、幕末までに4千人以上もの門人があった。しかも平民の入塾者が多かった。庶民が学問を志すことが社会の変化を物語っていた。彼らは古典を学ぶ中で、新しい国家観を育みつつあった。「19世紀初頭は、自生的な変革の理念がいっせいに芽をふきはじめた時期だった(p.47)」。少なくとも彼らは、既存の秩序に飽き足らなくなっていたのだ。
1830年の「おかげまいり」はそれまでにない規模だった。おかげまいりとは、伊勢神宮に男女群れをなして参拝することである。彼らは一時の解放感を味わったが、それは一揆とは違い世直しの意味はなかった。ところが1837年に大塩平八郎の乱、そして越後国ではそれに倣った生田万(よろず)の乱が起こる。それらは「世直しの想念」を人々に形作る役割をした。関東では動乱が続き、相楽総三の赤報隊はその最後の象徴である。幕末、人々が「世直し」を求めていたことが明治維新の前提となった。しかし相楽総三は、新政府軍によって下諏訪の地で処刑される。人々が求めた「世直し」を抹殺することで明治政府は成立したのである。
文明開化を唱導した明治初期の知識人たちは、民衆を露骨に愚民と見なし、伝統を全否定すべきものと考えた。そして福沢諭吉の『文明論之概略』に象徴されるように、西欧文明への移入を「実学」として当面の目標に定めたことは、「自生的な近代への構想力を衰弱させてしまった(p.76)」。そして世直しの想念は西欧化にとって邪魔なものとして一層抑圧された。まさに文明開化たけなわの明治7年、中山みき(天理教)は「おふでさき」で開化に対する神の怒りを表明した。彼女は明治維新の当初では、新しい社会の到来として歓迎していたのにだ。
明治16年、小室信介は『東洋民権百家伝』を出版した。「幕藩体制下の百姓一揆についての最初の包括的な著作である(p.81)」。福沢諭吉らが一揆を全く評価しなかったのに対し、小室はこれまでの英雄や聖人の価値を相対化し、一揆の指導者を称揚した。しかし民衆による反体制の伝統は断絶する。圧倒的な西欧文明の流入は人々を目覚めさせたが、目覚めた人々は西欧文明をモデルに専制体制の打破を考え、民権運動へと流れていくのである。そして政府は民権思想に対抗すべく、自然科学、道徳主義教育、二宮尊徳の報徳思想などを動員した。
民権運動が終熄し帝国憲法が発布された頃、陸羯南は日本新聞社の社主・主筆として、国粋主義の言論人として突き動かされていた。彼はいわば乗り遅れた側なのだった。彼は、中央本位・藩閥本位・特恵資本本位の近代化、つまり中央にコネのある小さなサークルだけでの近代化からあぶれた側にいた。 政府が進める自由主義は、弱肉強食を肯定して強者の支配を正当化した。それが国際関係にも敷衍され、植民地化が進められる。羯南はそれを批判し、西洋文明への無条件な追随ではない、新しいありようの文明を模索した。そしてその批判の上に、「近代化のおくれた要素とみなされてきた伝統=国粋を、逆に基軸としつつ、近代化を構想しようと(p.101)」した。
雪嶺三宅雄二郎は、その日本新聞社に論説を寄せた一人であるが、彼は1891年に『偽悪醜日本人』を出版。近代日本の病弊を全篇にわたって指弾した。彼はいたずらに富国強兵にはしらない文化国家としての道を主張した。無批判な西欧化の弊害は様々なところで認識されはじめ、正岡子規が俳句と短歌の革新運動を起こすなど、文化面でも日本の伝統を見直すことで新たな国家のアイデンティティを形成する方向が模索された。その課題を突き詰めた思想家が北村透谷である。透谷は物質文明に偏った日本の近代化を痛歎し、抑圧された人々の立場で社会を見た。そして借り物の文明ではなく、元禄文学から読み取れる「平民の声」、「国民の元気」によって創造的文明をうちたてようとする。しかし彼の孤立した戦いは「偽文明」によって押しつぶされ、明治27年についに縊死したのである。
南方熊楠は、明治中頃から進められた神社合祀政策に傲然と反対した。彼の住んでいた和歌山県は、隣の三重県とともに最も激しく神社合祀が進められたところである。神社合祀は人々の生活に即した信仰を破壊し、「国家の栄光に直結する信仰を導入しようとした政策(p.117)」であった。明治政府は西洋化を進めながら、明治中期頃になると「ことさらに伝統的な文化を強調する姿勢(同)」を見せはじめ、にもかかわらず伝統を破壊して神社や信仰を画一化していった。そして神社合祀は、それによって神林の公売が増え、山林の濫伐が行われることで、国家に繋がる村の有力者層にうま味をもたらした。明治政府は、人々の生活と信仰、伝統と景観を破壊し、国家に従属させていった。夏目漱石は「開化が進めば進む程競争が益(ますます)劇しくなって生活は愈(いよいよ)困難になる(p.125)」とその病弊を率直に指摘した。
「2 集権化と自治」では、人々の間に芽生えはじめた「自治」が摘み取られ、全国民が国家に従属させられていく次第が語られる。
嘉永6年(1853)、8千〜9千人もの南部藩の農民集団が、120キロメートルもの道を歩き通し他領へ逃散した。指導者の一人三浦命助はやがて捉えられるが逃亡。そして彼は京都に向かう。彼は幕藩体制への反発から王朝的なものへと期待したのである。つまり既存の体制からの離脱が、自立的な体制の樹立を目指すのではなく、それに変わるより大きな権威に幻想を託す形として現れた。中央集権を目指したのは明治政府だけではない。人々が幕藩体制の限界を感じ取り、自律的に「思想」を形成していく中で、中央志向への滔々たる流れが出来ていった。
明治15年(1882)、福島県で専制的に土木事業を進める県令三島通庸(みちつね)に対決したのは、33歳の県議会議長野中広中であった。三島は、国家が先にあり、その代行者としての中央官僚がいて、その下に地方官僚がいるという明治国家の思想で県会を無視しようとした。一方、野中は、まず民意があり、それを実現するために地方政府がある、という逆の思想を持っていた。彼は明治政府を国家ではなく「中央政府」にすぎないと捉え、その専制支配に基づく恣意性を「私」とし、むしろ「住民の個々の日常的な要求の集合体をこそ「公」ととらえ(p.146)」た。そこには「自治」を中心とした国家観が芽生えていた。しかしその運動は弾圧され、三島通庸の政策は貫徹された(福島事件)。その後、専制性を強める政府をよそに、野中は三春町の戸長として自治に邁進した。しかし「三新法(郡区町村編成法・府県会規則・地方税規則)」(明治10年)にもとづく地方自治制度は、徴兵や戸籍といった国の事務を町村に押しつけ、形ばかりの議会でガス抜きするようなものだったから、地方自治は形無しになっていった。この自治制は「人々の関心を地域社会にとじこめるのを目的として(p.156)」、古い共同体(名望家支配)の温存を基調としていたからだ。
明治維新によって東京は急速に巨大化した。そこに天皇が移ったことは他の都市と隔絶した意味を東京に与えた。東京の巨大化は天皇制の強大化と歩調を等しくしていた。東京には大小の学校が林立し、若者たちの青雲の志をもやす対象になった。そして明治20年(1887)前後、「東京語」が成立。「中央対地方、表日本対裏日本、都会対田舎、そうして舶来対国産という二極分解を促進していった(p.172)」。東京は「辺境」を作ったのである。その辺境の最たるものが沖縄だった。その統治においては「住民の意向はすべて邪悪なものとしてしりぞけられ、ひたすら中央の意向の貫徹のみがめざされ(p.178)」た。「琉球王」の異名をとった薩摩出身の知事・奈良原繁の支配はまさにその悪例である。住民は「同化」を拒否する愚かな存在として表徴され、差別を助長していった。
「教育は、近代日本の歴史のなかで、集権化を促進し正当化するための、イデオロギー上のもっとも重要な装置であった(p.185)」。教育を通じ「日本人の国家主義化・画一化がひろくふかく進行した(同)」。教育は自治・自立への志向を抑圧し、「従順なる臣民」を作るためにあった。私立学校ではもっと自由な教育が行われていたが、やがて国家はそこにも容喙した。近代日本の教育行政は、文部省だけでなくさまざまな官庁が関与したことが特徴だ。内務省は青年団の組織化を通じて社会教育に介入したし、陸軍省は学校教育に軍事教練を導入、そして内務省は教育勅語を推進した。ことに「軍事と教育は、天皇の意志がもっともつよい拘束力をもった二大部門(p.194)」であり、教育勅語、戊申詔書、国民精神作興ニ関スル詔書、青少年学徒ニ賜ハリタル勅語のように、教育法規の重要なものは議会を経ない「勅語」「勅書」の形式で出された。教育は治安対策として構想され、「学習するがわの、多様性への志向や自発性や創意が抑圧された(p.196)」。明治13年(1880)に「修身」が筆頭学科となったことはその象徴である。教育は国家にとって都合のよい「道徳」を画一的に押しつける場だった。
一方、都会に出て学問を身につける機会がなく、田舎に閉じ込められていた青年たちは、青年会などを組織して夜学会を開き勉強や議論を行った。こうした青年たちの自発的な結社の動きは明治20年代に盛んになった。彼らは選挙権も被選挙権も持たなかったが、かえってそこには自治・自立の志向を認めることができる。しかしその活動には、「善行」の励行によって、国家から認めてもらおうとする傾向が強かった。それに呼応するかのように、政府の方でも地方自治に関心を寄せるものが現れた。特に精鋭の内務官僚においてである。そして彼らは、「青年会・教育会・農会の組織化を鼓吹し(p.208)」、行政の末端としてそれらを位置づけることで、全国民を国家の手足とする構想を抱いた。それはやがて「地方改良運動」として実現化する。特にそれは「租税の滞納を一掃する運動」となった。
「3 大国化と公理」では、日本の帝国主義化への道程が描かれる。
文久元年(1861)、福沢諭吉は幕府からヨーロッパ出張を命じられた。福沢にとってアメリカに次ぐ2度目の海外である。彼はヨーロッパの現状を封建的夷狄観から解放された目で見、西洋文明の全面的な受容こそ日本にとって必要だと断ずるに至った。日本では尊皇攘夷運動が高揚した時期である。この時期の福沢にとってはヨーロッパこそが善であった。アヘン戦争も100%イギリス側の視点で見ている。一方で吉田松陰はアヘン戦争を列強が中国を侵略したものと見た。西欧は、福沢にとっては「文明」で、松陰には「列強」だったのである。やがて日本は文明化された列強を目指していく。
明治15年(1882)、牛場卓蔵は福沢諭吉の推薦を受け、金玉均とともに朝鮮へ渡った。朝鮮を「開化」するための顧問のような役割だった。福沢は朝鮮人を露骨に愚民と見なして強硬論を唱え、日本の「文明」を上から目線で輸出しようとしたのである。2年後、金玉均らが計画したクーデター(甲申事変)にも福沢が裏で関わっていた。福沢が朝鮮を「開化」しようとしたのは、日本が列強になるための道具として朝鮮の保護・改革を考えた結果だった。福沢も、文明開化を喧伝したころは公理の感覚を持っていたが、もはや国際関係における力の政策を臆面もなく説くようになった。福沢と違い自由平等を叫んでいた人たちも、朝鮮に対しては大国意識をもって臨み、押しつけがましく「朝鮮は独立すべきだ」と独善的に主張した。結局は、日本が「大国」であるために、踏みつける対象が必要だったのだ。こうして公理の思想は根絶やしになった。
内村鑑三は、当初日清戦争を支持していたが、戦後は非戦論者になった。それが高邁な理想ではなく、単なる力の論理で行われたという現実を思い知ったためだった。内村には国家と違って「良心」があった。「「真理は国家より大なり」と宣言して、かれは、世に流行する国家主義との絶縁を宣言(p.253)」する。彼は軍事強国となり腐敗した日本の近代化を否定し、むしろ古き良き時代に憧れ、古風なピューリタリズムの信仰を敬慕した。そして日本によって圧迫される国、押しひしがれている人々との連帯を強め、軍備ではなく教育、支配階級の解体と平等の実現、地方自治、といった大国化と逆の理想を追求していくのである。しかし社会矛盾に苦しんでいた国民はそうした理想を共有することなく、むしろ現状打破の希望を対外的な強硬論に託し、積極的に大国化を支持していったのである。
民権論者の宮崎滔天は、中国革命の夢を抱き中国に渡る。しかし他の中国浪人=大アジア主義者とは違い、彼は利益や名誉を求めていなかった。滔天は失敗と窮乏の中で落伍していったが、身を落としていくことで、彼はかえって自由になった。彼に中国人を率いようとする独善はなく、孫文らを支援し、自らを助力者と限定することで最も深く中国革命に関わり得た。彼は資本主義列強に圧迫されたアジアの恢復の主導力を日本ではなく中国に期待し、その革命に未来の文明の光を見た。にも関わらず、現実の日本は中国や朝鮮の利権に目が眩み、公理を無視して侵略を続けていった。
与謝野晶子は「君死にたまうこと勿れ」と戦争にいく弟に呼びかけた。しかしこの肉親に対する素直な情愛が「乱臣、賊子」(評論家大町桂月)として強烈に批判される。なぜ生きてほしいという当たり前のことを書いて悪いのか。軍国日本にとって「生命の尊重」こそ最も斥けてきたものだったのだ。与謝野晶子は反戦者だったのではない。むしろ戦争に模範的に協力する主婦であった。だが「そのなかにあって彼女には、なにかうべなえぬものがあった(p.286)」。「生命」の尊重が否定されたとき、「彼女には、秩序の全構造がまやかしとみえてくるのであった(同)」。女性は特にそのまやかしの矛盾を押しつけられていた。男性本位の社会秩序と、それと表裏一体の軍国主義の中で、女性は道具に貶められた。彼女は女性の論理でそのことを糾弾した。しかしその彼女であってすら、軍国主義の中に身を投じてゆくことになるのである。
全体として本書は、異常な迫力があり、まるで疾走するような文体で書かれている(ひらがなが多いのも特徴)。著者の追求した「もう一つの近代」は本書に登場する様々な人々の理想の集積であるが、それをまとめた文章はなく、唐突に本書は擱筆されている。野暮とは思うがそれをまとめれば、それは「虐げられた人々の視点に立ち、民衆の暮らしに立脚して、伝統や文化や信仰を大事にし、地方自治と国家・階級・男女間の平等を実現した、より自由で多様性を受け入れる社会」とでもなろう。
もし、そうした方向に日本が進んだ場合、日本は独立を保てたのだろうか? と人はいうだろう。西欧の列強に対抗できなかったのではないかと。もしかしたらそうなのかもしれない。しかし「もう一つの近代」の構想はほぼ例外なく、その全てが切って捨てられているところを見ると、全面的に採用しないにしても、もう少し斟酌してもよかったのではないか、と思わずにはいられない。まさにこの、国家の意向と少しでも異なるものを全否定して生まれたのが近代日本であったのだ。本書はこの単純な事実を、生き生きとしたエピソードで語るものである。
ただし、本書は象徴的な事例で畳み掛けるような書き方をしているため、事実を単純化して述べる点が散見される。例えば相楽総三の赤報隊の処分については、本書では「世直しの否定」として描かれているが、実際には相楽が処分されたのは何度も上官の指示に従わなかったためも大きく、形式的には世直し的な部分(年貢半減の約束など)が主たる理由ではなかった。とはいえこういういことをいちいち指摘するのはあまり意味がないだろう。大筋として、「もう一つの近代」を近代日本が否定し去ったのは動かしがたい事実である。
近代日本の軍事大国化を、それに抗った人々を通じて描いた異色の思想書。
【関連書籍の読書メモ】
『文明国をめざして—幕末から明治時代前期(日本の歴史13)』牧原 憲夫 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2022/06/blog-post_16.html
明治時代、どのようにして民衆が「文明化」されたかを述べる本。文明開化を庶民から見るスリリングな論考。本書と重なる視点が多い。
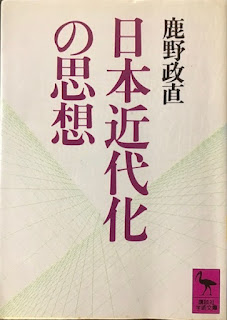
0 件のコメント:
コメントを投稿