佐土原藩の山伏、野田泉光院成亮(しげすけ)は、文化9年(1812)から6年2ヶ月にわたって托鉢しながら全国を旅し、その様子をマメに日記に記した。本書は、その日記『日本九峰修行日記』を読み解くものである。
彼は山伏としては大先達という非常に高い位を持ち、佐土原島津家から27石の禄を受ける家臣でもあった。僧侶であり同時に武士であったのは不思議だが、彼は元は薩摩国出水の野田庄の武家の流れだった。安宮寺という山伏寺を世襲しつつ、同時に武士の身分も受け継いでいったようだ。
ともかく泉光院は主君の命を受け、平四郎という合力(剛力=荷物持ち)を連れて、全国を巡る旅に出るのである。
私は本書を2つの興味から手に取った。第1に、当時の旅について知りたいということ、第2に、宗教者の回国がどのようなものであったか知りたいということである。
第1点からまず興味を引いたのが往来手形のことである。当時は、檀那寺や役所から往来手形というパスポートを発行してもらい旅をした。そして各地の関所で往来手形を確認した……ということになっている。ところが本書を読むと、まず関所・番所自体が少ない(泉光院は、番所の大規模なものが関所、というような用語の使い方をしている)。領国(藩)を超えるときも関所などないことがほとんどである。関所がないのだから、手形は見せようがない。また番所がある場合も、手形を見せなくても通過できるところが多い(何を確認していたのだろうか?)。これは幕府の番所でもである。逆に、通行の際に手形は改めずにお金を取る番所もあった。全体的に言って、往来手形の扱いや番所の通行はかなりいいかげんである。なお、泉光院が泊まる際も一度を除いて往来手形を見せて欲しいと言われることはなかった。ただし、唯一の例外が薩摩藩で、薩摩藩では非常に厳しい「出入国管理」をしていた。薩摩藩の特殊性はここでも際立っている。
そして、泉光院たちは旅の途中に大勢の旅人に出会う。当時、勝手気ままにふらふら旅している庶民がかなり多かったようだ。特に六部(六十六部廻国聖)とはよく出会う。六部というのは、ちゃんとした(専門の)修行の回国もあったが、自称の六部も多かったようだ。妻を尼といって連れ歩く夫婦の回国者もかなり見受けられる。ほとんど観光旅行のような感じである。なお泉光院は、「妻を尼といって連れ歩くとはけしからん」と思っているが、しかし泉光院自身も妻帯しており、宗教者として妻帯すること自体を非難しているわけではないと思う。
ではその旅人たちはどうやって旅を続けていたのかというと、托鉢しながら普通の民家に泊めてもらっていた。本書を読んで一番驚かされるのはここで、当時の日本には見ず知らずの人を喜んで泊める人たちが日本全国にいたのである。泉光院たちも、6年以上の旅でただの一度も野宿していない。宿に困った時もすんでのところで親切な人が現れて泊めてもらえるのである。
というのは、当時の農村の人々は情報に飢えていた。日本中を回っている旅人から話を聞くことは楽しい娯楽でもあったのだ。とはいえ、世の中がみんなそうだったわけではない。特に都市部では泊めてくれる家が少なく、泉光院たちも木賃宿や旅籠に泊まっている。また農村部でも一向宗と日蓮宗の村では苦労し、ことに日蓮宗の村は托鉢も出来ず回国者を一切泊めないためおおむね素通りしている。
また、村の申し合わせで旅人を泊めないことになっている土地もあった。ところがそういうところにも辻堂(数軒が集まって檀那寺以外に維持した無住の小さなお堂)があって、そこを使わせてもらうことができた。逆に回国者を泊めることを誇る土地もあり、そういう場所では家々が「今年はうちは何人を泊めた」と自慢しあっていたり、回国千人宿という回国者ばかりを泊める場所があった。回国者の扱いはこのように色々だが、日蓮宗以外の村ではたいてい親切な人が困った人を泊めていた。
そして、当時の回国には「年宿(としやど)」という風習があった。どうやら、年末年始というのは托鉢や移動をしないという了解があったらしい。よって回国者は12月25日頃から2週間〜1ヶ月くらい、一つの家に逗留して年末年始を過ごすのである。これが「年宿」である。見ず知らずの人を1ヶ月も泊める家を見つけるのはなかなか難しい、と感じるがさにあらず。泉光院は年末が近くなると「今年の年宿はもうお決まりですか」などと声を掛けられ、「決まっていなかったらうちへお越し下さい」などといって毎年あっさりと年宿の家が見つかるのである。驚くべき親切さである。
ちなみに、そのようにして泊まるのはタダだったか? 泉光院の日記には、「謝礼を断られた」という表現がしばしば出てくるので、泊めてもらった家には普通はそれなりの謝礼はしたらしい。しかし彼らが謝礼目当てに旅人を泊めたのではないことは明白であり、謝礼は少なくとも木賃宿などの宿泊料よりも安かったようである。
ともかく、当時の人たちが今から見れば度外れた親切心を持っている、ということには本書を読みながら何度も驚かされた。宿泊だけでなく、托鉢についてもそれは言える。六部などの回国者は、托鉢をしながら日々の糧を得て旅を続けたのであるが、托鉢について再考を促される事例が途中に出てきた。
ある時、合力の平四郎が、「札を配って托鉢をするのは、札を作る手間もあり効率が悪い。自分は札なしで、泉光院は札ありで托鉢をして、どちらが多く托鉢を集めるか競争しよう」と言い出したようなのである。その結果は、平四郎が米4合に対して、泉光院が米5合と銭百文で勝ち、結局それまで通り札を配りながら托鉢をすることになった模様である。
この事例で非常に驚くのは、平四郎は僧侶でもなんでもない町人である、ということだ。町人が托鉢をしても、高位の山伏の托鉢と同じくらい米や銭を集めることができたのである(少なくとも平四郎はそう考えていた)。他の箇所でも平四郎は泉光院とは別に托鉢をしてそれなりの実績を上げている。泉光院は、身をやつしていたとはいえ職業的宗教者であり、服装も山伏の恰好だったはずである。泉光院に喜捨する人々がいたのはわかる。しかし平四郎は全くの俗人だ。泉光院の弟子でもなんでもない。その平四郎が一人で托鉢してもそれなりに集まったということは、人は何に対して喜捨していたのだろうか。
私はこれまで、回国者や山伏というのは決まった服装があり、その服装をしている者は宗教者と見なして人々は喜捨をしたのだ、と考えていた。しかし平四郎のことを考えるとそうではないらしい。宗教者であるか否かに関わらず、托鉢には人々は協力していたようなのだ。しかも、泉光院と平四郎が托鉢勝負をしたことを考えても、宗教者だからといってたくさん托鉢に応じる、というわけでもなかったのだ。もちろん、人々は喜捨が作善の行為であるという意識はあった。だが誰に施すかはそれほど重要ではなかったようなのである。困っている人を助けること自体が作善だと思っていたのかもしれない。
そしてもう一つ気付いたのは、托鉢では結構お米をもらっているということである。江戸時代の農村では、白い米を食べられるのは限られた日だけだった、というようなイメージがあるがそうではない。泉光院たちはよく白い米をもらっている。控えめに見積もっても、白い米が非常な贅沢品であったということはありえない。
ちなみに、托鉢には様々な人が応じたが、人が多いところで多くの米や銭が集まったかというとそうでもなく、むしろ農村の方が托鉢はしやすかった。日蓮宗以外で一番やりづらかったのは、商業都市だったようだ。商業が盛んになると親切心や真心が失われるということはあるらしい。とはいえ、托鉢に応じるかは貧富の問題というよりライフスタイルの問題なのかもしれない。泉光院自身、「田舎の方が面白い」といって田舎では悠々と楽しく過ごしている。
泉光院は当時としては非常な知識人である。田舎に彼がやってくると、その学識や全国を廻った経験、そして祈祷の能力といったものが買われて、田舎では引っ張りだこになるのである。 泉光院はしょっちゅう病気平癒の祈祷をやっている。そして滞在するうちに、うちにも祈祷してくれという依頼が舞い込んだかと思うと、四書の講義を頼まれたりする。四書(孔子、孟子、大学、中庸)など、田舎の人たちに何の関係があったのかと思うが、泉光院自身も「田舎の青年を教えるのは楽しい」といって熱心に講義する。すると近所の人が大勢集まってきて、老若男女が四書の講義を熱心に聞く、ということになる。どうも田舎の人は向学心がすごくあったようだ。
向学心というより、田舎の人にとって知識も娯楽の一つだったのかもしれない。そしてそういう滞在をする際には、ほとんど例外なくその地方の人と俳句、連句、短歌のやりとりがある。どんな農村にもこうした短文詩を嗜む人がいて、コミュニケーションに使われていた。現代ではすっかり失われてしまったが、このように文学的な素養が全国の寒村にまで行き渡っていたなんて夢のようである。
ところで、泉光院と平四郎の関係は面白い。平四郎は荷物持ちとして雇用されており、二人は主従ではあるが、その関係は我々が想像する「江戸時代の主従関係」とはほど遠い。例えば、平四郎はときどき泉光院に説教をしている。 平四郎は経済合理性を重視するタイプで、泉光院が効率を考えないのが気に食わないようなのだ。先ほどの托鉢勝負もそういう考えからもちかけられた。泉光院は身分の高い武士で、平四郎は泉光院に雇用された町人なのに、全くへいこらしていないのである! 平四郎はちょっと変わり者ではあったらしい。しかし、二人の関係はほとんど対等と言って差し支えなく、武士と町人に厳然とした上下関係はなかったと判断するほかない。
その他ビックリしたのが洗濯。泉光院は洗濯のために何日も一つの家に滞在することがある。どうして洗濯に何日もかかるのかと思っていたが、この頃は着物を解いてから洗って糊をつけ、仕立て直すのが正式の洗濯だったらしい。洗濯とは仕立て直しまで含んでいたのである。しかし、どうして洗うためにいちいち解いたり仕立て直ししたりする必要があったのだろう。
このように、泉光院の旅は、江戸時代の社会が垣間見えるものとなっており滅法面白い。宮本常一もその日記を当時の庶民の暮らしが記録されたものとして本に書いている(『野田泉光院』)。本書は庶民の暮らしというより、旅の足取りを追うことが主眼になっていて、泉光院が記録した地名を現代の地名と照らし合わせて、ほとんどの地名を同定している。こうして泉光院の足取りを辿れることは、地名がそれほどは変更されていないからで、著者は「地名が文化遺産」であるという。無定見な地名の変更は、土地の歴史を断絶させることでもあると感じた。
最後に、泉光院は何のために日本を巡る旅に出たのかというと、本書にははっきりと書いているわけではない(日記にもはっきり書いていないようだ)が、まとめると次の3つである。第1に、主君の佐土原島津家の代参として日本三大虚空蔵を巡ること。すなわち柳津(やないづ)=福満虚空藏菩薩圓藏寺、常陸那珂郡=村松山虚空蔵堂、安房郡天津小湊=千光山清澄寺にある虚空蔵菩薩である。第2に、日記のタイトルにもなっている霊山九峰に登攀することである。すなわち英彦山、羽黒山、湯殿山、富士山、金剛山、熊野山、大峰山、箕面山、石鎚山である。泉光院は常識外れの体力を持っており、その気になれば一日に平気で60キロくらい歩く。日記では登山もあっさりとしか記録されていないが、肉や魚を食べない人がこのような強靱な肉体を持っていたことにも驚かされる。そして第3に、西国三十三ヶ所、板東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所 合計百ヶ所の「百番札」を納めることであった。
本書は全体として、泉光院の日記を順を追って読み解いていくという地味なものであるのに、非常に面白く読んだ。親切な人々との温かい交流、びっくりするような当時の社会の有様、泉光院と平四郎の関係(途中、仲が悪くなったりする!)、そして旅そのものの行方まで、いろんな要素で読ませる本である。
江戸時代のイメージが一変する、読んで楽しい日記の解説。
【関連書籍の読書メモ】
『江戸の旅』今野 信雄 著
https://shomotsushuyu.blogspot.com/2022/04/blog-post_24.html
江戸時代の旅がどんな風であったかを述べる本。江戸の旅の実態をわかりやすく知れる良書。
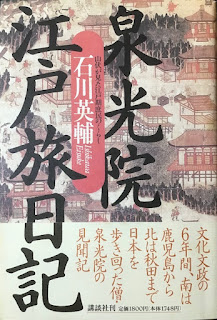
0 件のコメント:
コメントを投稿