科学史の金字塔的な本。
著者のジョージ・サートンは「科学史」を独立した学科として構築することを企図して本書を構想した。「科学史」は、例えば数学史であれば数学研究の一分野(しかもほとんどオマケのような一分野)でしかなかったし、或いは文化史の中の一つのトピックに過ぎない面があった。そういう歴史学の付属物としてではなく、「科学史」自体に学問としての固有の価値があることを信じ、 サートンは大規模な叢書をつくり上げることによって「科学史」そのものを打ち立てようとしたのである。
その叢書は次のような構成として計画された。
第一叢書:編年的に構成された、地域横断型の科学史の概観(7〜8巻)。
第二叢書:例えばユダヤ文明、イスラーム文明、中国文明といったように、種々の文明における科学発展の概観(7〜8巻)。
第三叢書:数学、物理学など分野ごとの発展の概観(8〜9巻)。
つまり、サートンは科学史を縦糸的(年代記)、横糸的(地域的)、分野的という3方向から編むことにより、科学史の目でしか見ることの出来ない人間学を確立しようとした。もちろんこのような大規模で百科全書的な構想はサートン一人の手に負えないことは自身がよくわかっていた。ただサートンは、自らが出来るところまでやってみよう、という決意でこの仕事を始めたのである。
そして結果的に成し遂げられたのは、第一叢書の最初の3巻(古代・中世)だけであった。全体の構想の、ほぼ1/8にあたる量である。しかし、この3巻だけでもサートンの名は科学史史に永久に記される価値がある。 それくらい、科学史において画期的な業績であった。
この3巻(日本語訳では5分冊)の特色は、西洋中心だったそれまでの科学史から脱却し、東洋(特にイスラーム圏、中国、日本)の業績を詳しく紹介するという、世界史的な視座に立った科学史となっていることである。特にイスラーム圏の科学を詳細に研究したサートンは、イスラーム圏の科学がどれだけ大きく科学の発展に寄与したか熱をこめて記述しており、仮に本書がイスラーム圏のみの記述しかなかったとしてもその価値は非常に大きい。
その内容を紹介することは科学史の無様な要約になってしまうし、関心のある人は自ら目を通すであろうから辞めるが、科学史について深く知ろうという人でなくても、この第1巻の序章だけでも面白い。
例えばサートンはこの序章で、中世期には東洋の方が科学の水準が進んでいたのに、近代になってなぜ西洋がそれを追い越し、圧倒的な差がついてしまったのか、という疑問を提示する。そしてそれに対し、「西洋人と東洋人とはスコラ学の大きな試練を受けたが、西洋人はそれを突破し、東洋人はそれを突破しそこなったのである」との回答を与えている。
スコラ学という病理の唯一の治療法は実証的経験に基づいて知識を再構成しなおしてくことだったが、東洋では遂にその大事業をする人間が現れなかったのであった。この回答の含蓄の深さは、実際に本書を手にとっていただかないとなかなか伝わらない。科学の発展の歴史というある意味では無味乾燥な事実の羅列であるにもかかわらず、ここには確かに新たな人間学・文明史学が誕生していると思う。
なお、日本語訳は5分冊あるが、原書3巻の抄訳である。原書では、(1)その時代の主な科学的事績の概説、(2)批判的書肆解題(その時代の科学書の紹介)、(3)それらに対するサートンの覚書、の3つの部分を年代記的に並べていく構成が取られているが、日本語訳ではその(1)の部分のみを訳出しているのである。これは、サートン自身が(1)の部分を通史的に読めるように意図して著述しているため無理な抄訳ではなく、(2)や(3)まで目を通したいという専門的な向きはどのみち原書で読むと思われるのでやむない処置であろう。
ちなみに、日本語の書名は「科学文化史」を銘打っているがこれは不可解である。サートンは、文化の一様態としての科学というより「科学史」そのものを記述したかったわけであるから、単に「科学史」とすべきであった。本書ではそれまでの科学史の範疇に収まらない歴史学、言語学なども含まれているから「文化」をつけたのだろうが蛇足だ。原題は "Introduction to the History of Science"(科学史概説)であり、素直にこれを直訳する方がよかったと思う。
なお、本書が切り拓いた地平には、サートンに続いて新たな科学史がどんどんと打ち立てられていくことになる。例えばその嚆矢はニーダムの『中国の科学技術』(全14巻)であろう。科学史の分野で顕著な業績をあげた人に送られる賞がジョージ・サートン・メダルという名前なのも納得である。
そういう独立した学科としての「科学史」を打ち立てた不朽の名著。
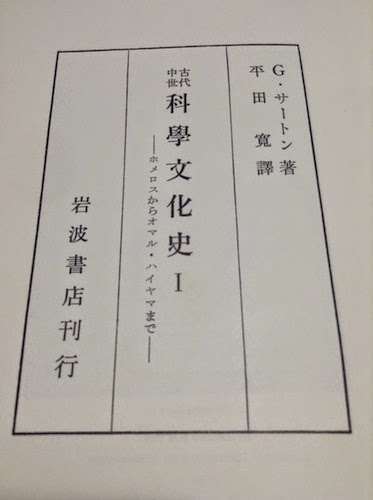
0 件のコメント:
コメントを投稿